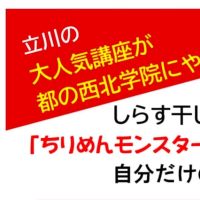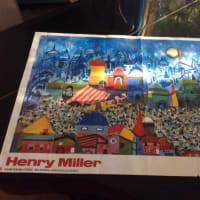立川市立小学校科学教育センター(私が事務局長)のことが、今年の3月に立川市議会予算委員会で取り上げられていました。
後からわかりました。
応援的な質問と前向きな答弁でうれしく思います。
それではと、市議会会議録をさかのぼって検索してみました。
出てくる出てくる!
理科離れを憂い科学教育を推進する現場の先生方、
本来は理科は大好きな子どもたち、
共感し応援する保護者・市民、
そして
市議会でのたゆまぬ取り組み
行政の前向きな対応
他区市では、科学センターがどんどんとつぶれている中で
立川は、これらの相乗効果が発展の要因なのです。
今年度は、科学センター53年の過去最高の164人の応募がありました。
市民、保護者にしっかり根付いた立川の科学センターです。
科学センターの卒業生たちは、様々な理科系分野やいろいろな分野で活躍しています。
科学センター出身の保護者たちが、自分の子どもを通わせるようになりました。
ここ数年で応募倍増です。
この要望に応える必要があります。
市内の社会教育・生涯学習では、NPO団体、社会教育団体、児童館、図書館、学生たちなどの科学実験の様々なイベントが広がりを見せています。
思いきって科学センターも入る「科学館」を作ってはと、本当に思い、本気で考えています。
以下、市議会会議録(市議会ホームページより抜粋)
平成29年3月予算特別委員会
◆委員(谷山きょう子君) 319ページ、事項別明細書と、343ページ、中学校普通教育振興についてお聞きいたします。
319ページは教育事業事務についてです。
小学校高学年を対象とした科学センター事業の概要と現況について、簡単に説明をお願いいたします。
◎指導課長(小瀬和彦君) 科学センターでございますが、これは本市が先駆けて昭和43年度から実施しているところでございます。本年度は154名もの応募がございまして、その児童が八小を中心に今、会場を中心にして活動しているところです。非常に子どもたちの理科に対する興味関心を喚起するいい場になっていると考えております。
以上です。
◆委員(谷山きょう子君) また後ほど、財源として市税がどれぐらい経年で変化しているか教えていただければと思います。
人数はほぼ横ばいということでした。
実は、私の長男も科学センターに通っておりました。小学校時代は科学的な体験をすることが大事だと科学センターの講演会でも先生がお話をされておりました。中学生以降に受験勉強などの詰め込みは幾らでもできますが、体験を通した学習は小さいときこそ大切であり、ここが学ぶことのベースとなるというお話でございました。この趣旨に重きを置いた立川市の取り組みは大変評価するものです。ぜひ継続的にしっかり市税も投入して続けていっていただきたいです。
次に、中学校の理科実験室、実験テーブルごとの水栓に関する調査を資料で出していただきました。9校中5校は、実験用のビーカーなどを洗う実験台にある流しでは、入っている薬品が目に入る危険を防止するために、水栓にゴム管等のホースがついておりませんでした。また、各学校の主な理科振興備品の購入年度も資料で出していただきましたが、学校によっては31年目から40年前、昭和52年から61年度に購入した顕微鏡、双眼実体顕微鏡が18台もございました。これは、今の中学生の親御さんが生まれた年に購入したものでもおかしくないくらいの古さです。全体としても21年前から41年以上前の備品が239もございました。中学校に入った子どもたちは、余りに古い理科の備品にショックを受けているという話も聞いております。これらは、暗黙に立川市での教育姿勢が子どもたちにメッセージとして送られているようなものだというふうに私は考えますが、御見解をお願いいたします。
◆委員(谷山きょう子君) やはりその子どもたち、科学センターを受講した子どもたちは特に、中学校に上がった瞬間に、余りにも備品の古さにびっくりするんですね。これから科学をやっていきたいというふうに思っている子どもたちにとっては、すごく衝撃的なことだと思いますので、やはり順次入れかえのほうをしていただきたいというのが要望です。
私が言いたいことは、これから子どもたちの未来は、今の職業の半分がなくなるというふうに言われています。人工知能AIを中心とした、今までは人・物・金ですが、人・情報機械の社会になると言われております。その中で、子ども時代にいかにさまざまな体験を積むかということが大切になってくると思います。
立川の教育として、科学センターのようなすばらしい取り組みがなされてきたという経緯もありますので、やはり科学センター受講者が中学校での理科学習に希望を持って取り組めるよう、環境をしっかりと整えていただきたいというのが要望でございます。それについての御見解をお願いいたします。
◆委員(谷山きょう子君) やはりきのうもその前も、予算でずっと言い続けてきているんですけれども、立川で子育てをしたいというふうに思えるまちの実践として、やはりこのような科学センターというすばらしい取り組みを立川はされております。そういった理科に関する環境の整備というのをぜひ強化していただきまして、今後とも教育に取り組んでいただくよう要望とさせていただきます。
以上です。
平成28年12月文教委員会
◆委員(中山ひと美君)
クラブ活動、体力だけじゃなく、これ以前にちょっと第4回宇宙エレベーターロボット競技会というのをいただきました。これ文化部のほうのクラブ活動と思うんですけれども、要するに科学センター教室というのが多分平成何年かから、もう昭和のときからできたんですね。これ、平成になりまして20年からかなりオープンになりまして、抽せんだったのが希望者全員にということで今もなお皆さんの努力で、先生の誠意でもってやっている。
これ、物すごいことじゃないですか。宇宙センターのこの、ここまで来るというのは、これはやはり今までの何十年もの成果だと思うんですね。これと同じで、やっぱり例えばサッカーなりバスケットなり授業もありますけれども、今は専科じゃないじゃないですか。要するに専科教育をなさってくださいという、体育の専科教育をということでお願いを要望していますけれども、美術と音楽はあるんですけれども、どうも体育はないんですよね。
平成28年6月 定例会
(稲橋ゆみ子議員) それから、科学教室というところでとても人数が増員となっています。そういった状況にあわせて、今回、大規模改修をするというところでの取り組みということは、十分そういったものも配慮しているのかどうか、その点についてお聞かせください。
(栗原教育部長)
科学センターでございますが、現在は、科学センター、理科室とは別室で設けているところでございますが、改修後につきましては、科学教育センターと理科室は兼務という形で運営をしていくということで改修をしていきます。
平成24年6月定例会
◆21番(大沢豊君) 次に、教育委員会の方にお伺いします。
つい最近知ったんですけれども、東京新聞が行います第14回教育賞に立川六中の岡村先生が選ばれたということであります。3月13日の新聞記事を読んで、私は大変うれしくなりました。
この岡村先生は、子どもたちにラジオを、小型のラジオですね、スピーカーのついていないイヤホン式のラジオをハンダごてなどを使ってつくってもらって、それを被災地に届けたということです。二つの意味でも大変すぐれた取り組みをされておられます。私は本当にこれは評価しますけれども、教育委員会のほうから何かあれば、お答えいただきたいと思います。
○議長(佐藤寿宏君) 教育部長。
◎教育部長(近藤忠信君) この六中の岡村先生につきましては、以前から、特にアマチュア無線の中では大変有名な先生でございまして、そういう中で子どもたちに科学の楽しさ、重要性を、部活動を通じながら指導しているところでございます。
立川市内の中学校の中では、部活動の中で科学的な部活動は余りないわけでございますが、特に六中のサイエンスの部活動につきましては、いろんな活動をしている中で、特に特徴的なものにつきましては、立川では小学校5・6年生に、科学センターを開設しているわけでございますが、その科学センターの中で、この六中の部活動の子どもたちが指導者と一緒になって、小学生にさまざまな科学の楽しさを教えている、そういう指導者の一人として活動しているというところが大変すばらしいところであるというふうに考えております。
○議長(佐藤寿宏君) 大沢議員。
◆21番(大沢豊君) 今、六中の取り組みあるいは科学センターの取り組みについて伺いました。私も子どものころ、ラジオをつくったり、あるいは自宅にある真空管ラジオを分解し、それを無線送信機に組みかえたりして、そういうことを楽しんでおりましたけれども、やはりそうしたことは、1回やってみるのとやってみないのでは全然違うことで、1回やれば、それが次にまた発展するという可能性があります。そうした指導のできる方をどんどんふやしていただいて、少しでも理科教育について、あるいは実験教育について取り組まれるようにお願いいたします。
また、最近は民間の事業者が理科教育あるいは科学教育に訪問事業をしているようですけれども、立川ではどうでしょうか。
○議長(佐藤寿宏君) 教育部長。あと2分ですから。
◎教育部長(近藤忠信君) わかりました。では2分以内で。
立川市におきましては、理科の指導の指導力向上にさまざまな研修等を活用しながら向上を図っております。
今、議員がおっしゃったように、企業の先生を招いた講習会もやっておりますが、それ以外にも、立川市にはかなり高度の指導ができる研究所、先生方がたくさんいらっしゃいます。例えば国立の極地研究所だとか、南極・北極科学館を活用した研修も実施しておりますし、それ以外にも、立川市におきましては、小中学校の教育研究会の中に理科部会というのがございまして、その理科部会の中で、お互いに理科指導の専門性を高める実技等の研修も実施しているところでございます。
また、昨年度、平成22年度におきましては、東京都の事業でございますが、コア・サイエンス・ティーチャー事業というのがございまして、理科の得意な好きな先生をそこに、立川市におきましても1人派遣いたしました。その先生が理科教育の教員に対する指導的のリーダーという位置づけになりましたので、今年度はそのコア・サイエンス・ティーチャーの先生を中心に、小学校の教員の理科指導の指導力向上を、研修会等を通じて図ったところでございます。
○議長(佐藤寿宏君) 大沢議員。あと三十少しですから。
◆21番(大沢豊君) 科学技術や機械工学の知識、宇宙へ進出するための技術や理論物理などの推進とその実証実験、これは最近のニュースでも大きく取り上げられています。
日本は今でも世界を大きくリードしている科学技術立国であります。しかし、これには後に続く若い学生、研究者を育てなければなりません。現状を見ると不安なところもあります。しかし、立川市はそうした取り組みをしっかりとやっておられるようなので、ますますそれを強めていただきたいというふうに思います。
終わります。
平成23年12月 定例会
◆23番(守重夏樹君)
先ほど、教育長のほうから、学校教育の中で子どもたちへ早期に正しく環境教育、環境を理解してもらう、そのような取り組みをされているというお話を伺いました。大変うれしく思います。
ただ、この科学の実験は、なかなか時間どおりにははかどらず、通常の授業時間では難しい面もあろうかと思います。そんな中の取り組みとして、先ほど教育長が述べられた科学センターの充実があろうかというふうに思います。
ことしの夏、八小で行われたNPO法人の科学教室などの応援をぜひされてはどうか、そんな思いがしております。私も見てまいりました。この科学教室では、児童、保護者も3日間の体験を堪能されていました。また、そのようなアンケート調査にも目を通すことができました。参加者がみんな満足されているようでしたが、その中には、実験に要する時間は個人差があり、それぞれが終了するまで時間を延長するなり、工夫をされておりました。
通常の授業ではこれらの時間のやりくりが大変であると考えますので、こういったNPO法人等が支援をされていくことで環境教育がもっと前に進むんではないか、そんな思いがありますけれども、ぜひお考えをお聞かせください。
○議長(堀憲一君) 教育長。
◎教育長(澤利夫君) 科学センターにつきましては、立川市も非常に力を入れておりまして、参加を希望する子どもたちはすべて受け入れる体制をとっておりますので、今後とも、今御案内がございましたNPO法人、それから立川出身の退職された大学の先生の講義なんかもやったこともございますし、いろいろな意味で、先ほど地域資源という話がございましたが、このNPO法人も含めて地域資源、個人も含めて活用を何とかこの科学センターの中でやっていきたいというふうに思っています。
○議長(堀憲一君) 守重議員。
◆23番(守重夏樹君) それでは、要望させていただきます。
この自然エネルギーの開発導入は、将来的な大きな課題であろうかというふうに思います。そのためには、今お話ししましたように、立川っ子が環境教育に関心を持っていただく、そんな方向づけがまず必要ではないかな、そんなふうに思っていますので、ぜひとも教育委員会も積極的な取り組みをされることを要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。
平成21年9月 決算特別委員会
◆委員(中山ひと美君)
科学センターも立川では物すごく人気がありますが、それとどんな感じで連携とっていらっしゃるのか、お尋ねしたいと思います。
◎指導課長(樋口豊隆君)
それから次でございますけれども、理科教育というところでございますが、理科の支援員の配置につきましては平成20年度は小学校13校、21年度は小学校14校に配置しています。これは小学生の理科離れを防ぐ、理科に興味、関心を持たせるというような趣旨で進められております。このことが関連すると思いますけれども、以前も御答弁させていただきました小学校5年生ですが、都教委の意識調査で理科が楽しいという子どもが16年度は45.2%でした。平成20年度は58.4%です。年々理科が楽しいという子どもは増加しております。それと連動するように科学センターも18年度の参加者は91名、20年度は124名、21年度は127名、立川の1つの特色として小学生は理科が好きという子が他の教科に比べると物すごく高いというのは立川市の1つの特色であるというふうに思っていますし、その効果、今後もまだ期待できるのではないかなというふうに思います。
平成21年3月 文教委員会
◆委員(中山ひと美君) それでは、2点、平成21年度から中学校のハートフルフレンド導入について、わかることをすべて教えてください。
それから、2件目、小学校の科学教育センター、成果と今後についてわかる範囲でお知らせください。お尋ねします。
それから、小学校の科学教育センターでございますが、小学校科学教育センターは、昭和43年、1964年4月に立川市独自で設置されまして、現在は第八小学校をセンター校にして、本年度、小学校5年生71名、6年生53名が二つのグループに分かれて、土曜日などを活動、主に年間18回、理科や科学に関する実験、体験、研究発表などの活動を行っています。
科学教育センターの成果でございますが、児童では、科学に対する興味、関心が今まで以上に高まったとか、ほかの学校の小学生と横のつながりができて友達の輪が広がったとか、協力して研究活動ができるようになった。それから、イカの解剖実験、それを行って、命の神秘とか生命の尊重、そんなことも学んだとか、秋川に行って、自然を守ることの大切さとか、自然の中での動植物愛護、そんなことを考えたとか、あとやっぱり学校の先生、要するにさまざまな先生方から学べることで、新たな発見とか科学の楽しさ、自然の大切さを学べた。もっと調べたいことができたから、来年も申し込んで研究したいなど、作文に子どもたちが書いております。
また、指導に携わった先生においても、やっぱり小学校の先生方は、全科を教えるわけですが、特に理科のやっぱり自分自身の研究、そして研修の場にもなったし、さまざまな子どもたち、参加している子どもたちのいろいろな意見から、やっぱり自分たちがどう指導していったらいいか、その指導を学ぶこともできたと、そんなような成果を報告されております。
今後についてでございますが、平成21年度は、本年度と同じように年間12日、講座数は18回開催する予定でございます。また、予算面で、指導員の先生方、本年度よりもふやして、参加する子どもたちが全員が参加できるような体制をとって、さらに子どもたちの研究意欲とか、期待にこたえてまいりたい、そのように考えております。
以上です。
◆委員(中山ひと美君)
それから、小学校の科学教育センター、これ本当に私、感想文をちょっと読む機会がありまして、読ませていただきました。本当に子どもたちが素直に感想を述べていて、今、指導課長のほうから紹介もありました。本当にこれも物すごく歴史のある科学センター、立川市においては歴史のある科学センター教育であるなと思っております。何よりおうちに帰って、お母さん、お父さんに話す機会がふえたというのもありました。すごいなと思ったんですけれども、ことわざにもあるけれども、やっぱり見てやる、そして楽しみながら実感できるのが、教科書よりも断然いいことだと思います。私、これ5年生が書いた文章とは思えないぐらいな感想だなと思っております。
今、指導課長から、なるべく全員できるようにというのは、もう応募者全員やっていただけるということなのでしょうか。--ありがとうございます。これぜひ理科離れしている、科学離れしている今の世の中の中で、やはり立川市の子どもたちがこんなに興味を持ってできるというこのセンターは、もちろん指導員の皆さんの御協力のもと、そして両親にもみんなに感謝して、子どもたちが生き生きと実験できるというこのシステム、拡大、またみんなができるようにやってほしいなと思います。
◎教育長(澤利夫君)
ただいま、理科教育、科学教育センターから始まりまして、教育センター構想についてのお尋ねでございますけれども、この教育センター構想については、市長公約にもございますけれども、これまで基本計画等におきましても、多用な教育課題に対応するということで、目指すとしておりました。
ここで、幾つか具体的に我々としてもセンター構想を取りまとめている段階に、原案ですけれども、取りまとめている段階にございますけれども、やはりもう各市においてほとんどの--ほとんどというんですかね、もうそういったものありますので、ないのはうちと幾つかの市でございますので、そういう意味では早急に設置したいというふうに思っております。
ただ、余り事業内容を幾つかこの間も御紹介申し上げましたけれども、十幾つあるんですが、しかしそれを全部フルメニューでフル装備でセンター設置というのは、なかなか今の時代、難しい面もありますので、ですから今、委員御発言なさったように、やっぱり既存施設を使って、ナショナルセンターあるいはブランチも含めて、やっぱりいろいろなところでまずはつくっていきたいというふうに思っております。