カズオ・イシグロ「人間は皆、“自分には存在する権利がある”と証明したいのです」
7/31(土) 12:40配信
6
Photo: David Cooper/Toronto Star via Getty Images
3月に世界同時発売されたカズオ・イシグロの最新作『クララとお日さま』は、オバマ元米大統領の「お気に入りの書籍リスト」入りするなど、世界的に注目を集め続けている。 【動画】カズオ・イシグロのノーベル賞受賞スピーチ 作品内で思わず繰り返してしまうテーマや、父親になったことが作家としてのキャリアに与えた影響など、率直な質問を米紙「ワシントン・ポスト」がぶつけてみた。 『日の名残り』や『わたしを離さないで』で有名なノーベル賞作家、カズオ・イシグロの8作目の小説『クララとお日さま』は、またもやベストセラーとなった。 人間のティーンエイジャーの孤独を癒やすために開発された、太陽光で駆動する「人工フレンド」の物語は、人間が経験する深遠な問題を掘り下げている。 それは、愛する人を守り、世話したいという本能や、見てもらいたい、理解してもらいたいという欲求、死という運命の痛切さなどだ。寓話的で心を動かすこの作品は、読書会での議論にもぴったりだ。 このたび、イシグロはロンドンの自宅からインタビューに応じ、自作について、ノーベル賞について、親であることについて、そしてパンデミックの時代をどう乗り切っているかなどについて語ってくれた。
皆「自分はまっとうに生きてきた」と言いたい
──『クララとお日さま』を読んだとき、あなたの過去の作品を思い出しました。私たちの存在の権利を証明すること──つまり、どこであろうと今いるこの場所に私たちはいる資格があり、私たちの存在には目的があって決してむだではなかったのだと証明すること──それを切に望む気持ちが、あなたの作品の多くで中心的なテーマになっているようですね。 『日の名残り』の執事も、『わたしを離さないで』のクローンも、そのような気持ちを抱いていると思います。そして本作の人工知能の友達、クララもです。こうしたテーマでたびたび作品を書くのは、どうしてだと思いますか? そのテーマに何度も回帰していると、ご自分では思いますか? そうですね、まさにおっしゃる通りです。おそらく違う角度から、同じテーマに繰り返し取り組んでいるのだと思います。 存在の権利を証明したいという思いが人間にあるというのは、興味深いばかりか、たとえそれが間違った方向へ向かったとしても、素晴らしいことだと思うのです。それがあるから、私は人間を愛しているのです。 私たちは牛や羊などの家畜ではありません。ただものを食べて、子孫を残して、死んでいく、それだけでは満足しないのです。私たち人間は、つねに自分にこう問いかけます。「自分は何かの役に立てただろうか? 自分はまっとうな人間だろうか……?」と。犯罪者であっても、「自分はまっとうな犯罪者としてやれているか? 仲間に筋を通せているか?」と自問するでしょう。 これは人間固有の考え方です。キャリアに関してだけではなく、親として、きょうだいとして、友人として、配偶者として、自分はまっとうに生きてきた、みんなそう言いたいのだと思います。 ──自然界や人間社会を正確に理解しようとする機械、そんなテクノロジーと生身の人間を並置するというのは、物語を紡ぐのに絶好の設定でしょうね。 これは近年の人工知能の進歩を念頭に置いているのでしょうか? また、テクノロジーは恐怖の対象なのか、歓迎すべきものなのか、あるいはその両方か、どう考えますか? 両方だと思います。私はAIや遺伝子技術などについて読んだり、話し合ったりするのに熱中してきました。長年、そのような分野に興味があったのです。ただ、それに関する本を書いたり、どんな形であれ、それが自分の小説に登場したりするとはまったく予期していませんでしたが。 怖いなと思うこともあります……それでも、そうしたテクノロジーは、特に医療の面では素晴らしい可能性を秘めているでしょう。もちろん、危険も大きいです。 だから、テクノロジーから利益を得られるように、テクノロジーが文明を破壊するということがないように、社会全体が自分たちの方向性を調整しなければなりません。
カズオ・イシグロ「人間は皆、“自分には存在する権利がある”と証明したいのです」
7/31(土) 12:40配信
6
Photo: David Cooper/Toronto Star via Getty Images
3月に世界同時発売されたカズオ・イシグロの最新作『クララとお日さま』は、オバマ元米大統領の「お気に入りの書籍リスト」入りするなど、世界的に注目を集め続けている。 【動画】カズオ・イシグロのノーベル賞受賞スピーチ 作品内で思わず繰り返してしまうテーマや、父親になったことが作家としてのキャリアに与えた影響など、率直な質問を米紙「ワシントン・ポスト」がぶつけてみた。 『日の名残り』や『わたしを離さないで』で有名なノーベル賞作家、カズオ・イシグロの8作目の小説『クララとお日さま』は、またもやベストセラーとなった。 人間のティーンエイジャーの孤独を癒やすために開発された、太陽光で駆動する「人工フレンド」の物語は、人間が経験する深遠な問題を掘り下げている。 それは、愛する人を守り、世話したいという本能や、見てもらいたい、理解してもらいたいという欲求、死という運命の痛切さなどだ。寓話的で心を動かすこの作品は、読書会での議論にもぴったりだ。 このたび、イシグロはロンドンの自宅からインタビューに応じ、自作について、ノーベル賞について、親であることについて、そしてパンデミックの時代をどう乗り切っているかなどについて語ってくれた。
皆「自分はまっとうに生きてきた」と言いたい
──『クララとお日さま』を読んだとき、あなたの過去の作品を思い出しました。私たちの存在の権利を証明すること──つまり、どこであろうと今いるこの場所に私たちはいる資格があり、私たちの存在には目的があって決してむだではなかったのだと証明すること──それを切に望む気持ちが、あなたの作品の多くで中心的なテーマになっているようですね。 『日の名残り』の執事も、『わたしを離さないで』のクローンも、そのような気持ちを抱いていると思います。そして本作の人工知能の友達、クララもです。こうしたテーマでたびたび作品を書くのは、どうしてだと思いますか? そのテーマに何度も回帰していると、ご自分では思いますか? そうですね、まさにおっしゃる通りです。おそらく違う角度から、同じテーマに繰り返し取り組んでいるのだと思います。 存在の権利を証明したいという思いが人間にあるというのは、興味深いばかりか、たとえそれが間違った方向へ向かったとしても、素晴らしいことだと思うのです。それがあるから、私は人間を愛しているのです。 私たちは牛や羊などの家畜ではありません。ただものを食べて、子孫を残して、死んでいく、それだけでは満足しないのです。私たち人間は、つねに自分にこう問いかけます。「自分は何かの役に立てただろうか? 自分はまっとうな人間だろうか……?」と。犯罪者であっても、「自分はまっとうな犯罪者としてやれているか? 仲間に筋を通せているか?」と自問するでしょう。 これは人間固有の考え方です。キャリアに関してだけではなく、親として、きょうだいとして、友人として、配偶者として、自分はまっとうに生きてきた、みんなそう言いたいのだと思います。 ──自然界や人間社会を正確に理解しようとする機械、そんなテクノロジーと生身の人間を並置するというのは、物語を紡ぐのに絶好の設定でしょうね。 これは近年の人工知能の進歩を念頭に置いているのでしょうか? また、テクノロジーは恐怖の対象なのか、歓迎すべきものなのか、あるいはその両方か、どう考えますか? 両方だと思います。私はAIや遺伝子技術などについて読んだり、話し合ったりするのに熱中してきました。長年、そのような分野に興味があったのです。ただ、それに関する本を書いたり、どんな形であれ、それが自分の小説に登場したりするとはまったく予期していませんでしたが。 怖いなと思うこともあります……それでも、そうしたテクノロジーは、特に医療の面では素晴らしい可能性を秘めているでしょう。もちろん、危険も大きいです。 だから、テクノロジーから利益を得られるように、テクノロジーが文明を破壊するということがないように、社会全体が自分たちの方向性を調整しなければなりません。
「キャリアのために子供を持つのを避けるのは違う」
──『クララとお日さま』では、親子関係が物語の核の一つになっています。父親であることは、作家としてのあなたにどのように影響しましたか? もし親という立場を経験しなかったら、自分がどのような人間になっていたのかも、どのような作家になっていたのかも想像がつきません。 親になると、ものの見方が変わるのです。感情的にも、知的にも、世界が違って見えるようになります。また、長期的にものを考えるようになると思います。自分の人生のスパンだけでなく、自分の子供、孫、ひ孫の人生のスパンでものを見るようになります。 人生に対する見方も、私たちの存在そのものも、すべてが変化するようです。そしてそれは、今言ったような共感的、感情的なレベルで変化するのです。 子供を持ってしまったらキャリアが台無しになると言う作家にときどき出会いますが、それはとんでもない間違いだと思います。ただ座って一定の量の文章を生み出すことだけが、作家としてのキャリアだと考えているなら別ですけど。 ──とはいっても、ときには執筆の邪魔になってしまうこともあるのではないですか。 (笑)芸術家の創作努力とは、人生を経験し、それを反映しようとすることです。子供がいない作家は深みのある作品を書けない、とは言いません。子供がいなくても素晴らしい作品を書く人はとてもたくさんいます。 ただ、作家としてのキャリアに良くないと考えて、子供を持つのを避けようとするのは違うのではないか、と思います。
文学の意義を考えて不安になる
──2017年のノーベル賞の受賞スピーチであなたは、ノーベル賞とは「人類共通の努力に対して偉大な貢献をした」しるしだと語っていました。その「努力」とは何でしょうか? あらゆる分野をまたぐ究極の名誉だと考える人もいる、この偉大な賞をいただいてからというもの、私は自分だけではなく文学という活動が、医学、物理学、化学、そしてもちろん平和と並んで、こうした名誉に値するものなのかどうかを考え続けてきました。他にも、現代になって加えられた経済学賞もありますね。 もちろん、文学も同じように重要だと言いたいのですが、真夜中にふと不安になります。なぜかというと、もし医学がなければ、現実に問題が生じます。ほかの科学の諸分野や、平和な状態がなかったとしても同様でしょう……でも文学、これは本当にそこに並ぶ資格があるのか? そして私がそれを代表していいものか? そう考えてしまうのです。 けれども長年言っているのですが、読書がなければ、文学がなければ、人間同士のコミュニケーションにおいてきわめて重要なものが欠けることになります。 私たちは、ただ事実を知ればそれでいいというわけではありません。お互いの思いとか、感情をどうにかして分かち合えるようにならなければならないのです。さまざまな状況で人が何を感じるか、お互いに伝え合えなければなりません。そうでないと、知識を持っていても、それをどう使えばいいかわからなくなります。 映画のストーリーを作るにせよ、会ったときに相手に話すストーリーを作るにせよ、これは非常に基本的なことです。それができなくなったら、まずいことになるでしょう。私たちはとてつもなく孤独になり、文明としての機能を果たせなくなってしまいます。 ──朝起きて、さあ一日を始めようと最初に思ったとき、あなたのモチベーションを高めているものは何ですか? みんなそうだと思いますが、パンデミックやら何やらで、私は人とのつきあいがなくなってしまっています。こういう状況でなければ、楽しみなイベントとか、会いたい人に会うのを楽しみにしながら一日を始めることもよくありました。知らない人や旧友や家族と話すのは好きですから。 人と会話をすると、つねに新しいことを知れるので、わくわくします。最近では、パンデミックのことだけでなく、欧米の社会がどこに向かっているのか、いろいろと考えさせられることがあります。 私たちはとてもたくさんの難題に直面していて、憂鬱な気分になることもあるでしょう。けれども──不謹慎な言い方はしたくないのですが──それが私の一日の活力になっているのです。 「この問題についてもっと深く知ってみよう。今読んでいるこの本は素晴らしいし、そこに載っている考え方もおもしろい」というようなことを考えています。 この1年ほどの間にひどいこともたくさん起こりましたし、多くの人が大切な人を失いました。ですが、決して考えるべきことのない時代などではありません。
谷口ジローと遠﨑史朗による山岳マンガの傑作『K』(ケイ)、ヤマケイ文庫で復刻。プロ登山家・竹内洋岳氏の特別寄稿も収録【山と溪谷社からのご案内】
2021年07月11日(日)
山と溪谷社は、長らく入手困難となっていた山岳マンガの傑作『K』(谷口ジロー・画、遠﨑史朗・作)を復刻し、2021年7月10日に刊行しました。
本作は、K2北壁で遭難した石油王の息子の救助譚にはじまり、プモ・リ北壁、エベレスト南西壁、マカルー西壁、そしてカイラスで遭難者の救助に挑む、国籍も名前も不明のクライマーKの物語です。
谷口ジローはヒマラヤの高峰の大きさや岩壁の高さを緻密に描写し、登山者のみならず、読む人すべてに圧倒的な山の凄まじさ、迫力を伝えます。また遠﨑史朗は、主人公のKを単なるスーパーマンとして設定していません。恐怖に震えるときもある、謙虚で誠実な人間としてKを描いています。ふたりの名匠の手による迫真のクライミング場面、そしてKが見せる数々の表情は、多くの人の心をうってやみません。
本作品はいまから35年前、1986年に連載が開始。1988年にリイド社より単行本化されました。その後、カイラス編を追加して1993年に双葉社より再刊されました。本作は双葉社版を底本としております。
なお今回の復刻にあたり、特別寄稿と文庫解説を収録しております。特別寄稿は、8000m峰14座全山登頂を日本人として初めて成し遂げたプロ登山家・竹内洋岳氏が自らの高所救助体験を織り込んだ「〝K〟という未知の存在」。文庫解説は、山岳マンガ・小説・映画評論家のGAMO氏による「異才の人 谷口ジロー」です。稀代の山岳マンガである本作品を「ヒマラヤ登山」と「山岳マンガ」というふたつの視点から深く掘り下げ、新たな復刻版としてお届けいたします。













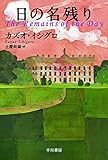








![カズオ・イシグロ 文学白熱教室 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51gzzUDg6IL._SL160_.jpg)










