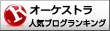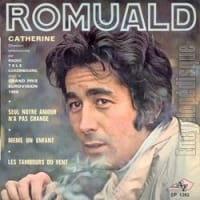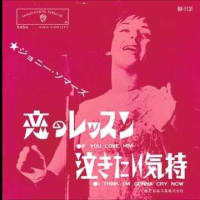各地の地域団体・・・自治会、町会、町内会など呼び方は様々でしょうが、おおかた何処の地域にも昔からの「隣組」的な自治団体があると思います。
山間部などでは「区」という名称で、かつての「大字」単位くらいの行政組織もあるようです。
私の住む東京近郊の市では、直ぐ隣が23区の一つですので、戦後の高度成長時代には住都公団の団地や民間企業の分譲地、田畑を潰して農家が建てた貸家やアパートなどに、全国から移り住む人たちで溢れかえり、旧来の「隣組」は崩壊。改めて町会を組織したのですが、広報、ゴミ、治安、清掃など、行政が直接処理するようになれば、ますます町会の役割は減少し、加入する世帯も減ります。
結局、各種の「お祭り」やイベント、子供や高齢者にターゲットを絞った行事の開催などや、防災訓練、避難訓練などの災害対策・・・といったことが中心になります。最近は大きなマンションや団地の自治会などとの連携も出来るようになりましたが・・・
10世帯ていどで「組」、10組くらいで「区」、「区」が15区で「町会」を形成しています。「組」はそれぞれ責任者を毎年選んで頂き、「区」長さんは町会の役員になって行事などを運営しています。当然経費や様々な寄付金もそれぞれの単位で集めて頂いています。その手間の対価として僅かながらの「手当金」を年一度支給するのですが・・・これが大変、会計担当の私が一番苦労する仕事です。何が・・・手当金は世帯数にスライドしますので、各組毎の金額を計算すること。各組に支給するために金種を集計すること。その金種表を持って銀行から大量の重い硬貨を運ぶこと。その硬貨を各区、組に振り分けていく作業・・・です。
ここで、ようやくテーマにたどり着きました。そう、銀行は昨年からこうした硬貨の出入金は枚数に応じて手数料がかかるようになったことです。
窓口の係員は「手数料がかかりますが・・・」と言ってくださいますが、大汗をかいて集計した金種表どおりに揃えないと支払いは出来ませんから仕方ないですよね。
支払いの席で役員同士「銀行はセコくなった・・・」とぼやいていたのです。するとひとりの役員、この人は地区にある小さな神社の会計を担当しているのですが、「お賽銭は大変だよ!ご縁を担いで5円玉50円玉が多いし。だから入金する時に手数料を沢山取られる!」と。
そこで・・・来年からは、手当の支払時期を変えて新年のお賽銭と町会のお金を両替すれば手数料がかからない!ということになりましたが、金種のミスマッチが多いと思うし・・・それに、誰がこの作業をやるんでしょうかね?手数料は頂けないのかな?