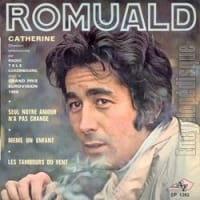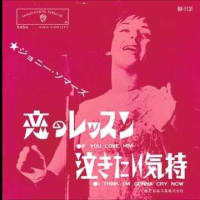故安倍晋三氏が首相についてから、殊更政治家の言葉が軽くなるとともに嘘がはびこるようになってしまったように思います。今また故安倍元首相に重用されていた高市氏大臣が追及されています。まことに情けない限りですが、かつて故安部氏が繰り返したような「捏造」や「辞任」などの言葉に『重み』のない使い方は、ことさら自己弁護のために強い表現によって相手をひるませる、『恫喝』のようなやり方に感じます。しかし、いまや言葉の軽さゆえに自縄自縛に陥っているのでしょうか?
以前も岸田首相が好んで使う「丁寧な説明」という中身のない言葉について、同じような言葉の軽さをこのブログで書いたと思いますが、今なぜここまで真実味のない軽くて外面だけを飾った言葉が多いのでしょうか。
ふと感じたことは、今の政治家には「文人」が全くいないな~ということでした。かつて中曾根康弘氏は俳句好きで知られていました。
その中曽根氏の官房長官を務めたことがある藤波孝生氏も俳人として有名でした。角川書店やふらんす堂から句集も数冊出しています。また、中曽根氏の国会での証人喚問で、質問に立った共産党の議員が藤波氏の俳句「控えめに 生くる幸せ 根深汁」 を引用しました。
一方短歌のほうでは、長く自民党税制調査会の会長を務めた山中貞則氏は歌集も出す歌人でした。豪快な人柄と税制通で存在感のある政治家でした。
万葉の時代もそうでしたが、本当にトップに座るような人よりも、「癖のある政治家」に文人は多かったようです。例えば、大伴旅人、家持の親子も旅人は大納言。家持は中納言と高級官僚兼政治家を務めています。
しかし、今の時代、こうした誰もが一目置かざるを得ない癖のある・・・言葉の重みが一味違う・・・文人政治家と目されるような人は知る限り誰もいないように思います。であればこそ、いま必要としているのは言葉の重さを知ることができる文人である政治家・・・なのかもしれませんね?