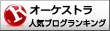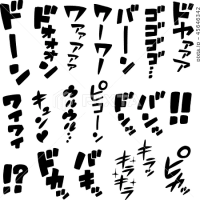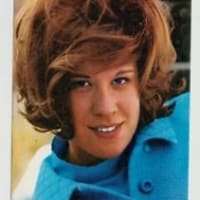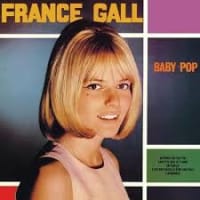第二の人生の趣味を楽しんでいる高齢者の方、あるいは「俳句甲子園」を目指しているような若い方。様々な方が俳句を楽しんでいらっしゃいます。万葉の時代の「歌」や平安の「和歌」その後の「連歌」「俳諧」から現代の「短歌」「俳句」まで、日本は世界でも珍しい短詩・定型詩の盛んな国です。新聞に短歌・俳句の欄があって沢山の市井の民が投稿しているなんて国はほかにないでしょうね?
さて、私もまた俳句を楽しんでいる老人の一人ですが、俳句に親しむ方の多くは「結社」と呼ばれる「座」のメンバーとなり、句会に出席して特定の句誌を主宰するリーダーたちの指導・添削を受け、その句誌に掲載してもらう形で参加するか、またはそうした結社には参加せず、総合俳句誌、新聞俳句欄、NHKの俳句講座などに応募して腕を磨くという形か、概ね二つの方向に分かれるかと思います。
私も前者の方向、公民館の俳句講座に入り、引き続き句会に参加。講座や句会の指導者が関与している小さな結社に入りその結社誌に掲載してもらう・・・という形で俳句を作っています。
しかし、隔月に発行される俳句誌に掲載原稿を送っても、指導者集団からかなりの添削・修正が入ってから結社誌に掲載されます。確かに私は初心者ですし、数々の文法上の間違いや適切でない用語、韻律の悪い吟い方もありますから、直していただけると「なるほどこうすればいいのか!」と気づくことも多くあります。しかし、自分では絶対に使わない~使いたくない言い回しになったり、まったく知らない季語や古語を使ったりした添削になると果たしてこれは自分の句かな?と感じます。たとえそれが素晴らしい句へ変わっていたとしてもです。
ただ、こうしたことは結社では当たり前のことのようですね?多くの仲間たちはこのことを特に疑問に思っていないようです。もちろん、修練の場である句会では自由に批評しあい「こうした方がよくなるのではないか?」「この表現はつまらない。」などと意見を戦わせたり指導者の指導を受けることが重要でしょう。作者が意見や指導に納得して推敲し修正する、のは当然です。しかし、いったん句誌に原稿として渡したらしたらたとえ指導者といえども「勝手に」修正するのはどうなのでしょうか?もちろん作者と連絡を取り合い修正内容を確認したり、その修正で良いかどうか議論するとかなら別ですが、何も言わずに句を修正して掲載するのは、いかにつまらない駄作であれ、また、指導者や主宰といえども僭越であり修練に役立たないと思いますが?もし、掲載の水準に達しないのであれば、無理に掲載せずにボツとすればよいのではないでしょうか?俳句を楽しんでいらっしゃる方々はどのように考えているのでしょうね?