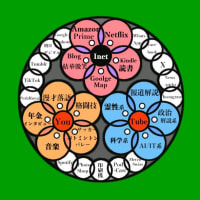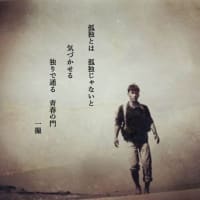じつに『自分なり』で適当な考えであるが、
私にとっては、釈尊の死後、500年を経て難産の末ようやく『大輪の華』を咲かせたものが『大乗仏教』であって
例の『天上天下唯我独尊』の話もじつはこの時のことを象徴し、『悟り』は誰もが咲かす『華』であることを証明してみせた
釈尊の『えっへん!』という喜びの表現ではなかったか・・・。(私自身はまた別の解釈もあるが…)
別な言い方をすれば、彼の死後5世紀を経て『悟った』人間が沢山出現し、誰でも『悟りの華』は咲かすことが出来ると、確信した時期であったろう。
故に、大乗経典に『法華経』、『華厳経』と『華』をテーマにし、なにより在家者が菩薩等を論破する主人公のお経『維摩経』が生まれたわけだ。
(この『維摩経』こそ後に『禅』を産む温床であったことは、いつかまた書きたい)
『人は何のために生きるのか?』という究極の『問い』に、人も『命の華』を咲かせる存在である・・・という簡単明瞭な『解答』を
全人類に向かって宣言したのが『大乗仏教』であり、中でも『禅』という『大輪の華』を後に咲かせる道を開いていった。
釈尊が自己の中に発見したのは後に『仏性』とも『仏法』とも名付けられる『悟り種』であったろう。
最初、釈尊は自分以外の人間には『無理』と思った節があるが、その迷いを払拭して後の45年の生涯を『悟りの華』の育成に捧げたのだ。
その結実が『大乗仏教』であった。
ある人は、『大乗経典』は仏陀自身の言葉ではないから、本当の仏教ではない・・・と主張するが
『悟り』や『仏性』が『拈華微笑』という以心伝心の『形』で伝えられる『法』であることが解れば、それが間違っていることがわかる。
『悟りの種』が大輪の『悟り華』を咲かすには・・・ 無我(の大地)+ 意識(の水)+ 感動(の光) などが必須であろうか。

先日、レマン湖畔で見かけた華。 一本の幹から桃色や黄色、よく観ると青い蕾(実?)もあって、美しい華(樹木?)であった。