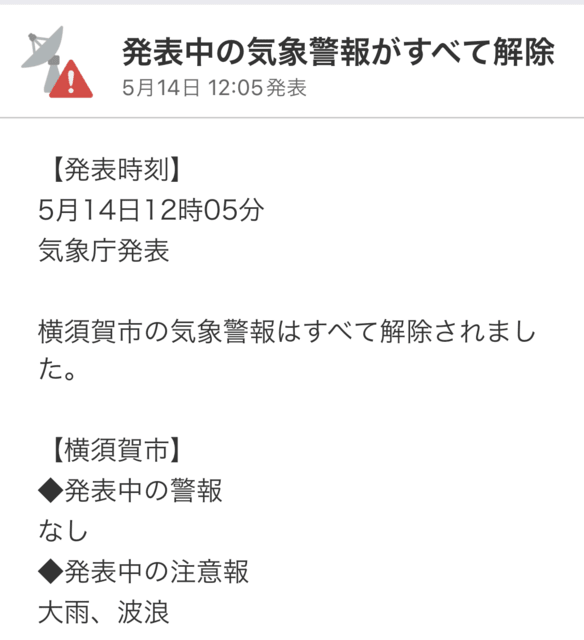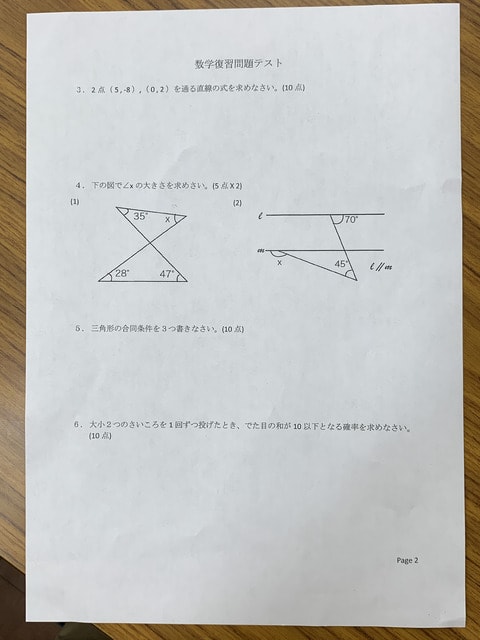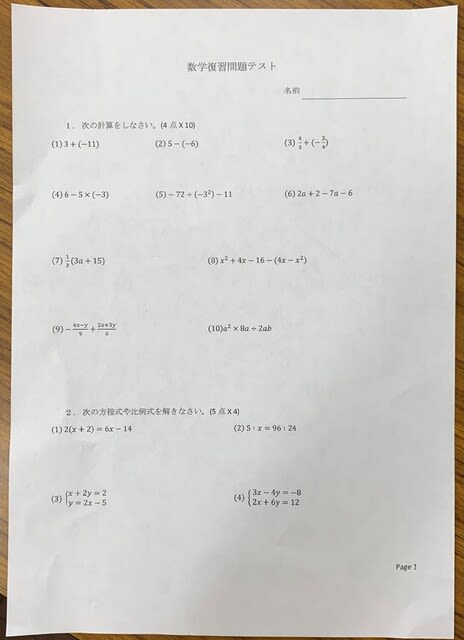起床 5:15
天気 曇り(起床時の気温 16℃) 日の出 4:36/日の入り 18:38






今日の朝刊







今日はブックオフ(粟田)で英語の参考書を探しに行って来たが一冊もなかった。
そのあと、プールへ行って、少し大回りして帰ってきた。
プール⇒北久里浜駅⇒衣笠通り⇒衣笠十字路・・・
運動量=1327kcal (16,898歩)





◆沖縄復帰50周年
●天皇陛下のお言葉全文 沖縄復帰50周年記念式典
令和の皇室
2022年5月15日 14:50
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE139XL0T10C22A5000000/ より

沖縄復帰50周年記念式典にオンラインで出席し、お言葉を述べる天皇陛下(15日午後、沖縄県宜野湾市)
天皇陛下の沖縄復帰50周年記念式典でのお言葉は以下の通り。
沖縄復帰50周年に当たり、本日、沖縄と東京をオンラインでつなぎ、記念式典が開催されることを誠に喜ばしく思います。
先の大戦で悲惨な地上戦の舞台となり、戦後も約27年間にわたり日本国の施政下から外れた沖縄は、日米両国の友好と信頼に基づき、50年前の今日、本土への復帰を果たしました。大戦で多くの尊い命が失われた沖縄において、人々は「ぬちどぅたから」(命こそ宝)の思いを深められたと伺っていますが、その後も苦難の道を歩んできた沖縄の人々の歴史に思いを致しつつ、この式典に臨むことに深い感慨を覚えます。
本土復帰の日、中学1年生であった私は、両親と一緒にニュースを見たことをよく覚えています。そして、復帰から15年を経た昭和62年、国民体育大会夏季大会の折に初めて沖縄を訪れました。その当時と比べても、沖縄は発展を遂げ、県民生活も向上したと伺います。沖縄県民をはじめとする、多くの人々の長年にわたるたゆみない努力に深く敬意を表します。
一方で、沖縄には、今なお様々な課題が残されています。今後、若い世代を含め、広く国民の沖縄に対する理解が更に深まることを希望するとともに、今後とも、これまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ、豊かな未来が沖縄に築かれることを心から願っています。
美しい海をはじめとする自然に恵まれ、豊かな歴史、伝統、文化を育んできた沖縄は、多くの魅力を有しています。沖縄の一層の発展と人々の幸せを祈り、式典に寄せる言葉といたします。
●沖縄復帰50年 → 沖縄について知っておきたいこと
https://www.asahi.com/edua/article/14618300 より

沖縄の歴史を知ろう
50年前の5月15日、太平洋戦争のあと長くアメリカに統治されていた沖縄が日本に復帰しました。今年が復帰50周年となり、沖縄では当日に復帰記念式典が行われます。そのほかにも今年は全国で沖縄をテーマにした行事がたくさん予定されています。沖縄の人は沖縄以外の日本のことを「本土」といいます。沖縄には、本土と違う歴史や課題があります。この機会に沖縄についての知識を深めるといいと思います。
「沖縄について知っておきたいこと」ですが、わたしが思いつくのは四つです。①昔は独立した王国であったこと②太平洋戦争で大きな被害を受けたこと③アメリカ軍基地が集中していること④観光以外の産業が大きく育っていないこと、です。
まず、沖縄の歴史です。北は奄美諸島から南は八重山列島まで、琉球諸島には古くから人が住んでいました。12世紀ごろには豪族があらわれはじめ、1429年に尚巴志(しょうはし)が豪族を統一して、尚家を頂点とする琉球王国ができました。琉球王国は中国、日本、朝鮮、東南アジアと貿易をし、独自の海洋王国を築きました。その中心が、沖縄本島の那覇市郊外に位置する壮麗な首里城でした。
その首里城が約3千人の薩摩藩の軍勢に占拠されたのが1609年です。薩摩藩は琉球の貿易の利権を奪おうとしたと考えられています。それからの琉球王国は中国との君臣関係を維持しながら、実際は薩摩藩と徳川幕府に従属しているという微妙な国際関係の中で存続しました。
しかし、明治維新により成立した日本政府が1879年に軍隊を派遣し、首里城から国王を追放して、沖縄県としました。軍事力を使って琉球の帰属をはっきりさせようとしたのです。これによって450年続いた琉球王国は滅んで、沖縄は日本の一部となりました。日本史ではこれを「琉球処分」といいます。
沖縄の歴史でもうひとつ覚えておかなければならないのは、太平洋戦争における沖縄戦です。1941年12月8日、日本軍がアメリカ・ハワイの真珠湾にある軍事基地を奇襲攻撃して太平洋戦争は始まりました。当初は日本軍が進撃し、東南アジアから南太平洋の島々まで支配下に置きましたが、そのうち物量に勝るアメリカ軍に押され始めます。
日本は「本土防衛」のために沖縄本島や離島に基地や陣地をつくっていました。日本の敗色が濃厚になっていた45年3月26日、アメリカ軍は沖縄本島の西にある慶良間諸島に上陸、4月1日にはついに沖縄本島に上陸しました。日本軍は本土決戦の準備時間を得るために戦闘を長引かせようと抵抗しましたが、アメリカ軍とは大きな力の差があり、6月23日に完全に制圧されました。
沖縄戦は、太平洋戦争で最大規模の地上戦でした。そのため、被害は大きく、20万人あまりの人が亡くなったとされています。そのうち沖縄県民は、一般住民が約9万4千人、沖縄出身の軍人軍属が約2万8千人で、あわせて約12万2千人とされています。当時の沖縄県の人口は約48万人ですので、県民の4人に1人が亡くなったことになります。6月23日は「沖縄慰霊の日」として、平和を考える日になっています。
●米軍統治下における沖縄の状況について
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/tyosa/documents/p05.pdf より
戦後すぐの昭和20年(1945年)から昭和24年(1949年)までの5年近く、本土では戦後の復興政策が図られる中、沖縄はほとんど放置状態で「忘れられた島」と言われました。これは、アメリカの軍部と政府側の調整に時間がかかり、明確な統治政策が図られなかったためです。
その後、昭和24年(1949年)5月にアメリカ政府は沖縄の分離統治の方針を決め、昭和25年(1950年)2月にGHQが沖縄に恒久的基地を建設するという声明を発表し、沖縄の分離統治を決定しました。この時から米軍による沖縄の基地化が進んでいきました。
昭和27年(1952年)にサンフランシスコ講和条約により日本は独立国としての主権を回復しますが、その代償として、沖縄は日本本土から分断され、米国の施政権下に置かれました。沖縄には日本国憲法の適用もなく、国会議員を送ることもできませんでした。
一方、経済においては、基地建設を進める上で本土への支払いがアメリカに有利になるよう強いドルの政策が取られていました。実態に合わない強いドルの影響で、沖縄では製造業が育たず、基地依存の輸入型経済という環境になってしまいました。沖縄県公文書館提供

キャンプ桑江での通貨切替(現・北谷町) 昭和33年(1958年)那覇市歴史博物館提供

行進を続ける米兵(現・沖縄市) 昭和35年頃(1960年)
また、米軍の施政権下におかれた沖縄は、27年間もの間、日本政府から十分な支援を受けることができませんでした。
その結果として、昭和47年(1972年)に本土に復帰した時の沖縄は、道路、港湾、学校、病院、住宅など社会資本のあらゆるものが不足していた状況でした。
そこで復帰以降、沖縄が持つこのような特殊事情を踏まえ、格差の是正、沖縄の自立的発展の基礎条件の整備等を目的として、3次にわたる沖縄振興開発計画及び沖縄振興計画の実施により沖縄の振興が図られてきました。
天気 曇り(起床時の気温 16℃) 日の出 4:36/日の入り 18:38






今日の朝刊







今日はブックオフ(粟田)で英語の参考書を探しに行って来たが一冊もなかった。
そのあと、プールへ行って、少し大回りして帰ってきた。
プール⇒北久里浜駅⇒衣笠通り⇒衣笠十字路・・・
運動量=1327kcal (16,898歩)





◆沖縄復帰50周年
●天皇陛下のお言葉全文 沖縄復帰50周年記念式典
令和の皇室
2022年5月15日 14:50
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE139XL0T10C22A5000000/ より

沖縄復帰50周年記念式典にオンラインで出席し、お言葉を述べる天皇陛下(15日午後、沖縄県宜野湾市)
天皇陛下の沖縄復帰50周年記念式典でのお言葉は以下の通り。
沖縄復帰50周年に当たり、本日、沖縄と東京をオンラインでつなぎ、記念式典が開催されることを誠に喜ばしく思います。
先の大戦で悲惨な地上戦の舞台となり、戦後も約27年間にわたり日本国の施政下から外れた沖縄は、日米両国の友好と信頼に基づき、50年前の今日、本土への復帰を果たしました。大戦で多くの尊い命が失われた沖縄において、人々は「ぬちどぅたから」(命こそ宝)の思いを深められたと伺っていますが、その後も苦難の道を歩んできた沖縄の人々の歴史に思いを致しつつ、この式典に臨むことに深い感慨を覚えます。
本土復帰の日、中学1年生であった私は、両親と一緒にニュースを見たことをよく覚えています。そして、復帰から15年を経た昭和62年、国民体育大会夏季大会の折に初めて沖縄を訪れました。その当時と比べても、沖縄は発展を遂げ、県民生活も向上したと伺います。沖縄県民をはじめとする、多くの人々の長年にわたるたゆみない努力に深く敬意を表します。
一方で、沖縄には、今なお様々な課題が残されています。今後、若い世代を含め、広く国民の沖縄に対する理解が更に深まることを希望するとともに、今後とも、これまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ、豊かな未来が沖縄に築かれることを心から願っています。
美しい海をはじめとする自然に恵まれ、豊かな歴史、伝統、文化を育んできた沖縄は、多くの魅力を有しています。沖縄の一層の発展と人々の幸せを祈り、式典に寄せる言葉といたします。
●沖縄復帰50年 → 沖縄について知っておきたいこと
https://www.asahi.com/edua/article/14618300 より

沖縄の歴史を知ろう
50年前の5月15日、太平洋戦争のあと長くアメリカに統治されていた沖縄が日本に復帰しました。今年が復帰50周年となり、沖縄では当日に復帰記念式典が行われます。そのほかにも今年は全国で沖縄をテーマにした行事がたくさん予定されています。沖縄の人は沖縄以外の日本のことを「本土」といいます。沖縄には、本土と違う歴史や課題があります。この機会に沖縄についての知識を深めるといいと思います。
「沖縄について知っておきたいこと」ですが、わたしが思いつくのは四つです。①昔は独立した王国であったこと②太平洋戦争で大きな被害を受けたこと③アメリカ軍基地が集中していること④観光以外の産業が大きく育っていないこと、です。
まず、沖縄の歴史です。北は奄美諸島から南は八重山列島まで、琉球諸島には古くから人が住んでいました。12世紀ごろには豪族があらわれはじめ、1429年に尚巴志(しょうはし)が豪族を統一して、尚家を頂点とする琉球王国ができました。琉球王国は中国、日本、朝鮮、東南アジアと貿易をし、独自の海洋王国を築きました。その中心が、沖縄本島の那覇市郊外に位置する壮麗な首里城でした。
その首里城が約3千人の薩摩藩の軍勢に占拠されたのが1609年です。薩摩藩は琉球の貿易の利権を奪おうとしたと考えられています。それからの琉球王国は中国との君臣関係を維持しながら、実際は薩摩藩と徳川幕府に従属しているという微妙な国際関係の中で存続しました。
しかし、明治維新により成立した日本政府が1879年に軍隊を派遣し、首里城から国王を追放して、沖縄県としました。軍事力を使って琉球の帰属をはっきりさせようとしたのです。これによって450年続いた琉球王国は滅んで、沖縄は日本の一部となりました。日本史ではこれを「琉球処分」といいます。
沖縄の歴史でもうひとつ覚えておかなければならないのは、太平洋戦争における沖縄戦です。1941年12月8日、日本軍がアメリカ・ハワイの真珠湾にある軍事基地を奇襲攻撃して太平洋戦争は始まりました。当初は日本軍が進撃し、東南アジアから南太平洋の島々まで支配下に置きましたが、そのうち物量に勝るアメリカ軍に押され始めます。
日本は「本土防衛」のために沖縄本島や離島に基地や陣地をつくっていました。日本の敗色が濃厚になっていた45年3月26日、アメリカ軍は沖縄本島の西にある慶良間諸島に上陸、4月1日にはついに沖縄本島に上陸しました。日本軍は本土決戦の準備時間を得るために戦闘を長引かせようと抵抗しましたが、アメリカ軍とは大きな力の差があり、6月23日に完全に制圧されました。
沖縄戦は、太平洋戦争で最大規模の地上戦でした。そのため、被害は大きく、20万人あまりの人が亡くなったとされています。そのうち沖縄県民は、一般住民が約9万4千人、沖縄出身の軍人軍属が約2万8千人で、あわせて約12万2千人とされています。当時の沖縄県の人口は約48万人ですので、県民の4人に1人が亡くなったことになります。6月23日は「沖縄慰霊の日」として、平和を考える日になっています。
●米軍統治下における沖縄の状況について
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/tyosa/documents/p05.pdf より
戦後すぐの昭和20年(1945年)から昭和24年(1949年)までの5年近く、本土では戦後の復興政策が図られる中、沖縄はほとんど放置状態で「忘れられた島」と言われました。これは、アメリカの軍部と政府側の調整に時間がかかり、明確な統治政策が図られなかったためです。
その後、昭和24年(1949年)5月にアメリカ政府は沖縄の分離統治の方針を決め、昭和25年(1950年)2月にGHQが沖縄に恒久的基地を建設するという声明を発表し、沖縄の分離統治を決定しました。この時から米軍による沖縄の基地化が進んでいきました。
昭和27年(1952年)にサンフランシスコ講和条約により日本は独立国としての主権を回復しますが、その代償として、沖縄は日本本土から分断され、米国の施政権下に置かれました。沖縄には日本国憲法の適用もなく、国会議員を送ることもできませんでした。
一方、経済においては、基地建設を進める上で本土への支払いがアメリカに有利になるよう強いドルの政策が取られていました。実態に合わない強いドルの影響で、沖縄では製造業が育たず、基地依存の輸入型経済という環境になってしまいました。沖縄県公文書館提供

キャンプ桑江での通貨切替(現・北谷町) 昭和33年(1958年)那覇市歴史博物館提供

行進を続ける米兵(現・沖縄市) 昭和35年頃(1960年)
また、米軍の施政権下におかれた沖縄は、27年間もの間、日本政府から十分な支援を受けることができませんでした。
その結果として、昭和47年(1972年)に本土に復帰した時の沖縄は、道路、港湾、学校、病院、住宅など社会資本のあらゆるものが不足していた状況でした。
そこで復帰以降、沖縄が持つこのような特殊事情を踏まえ、格差の是正、沖縄の自立的発展の基礎条件の整備等を目的として、3次にわたる沖縄振興開発計画及び沖縄振興計画の実施により沖縄の振興が図られてきました。