When words leave off music begins.
BGM on "♪YouTube":
Vitali Chaconne [Arthur Grumiaux]




 :日本スリーデーマーチ(2011.11.04~06)の森林公園ルートの歩行は二日目(11/05)となるため、当日の武蔵丘陵森林公園は無料開園となります。
:日本スリーデーマーチ(2011.11.04~06)の森林公園ルートの歩行は二日目(11/05)となるため、当日の武蔵丘陵森林公園は無料開園となります。








 、サスガです!これからが楽しみですね。
、サスガです!これからが楽しみですね。










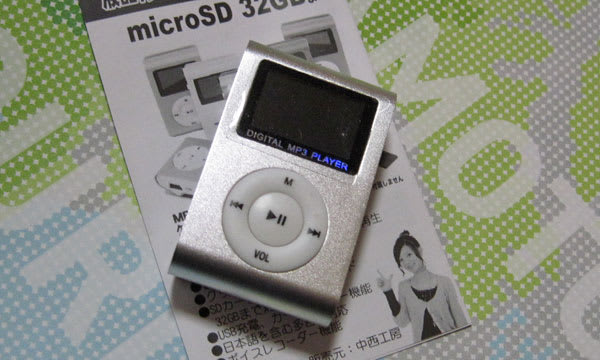








当社は、中山道の宿場として繁栄した桶川宿に祀られてきたため、一般に「桶川稲荷神社」と呼ばれ、近世以来、商売繁盛の神として信仰が厚い。かつては、遊郭や飲み屋の女性たちが夕方、店に出る前に参詣する姿がよく見られ、その艶やかな姿を眺めようと、当社に足を向ける男性も少なくなかった。また、昭和三十年代までは社殿の背後に清水を満々とたたえ、どんな干ばつにも涸れたことのなかった池があり、その水が疝気(下腹部)に卓効があるとして近郷近在から多くの人が水を受けたり、病気平癒を祈願しに訪れたという。今も時折、参拝者から「お水を受けたい」との申し出があり、その場合は宮司家の井戸に水を頒けている。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)

当社の境内は、かつては近在の若者が娯楽として力競べや草相撲をした所でもある。境内にある「大盤石(だいばんじゃく)」と呼ばれる卵型の大きな石は、そうした競技の名残で、嘉永五年(1852)に岩槻の三ノ宮卯之助という力士が持ち上げた伝えられ、当社のシンボルとして親しまれている。縦1.2m、横60cmもある巨大なのもで、重さ二〇〇貫(約700kg)と推定されている。ちなみに三ノ宮卯之助は江戸一番の力持ちといわれ、勧進相撲でも活躍したという。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)


 :ここです ブログ人マップ
:ここです ブログ人マップ

 )
)




 その後・・・・(2011.11.04)
その後・・・・(2011.11.04)

 )
)






 、ホットコーヒー
、ホットコーヒー 、麦焼酎などもありました。
、麦焼酎などもありました。



 :紅葉見ナイトは平成23年11月5日(土)~12月4日(日)の期間で開催です。
:紅葉見ナイトは平成23年11月5日(土)~12月4日(日)の期間で開催です。
















 :ネット情報によると今年も小雪太夫はお出でにならなかったようです・・・・。
:ネット情報によると今年も小雪太夫はお出でにならなかったようです・・・・。