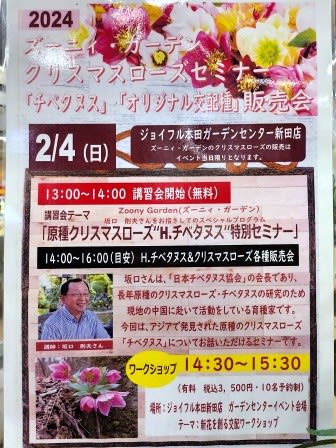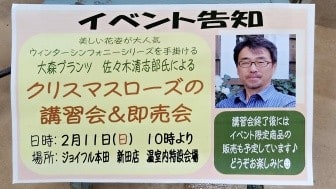When words leave off music begins.
BGM on "♪YouTube":
Vitali Chaconne [Arthur Grumiaux]





再建記念碑 平成元年七月吉日建之
当社は川北山根大平の三郷を以って葛袋となし、其の中央山頂に五社大神と南方に白髪大神を守護神として祀り、明治五年両社を合祀し村社に列せらる。明治三十三年社殿を改築し、同四十年愛宕神社及び八坂神社を合祀し。社号を葛袋神社と改称す。
昭和六十一年十一月二十七日不慮の火災により、社殿を焼失し、氏子一同再建を誓い多額の浄財を寄進し、平成元年四月十六日竣工壮麗清浄なる神殿に神霊を奉安す。
仍って茲にその梗概を誌し永く後世に伝えんとする。
総工費弐阡伍百七拾参万円



葛袋では、かつて村の中央にそびえる坂東山(標高八五メートル)中腹に五社権現宮、村の南方に白髭神社・愛宕神社・八坂神社をそれぞれ祀っていた。このうち白髭神社が村の鎮守であった。
明治五年、白髭神社を坂東山の五社権現社に合祀して相殿となり、「五社大神・白髭大神社」と号して村社となった。更に同四十年、愛宕神社と八坂神社をこれに合祀し、同四十五年に村名を採って葛袋神社と改めた。次いで、大正五年には、坂東山の麓の現在地に社地を移した。この坂東山は、昭和二十九年からセメント材採掘のために秩父鉱業によって切り崩され、現在では跡形もなくなっている。
このように、当社の中心となっているのは五社権現社と白髭神社である。五社権現社は、その社名から察するに、熊野十二所権現社の内の熊野五所王子と呼ばれる若一王子(天照大神)・禅師(忍穂耳尊)・聖(瓊々杵尊)・児宮(彦火々出見尊)・子守(鸕鶿草葺不合尊)の五柱を祀る社と考えられ、恐らく熊野修験により奉斎されたものであろう。一方、白髭神社については「(隣村の)下唐子の白髭神社(現唐子神社)が当社の兄さんである」との口碑が伝えられている。下唐子の白髭神社は、応永十八年(一四一一)の創建と伝えられることから、当社の創建もこのころまでさかのぼるのであろうか。
昭和六十一年に社殿を焼失したが、平成元年に再建が果たされた。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)






屈巣久伊豆神社 鴻巣市屈巣二三一二 ー 一
□歴 史
当地の地名は元来、国主と書かれたが、正長年間(一四二八 ー 一四二九)当社境内の老榎樹に鷲が棲みつき、度々子供を傷つけたことから村人がこの鷲を祀って鷲神社と号してからは、鷲も巣の中に屈して出てくることも無くなったために屈巣と改められたという。
また、『明細帳』には「本社々殿ハ宝亀元年(七七〇)九月ノ建立ニシテ今ヲ距ル千有余年爾後数回再建ノ事記アル棟板等今ニ存在セリ、而シテ又土俗ノ口碑ニ前玉(さきたま)神社ノ一社ナリト伝フ、蓋シ本社久伊豆神社祭神大己貴命ハ大国主命ニシテ古ヘ村名ヲ国主村(今ハ屈巣村ト伝フ)ト唱ヘシハ即チ大国主ノ二字ヲ村名ニ呼ヒシニ原因セシナラン、以上土俗ノ口碑ト当時存在セル棟木ノ年号トニ依レハ古ヘ前玉神社ニ座ス其一ヲ祭リシモノニテ式内ノ神社タルコト明ナリ且ツ中古当社ノ殿内ニ八幡社鷲神社ノ両祠を配祀ス、然レドモ其縁由詳ナラス」とある。
また、『風土記稿』には、村の鎮守として祀られ、正保二年の棟札を蔵し、本山修験の桜本坊が別当を務めていたことが記される。時代は下って、明治四二年に村内の一六社が合祀された。
□主祭神
・大己貴命(おおなむちのみこと)
□神社年中行事
・四方拝(一月一日) ・祈年祭(二月二十六日)
・春の例祭(四月十五日) ・大祓い(六月三十日)
・秋の例祭(十月十五日) ・七五三 祈願祭(十一月十五日)
・新嘗祭(十一月三十日) ・交通安全祈願(十二月十三日)
・大祓(十二月三十日)








鴻巣市指定有形文化財 忍領境界石標 昭和五三年三月九日指定
この石標は、忍藩が他領分との境界争いが起こらないよう安永九年(一七八〇)に屈巣村(現川里村屈巣)と安養寺(現鴻巣市安養寺内)との境に建てたものである。
忍藩内に一六本建てられたものの一つである。明治の廃藩置県後、一時個人所有になったが、その後久伊豆神社に寄附されたもので、川里の歴史を語る貴重な資料である。
「従是北忍領(これよりきたおしりょう」と彫られている。
高さ一三三cm 幅三〇cm 小松石
平成七年七月 鴻巣市育委員会
 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ



火雷若御子神社
明治十二年(一八七九)の「上野国神社明細帳」によれば、「当社ハ往昔、那波郡下ノ宮火雷神社ヨリ勧請スト言ヘドモ、其年月詳ナラズ、其後保食命ヲ合祭シ村名を以テ社号トスト伝フ」と記述されています。創建後、途中で中里神社と改称され、同二十八年に火雷若御子神社と復称されました。
祭神は火産霊命(ほむすびのみこと)・宇気母智神(うけもちのかみ)です。境内社に秋葉社(祭神は軻遇突智神[かぐつちのみこと])、城峯社(大山祇命[おおやまぎのみこと])、八坂社(素盞嗚命[すさのおのみこと]、菅原社(菅原道真公)等が祀られています。
境内には近隣には見られない御沓堂(おくつ)があります。この土地の人々は農耕馬のための雷除けとして、無事に農業が営めるようにとの願いから、馬を引っ張ってお参りをし、御沓堂に馬のわらじや蹄鉄を奉納しました。今もその一部が残っており、道路沿いに石仏・石神等の石造物が並んでいます。















 )
)





































当社は「住殿稲荷(じゅうどのいなり」、又は「住殿様」と呼ばれる。住殿の名の起こりは、鎌倉幕府滅亡の端緒となった元弘の乱(1331)に、鎌倉を攻めた新田義忠が布陣したことによるという。これを裏付けるかのように、当社裏には、新田軍の戦死者を葬ったと伝える殿塚の地名があり、かってここに建武元年(1334)の五輪塔があったという。
また、住殿の称は永禄三年(1560)に新田氏と深谷城主上杉憲政との間に生じた境界争いの時に起こったとする説がある。このことは、『新田家御軍記(写本)』に「之を以て新田方勝利を得、勝鬨を上げ、軍勢を率ゐて速かに石塚郷稲荷之陣に退き、社頭に於て待てども敵来たらず。篝火を焚いて夜を明かして凱陣す。依て以て今此の所を住殿之森と称する也」と見える。
以上のことを勘案すると、幾度か陣を布いた地にいつしか当社が祀られ、後に石塚村の鎮守となったものであろう。
明治九年に村社となり、同四十年には石塚字本村の無格社赤城神社、同境内社神明社・八坂神社、字谷田の無格社大宰府神社(現天神社)を合祀した。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)



社殿改築之碑
住殿の社に神鎮まります稲荷神社は石塚郷人の鎮守神として世情如何に変われども我民族の道統たる敬神崇祖・神人和合の祭事は綿々と受け継がれて来た。明治の年に郷内の社を此の地に合祀して以来百余年の星霜を経過した本殿覆殿拝殿など積年の風雨により損傷甚だしく之が修理について憂慮するところであった。平成十一年四月二十五日に稲荷神社々殿改築整備奉賛会を発起し浄財の勧募を開始することとなり氏子崇敬者より多大な奉賛を拝受し平成十七年八月九日起工・平成十八年二月竣工することが出来た。茲に長期にわたる奉賛会役員の努力と関係各位の赤誠の結晶に深く敬意を表し又地区の弥栄を祈念するとともに荘厳秀麗な社殿の完成を祝し改築の記念とする。
平成十八年 二月吉日 稲荷神社 宮司 江守義好




 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ