
過去記事に 芳しくはないですが 「トイレ」 の話を載せました
災害時に断水して閉口しました。
1回のトイレ洗浄に使用する水量は、メーカーや機種、節水タイプであるかどうかなどにより違いますが、一般的な便器の場合、大レバー使用時は13~8リットル程度、小レバー使用時は11~6リットル程度の水が流れるそうです。
トイレの水の役割は、排泄物を便器から流し出すだけではなくて配管に落ちてから平均10メートル以上流せなければならないという下水の基準があるそうで、どうしても相当量の大量な水が必要となるようです。
大の場合の方が多くの水が必要となり、大レバーと小レバーでは使用水量に2リットルの差が出ます。
水洗トイレの水を流すレバーやボタンの 「大」 と 「小」 があり 女性の場合、小の時にもトイレットペーパーを使用するため大レバーしか使ったことがないという人も。 男性でも、小レバーできちんと流すことができるのか不安に感じて常に大レバーを使用しているという人も多いようです。
一般家庭での水道水を使っているのはトイレで、家庭内で使われる水量の約28%がトイレでの使用だということです。【風呂24%、炊事23%、洗濯17%】家族全員が一日に何度も使用するから多くなるのでしょう。
断水時には 「飲み水」 「料理用水」 「洗面・歯磨き」 「身体拭き用」 が必要になりますが 「トイレの排水用」 がこれほど必要だとは思いませんでした。 2Lのペットボトルの飲料水を2箱と飲料用のお茶2Lを2箱、10Lのポリタンク2つにも水道水をキープしていましたがイザとなったらトイレが異常に消化してくれるので 『あっという間』 に無くなりました。

前にも書きましたがこのボトル4本で1回分です。 (+o+)
賞味期限切れの水は飲めるので台風など非常時に捨てないで!消費者・行政・メディア みな賞味期限を誤解 という記事をご紹介
井出留美 | 食品ロス問題ジャーナリスト・博士(栄養学) 9/13(金) 12:40
(写真:Natsuki Sakai/アフロ
https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20190913-00142504/
千葉県富津(ふっつ)市で、台風15号の被災者にペットボトル水が配られた。そのうち約1800本が賞味期限切れだったため、市民からの指摘を受けて富津市がお詫びし、「飲用ではなく生活用水として使ってほしい」と呼びかけていると、2019年9月12日付の東京新聞夕刊が報じている。
『賞味期限切れ「飲料水」配布 富津市、生活用水用を誤って1800本』
ペットボトル水の賞味期限は飲めなくなる期限ではなく、通気性のあるペットボトルから水が蒸発し内容量が変わるための「期限」
2019年7月29日付の熊本日日新聞では、熊本市が、ほぼ賞味期限切れの130トンの備蓄水に困っており、花壇の水やりや、足を洗うなどに使っていると報じていた。
その際、筆者は、「なぜ賞味期限切れの水は十分飲めるのに賞味期限表示がされているのか?ほとんどの人が知らないその理由とは」という記事を書いた。
ペットボトルの水に表示されている賞味期限は、飲めなくなる期限ではない。
長期保管中に水が蒸発し、表記してある内容量を満たさなくなるため(計量法に抵触するため)、規定の内容量をきちんと満たすための期限である。
もちろん、直射日光や高温・高湿を避けるなど、保管がきちんとしていたことは、飲用するための前提条件である。
が、ただでさえ水が不足する非常時には、五感で味を確かめて、飲用として使うことは十分可能だ。
2018年7月3日付の産経新聞の記事「賞味期限を過ぎたペットボトルの水は飲めるか、飲めないか?」の中でも、日本ミネラルウォーター協会事務局長が、「水の賞味期限は、表示された容量が確保できる期限です」と回答している。
前述の東京新聞の記事によれば、ペットボトルに表示されている期限は2018年4月とのこと。まだ過ぎてから1年4ヶ月程度だ。
賞味期限は、品質が切れる日付ではない

ペットボトルの賞味期限については、関係者しかわからないのは仕方ないかもしれない。筆者も、食品メーカーに長く勤めていたのに、ペットボトル水の製造メーカーと契約して仕事をするまでは、まったく知らなかった。
だが、それ以外の食品や飲料に関しても、「賞味期限」のことを、「品質が切れる期限」だと誤解している人があまりにも多い。
たとえペットボトルの水の賞味期限が切れていたとしても、それは「美味しさの目安」が過ぎていたにすぎない。
品質が劣化しやすい、日持ちがおおむね5日以内のものに表示される「消費期限」とは違う。
賞味期限(赤)と消費期限(黄)のイメージ(農林水産省HPより)
消費者も、行政も、メディアも、賞味期限を誤解している現実
今回、千葉県富津市に「期限を過ぎたものを配ったのでは」と指摘したのは市民だった。
そして、それを受けて、「このような事態を招き申し訳ない」とお詫びし、「飲用しないで」と呼びかけたのは行政(市)だ。
その事態を報じたのがマスメディア。
消費者(市民)も、行政も、マスメディアも、全員、「賞味期限が何たるか」を誤解している、ということになる。

本来は、消費者自身が、賞味期限の意味を理解していなければならない。
消費者が理解していなかったとしても、行政が、市民から指摘を受けたときに「この賞味期限というのは、品質が切れる日付ではなく、美味しさの目安なんですよ」と説明できなければならない。
賞味期限が過ぎたものを「誤って配った」と報じたメディア。記事を書いた記者も、この記事を通した責任者も、賞味期限の意味をきちんと理解しておられないのだろう。


という記事もありました。
ほかには、
心配なのはマイカーを持っていない世帯の方々。
昨今の高齢ドライバーによる事故の報道を見て免許を返納し、車を手放された方もおられるでしょう。

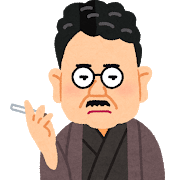
しかし、そうした方々は、暑い夏や、寒い冬の時期に今回のような長期の停電に見舞われた場合、どうやって発災直後の厳しい時間をしのげばよいのでしょうか……。
遠い避難所まで、車なしでどうやって移動すべきなのか?
配水車まで歩いて行って、重い水をどうやって運ぶのか?
マイカーを持つ人と持たざる人の間では、大げさかもしれませんが、災害時における「命の危険度」に大きな差が出かねないのです
こういった心配もあるのですね。 やはり体験しないと分からないことが多かったのでとても勉強になります。















