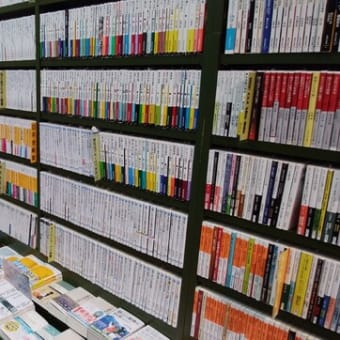ー 暴 走 自 転 車 ー

先日、歩道を歩いていた。右は車道である。突然右側を自転車が走り抜けた。
危うく肘が当たるところだった。思わず「こらあーつ」と大声を出した。声は聞こえただろうに止まりはしない。後ろ姿から判断すると若い男である。ゆるい下り坂でペタルを踏んでいるから時速30キロは出ていた。
自転車も走ることができる歩道だからそれ自体は違反ではない。
しかし、前を歩く人がちょっとでも右に寄れば衝突する。悪くすると車道に飛ばされて走ってきた車に轢かれるかもしれない。男はそこまでの危険予測ができない。
衝突しないまでも、すぐ脇をいきなり走り抜けたら、歩いている人はびっくりするだろう、だから手前の方でベルを鳴らそう、「すみません」と声をかけようという気配りもできない。
なぜか。
「ふれあい恐怖」だという人がいる。ベルを鳴らすと知らない人と話をすることになるかもしれない。人といると緊張する。居心地が悪い。何を話せばいいかわからない。これである。ひどくなると何年も自分の部屋に引きこもる。
問題はなぜ他人と関わることを避けるようになったかである。
多分子どもの頃の遊びが足りなかったのだと思う。昭和30年代、子どもは個々に学校に行き、思い思いに家に帰り、奔放に遊んだ。川遊び、木登り、相撲・・・
トラックも遊び道具になった。村の砂利道をトラックがのろのろやってくると、ほこりの中をうしろから追いかけた。そして荷台に手をかけ、バンパーに足をかけて束の間の無賃乗車を楽しんだ。トラックのスピードに神経を集中し、これ以上つかまっていたら危ないと感じたところで飛び降りた。
いろいろな遊びの中でどうしたら自分や友だちが怪我をせずにすむか、どうしたら仲良くやっていけるか、ことば使いや気配りや人と話をするときの間合いの取り方まで脳が自然自然に覚えていった。
もちろん今子供がトラックにつかまろうとしたら厳しく叱らなければならない。ただ体を動かさないと脳も発達しないことは間違いない。
もちろん今子供がトラックにつかまろうとしたら厳しく叱らなければならない。ただ体を動かさないと脳も発達しないことは間違いない。
今、悪童連がいなくなった。道草ということばも聞かなくなった。
登下校の時刻になると街はおじさん、おばさんの持つ黄色い旗で埋まり、子どもは旗の間をぞろぞろ歩く。旗をやめろとは言わないが、子どもは脳を発達させる大事な機会を失っている。