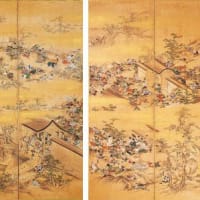島崎藤村
詩人、作家。本名春樹(はるき)。別号古籐庵無声(ことうあんむせい)。明治5年2月17日(旧暦)筑摩(ちくま)県(現長野県)の旧中山道(なかせんどう)馬籠(まごめ)宿(現在は岐阜県中津川市に所在)で本陣、庄屋(しょうや)、問屋(といや)を兼ねた島崎正樹の四男として生まれる。島崎家は正樹で17代目の旧家であったが、藤村の出生時は明治維新に伴う諸改革で没落しつつあり、1881年(明治14)数え10歳で修学のため上京した彼は以後親戚(しんせき)や知人の家で成長した。91年明治学院卒業。存学中に受洗したキリスト教やヨーロッパ文学の影響で文学に志し、巌本善治(いわもとよしはる)主宰の『女学雑誌』に寄稿を始め、かたわら明治女学校の教師となったが、許婚(いいなずけ)のある教え子への愛に苦しみ教会を離れて、93年関西放浪の旅に出た。
1.詩人藤村
同年、星野天地(てんち)や終生先達と仰いだ北村透谷(とうこく)らの『文学界』創刊に参加、透谷の影響で劇詩を書いたが、やがて新体詩に転じ、仙台の東北学院に赴任したころから発表した詩編をまとめて『若菜集』(1897)を刊行、詩人としての名声を高めた。以下『一葉舟(ひとはぶね)』『夏草(なつくさ)』(ともに1898)、『落梅(らくばい)集』(1901)の3詩集を出したが、しだいに自分の詩想と釵情詩の形式との差を感じ始め、信州の小諸義塾(こもろぎじゅく)の教師となり結婚したころ(1899)から自然と人生に対する観察を深めて小説埶筆に向かった。
2.作家的地位の確立
『破戒(はかい)』(1906)によって作家地位を確立した彼は、次の長編『春』(1908)において『破戒』流のフィクションを捨て、『文学界』時代の実生活をもとに自伝的小説に転じ、田山花袋(かたい)の『蒲団(ふとん)』(1907)とともにわが国の自然主義文学の進路を決定した。第三の長編『家』(1910~11)はこの方向を徹底させた作品で、彼と一族をモデルに旧家の退廃した論理を写し出し、自然主義を代表する傑作となった。この小説を執筆に妻を失い、黙々として育児と執筆に励んでいた彼は、家事手伝いにきていた姪(めい)と過失を犯し、背徳を恥じて1913年(大正2)単身フランスに渡った。やがて『新生』(1918~19)に描かれるこの事件は、観察を武器としてあらゆるものを対象化してきた彼の作家生活が生んだ「信のない心」や煩雑な日常生活の倦怠(けんたい)感がもたらしたものであった。パリの生活は異国への「流罪」であるとともに、未知の世界、とくにカトリック的な価値観への眼(め)を開かせ、日本の近代化の考察や東西の比較に進ませる原動力となった。滞仏2年目、周囲の環境になじみ『桜の実の熟する時』(1914)執筆や故国への通信も軌道にのったころ第一次世界大戦が勃発(ぼっぱつ)し、一時フランス中部の都市リモージュに避難したが、前途の不安は強まり、経済的困窮も加わって、16年(大正5)、3年ぶりに故国の土を踏んだ。