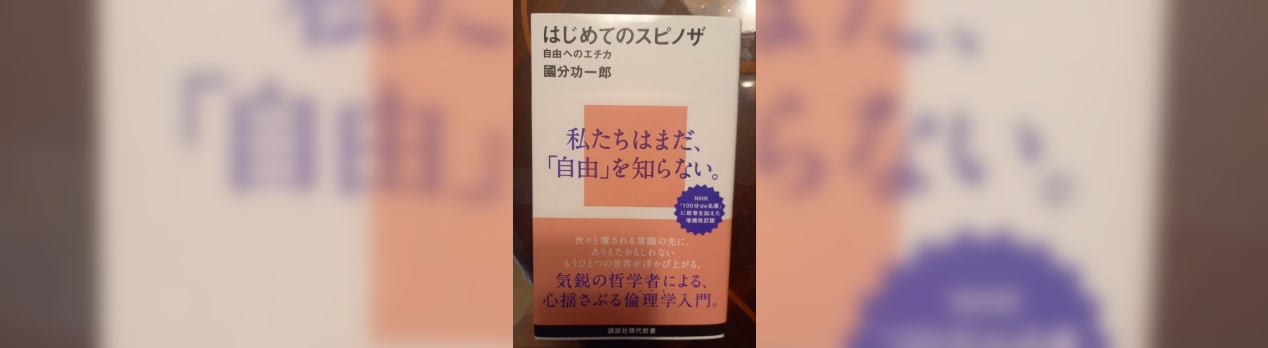17世紀の哲学者、スピノザを読んでみようと思ったのですけれど…
主著の『エチカ』は名うての難解な本であるので、いきなり読んでも、まずまともな理解には至らないことがわかっているので…
解説書、それもなるべく易しそうな入門書を読んでみました。
これを読んだ後に原典に当たったところで、しょせんその世界を完全理解することなど、私の力で出来るはずもないのですが。
スピノザに関しては、有名なポスト構造主義の哲学者、ジル・ドゥルーズなどにも著書がありますけれど…
とりあえず読んだのは、日本の哲学者、國分功一郎氏が書いた『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』という本です。
私自身の中で響いた部分に関してレビューと、そこから考えたことを書いてみます。
まず、スピノザの哲学は「有神論」です。ただここでいう「神」というのは、キリスト教-とりあえずローマ教会のドグマによる…
「あの神」ではなく、神羅万象を「司る者」でもなく、神羅万象「そのもの」を、スピノザは神と名付けています。
この本の中では「神即自然」と表現されています。
宇宙のすべて、自然の法則の「外」や「上」に神という存在を設定するのではなくて「それそのもの」を神と見なすのです。
いわゆる「汎神論」であって…
標準的なキリスト教徒の感覚からすると「スピノザは無神論である」だということにもなるみたいです。
自然「そのもの」に神を見る、という感覚は、日本の信仰の伝統からするとすんなり受け入れられるのかもしれないです。
そしてキリスト教が鉄板ドグマの「西洋人」にもそんな感覚が存在したのだと、意外に思うかもしれませんが。
日本の「八百万の神」が、自然の個々の現象や物を、細かく分けてそれぞれに一種の「霊性」を見るのとは違って…
スピノザの汎神論の場合は、広大無辺にして「外側」が存在しない(そしておそらく意志も持っていない)存在を設定して…
それを「神」と、便宜上名付けている、という感じのようです。
まあ、そんなものは神とは呼べない、という意味で、一般的なキリスト教徒から無神論と言われてしまうのでしょう。
なので、その著作がローマ教会から禁書扱いされたことがあったのも、仕方ないのかもしれません。
ただスピノザ個人としては「異端」という自覚はなくて、キリスト教の神も彼の神も実体に変わりはないと思っていたのではないか…
と、私には思えます。
ともあれ…
スピノザ的には、この世界?宇宙?そのものが一体としての神であるわけで、個々の事物や現象はその「あらわれ」なわけです。
なので、この世にあるすべての「もの」(この本では個体、という言葉を使っていますが)はそれぞれに「完全」なものであって…
それが「不完全」に見えるのは、人間の一般的観念から見た、偏見である、というのです。
では、世の中に善いことと悪いことがあるように見えるのはなぜか。
それは、事物の「組み合わせ」によって生じる、という考え方をスピノザはしている…
と、國分先生は説明します。
スピノザが音楽を使って説明していることが、ここで書かれています。
たとえば元気が出なくて落ち込んでいる人が、ある音楽を聴いたら、それに励まされて生きる力を回復するかもしれない。
でも同じ音楽が、身近な人の死を悼んでいる人にとっては、耳障りで不愉快なものになる、というのです。
ここで本の中の文章から引用してみます。
音楽それ自体は善くも悪くもない。ただそれは組み合わせによって善くもわるくもなる。つまり、自然界にはそれ自体で善いものや悪いものはないけれども、うまく組み合わさるものとうまく組み合わさらないものが存在する。それが善悪の起源だとスピノザは考えているわけです。
では、善も悪もないのだったら、人間はどんな生き方しても、どんな振る舞いをしてもいいのか。
そうではないのです。
物事の組み合わせ、言い換えれば「関係性」によって、善いものと悪いものは生じてきてしまう。
ただ、どんな時と場所、ケースにも万能に当てはまる、固定された「道徳」というものを、スピノザは否定しているのです。
事物には、個別的、具体的に人や事物の「活動能力を増大させる」あるいは「減少させる」ものがある、という表現をスピノザはします。
この本の中では、別の例として「ステーキ」が出て来ます。
ステーキそのものは、善い食べ物でも悪い食べ物でもない。
ただ、たんぱく質を取って力をつけたい健康人にとっては善い食べ物だけれど、胃が悪かったり、高脂血症の人には悪い食べ物です。
そういう風に、個々の差異や状況に応じて、実験や、経験則にあてはめた選択をしながら、人は物事の善悪を判断しなければならない。
スピノザ的には、それを「より小なる完全性から、より大なる完全性へ」と表現するようですが。
たとえば、中国の事物は悪い、とか、中国人は悪人だ、と言って決めつけてしまうのではなく…
この場合は、これは善くない物だ、とか、この人に関して言えばこれは悪い人だ、と個々に判断する。
それは面倒くさいけれど、そうしないと善い方向には向かわない、必ず悪い結果を生み出す…
それこそ「完全性を損ない」社会の「活動能力を減少させる」ということなのでしょう。
現在の私の場合に引き寄せて考えれば、困った母親が「絶対悪」として存在するのではなくて…
私の活動能力を減少させる、関わることによって私の生きる力を減退させられるような関係性、組み合わせのものとして…
現在の母がいる、ということなのだと思います。
彼女のいうことにいちいち応じて振り回されたり、不用意に関り合うことは「善くないこと」だけれど…
だからといって彼女の存在を悪として、母など死ぬに任せてしまえばいい、ということでもないのでしょう。
もうひとつのポイントとして印象に残ったのは、スピノザの、物事の本質に関わる考え方です。
古代ギリシャ以来の哲学は、事物の本質を基本的に「形」=形相=エイドスと呼ばれるものに帰して来たと。
エイドスというのは、見かけ、形に関わる単語で、固定した性質を表すものです。
エイドス的なものの見方は、それこそ「道徳」に至る道であるということです。
たとえば、男性と女性の別というのを、本質と結びつけるというのも、一例です。
ここでまた國分先生の文章を引用します。
男であること、女であることを、本質的なことと考えてしまうと…
その時、その人がどんな個人史を持ち、どんな環境で誰とどんな関係を持って生きて来て、どんな能力を持っているのかということは無視されてしまいます。
その代わりに出てくるのは、「あなたは女性であることを本質としているのだから、女らしくしていなさい」という判断です。エイドスからだけ本質を考えると、男は男らしく、女は女らしくしろということになりかねないわけです。
そうではなくて、ものや人が持っている「力」=コナトゥスを本質として考えるのが、スピノザ流ということになります。
力というのは、この場合、物理的なパワーという意味ではなくて、他のものに対して作用する性質を差しています。
これを『エチカ』の中では「変状する力」と呼んでいるようです。
たとえば人が同じインプットを受けたときに、どんなアウトプットをするかというのは、同じ人でも時と場合によって異なります。
これが「変状する力」=コナトゥスであって、物事の本質であるというのです。
ライク・ア・ローリングストーン…ではないですが、常に変化し続ける様態として、個々の事物の本質をとらえているわけです。
そして『エチカ』では、人はコナトゥスがうまく働いて生きているとき自由である、と書かれていると。
さらに、ひとりひとりが自由に生きられることこそ、社会が安定するために一番必要なものであると。
個々のコナトゥスがうまく働く社会が、より「活動能力が多く」「完全性の高い」社会なのですね。
『エチカ』の中では、政治論や国家論は語られていないようです。
しかし、スピノザの考え方の中には、一種の「社会契約説」があると。
ただそれは、ホッブスなどの言う社会契約のように、最初に「決められた」ものではなくて…
毎日、毎時、更新され、確認され続けて行くものだというのです。
だから社会の構成員は、常に緊張感を持って「契約」に向き合う必要がある、と。
日本国憲法の中に、民主主義は国民の絶えざる努力によってしか、維持されないということが書かれているのと同じことですね。
私たちはいつの間にか、社会を固定したものと考え、その「お客さん」になってしまい、それを怠ってしまいました。
結果、こういう世の中になった。
世界やこの国のこと、人間とその営みを「エイドス」的=形相的にしか見ない、という姿勢がその裏にあったのかもしれない。
いや、日本だけでなく、世界中の人々が、そういう見方でしか、この世界を見られなくなってしまった。
常に移り変わる性質を持った「力」=コナトゥスの集合体として、そして最終的には、一つの「神」の一部として、すべてを見る…
そうしたスピノザ的考え方から、あまりにかけ離れたところに来てしまった。
様々な危機や、それこそ「西洋近代」に続くこの世界の行き詰まりは、そういう所から来ているのかもしれません。
國分先生はこの本の中で、スピノザを理解するためには、思考のOSを書き変える必要がある、と書いています。
うまくいかない事や、相手があるときには、それを絶対悪として、完全否定して「消す」のではなくて…
その場その時に応じた「関係性」を組み替える試み、努力をしないと、何事も解決には向かわない。
それどころか、むしろ悪くなるばかりだということを、スピノザは教えてくれているのではないかと思います。
この本の最後で、國分先生は「哲学が研究の場に閉じ込められるようなことは、断じてあってはなりません」と書いています。
哲学は、机上の空論になってしまってはいけない、意味がないのだということでしょう。
たとえば、スピノザの「組み合わせとしての善悪」の概念を使って、人間関係や社会関係を考えるとか。
そうやって「使いこなして」はじめて、哲学というのは存在価値をもつのでしょう。
観念的な自己満足に終わるようなものなら、哲学などというものに意味があるのかどうか、かなり怪しくなってきます。
コアな信仰者以外にとっての「キリストの教え」とか「仏の教え」などがそうであるのと同じように。
なので…
私も、読めるかどうかわかりませんが、一度『エチカ』そのもの、原典を読んでみようかと思っています。
そして、それを実生活に使ってみることができれば、スピノザ先生もきっと本望なのでしょうね。