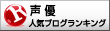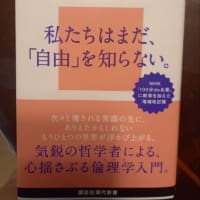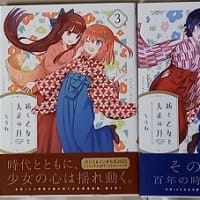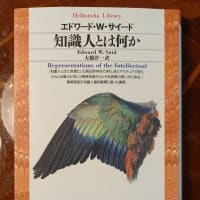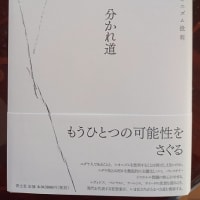積ん読してた書籍の中から。
『アセンブリ-Assembly』
Assemblyは、組み立て、転じて集会、集合、集いという意味です。
2015年に英語版が出版され、18年に日本語訳が出ています。
民衆が政治的に「集う」ことの意味と現代の民主主義の条件について論じた書物で…
どうやら「アラブの春」と呼ばれるムーブメント=2010年のチュニジアで起きた「ジャスミン革命」にはじまり…
2012年ごろにかけてアラブ世界のあちこちで発生した、大きな反政府デモと民主政権樹立の動きに触発されて書かれたもののようです。
相変わらず、決して読みやすい本ではないのですけれど、この著者と私との相性がどうやらすごく良いらしく…
読み始めると進みは遅いながらも夢中になってしまいます。
日本ではデモや集会は悪いこと、はた迷惑な行為というのが「普通の人」の認識になってしまっていますが…
これらは民主主義の政体のもとで生きる「市民」の当然の権利であって、これなしでデモクラシー、民主主義を語ることなどできないものです。
欧米の民主主義の国では、デモや集会のやりかたと意義について、学校できちんと教えています。
日本国憲法にも「集会の自由」は、思想信条、言論の自由などとセットになって保証され、明文化されています。
それにも関わらずこの国では、基本的な権利であるこれについて、タブーであるかのように理解されています。
ひとつには、学校教育であえて教えないようにされているというのがあります。でもそれ以前の問題として…
そもそも日本には、西洋世界やアラブ世界の都市にあるような「広場」=誰でもいつでも、自由に使える公共空間といいうものがありません。
公園はありますが、ほとんどの公園は庭園のしつらえだったり、遊戯場、競技場だったりして、多人数がいつでも自由な目的で使える空間ではないです。
そして、しばしば塀や生垣で遮られていて誰もが目にできる「公開」の場ではないです。
勢い日本では、政治にまつわる集団行動は主に道路で行われるものになりますが、そうすると交通の妨げにはなるので「迷惑」と取る人が多くなりますし…
そもそも道路交通法で、道路は通行の目的以外で使用してはならないとされています。
他の目的で使用する場合は「原則としては」警察の許可を取れ、ということになっています。
(近ごろ少し流行っている、ひとりでやる行動「スタンディング」程度の規模なら、許可など必要ないはず…なのですが)
その割には、マラソン大会などのスポーツイベントやお祭りには、大々的に交通を遮断して行うことが容易に警察から認められて…
人々もスポーツやお祭りなら「仕方ない」と、抵抗感なく不便を受け入れるのですが、それが政治的な目的だとなると「迷惑千万!」と怒るのです。
その背景にあるのは…
一般市民は、政治になど口を突っ込むものではないというのが「大人の常識」だという暗黙の了解です。
最近ではそれ以前の問題として、政治について個人的な意見を口にしただけで「思想強め?」とからかわれ、それ以上の対話を拒絶される。
いや正確に言えば、人々の間でタブーとされている「政治的なこと」「思想」というのは、あくまでも現在の権力・権威・体制に異議を唱える方向のものだけであって…
その逆に体制や権力に迎合することを考えたり口にしたりすることは、なぜか「政治的」なことではない、とされるのです。
そういう方向での、自粛と相互監視が行き渡っているかのよう。
独裁的政権による圧政のもとで、怯えて仕方なく口をつぐまされている社会より、ある意味もっと息苦しい、病んだ状態かも。
これはどう考えても「民主」国家のありさまではないですよね。
我々が知らないだけで、そんな「自由主義」「民主主義」国家…少なくとも「西側」の国は、日本以外にはどこにも存在しないのです。
「民主主義」とは、多数決のことであり「民主的に決めようや」というときには、決をとって多数派に従おうぜ、という意味だったりする…
いい大人で自称「社会人」の人々が、自分の国の成り立つ基盤であるはずの「民主主義」について、最低限の理解さえできていない国。
そんな「なんちゃって民主主義国」の日本。
政治や行政に関わる者が対外国の場面ですぐ口にする…
「自由と民主主義という共通の価値観を共有する、西側諸国の一員としての日本」というセリフ。
あの、おためごかしというか明らかに虚偽欺瞞のセリフを聞くたびに、私などは吐き気と寒気を感じます。
白人が主導権を握る「西側諸国」=主に米国は、そんな欺瞞を裏では理解していながら、ソ連→ロシアや中国に対する防波堤として…
そしていざとなったら「鉄砲玉」としてそれらの敵に投げつけて犠牲になってもらう…別の言い方をすれば「いつでも捨てられる駒」として日本国と日本人を見ているんです。
また脱線しかけているので話を戻します。
そんな特殊な国に住んでいる者としては、この『アセンブリ』の論点について、我々は議論の入口にさえ立てていない感じがしてしまうのですが…
それでも、我々の国を含めた現代世界の国々、民主主義国家に限らず、様々な社会に共通する重要な問題が論じられていることは確かです。
それは、人が孤立することなく、社会を構成する要素として、繋がり、集まることの重要さ。
さらに…
難しい言葉で言えば、常に新たな人々を、社会の中に「包摂」し続ける営みの大切さ、そして難しさについてです。
ああ……本のタイトルとテーマについて思ったことを書いただけで、こんなに長くなってしまいました。
それほど日本という国が、良い意味ではなく極めて特殊で、民主主義国家としては機能していない、欺瞞に満ちた国だということだけ今回は訴えたいです。
(西側諸国よりは中国や北朝鮮に親和性の高い社会だと思います。みんな信じてくれないと思いますけど)
この本の中の言葉をひとことだけ引用してみると、人々が「市民」として…
<共に行動するための諸条件が徹底的に破壊され崩壊している>
状況に、まさに合致していると思います。
次回は「序章」の内容の「さわり」を私なりにできるだけ分かりやすく、できるだけ短く書いてみるつもりです。
次回がいつになるかは、分かりませんが。もう序章は読んでいるので、忘れないうちになるはやで書きたいと思います。