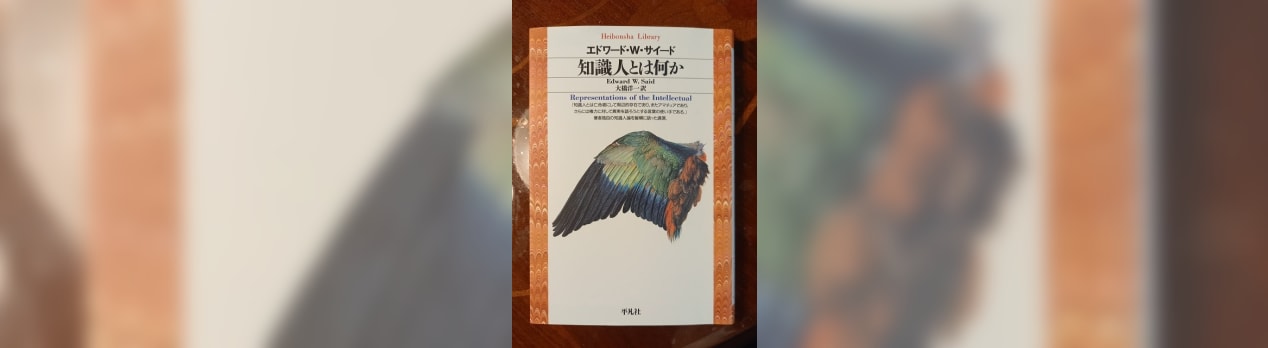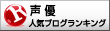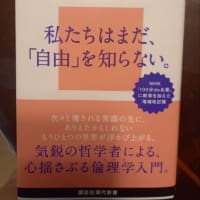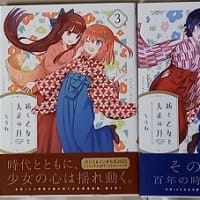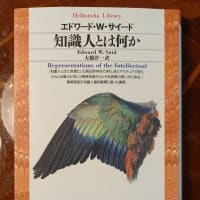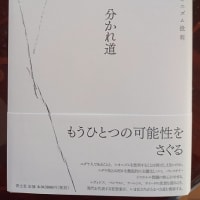まずこの本の書名に使われている「知識人」という言葉についてですが。
英語ではIntellectualとかIntelligentsiaという単語になります。日本ではインテリともいいますね。
この語彙に対して、多くの日本人はどんなイメージを持っているでしょうか。
テレビや新聞などのマスコミに「〇〇に詳しい✕✕さん」として出て来てコメントする人物でしょうか。
あるいは「本を書いている人」とか「大学で教えている人」または何か知的な分野での「専門家」と言われる人々でしょうか。
日本語でも、かなりあやふやな定義の言葉であると思います。
いずれにしても、あまり良い印象は伴わない言葉になっているような気がします。
とくに「インテリ」という言葉は、人々の嫌悪感、あるいは軽蔑の気持ちさえかきたてる物なのではないかと思います。
一般庶民にとっては「いいご身分」「勝手なことをしゃべり散らしてお金儲けしてる連中」と言いたくなるような存在かと。
これは著者のサイードが市民権を得ていた(彼はパレスチナ人ですが)米国でも同じ、というか…
「Intellectual」という言葉に手あかが付いて陳腐化したのは、日本より早く、日本よりはなはだしかったように書かれています。
これについては国によって多少の差があるようで…
たとえばイタリアのような欧州の大陸の国では、intellettuali(知識人)とかCulturati(教養人)という語は、いまだに…
一応、ポジティブな言葉であり続けています。ここ5年、10年の間に、それでもだいぶ色あせてはきたようですが。
カルチャーの大衆化や、社会の中で「知」よりも富と利潤が尊ばれるようになっている、その度合いによるのかもしれません。
ただ、この本の中でサイードが「知識人=intellectual」と言っているものは…
マスコミや政府の諮問機関、企業の研究所といった「権威筋」に奉仕して、大きな利益を得たり…
あるいは大学の「象牙の塔」に籠って、高いところから世間を見下ろしているような人々ではありません。
仲間内だけで通用するような、難解な専門用語を使って自己満足に浸っているような人々でもない。
公衆に向けて、あるいは公衆になり代わって、その普段は言葉にならないメッセージなり、意見なり、立場なりを言語化し代弁する人。
とくに「日頃忘れられたり、厄介払いされたりしている人々」の声を代弁し、その問題を表面化することをする人がここでいう「知識人」だと。
それはしばしば、人々や多数者を不快にしたり、イライラさせたりすることもあり…
それゆえに、メジャーな社会から追放の憂き目に遭ったり、比喩的に火炙りにされたり、十字架にかけられたり…
そうしたリスクを覚悟しながら、観察し、考え、発言し、行動する人々のことを差すのです。
サイードは「知識人」を…
正統思想やドグマを生み出すのではなく、正統思想やドグマと対決しなければならないし、政府や企業に容易にまるめこまれたりしない…
安易な公式見解や既成の紋切り型表現をこばむ人間であり、なかんずく権力の側にある者や伝統の側にある者が語ったり、行ったりしていることを検証もなく無条件に追認することに対し、どこまでも批判を投げかける人間である。ただ単に受け身の形でだだをこねるのではない。積極的に批判を、公的な場で口にする…
人間であると定義します。
「いいご身分」でも「お気楽」でもない。たいへんな、いばらの道です。
だから「知識人」というのは…
「周辺的存在」(アウトサイダー)であるのと同時に、一種の「亡命者」であると。
そしてまた、彼はこうも書いています。
もっとも姑息なのは、他民族文化における悪弊を声高に告発しておいて、そのくせ自民族文化におけるそれと全く同じ悪弊には目をつぶるというやり方であろう。
たとえばもし基本的人権にもとづく正義を主張したいのなら、それを万人にひとしく適用すべきであって、えこひいきをして、自分の側や、自分の文化や、自国の同盟国の罪を酌量してはならない…
これをサイードは「ごく当たり前の結論」といっています。
しかしこれは、言うは易く行うは難し、のことでもあります。
サイードはパレスチナ人ですが、ユダヤ人でありながら、イスラエル国家の植民地的侵略と、殺戮を批判した…
ハンナ・アーレントやジュディス・バトラーは、ユダヤ人の中の裏切り者「反ユダヤ主義者」のそしりをうけたのです。
我々に引きつけて考えれば、まさしく「反日」「非国民」という罵倒をまともに浴びて、動じない風でなければならないわけです。
つまり「知識人」は、権力だけでなく、大衆が間違った方向に走りかかっている場合、それをも敵に回す覚悟がなければならない。
それをさけて、逃げて、多数派のご機嫌取りをしてはいけないと。
自分が信奉する「神」こそすべてで、向こう側にいるのはいつも「悪魔である」という発想を…
彼は「普遍的なものをめざす意識がみじんもない」と言って、切って捨てます。
一方の側を善であり、もう一方の側を悪であると決めつけるような分析は、真の知的分析においては慎むべきなのである。
そもそも「あちら側」や「こちら側」といった「側」(サイド)の発想自体に、複数の文化が争点となる場面では問題がありすぎる。
とサイードは指摘します。
ものごとを「側」(サイド)で腑分けして考えるやり方は危険だし、根本的に誤りである。
これは、私自身も普段から強く強く思っていたことと一致するもので、深く共感しました。
なぜならば、サイードの言によれば…
文化は決して防水加工した商品のように、同質的で、それだけでまとまっていることはな…
いからなのです。
そして国家や集団といったものも、視野狭窄的に見れば、宿命的に対立し、角突き合わせるような存在であるかもしれませんが…
すこし視点を拡げて多角的に見るならば、互いにつながっていて、影響し合い、相互依存の関係にあるものだからです。
だから、相手を攻撃し破壊するということは、結局は、自分自身をも攻撃し破壊することになる。
それはほとんどの人が…政治家や官僚や経済人マスコミ人の「偉い人たち」も含めて、見えなくなっていることではありますが…
大きな観点からみたときの、まぎれもない「真理」だからです。
それに気が付いて、なんとか気づいていない人に「報せる」人が、この世界には必要であって…
そういう人を「知識人」と呼ぶならば、それは社会にとって、世界にとってポジティブなものでしかありえない、と私は思います。