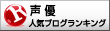『分かれ道-ユダヤ性とシオニズム批判』(ジュディス・バトラー著)のレビューも5回目。
みなさん、いい加減飽きてしまったことでしょう。ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。
そして5回とも読んで下さった方には、心からお礼申し上げます。
5回に渡って長々と書いても、まだ感想としては書き足りない気がしますが…
今回で終わりとさせていただきます。やっと。
最後に扱うのは、第七章と第八章です。
●絶滅収容所体験の政治利用
第七章で評論の対象として扱われているのは、ユダヤ系イタリア人の作家、プリーモ・レーヴィです。
彼はいくつかあったナチスの「絶滅収容所」の中で間違いなく一番有名で、おそらく誰もが知っているアウシュヴィッツからの生還者です。
絶滅収容所から生還した人々には、意外なことに…と言って良いのかどうか分かりませんが、後に自死した人が多いことが知られています。
せっかく奇跡的に命を拾ったのに、なぜか。理由は第三者によって、いろいろと考察されているのでしょうけれど…
レーヴィも最後は自ら命を絶ちました。彼の場合はなぜだったのか。
彼は戦後、ユダヤ人絶滅収容所の体験を、積極的に「語る」作品をいくつも書いています。
そして後年、戦後にナチスの弾圧によって難民となったユダヤ人の「安住の地」という名目で建設されたイスラエル国家について…
厳しい批判的言説を展開しました。当然それは反ユダヤ主義として、同胞から激しく攻撃されました。
1982年になって、レーヴィはアウシュヴィッツを再訪する際に、イタリアの新聞にこう書いています。
「誰もが誰かにとっての『ユダヤ人』である。そして今日においては、パレスチナ人がユダヤ人にとっての『ユダヤ人』なのだ」
彼が書いた絶滅収容所体験は、他のホロコースト(ヘブライ語で「ショア―」)に関する多くの記録がそうであったように…
イスラエル国家が戦後行って来たことー隔離壁、兵糧攻め、包囲攻撃、理由なき殺害などーの正当化に「政治利用」されました。
そのことに対する「ショアーの生き証人」としての抗議の気持ちが、レーヴィにはあったのでしょう。
しかし彼は、自分の街の壁に落書きされた、戦後ユダヤ人とナチスを同一視する、反ユダヤ主義のスローガンを見てショックを受けます。
一方ではアウシュヴィッツ体験から導き出される原則を、シオニストに利用され…
また逆に、それは、反ユダヤ主義的な言説にも政治利用されているのではないか…
その板挟みの中で、レーヴィは抑うつ状態になって行った…と。なんとも痛ましいことです。
最後の数年間のレーヴィについて、バトラーはこう書いています。
ドイツ人を憎んでいるかと問われたときレーヴィは、一国民全体を国民性に基づいてカテゴリー分けするべきではないし、できるとも思わない、と語っていた。
そしてこうも答えていたと。
私たちはホロコーストの苦難を持ち出して、すべてを正当化するようなことをしてはならない。
こうしたジレンマや悲劇は、ホロコースト=ショア―の体験だけでなく、戦争や政治的迫害の体験をした人々に普遍的なものなのかもしれません。
バトラーはこの章をこう結びます。
歴史的苦難を、現代におけるいかなる種類の政治的宣伝利用からも切り離すことは、私たちが、レーヴィの導きに従って、歴史を損なうことなく正しくとらえ、現在において正義のために闘うのなら、なすべきことの一部である。
歴史を損なうことなく、正しくとらえる……そうでなければ、歴史の体験を語ることは危険でもある、という教訓です。
ユダヤ人とは全く違う戦争体験を持つ私たちは、どうとらえるべきでしょうか。
個人的には、日本人の間で語られる「戦争体験」は99.9%が、空襲の体験や食料不足、被爆体験など…
「被害者」としての体験であると思っています。
それも「どうしてそのような目に遭ったのか」という部分が、全く欠落した形で語られるものです。
戦争は人間が行うものです。地震や水害・土砂災害のような天災とは全く違う。
それなのに、まるで不運な、そして避けられない天災にでも遭ったかのような感覚で「大変だった、つらかった」ことだけが語られる。
そして漠然と「戦争はいやだ」「戦争はだめだ」と。それだけです。
これで、現代の人々に何か役に立つ教訓が、そこから引き出されるでしょうか?
戦争がいやで、だめなら「なぜ起きたのか」「何がいけなかったのか」「責任を負うのは誰か」について語られなければ、ほとんど意味がない。
もう二度と、と口だけで言ったところで、どれほどの影響があるでしょう。
実体験のない人に漠然と伝えたところで、心に響くものが十分に多いという保証はない。
そして、あの戦争は我々にとって、被害一辺倒のものだったのか、という重大な問題が残ります。
空襲だけが、空腹だけが「戦争」のすべてではない。考えてみれば、当たり前のことです。
そして「対米戦」だけが戦争ではなかった。陸軍兵力の大半は、大陸に投入されていたわけですから。
その「戦地」では何が起きていたのか、何が行われていたのか…そこに「加害」というものが必然的に立ち現れて来ます。
そこをほぼ完全に避けている…おそらくは、意図的に避けられている部分があるのではないでしょうか。
歴史の中の体験が「政治」によって汚され、変質されている。それは我々の国でも同じことです。
そんな「被害の側面一辺倒」で「まるで天災みたいな」戦争体験でさえもが、最近は風化して…
物心ついた状態で、きちんと体験した人自体が、もうほとんどいなくなって来ている。
私たちは、大丈夫でしょうか?
●未来に語りかけることば
第八章(最終章)のテーマは、パレスチナ人思想家のエドワード・サイードと、同じくパレスチナ人の詩人マフムード・ダルウィーシュです。
章の後半では、2003年にサイードが亡くなった際に、友人でもあったダルウィーシュが、友への追悼のために捧げた詩…
「エドワード・サイード 対位法的読解」という詩の読み解きを中心に話が進みますが…
その前段で、著者のバトラーはこんなことを書いています。
事実、イスラエルは、現状の形態では、収奪のメカニズムなくしては自らをイスラエルとして維持することができない…イスラエルがさらされている脅威は、収奪と強制退去/国外追放にその存在を根源的に依拠するイスラエルのありようの帰結である。
そうなってしまう原因のひとつとして、イスラエルはその国家内でのユダヤ人の独占的な主権を維持するために…
あくまでもユダヤ人の数的な優位を保たねばならないということがあります。
しかし人口の増加率は、アシュケナジーム=ヨーロッパ系ユダヤ人よりも、パレスチナ人を含む少数民族たちの方がずっと高い。
結果、どうしなければならないか。国外からの「ユダヤ人」の継続的な植民地型入植を継続する、だけではとても足りません。
それとともに、パレスチナ人はもちろんそれ以外の少数民族の土地を奪い、強制退去させ、食料や水を手に入れ難くするなど…
様々な迫害を伴う、占領政策を続けなければいけない。そして、その恒久的な植民地主義を隠蔽し続けなければならない。
支配的な植民地構造の維持と、それを可能にしている軍事力がなければ、解体に向かってしまう運命の国家なのです。
そういうわけで…
文化的善意を「両側」で養おうとする…共存プロジェクトが問題含みであり続ける理由のひとつは、こうしたプロジェクトが、入植型植民地主義の構造と向き合えずにいるからである…これが間違った方向性であるのは…構造的不平等という土台の上に、みせかけの対等プロジェクトを据えている…
からだと、バトラーは論じます。「みんな仲良くしようよ」などという理念では、ユダヤ人、パレスチナ人を含む他民族の衝突は終わらない。だから…
現時点では…前途有望な二国民主義の兆しはほとんどない
ということになっている。
それほどこの土地での「民族間の共存」はもはや難しくなっており、解決の糸口さえ見えないのです。
この問題に関わって、バトラーは、パレスチナ詩人ダルウィーシュが、友人のサイードに贈った追悼の詩を引合いに出して来ます。
彼はこうも言った/もし私が君の先に死んだなら/私が遺すのは不可能なものだ/私は尋ねた、それは、はるかかなたにあるのかい?/彼は言った、ひと世代向こうにね(……)
彼は言う、私はあそこから来た、私はここから来た/しかし、私はあそこにもここにもいない。/私には出会いそして別れる二つの名がある/私にはふたつの言語があるが、忘れてから久しい/どちらが私の夢の言語なのかを(……)
彼は言う、私たちは生きるだろう。/だから、さあ、言葉の主人になろう/その読み手を不死の人とするような言葉の……
ダルウィーシュの詩の中で語りかけるサイードは、彼が遺すのは「不可能なものだ」と言います。
パレスチナ問題の解決は、不可能なものだ、ということでしょうか。
確かに、不可能と言ってしまった方が良いようなものであるでしょう。
しかし、ダルウィーシュの「不可能なものは、はるかかなたにあるのかい」という問いに対して、詩の中のサイードはこう答えます。
「ひと世代むこうにね」と。
ひと世代むこうにあるということは「それは不可能なもの」ではない、ということでしょうか。
ただ私たちの世代には不可能だ、というだけのことで?
バトラーはこう書いています。
このパラドクスを理解するかどうかは私たちにゆだねられているのだろう。可能な生とは、不可能なものを志す生だという逆説を。
そしてまた、こうも言います。
(ここで)創造されているのはサイードその人である。彼がもはや語ることのできない時間のなかで語るサイード。彼の民が、カタストロフの時代を超えて、別の時代へと移行することを保証しながら。だとすればこの詩は、語りへの希望をまさに創造しているのだ。
そしておそらくまた、この詩は遂行的な力によって言葉と訴えを伝えるのだ。「わたしたちは生きるだろう」と申し立て、そして予言するために。それは希望の宣言だ。だが同時に、計り知れない自信の宣言でもある。
そして、この詩の最後に来るのは、次の別れの言葉です。
さようなら/さようなら、痛みの詩よ
バトラーはこれについて、次のように書いています。
もしひとがサイードの最後の願いを引き受けようとするならば、そのとき痛みの詩は、不可能を志す詩によって乗り越えられることとなる。
それはその読者を戒め檄する。行動せよ、語れ、考案せよ、不可能を志せと、読者を鼓舞する。そこでいう不可能なものとは、はてしなく続くカタストロフとは異なる未来だが、それだけでなくカタストロフとの断絶でもあり、それはまさに未来の可能性ともなろう。
それは国民の神話を遺棄することにかかっている、二国民主義に対する問いでもある…
ほとんど勝機のない中で、詩が私たちに指し示すのは進むべき方角ではなく、新たな政治地図の作図法だ…
「彼は言う、私はあそこから来た、私はここから来た、だが私はあそこにもここにもいない」。こうした詩行を語り得るのは誰だろう。イスラエル国家の内部にいる者たちだろうか。たしかにそうだ。西岸地区やガザのパレスチナ人たちはどうだろう。まちがいない。レバノン南部の難民キャンプはどうか。もちろんだ。
故国喪失とは別離(セパレイション)の謂だ。けれど連帯はまさにそこに見いだされる。そこはひとつの場所ではいまだなく、かつてあった、いまある、いまだない不可能な場所だーーそれはいま、起こっているのだ。
「不可能だが為さねばならないこと」という言い方は、この本の他の部分でバトラーが何度か使っています。
不可能でも、やら「ねばならない」こと、というのは、確かにあるのです。未来の子や孫のために。
不可能に思われても、無駄に見えても、それは今その場所に生まれて来た人間の責務です。
今は不可能であることが、いつか可能になる道筋を、今の人間がつけねばならないのです。
「現実的でない」という言葉でそれを回避するのは、卑怯者の「逃げ」です。
生きるというのは、厳しいことです。
国民間、人種間の溝や対立、過去のいまわしい記憶といったものは、世界のいたるところにある普遍的なものです。
この本に書いてある、イスラエルとパレスチナの問題は、世界のすべての地域の人々の問題でもあります。
歴史の中で海に隔てられて、それほど厳しい「他者」との軋轢を経験して来なかった我々日本人も、これからはそうはいかないことでしょう。
とくに、世界一の高齢化社会、すなわち「動ける働き手」不足に直面する日本人なのですから。
そして、不安定な東アジア情勢のただなかにいる日本人なのですから。
いつの日かユダヤ人やパレスチナ人のように…
故国喪失(エグザイル)と散逸の運命に見舞われることだって、絶対にないとは言えないと思います。
パレスチナとユダヤの問題は、だから、決して他人事ではない。
画面に映る、遠い場所のこと……であり続けるかどうかは、誰にも分かりません。