シベコンチームの皆さんこんにちは。シベコン広報部長のクレタです。
いよいよ2011-2012シーズンがスタートしましたね。音楽の秋、皆さんはいかがお過ごしですか。幸運なことに、私は昨シーズンに続いて今シーズンも、シベコンの演奏会がシーズンの幕開けになりました。というわけで、今日はヴィルデのシベコンレポートをお休みして、シベコンまわりの近況について書きたいと思います。
まず、9月のシベコンから。
9月11日にN響定期を聴きに行きました。私は別にN響ファンじゃないけれど、「シベリウスヴァイオリン協奏曲」をキーワードに検索するとN響定期に辿り着くという状況が昨シーズンから続いていて、思えば昨年の9月11日もN響定期でシベコン(ミハイル・シモニアン/指揮ネヴィル・マリナー)を聴いています。N響のシベコンはこれで3度目。他のオケも含むと7度目のシベコン体験です。
今では私もすっかりうるさ型のシベコンウォッチャーとなり、「たぶん今回もコンマスは堀さんで、チェロは藤森さんね。いつもはクールな藤森さんも、第3楽章の16ビートになると異様にいきいきと、前ノリで演奏するのよね~。」と、着眼点もどんどんマニアックになっています。
しかし、敵もさるもの。9月のN響定期には、そんなうるさ型の常連をも黙らせる大物ソリストがブッキングされています。
そのソリストとは、誰あろうレオニダス・カヴァコス。
カヴァコスについて、シベコンチームの皆さんにあえて説明する必要はないでしょう。1世紀に及ぶシベコンの歴史を語る上で欠かせない演奏家のひとりであり、1991年にラハティ交響楽団と組んで録音したCD(指揮オスモ・ヴァンスカ)が、シベコン史上に残るマスターピースであることは周知のとおりです。

そのカヴァコスのシベコンが、この極東の島国で、生で、一万円以下で聴ける。
「ビバNHK!」と、私が狂喜したのは言うまでもありません。
私はカヴァコスを今シーズンのシベコンの大本命に位置づけ、彼の演奏を後顧の憂いなく楽しむために、時と金を惜しまず、できる限りの準備をしました。私は発売開始と同時にN響ガイドに電話してA席(S席じゃないところがせこい)を確保しました。イメージトレーニングのために件のCDも買いました。自慢じゃないけど、それはものぐさビンボーの私にとって破格の先行投資でした。
それなのに、ああ、それなのに、

これは痛かった。期待が大きかったぶんダメージも大きくて、いつもなら高嶺の花のNHKホールのA席(S席じゃないところが・・・)に座っても心は沈んだまま。
急きょ代打に立つヴァイオリニストの竹澤恭子さんに対しても、
「誰を後釜に据えようがこのダメージは挽回できない、誰もカヴァコスには及ばない。」
なーんて、はなから上から目線でダメ出ししていました。
でもそれは演奏が始まるまでのこと。
いざ聴いてみると、この竹澤さん、
なかなかどうして、大向こうを唸らせる実力派でした。
はでなところはないけど深く考えさせる音楽。
その充実ぶりはどっしりとしたフルボディのワインのよう。

それに比べて自分は軽薄だな。
私は自分がカヴァコスより竹澤さんを格下に見なして侮っていたことを恥ずかしく思いました。ネームバリューや既成概念にとらわれて、もっと大事なものを見落としていたことを、竹澤さんは演奏を通して私に教えてくれました。
カヴァコスのシベコンが聴けなかったのはもちろん残念なことでした。でも彼ほどのスーパースターなら、いずれどこかでリベンジの機会は巡ってくる気がします(昨シーズンも来日してメンコン弾いてたし)。それよりも、竹澤恭子さんというすてきなヴァイオリニストを、今このタイミングで発見できた喜びのほうが自分の中では大きくて、それはマイナス面を差し引いてもお釣りがくるくらい価値のあることでした。
シベコンにはまだまだ学ぶべきものがあるんだな。そう思って、あらためて闘志(?)を燃やす、意義深い演奏会でした。めでたし、めでたし。
そして、シベコンに関してめでたいお知らせがもうひとつ。
神尾真由子さんについてはカヴァコス同様、シベコンチームの皆さんに説明の必要はありませんね。2010年5月にBBC交響楽団を従えて演奏されたシベコンは、彼女の類まれなる歌心によって歴史を塗り替える名演となりました。
演奏会のレビューは こちら
その神尾さんが「東芝グランドコンサート2012」の看板を担って、再びシベコンを弾くというではありませんか!

今でこそ「シベコンチーム」だの「シベコン広報部長」だの、好き放題に大口をたたいているクレタですが、もともとはG線とE線の区別もつかない市井のいちリスナーにすぎませんでした( 今でもそうだって)。私のターニングポイントは上述の演奏会を聴いたことで、以来、神尾さんの比類なき才能とひたむきな情熱は私のイマジネーションの源泉となり、そのイマジネーションをレビューの形でアウトプットすることで、私のクラシック生活は計り知れないほど豊かになりました。私のレビューは諸般の事情から第2楽章で中断していますが、神尾さんはもう新しい第1楽章を始めようとしている。
今でもそうだって)。私のターニングポイントは上述の演奏会を聴いたことで、以来、神尾さんの比類なき才能とひたむきな情熱は私のイマジネーションの源泉となり、そのイマジネーションをレビューの形でアウトプットすることで、私のクラシック生活は計り知れないほど豊かになりました。私のレビューは諸般の事情から第2楽章で中断していますが、神尾さんはもう新しい第1楽章を始めようとしている。
なんて、頼もしい。
おまけにその演奏が東京だけじゃなくて、名古屋と大阪でも聴けるとは。
つくづく、頼もしい。
あれからはや2年。神尾さんはその不世出の歌心にさらに磨きをかけて、シベコンの魅力を日本中の音楽ファンに伝道してくれることでしょう。
*** ***
最後に、シベコンネタではないのですが、
N響つながりで、9月のCプログラムについて少し書かせて下さい。
ノルウェーのピアニスト、アンスネスがラフマニノフのピアノ協奏曲3番を弾くというので、夫とふたりで聴きに行ってきました。ラフマニノフは夫がもっとも共感を寄せる音楽家で、特にピアノ協奏曲3番が大のお気に入り。そのため、この曲を語る時の夫はとても熱い。どれくらい熱いかというと、シベコンを語る時の私くらい熱い。
そんな夫がアンスネスの演奏を聴いて発した第一声は、
このラフ3が、これから僕のベンチマークになる!
続く第二声は、
類まれなる才能を持つひとりがいるだけで、凡庸なオーケストラが
類まれなる演奏をしてしまう見本のような演奏だ!
なるほど。私はN響を決して凡庸なオケとは思わないが、アン様のラフ3が傑出していたことに異論はなく、「うわ~、すごいもの聴いちゃったね。もう昔には戻れないね・・・ 」と、夫婦そろって客席で遠い目になってしまいました。
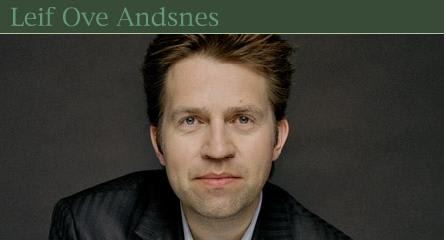
私達は何年か前に、アンスネスの弾くラフマニノフのピアノ協奏曲2番も聴いています。でも(座席の位置のせいかもしれないけど)、私は前回とは比較にならないほどの感銘を受けました。感銘を受けたというよりも、励まされた。
アンスネスの演奏はとても音色が美しく、技巧も的確です。
でもそれは彼の音楽世界の、ほんのとりかかりの部分に過ぎなくて、フランス料理で言えば食前酒のシャンパンみたいなものだったりします。
前回のラフ2では、私はそのシャンパンの味を楽しんだだけで、その奥にある、メインディッシュの部分の味わいはわかりませんでした。まだそこまで舌が(耳が)肥えていなかったのです。
今回のラフ3も、もちろん磨き抜かれた音色と超絶技巧は健在でした。でもこの人はそれに溺れるタイプではなく、むしろここぞ!というときに垣間見せるまっすぐな勇気と、その勇気を支えている知性にこそ演奏家としての真価があります。私はようやく念願のメインディッシュに辿りつき、その気高いスピリットに強く励まされました。
この演奏会のもようは2011年10月9日(←明日です!)のN響アワーでオンエアされます。生演奏の現場で彼から放たれて私が受け取ったもののうちの、どこまでが録画で再現されるかわからないけど、もう一度じっくり聴き直したいと思います。興味のある方はこの素晴らしい演奏を是非聴いてみてください。
というわけで、長いテキストになりましたが、今日はここで失礼します。
天候に恵まれそうな3連休、皆さん、どうぞ楽しくお過ごしください。
いよいよ2011-2012シーズンがスタートしましたね。音楽の秋、皆さんはいかがお過ごしですか。幸運なことに、私は昨シーズンに続いて今シーズンも、シベコンの演奏会がシーズンの幕開けになりました。というわけで、今日はヴィルデのシベコンレポートをお休みして、シベコンまわりの近況について書きたいと思います。
まず、9月のシベコンから。
9月11日にN響定期を聴きに行きました。私は別にN響ファンじゃないけれど、「シベリウスヴァイオリン協奏曲」をキーワードに検索するとN響定期に辿り着くという状況が昨シーズンから続いていて、思えば昨年の9月11日もN響定期でシベコン(ミハイル・シモニアン/指揮ネヴィル・マリナー)を聴いています。N響のシベコンはこれで3度目。他のオケも含むと7度目のシベコン体験です。
今では私もすっかりうるさ型のシベコンウォッチャーとなり、「たぶん今回もコンマスは堀さんで、チェロは藤森さんね。いつもはクールな藤森さんも、第3楽章の16ビートになると異様にいきいきと、前ノリで演奏するのよね~。」と、着眼点もどんどんマニアックになっています。
しかし、敵もさるもの。9月のN響定期には、そんなうるさ型の常連をも黙らせる大物ソリストがブッキングされています。
そのソリストとは、誰あろうレオニダス・カヴァコス。
カヴァコスについて、シベコンチームの皆さんにあえて説明する必要はないでしょう。1世紀に及ぶシベコンの歴史を語る上で欠かせない演奏家のひとりであり、1991年にラハティ交響楽団と組んで録音したCD(指揮オスモ・ヴァンスカ)が、シベコン史上に残るマスターピースであることは周知のとおりです。

そのカヴァコスのシベコンが、この極東の島国で、生で、一万円以下で聴ける。
「ビバNHK!」と、私が狂喜したのは言うまでもありません。
私はカヴァコスを今シーズンのシベコンの大本命に位置づけ、彼の演奏を後顧の憂いなく楽しむために、時と金を惜しまず、できる限りの準備をしました。私は発売開始と同時にN響ガイドに電話してA席(S席じゃないところがせこい)を確保しました。イメージトレーニングのために件のCDも買いました。自慢じゃないけど、それはものぐさビンボーの私にとって破格の先行投資でした。
それなのに、ああ、それなのに、
カヴァコス、ドタキャン!?

これは痛かった。期待が大きかったぶんダメージも大きくて、いつもなら高嶺の花のNHKホールのA席(S席じゃないところが・・・)に座っても心は沈んだまま。
急きょ代打に立つヴァイオリニストの竹澤恭子さんに対しても、
「誰を後釜に据えようがこのダメージは挽回できない、誰もカヴァコスには及ばない。」
なーんて、はなから上から目線でダメ出ししていました。
でもそれは演奏が始まるまでのこと。
いざ聴いてみると、この竹澤さん、
なかなかどうして、大向こうを唸らせる実力派でした。
はでなところはないけど深く考えさせる音楽。
その充実ぶりはどっしりとしたフルボディのワインのよう。

それに比べて自分は軽薄だな。
私は自分がカヴァコスより竹澤さんを格下に見なして侮っていたことを恥ずかしく思いました。ネームバリューや既成概念にとらわれて、もっと大事なものを見落としていたことを、竹澤さんは演奏を通して私に教えてくれました。
カヴァコスのシベコンが聴けなかったのはもちろん残念なことでした。でも彼ほどのスーパースターなら、いずれどこかでリベンジの機会は巡ってくる気がします(昨シーズンも来日してメンコン弾いてたし)。それよりも、竹澤恭子さんというすてきなヴァイオリニストを、今このタイミングで発見できた喜びのほうが自分の中では大きくて、それはマイナス面を差し引いてもお釣りがくるくらい価値のあることでした。
シベコンにはまだまだ学ぶべきものがあるんだな。そう思って、あらためて闘志(?)を燃やす、意義深い演奏会でした。めでたし、めでたし。
そして、シベコンに関してめでたいお知らせがもうひとつ。
神尾真由子さんについてはカヴァコス同様、シベコンチームの皆さんに説明の必要はありませんね。2010年5月にBBC交響楽団を従えて演奏されたシベコンは、彼女の類まれなる歌心によって歴史を塗り替える名演となりました。
演奏会のレビューは こちら
その神尾さんが「東芝グランドコンサート2012」の看板を担って、再びシベコンを弾くというではありませんか!

今でこそ「シベコンチーム」だの「シベコン広報部長」だの、好き放題に大口をたたいているクレタですが、もともとはG線とE線の区別もつかない市井のいちリスナーにすぎませんでした(
 今でもそうだって)。私のターニングポイントは上述の演奏会を聴いたことで、以来、神尾さんの比類なき才能とひたむきな情熱は私のイマジネーションの源泉となり、そのイマジネーションをレビューの形でアウトプットすることで、私のクラシック生活は計り知れないほど豊かになりました。私のレビューは諸般の事情から第2楽章で中断していますが、神尾さんはもう新しい第1楽章を始めようとしている。
今でもそうだって)。私のターニングポイントは上述の演奏会を聴いたことで、以来、神尾さんの比類なき才能とひたむきな情熱は私のイマジネーションの源泉となり、そのイマジネーションをレビューの形でアウトプットすることで、私のクラシック生活は計り知れないほど豊かになりました。私のレビューは諸般の事情から第2楽章で中断していますが、神尾さんはもう新しい第1楽章を始めようとしている。なんて、頼もしい。
おまけにその演奏が東京だけじゃなくて、名古屋と大阪でも聴けるとは。
つくづく、頼もしい。
あれからはや2年。神尾さんはその不世出の歌心にさらに磨きをかけて、シベコンの魅力を日本中の音楽ファンに伝道してくれることでしょう。
*** ***
最後に、シベコンネタではないのですが、
N響つながりで、9月のCプログラムについて少し書かせて下さい。
ノルウェーのピアニスト、アンスネスがラフマニノフのピアノ協奏曲3番を弾くというので、夫とふたりで聴きに行ってきました。ラフマニノフは夫がもっとも共感を寄せる音楽家で、特にピアノ協奏曲3番が大のお気に入り。そのため、この曲を語る時の夫はとても熱い。どれくらい熱いかというと、シベコンを語る時の私くらい熱い。
そんな夫がアンスネスの演奏を聴いて発した第一声は、
このラフ3が、これから僕のベンチマークになる!
続く第二声は、
類まれなる才能を持つひとりがいるだけで、凡庸なオーケストラが
類まれなる演奏をしてしまう見本のような演奏だ!
なるほど。私はN響を決して凡庸なオケとは思わないが、アン様のラフ3が傑出していたことに異論はなく、「うわ~、すごいもの聴いちゃったね。もう昔には戻れないね・・・ 」と、夫婦そろって客席で遠い目になってしまいました。
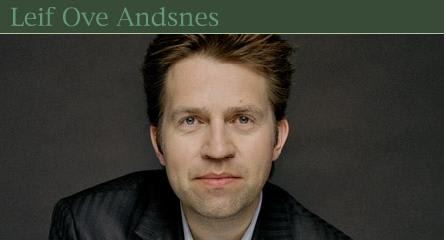
私達は何年か前に、アンスネスの弾くラフマニノフのピアノ協奏曲2番も聴いています。でも(座席の位置のせいかもしれないけど)、私は前回とは比較にならないほどの感銘を受けました。感銘を受けたというよりも、励まされた。
アンスネスの演奏はとても音色が美しく、技巧も的確です。
でもそれは彼の音楽世界の、ほんのとりかかりの部分に過ぎなくて、フランス料理で言えば食前酒のシャンパンみたいなものだったりします。
前回のラフ2では、私はそのシャンパンの味を楽しんだだけで、その奥にある、メインディッシュの部分の味わいはわかりませんでした。まだそこまで舌が(耳が)肥えていなかったのです。
今回のラフ3も、もちろん磨き抜かれた音色と超絶技巧は健在でした。でもこの人はそれに溺れるタイプではなく、むしろここぞ!というときに垣間見せるまっすぐな勇気と、その勇気を支えている知性にこそ演奏家としての真価があります。私はようやく念願のメインディッシュに辿りつき、その気高いスピリットに強く励まされました。
この演奏会のもようは2011年10月9日(←明日です!)のN響アワーでオンエアされます。生演奏の現場で彼から放たれて私が受け取ったもののうちの、どこまでが録画で再現されるかわからないけど、もう一度じっくり聴き直したいと思います。興味のある方はこの素晴らしい演奏を是非聴いてみてください。
というわけで、長いテキストになりましたが、今日はここで失礼します。
天候に恵まれそうな3連休、皆さん、どうぞ楽しくお過ごしください。










 ・・・なんて月並みな話題じゃあ、今どき読み手の心をそそらないのかもしれません。そもそも半年以上前(!)の、しかも震災前の演奏会を回顧するテキストをブログで更新して、そこにどんな意味があるのかという気もします。インターネット上の情報の多くは目先のものであり、それらの多くは時間の経過とともに価値を失います。もし私が万人に向けてブログを書くとしたら、こんな古い話題はさっさと切り上げて、もっとタイムリーな話題に目を向けることでしょう。過去の記憶を思い返して文章を組み立てるよりも、直近の体験をメモ風にパッケージしてリリースするほうがはるかに効率的です。
・・・なんて月並みな話題じゃあ、今どき読み手の心をそそらないのかもしれません。そもそも半年以上前(!)の、しかも震災前の演奏会を回顧するテキストをブログで更新して、そこにどんな意味があるのかという気もします。インターネット上の情報の多くは目先のものであり、それらの多くは時間の経過とともに価値を失います。もし私が万人に向けてブログを書くとしたら、こんな古い話題はさっさと切り上げて、もっとタイムリーな話題に目を向けることでしょう。過去の記憶を思い返して文章を組み立てるよりも、直近の体験をメモ風にパッケージしてリリースするほうがはるかに効率的です。
 」で始まる、この息の長いテーマに、般若心経レベルの呪術性を感じるのは私だけでしょうか。前回も書いたように、シベリウスはこの冒頭部分について「極寒の空を滑空する鷲のように」という言葉を残していて、私はその言葉を、コンサートホールでシベコンを聴く時のマントラにしています。チベットの坊さんが「色即是空、空即是色」と唱えて現世からの解脱を試みるのと同様に、私は現実という檻を離れて自由に心を解き放つために、この言葉で自らに暗示をかけるわけです。
」で始まる、この息の長いテーマに、般若心経レベルの呪術性を感じるのは私だけでしょうか。前回も書いたように、シベリウスはこの冒頭部分について「極寒の空を滑空する鷲のように」という言葉を残していて、私はその言葉を、コンサートホールでシベコンを聴く時のマントラにしています。チベットの坊さんが「色即是空、空即是色」と唱えて現世からの解脱を試みるのと同様に、私は現実という檻を離れて自由に心を解き放つために、この言葉で自らに暗示をかけるわけです。

 を打ち明けてしまわないともかぎりません。夫にシベコンデビューさせたいのはヤマヤマです。前回も前々回も、ふたりぶんのチケットを買おうとしました。でもその余波で自分がカミングアウトを迫られることを考えると、それは私の本意ではなく、悩んだ挙句、結局ひとりで聴くことになったのです。
を打ち明けてしまわないともかぎりません。夫にシベコンデビューさせたいのはヤマヤマです。前回も前々回も、ふたりぶんのチケットを買おうとしました。でもその余波で自分がカミングアウトを迫られることを考えると、それは私の本意ではなく、悩んだ挙句、結局ひとりで聴くことになったのです。 、チケットが手ごろな値段
、チケットが手ごろな値段  、プログラム前半がシベコンで後半はセンチメンタルなブラ4
、プログラム前半がシベコンで後半はセンチメンタルなブラ4  と、三拍子そろったデート仕様の内容で、宣伝用のチラシを見た私はすぐにこんな歌を思い浮かべました。
と、三拍子そろったデート仕様の内容で、宣伝用のチラシを見た私はすぐにこんな歌を思い浮かべました。 、知らない人のために説明すると、1987年に出版された俵万智の歌集「サラダ記念日」は、日本中に短歌ブームを巻き起こした大ベストセラーです。加えてこの歌集はバブル経済で景気が良かった頃の日本文化の象徴でもあります。バブルの頃私は20代で、イケイケではない普通の若者だったけど、それでも当時の記憶の多くは享楽的な祝祭モードに彩られています。気がつけば、私はチケットをペアで購入していただけでなく、近所で評判のフランス料理店に予約まで入れていました。バブルの記憶おそるべし。夫に話すと、堅苦しいのは苦手
、知らない人のために説明すると、1987年に出版された俵万智の歌集「サラダ記念日」は、日本中に短歌ブームを巻き起こした大ベストセラーです。加えてこの歌集はバブル経済で景気が良かった頃の日本文化の象徴でもあります。バブルの頃私は20代で、イケイケではない普通の若者だったけど、それでも当時の記憶の多くは享楽的な祝祭モードに彩られています。気がつけば、私はチケットをペアで購入していただけでなく、近所で評判のフランス料理店に予約まで入れていました。バブルの記憶おそるべし。夫に話すと、堅苦しいのは苦手  と二の足を踏むと思いきや、意外にも大乗り気。というわけで、俵万智のみそひともじをきっかけに、それまでの孤高のマントラモードは一転してフレンドリーなイベントモードに切り替わり、演奏会当日は夫婦揃って一張羅を着て客席に座ることになりました。こうなるともう極寒の空を滑空する鷲どころではなく、私が春先の蝶々のように浮かれていたのは前回のテキストに書いたとおりです。
と二の足を踏むと思いきや、意外にも大乗り気。というわけで、俵万智のみそひともじをきっかけに、それまでの孤高のマントラモードは一転してフレンドリーなイベントモードに切り替わり、演奏会当日は夫婦揃って一張羅を着て客席に座ることになりました。こうなるともう極寒の空を滑空する鷲どころではなく、私が春先の蝶々のように浮かれていたのは前回のテキストに書いたとおりです。