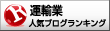応援よろしくお願いします。
前回は、国鉄当局が民営化を睨んで期末手当の支給について査定制度を導入することに対して、最大組織である国労の意見を述べてきましたが、今回は、労使協調宣言を結んで、かっての国労とは一線を画した対応を見せる動労の見解です。
公企労レポートによりますと。
動労の佐藤武副委員長は、今回の期末手当の支給について勤務成績を反映する事に対して、下記のとおり答えています。
今回国鉄が、ボーナスの査定制度を導入したことは、国鉄の今おかれている状況を抜きにしては考えられません。
つまり、雇用問題で労使が苦労している中で出されたわけであり、動労としてもこの間に、共同宣言、広域移動、派遣問題などを積極的に取り組んできました。
ですから、動労の組合員を正しく当局からの評価を受けることになると信じており、今回の提案も積極的に受け止めたいと考えております。
今までは、悪平等がはびこっており、苦労しているものとしていないものとの差をはっきりさせて苦労しているものには報いるべきだと思います。
今回当局に特に申し上げたいのは、動労の組合員は今までも、余剰人員解決のための企業人教育、派遣問題、広域移動などを受け入れてきました、そしてこれは良い人を選ぶものでしたが、今回の提案は悪い者を選び出すという意味がありますので、動労としてはそれを重視しているのです。
また、今回の制度は当局が今回の制度を導入する背景として、われわれ組合側からいう立場ではありませんが受け止める側として、今回の制度は「選別」であると捉えています。
われわれとしては、それを意識して対応してきたわけです。
今回の査定では、基準年齢で見たっ場合に、プラス・マイナス3万円の開きがあるのですが、個人的にはもっと差をつけてもよいと考えています。
つまり努力している人にはもっと報いるべきだということです、そういった意味では動労の組合員は全員がプラスであると信じています、ただし、当局は組合を査定するのではありませんが、動労の組合員は家族を含めてこの事態を認識して努力してきたわけですからこの点では、正しく評価をしていただけるものと信じています。
成績率の査定について々考えるかとの問に対しては、下記のように答えています。
公企労レポートの内容を引用しますと。
【成績率の判定は所属長ということですが、それに対する意見は】
提案内容を見ますと所属長、つまり管理局長と言うことになっていますが、材料を提供するのは現場の長です。現場の長だけで決めるわけではありませんがその評価が重くなるのは事実です。いっぽう所属長が査定するとなれば、そこでの判断がかりに1mm狂えば、下の方では10cmの狂いにもなるわけですから、慎重の上にも慎重にやってもらいたいと思います。
その辺これらの交渉の中で確認しながら、慎重な交渉をしたいと思います。いずれにしても、これは方法、手段の問題ですから、これを決めなければ金額の要求ができないし交渉に入れないわけで、じっくり交渉したいけどれど時間的な余裕が無いので、ここを抑えてなるべく早く解決したいと思います。
引用終了
ということで、動労としては今までの悪平等を断ち切るいい機会であり、当局にはそういった点を踏まえた上で、取り扱いには慎重を期してもらいたいと言う事でかっては鬼の動労と呼ばれた頃と比べると本来の労働者を守る組織としてして機能しているように思えます。
再び公企労レポートから引用しますと、
「一般の組合員はどう受け止めていますか】
内容はとにかくとして、こういうものはとうぜんでてくるものと予期していたものと思います。
動労のこれまでの取り組みは、こういうことを予測してやっていましたから、来るべきものが来たということです。いいか悪いかの議論ではない、こういう状況では当然と受けとめ、動揺はないと思います。
【特定の組合が妥結を拒否した場合、結果はどうなると見ておられますか】
国労も提案は受け多様です。しかし交渉がどうなるかということですね。他組合はとにかくわれわれは、早急にかつ慎重に交渉したい。当局とは人事協議会を130回やるなかで、こういう動きが見られたので早くから用意はしていました。23日のフォーラムで解明を求め、27日には明らかになるということ、内容もある程度知ったので24日の臨時中央委員会で全体の状況を報告、われわれの態度を確認しました。
【このことは、今後にも影響すると思いますが】
提案を見ますと、夏冬のことだけで、年度末のことにはふれていません。年度末は全く出ないのか、出てもわずかで差がついても2~300円ということだと思いますが、われわれは、いただくものはいただきたい。
いずれにしても、今回の提案の影響は大きいと思います。とにかくカットされる人には大きな意味があり。当局のきわめて巧妙なやり方と思います。
ということで、動労としては、今までの交渉を経たなかで当然の帰結として受け止めており、旧態然とした国労とはその温度差が鮮明になってきていることを感じることが出来る対応だと思われます。
注:年度末手当【別名、業績賞与と呼ばれるもので年度末に支給される賞与、郵政の場合は一般的には基準内賃金の0.5か月分が支給されていた。国鉄も動揺程度が支給されていたものと推測される。余談ではあるが、郵政の場合年度末賞与のみ現金支給であったため、家族に知られないへそくりにする人も多かったと記憶している。】
*****************************************************************
取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。
下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。
http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html
日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代
http://jnrera3.webcrow.jp/index.html
*****************************************************************