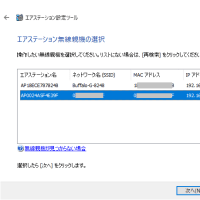2023.5.26 追記
予想よりも明るくならない可能性が出てきました。
詳しくはこちらをご覧ください。
追記終わり
いつも見ている福原直人さんの「星が好きな人のための新着情報 」で3月2日に明るくなると期待されている新彗星、紫金山-アトラス彗星 C/2023 A3 発見の情報がありました。
紫金山は中国の天文台の名前で過去にも彗星を発見していて番号登録された周期彗星が2つあります。
アトラスは以前も紹介した地球に衝突する恐れのある小惑星の発見を行っている自動観測システムの名前です。
吉田誠一さんのホームページが昨日更新されて情報が載っていました。
来年の9月28日に太陽に最も近づき(近日点)、その後、地球と最接近になるようです。
(軌道要素の T 2024 Sept. 28.55963 TT が世界時での近日点通過時刻です)
地球最接近の日の情報が出ていないのですが、星図の日ごとの移動量から推測すると10月13日前後のようです。
(地球に近いと移動量が大きくなる)
こちらの記事にも解説がありますが、近日点通過を10月10日と表記していて間違っていると思われます。
10月10日に太陽に最も近づくというのは見かけ上の位置関係の可能性がありますね。
そうなると彗星と地球の位置関係はとても良いことになり、塵の尾の実際の長さが長ければ見かけ上も長い尾を見ることが出来そうです。
近日点(太陽に最も近づいたところ)通過後、あまり日を置かずに地球に近づくということは明るくなることが期待されるわけです。
最大で0等級という予想が出ています。
近日点距離q=0.39ということで比較的太陽に近づくので核(中心の塊)が分裂すればもっと明るくなる可能性があります。
(分裂するには少し遠いかも)
アイソン彗星 C/2012 S1の時ほどは太陽に近づかないので消滅するということはなさそうです。
ただ、過去にもコホーテク彗星C/1973 E1 やオースチン彗星C/1989 X1のように太陽から遠い位置で明るく0等級クラスの大彗星になると期待されながら実際には3等級以上暗かったという事例があるのでどうなるかわかりません。
コホーテク彗星の時は友人が張り切っていましたが空振りに終わり、オースチン彗星の時は私自身、頑張ってみたのですが条件の良い空でも肉眼では確認できないほど暗かったです。
紫金山-アトラス彗星の救いは離心率eが1を切っているので周期数千年の長周期彗星であることです。
コホーテク彗星C/1973 E1 やオースチン彗星C/1989 X1は離心率が1を超えている放物線軌道で初めて太陽に近づいたと考えられています。
このような彗星は低い温度でも揮発する成分が多く含まれていて太陽から遠くても明るく見えると考えられています。
太陽に近づく前にこれらがなくなり暗くなってしまうということです。
太陽に何回も近づいている彗星は低い温度で揮発する成分が枯渇しているため予想外れになりにくいようです。
果たしてどうなるのか楽しみですね。
以前もお伝えした通り、マスコミが騒ぐと明るくならないとうジンクスがあるので本当に明るくなって来るまでは一般の報道機関では報道しないでもらいたいと思います。
(このジンクスが生み出されたきっかけの一つがコホーテク彗星です)
最近は天気予報コーナーでそれほど多くみられない流星群(例えば10月のオリオン座流星群等)でも紹介していることがあるので気になります。