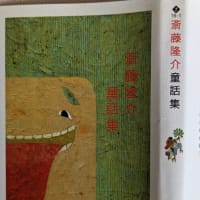壷井栄「二十四の瞳」の灯り
壷井栄「二十四の瞳」を読んだ。映画で観たこともある。
生涯にひとりでも、強い影響を受け、長い間慕いつづける「先生」と出会えた人は、幸福だといってよいのではないか。
この作品の先生は、体が小さいので「小石先生」とあだなをつけられた、「大石先生」が本名の女性教師である。
先生となった最初の受け持ちが、分教場の十二名の小学一年生。新米の先生と新米の小学生との出会いと別れ、そして再会、それが描かれている。
太平洋戦争の前から敗戦後までの日本。
貧しい暮らしが子どもたちの人生を裂く。さらに、むごいその戦争が、子どもたちの命をも裂いてしまう。
私の手元に一枚の写真がある。
白黒の古い写真。裏に「十年経っても二十年経っても仲良しでいましょうね」と書かれてある。男性の初老の先生がにこにこ笑っている。その前に、分教場の十名に満たない小学一年生が並んでいる(物語と似ている!)。木の橋の欄干(らんかん)からそろって河原を見下ろしている。高度成長期前の農村。みんな身なりは貧しいが、どの子も瞳は輝いている。無垢(むく)と呼べる最初の人生が映っている。
この物語の中に、脚を折ってしまった大石先生を見舞おうと、子どもたちが親に黙って八キロの道を歩いていく場面がある。小学一年生の足では、歩いても歩いても着けないような道のり。おなかを減らし、泣きべそをかきながら、でもようやく先生と会えた。
そこで、先生の提案で皆で記念写真を撮る。一枚の集合写真。子どもたち一人ひとりのその後の過酷さを支えた一枚の無垢の写真。それが私の一枚と重なった。
物語に描かれた十ニ名のそれぞれの人生、また時代背景は、ほんとうにリアルである。
哀しみもリアル、はじける笑いもリアル。苦しみもリアル。子どものずるさも大人のいじわるさもリアル。社会の黒い圧力もリアル。その圧力に屈してしまう、あるいは時代の風潮にのまれてしまう国民の弱さもリアル。しかし、それに負けまいとする反骨心もリアル。
途中幾度か胸がつまるような、つらい物語なのだが、しかし、まっすぐに貫いて輝く灯りがある。その灯りは強い。揺らがない。
それが大石先生の、十二名一人ひとりへの愛情である。貧しさも戦争も裂けなかった愛情である。そして、子どもたちの、大石先生への愛情である。貧しさも戦争も裂けなかった愛情である。
大石先生と出会えた子どもたちは幸いだった。その子どもたちと出会えた先生もまた幸いだった。
*この作品は、無料のインターネット文庫「青空文庫」でも読めます。
●ご訪問ありがとうございます。
ヒロシマの8月6日、ナガサキの8月9日、重い日だった。両市長の思いを込めた平和宣言、両市の子ども・成人の決意表明を、正座する思いできいた。広島県知事の一歩踏み込んだ挨拶も、響いた。記憶にとどめ、「微力だが無力ではない」ことを自分に課したい。
「二十四の瞳」を反戦文学ととらえれば、そうも読めるだろう。教育が舞台の。けれど、もっと広くもっと深く人間をみつめた作品だと、わたしは思う。いろんな場面が沁みた。
「反戦より厭戦」という気持ちが私には強い。いやだいやだ、戦争なんてごめんだ、この暮らしを暴力で恐怖で襲わないでくれ、破壊しないでくれ、という気持ちである。