



『天才バカボン』もまた、連載終了から九年ほどの時を経て、赤塚自らのリライトによる完全オリジナルとして、『おそ松くん』と同じく復活を遂げる。
1987年から92年に掛けて連載されたこのリメイク版『バカボン』は、アニメ『平成天才バカボン』(スタジオぴえろ製作)のオンエアとのタイアップを兼ねたシリーズでもあり、「コミックボンボン」、「テレビマガジン」、「ヒーローマガジン」、「デラックスボンボン」といった講談社系児童漫画誌を発表媒体としていた。
この『バカボン』リバイバルに到る経緯については、第八章にてページを割き、詳しく記述するが、1987年、テレビ東京で、アニメ『天才バカボン』、『元祖天才バカボン』が立て続けに再放映されたことにより、子供達の間で赤塚人気が再熱。このリピート放送は赤塚にとっても、奇跡の復活劇へと至る僥倖となった。
だが、新たにシリーズ化されたこれらの『バカボン』は、これまで培われた創作のノウハウを小出しにしつつ、作品を処理してゆくルーティンワークと化したものばかりで、いずれのシリーズも、旧『バカボン』のように、奇抜なアイデアを礎とする、ナンセンスな世界を体現した作品にはなり得ていない。
とはいえ、低学年向け作品であるこれら『バカボン』とは別に、「月刊少年マガジン」で復活連載した『バカボン』では、かつての「実物大漫画」や「説明付き左手で描いた漫画」といった、アバンギャルドな実験漫画に勝るとも劣らない鮮烈な刺激を湛えており、その不条理なセンシビリティーへの深化は、偶発的とはいえ、クラシカルな赤塚漫画の世界観を超出した、アーティスティックな類概念を発動するに至った。
当時、「月刊少年マガジン」で同時連載されていた、もとはしまさひでのバイオレンス系暴走族漫画『ヤンキー烈風隊』や、昨今のエロ萌え系コミックの元祖とも言える上村純子の『いけないルナ先生』がパロディーの対象となり、それらの登場人物が作中堂々と『バカボン』ファミリーと絡み合う、ヤマなし、意味なし、落ちなし、しかし、狂乱に満ちたカーニバル性を具有する、ポップ色豊かなバラエティーショーが、複数回に渡り執筆された。
その第一回目に当たる「わしの顔がヤンキーなのだ」(88年5月号)の大まかな粗筋は次のようなものだ。
ある朝、目覚めたら、『ヤンキー烈風隊』を読み過ぎたパパの顔が、この作品の登場人物である菊華連合の岩倉猛風のスカーフェイスになっていた。
やがて、その人格も凶暴、凶悪な自我を持つそれへと変貌。遂にパパに、岩倉のキャラクターそのものが憑依し、他の『バカボン』キャラに木刀でヤキを入れて暴れ廻るという、血生臭い暴虐性が全方位に向けて放出される超現実的仮定が、ドラマの主軸となって繰り広げられるが、最後は、ルナ先生のエッチな個人授業を受けて、落ち着きを取り戻し、元のバカボンのパパの姿に戻るといった、強引な落ちで幕を引く、所謂トンデモ漫画として描かれた。
因みに、このエピソードのラストのコマで、「もとはしまさひで ヤキを入れに来るなよ。オレにはケンタウロスがついているんだ」という、赤塚のメッセージが添えられている。
赤塚の言うケンタウロスとは、和製ヘルズ・エンジェルスとでも形容すべき、横浜を根城とする伝説のバイカーチームのことで、ケンタウロスの大将と赤塚は、兄弟分の盃を交わすほど熱い交友を持っていたことでも知られている。そうした関係から、このような失笑を禁じ得ないヘタレチックな挑戦状を、ネタとして、もとはしに叩き付けたのだろう。
続編となる「キケンがあぶない街なのだ!」(88年6月号)では、フジオ・プロで上村純子を裸で待っていたところ、もとはしまさひでの奇襲を受け、ボコボコにヤキを入れられたという設定で、赤塚本人が扉ページに登場。本編には、岩倉率いる菊華連合が現れ、『バカボン』ワールドをジャックする、何とも物騒なドラマが展開される。
続く、7月号掲載の「天才AKIRA」では、当時、漫画表現の一つの到達点として、世界的規模の人気と評価を得ていた大友克洋の『AKIRA』のワールドビューを、『バカボン』ファミリーがスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』のコンストラクションに絡めて再現する、ストレンジなパラレルワールドが創出された。
林立する超高層ビルが倒壊し、爆音をともに土煙が舞うお馴染みのシーンなどを、本家『AKIRA』にも引けを取らない緻密なタッチと壮大なスケールで完全コピーしている点は、スタッフワークとはいえ、間然するところが全くない。
トランキライザーを服用し、覚醒したレレレのおじさんが、島鉄雄の如く巨大化し、日本の伝統を失った原宿、六本木、赤坂、青山を竹箒で一掃しては、街全体を『AKIRA』の舞台となるネオ東京と同様に廃墟と化してしまう一連の流れは、幾分唐突でありながらも、生理的、情緒的高揚とは異質な、エンターテーメントに特化したカタルシスを喚起し、その脱力モードと先鋭的パロディーとの分水嶺を境界域とする笑いの匙加減は至って絶妙だ。
宙高く舞い上がるレレレのおじさんの竹ぼうきが、『美しく青きドナウ』をBGMに宇宙船へと形を変貌させるオマージュシーンも秀逸で、科学テクノロジーを媒介とする人類の進化に対し、クライシスを示唆する『AKIRA』の世界観と、人類とサイエンスの融合を新たな種の起源として捉えたキューブリックの哲学的メッセージから、同等の妥当性を導出しているところに、パロディーの次元を越えた、赤塚ならではの独創的且つコペルニクス的発想の妙が垣間見れる。因みに、ラストでは、長方形型の謎の物体・モノリスが出現。モノリスに導かれ、スペーストリップしたレレレのおじさんが、ボーマン船長と同じく、スター・チャイルド(胎児)へと転生し、地球をバックに宇宙空間を浮遊するといった、『2001年宇宙の旅』のパロディーへと切り替わる。
*
元々、赤塚漫画には、『おそ松くん』にオバQ、『もーれつア太郎』にデューク東郷、『レッツラゴン』に矢吹丈等が、突如、オマージュカットとして登場したり、〝オバQ&おそ松〟のブームの際には、『ギャハハ三銃士』、『オハゲのKK太郎』といった、作家や作品の枠を越え、人気キャラクターが度々共演する合作漫画が企画されたりと、赤塚自身、作品を面白くするなら、パロディーやコラボレーションも貪欲に取り入れる機を見るに敏な、自在な作家性を有した漫画家でもあった。
だが、これらのように、別作家の絵柄を露骨に引用することによって、丸々一本、エピソードとして仕立て上げてしまったのは、少年誌においては、初めてのケースであり、そういった意味では、これらのパロディーも、新たな笑いの起爆を射程に捉えた、赤塚ならではのゲリラ的ギャグ精神の健在ぶりを示したファインワークと言えなくもないだろうか。
(『松尾馬蕉』、『にっぽん笑来ばなし』といった成人向け作品では、各々、谷岡ヤスジ、東海林さだおのタッチを、一話ずつだが、パスティッシュとして融合させたエピソードもある。)
尚、かつてパロディー漫画の第一人者を名乗り、活動していた経歴から、これらの模倣画が、長谷邦夫によるものだという見解を示す向きもあるが、この精巧な絵柄は、長谷の拙劣且つ旧態依然の筆致では、決して描くことの出来ない高水準な筆力を要求されるもので、推測するに、当時フジオ・プロのチーフアシスタントだった峰松孝好、即ち、現在の吉勝太によって描かれたのではないかと思われる。
翌8月号では、バカボンのパパが恵比寿顔だけにエビスビール、バカボンが子供だけに、ノンアルコールのバービカン、ママがサントリーのママ(生)ビール、取締りがドライな目ん玉つながりはサッポロ・ドライと、『バカボン』キャラクターが酒に置換された、驚倒の仮想的並列世界「天才アルコール」が執筆される。
弁慶の如く、ビールの千本抜きを目指す栓抜きと、エビスビールのバカボンのパパとの対決軸を中心とするダウナーな着想に展開を求め、ドラマのインテグリティそのものを解体せんとした本作は、数ある『バカボン』の実験的エピソードにおいても、殊の外高い異質性を放つ一編だ。
登場人物が全て酒という、一見支離滅裂な状況生成を織り成しながらも、そのエクスプレッションは、シュールの概念を越え、更なる前衛への視野を開陳した、シュールの形而上学と例えて然るべき超常的ナンセンスになり得ている。
また、「天才アルコール」は、キャンベルのスープ缶のポスターに代表されるアンディ・ウォーホルのポップアート同様、平坦な空間の中にも、奥行きある彩度を表出しており、漫画の本道から離反した特異な世界観を呈示しつつも、その根底には、ウィットに富んだ赤塚ならではの遊び心が注がれている。
*
1988年バージョンの「月刊マガジン」版『バカボン』は、その最終回もまた、ホープレス極まりない、ナンセンスのタブーさえ侵犯する、観念的背徳に結末を委ねた内容だった。
パパとママが突然離婚し、愚兄賢弟に対する日頃の劣等感からか、バカボンがハジメを刺殺。更には、パパと目ん玉つながりが拳銃で撃ち合いをし、相撃ちとともに、両者果ててしまうという、非常にデンジャラスなものだが、その殺伐したカタストロフも、赤塚ギャグが持つ、何処までの野放図なナンセンスの位相空間故に許容される、危ういバランスの上に立脚したものだ。










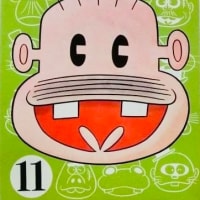









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます