




































(四) 雉鳴女 Kijinonakime
「 沖縄を単に「戦後」と、呼ぶべきじゃない! 」
修治は琉球本来の想像力にこそ、未来へと翔ぶ何枚もの羽根が生えていることを発見した。
薩摩や、日本や、アメリカと出逢う前の、かっての琉球は、真の未来派だったのだ。
壺川駅から北へ向かうゆいレールの車内では、乗客の大半が窓際に立ったままの修治の身なりをジロリとみた。
まず視線を修治の手元にチラリと止め、しだいにスイと垂直に下げ、足元辺りまでをキョロリとみる。そして眼をまた元に引き上げては、修治の顔色をジロリとみる。すると一度車窓の外に向けた視線を、また修治の顔にくるりと振り向けてきた。さらには、視点を安定させたかに修治のスタイルをしばし見つめていた。
「 これだけ熱くシャッフルな刺戟をしてくれると、塵も積もれば山となり、きっと文殊の知恵も出る 」
あなたの「わかる」は「かわる」のだが、その変わるが、分かるのだと、見つめられる修治はそう感じた。これは乗客らが修治の奇抜な姿にどこか普段ではない珍しいモノを発見したからだ。沖縄の生体に琉球は染みこんでいる。ラボラトリー気分を装う修治はシャッフルされることがじつに嬉しかった。プラトンは小ポリスにこそ理想を求めたのだ。
「 国力とか地域力とか個々の体力といった、今では手垢がついてしまったけれど、沖縄の本来はうんとナイーブなこれらの力の大元になるもの、つまり「美しい想像力」という得体の知れないものが生み出されてくる手立てについて、沖縄はすでに体得している 」
沖縄がどれほど途上県あつかいされようとも、かっての沖縄である琉球が修治にもたらしたものは、いつもいつも刺激に富んでいて、しかも快適で、修治は今日までそれを忘れたことがなかった。紅型をふくむ琉球衣装を見せられるのは、現代の日本人のような民族音痴には軽い痺れがやってくるような劣化する民族生体の刺戟になってよい。そこには到達した美意識がある。
「 東京音羽の住人たちは、そういうことはしない。また都内いたるところの人達もそうはしない。現実から大半が離れようとする 」
そう感じる修治は、モノレールの車内一つにも沖縄のゆるやかな時の流れを感じた。
それは沖縄に限らず、修治がそう感じる大半の街が、人口100万以下ほどの都市の器には満たない日本では平均水準にある相撲番付でいうと前頭一枚目以下の面々である。そこに共通してあるものは、人に止められる程度で流れる時の速度だ。現代の東京はこれを破壊させている。それを大都会の人は億尾なく忙しいというが、聞かされると欠伸こそあれ、生体に与える時間の本質はそう単純に科学で割り出せるモノではないだろう。東京は時間が萌えようと瞬いてみせる生体信号の本質を見落としている。
「 しかしこうもジロジロと品定めされると、どうにも居心地が悪い。気になると、無性にどこか気恥ずかしい。この感触は(男は強くなきゃ)みたいな感じで自身が人にそう感じさせている発見で、それに引き換え自身は、と思ってしまう懐かしい無言の圧力ではないか。あゝ、やはりこれが沖縄なんだ。東京では完全にこの生体圧力が消えているではないか・・・・・ 」
車窓から下の往来をながめながら肩越しにクルクルと回し続ける、ステッキ変わりに常に七色の日傘を携帯する比江島修治は、背後から寄せられる沖縄の視線を強く感じた。そして心地よい生体への圧力を感じた。それは沖縄の人が、人に対して無関心ではないことの証拠なのである。無関心がフォーマット化された東京では、すでにこれが壊れている。暑いなかでスーツを着て、ビジネスの現場に向かう男性を、修治は長らくやってきた。しかし修治は五年前にピタリと「闘う男」のイメージを辞めた。自身では脱ぎ捨てたと考えている。以来修治は、それまでは女性が夏にするシンボルであった日傘を持ち歩くことにした。しかも夏季の色目は、あえて七色の傘に限定した。




「 人間がする行為の半分はインストラクション(動作命令)で成り立っている。動植物でもそうだが、ということはコミュニケーションの半分はインストラクション(指令行動)で占められているということだ 」
修治の傘は単る陽射しを遮る日傘ではない。インストラクション信号として、七色にはそれなりの意味があった。心理学の実験やテストで、被験者にやり方などを指示することと同じで、傘の七色がその指示であり、修治は普段にそれを持ち歩きながら、被験者がどう反応をしめすかの実験をしていた。つまり修治が出逢う人々は常に被験者なのだ。
「 そもそも人の生きる活力として太古からインストラクションそのものはある。なのに日本の教育では、様々なインストラクションの表情の仕組みや、その活用の術を教えてこなかった。そうだとすると、人情でコミュニケーションされるにあたってどのように心理化され、伝達処理されているのかということを、活動をしている生活者の大半以上が理解していないということになる。なぜなら心の理解とは、その重要な骨格がインストラクションで成り立っているからだ。そのインストラクションが伝わらないということは、そもそも「理解」とは何か、理解はどういうふうに進行するのかということが理解されていないということになる。動かない心の情報や、閉じられた心の知識は、人情として何一つの力も持ち得ない。人の心はインストラクションで日々を動き、日常を切り抜けているではないか・・・・・ 」
日本の賢愚と正邪、損得で沖縄は揺れてきた。今もなお沖縄は揺れ続けている。
修治は日本人のインストラクションが、日本人らしくあるコミュニケーションの鍵を握っている、と考えている。また、どんな生活の本質も心の転移でできていると考えている。心の転移によって何がおこるかといえば、そこで初めて「人の心を理解する」ことのシャッフルがおこる。だから修治は、すべての営みは「アンダースタンディング・マインド」となるべきだと考えてきた。戦後の沖縄を振り返れば、一つの誤りは「敗戦のさせられ方」の甘さだった。戦争の閉じ方、戦後の開き方に敗北したのだ。終戦後も沖縄は消化されるどころか、火に油を注がれてきた。


国際通りの各駅を、ゆいレールは冷房を利かして真夏の軌道を滑りながら長閑に通過している。
七色の日傘を固く杖にして握りしめた比江島修治は、京都での保養生活を思い出していた。
「 あの保養を終えて、東京に帰った翌日に、この七色の日傘を千駄木の久保竜次に作らせたんだ・・・・・ 」
久保竜次とは和傘専門の傘職人である。修治が持ち歩く日傘にはオーダーメイドするまでに、飽くなき表明をさせるべき経緯があった。当時、物忘れの頻発に、うつ病を意識するようになった修治は妻沙樹子の提案で、沙樹子の実家近くにある別荘で静養することにした。当初は1ヶ月ほどと思っていたのだが、意外な居心地の良さから1年間の長逗留となった。そのころ沙樹子は神戸に本社を置く日本五流商社の顧問弁護士を引き受けて月に二度は関東と関西間を行き来していた。別荘はその商社のオーナー五流友一郎の持ち物であった。
「 京都の夏は油照り・・・。だが、あの別荘だけは不思議と過ごしやすかった 」
修治は八坂神社から帰ると別荘裏山の藪の茂みをじっと見ていた。
そして、眼をそうさせたまま、脳裏には遠い昔の、ある弔いの光景を浮かばせていた。
「 寒さが温んだら、もう一度、瓜生山(うりゅうやま)の頂に上がろう・・・・・ 」
数日前に奈良から戻った日にそう思い、修治は今日もまた同じようにそう思った。また南フランスのヴィヨン教授から懐かしい手紙を頂いて以来、そう思い続けてもいたのだが、これもうつ病のせいか少し老いたように感じる脚の痛みがなかなかそうはさせないでいた。
「 これでは・・・、あの、ほろうち、ではないか・・・・・! 」
裏の藪から眼を居間に移すと、テーブルの上には、3つのコーヒーカップ、清原香織が運んできたままの状態から微塵も動かないでそのままにある。すでに来客は去りコーヒーは冷めていた。
「 何や・・!。手ェつけはらんと。せっかく君子はんが・・・ 」
客の一人は、狸谷の波田慎五郎である。もう一客は、詩仙堂裏の駒丸扇太郎であった。香織はコーヒーを運んでから一度も顔を出してない。三人が何やら息を詰めた気配を匂わせていたからだ。それにしても二人は、足音一つさせないで風のように帰って行った。
「 香織・・・、裏山で雉(きじ)の鳴き声、聞いたことあるかい? 」
修治はぼんやりとした小さな声でそう訊いた。
「 雉やしたら、裏には来ィしまへん。崖ェあるさかい子ォこさえるの向きへんのや思うわ 」
と、意外に味気なく、夕餉支度に追われてそうあっさりと答えると、香織は手つかずのカップを盆に下げてキッチンへと向かった。そのいかにもさり気ない後影を見つめながら修治は「やはり瓜生山か・・・・・ 」と思った。
羽をバタつかせてケンケーンと鳴く。これを雉の、ほろうちという。
春を告げる声でもある。早春の草原や果樹園の茂みなどで耳にする。縄張りの主張やメスへのアピールだ。4月ごろ繁殖の季節を迎えると、この時期の雉は、赤いトサカが大きくなり体も大きく見えるようになる。行動をより大胆にするようになる。だが冬場、ほろうちをしないわけではない。 一度、修治は高野川を渡った鞍馬山に向かう柿園で聞いたが、あれは晩秋であった。雉の居る場所はかなり薄暗いところで、上空が遮られているほど安心できるのか人が近づいても逃げないことが多い。また一度は大原のミカンの木の下で、ほろうちは直立して鳴き始めるが、その姿をみたことがある。修治の記憶では、そのときメスがすぐ横にいた。冬の雨後、緑のない枯れ草を歩く雄の雉はよく目立つ。
しかし、修治が想う雉は、やはりどうしても瓜生山の雉なのだ。


来客が去れば応接の四脚はポッカリと穴を開けたように夕暮れの陰でそう見える。
「 アメノワカヒコの妻のシタテルヒメの泣く声が、風と共に高天原まで届いた。・・・・・そして、高天原にいるアメノワカヒコの父のアマツクニタマとアメノワカヒコの妻子達が聞いて、地上に降ってきて泣き悲しんだ・・・・・。ああやはり、これは・・・・・、あの、ほろうち、ではないか・・・・・! 」
またそう思えると、応接の椅子に腰を落として、もう一度、波田慎五郎の話を泛かべた。
「 ねっ、どうして降らないの?・・・・・ 」
と慎五郎は、娘の夕実から問われた。
「 ふーん、どうしてだろうかね・・・・・・ 」
と、慎五郎は答えた。
子供は大人社会を選べない。多くの場合、希望と化した予測は裏切られることになる。だが親としては、そこから子供を持つということの、そして子供を育てるということの喜びをいだく不思議さが始まる。意外な個性を持った子が育ち、驚かされることになるのだ。そんな慎五郎はしだいに、子の夕実に囚(とら)われ、夕実の夢がいう「雨」に囚われていくという感覚を抱いてみることにしたそうだ。
そんな慎五郎の話を思い出すと、修治はそこにRobert Villon(ローベル・ヴィヨン)教授の顔が懐かしく重なってきた。
慎五郎が娘に抱く気持ちを浮かべてみると、放置すればやがて喪失感を抱くであろう子の夕実。恍惚とした時の夢を見つめながら喪失感に近い溜息をついてみせたヴィヨン教授。この二人が修治に、共通して感じさせるものは、同じ性質が引き起こしてみせる喪失感ではないか。修治はそれが、どちらも人間の想像力をかき立てる美学としての表現だと確信すると、白い教授のパナマ帽を眼に想い泛かばせ、そこに悔悟の念を抱きながら昭和53年10月の出来事を思い出した。






親子なのだから、師弟なのだからいずれは解り合えるという幻想は幻想として、宿命的に相容(あいい)れない親子や師弟というのも間違いなく存在する。 そうだとすると、夕実とヴィヨン教授はその宿命を前にして立ちすくみ、慎五郎はその宿命にどれほど荒々しく爪を立てようとしたであろうか。そう考えるとあのフランスでの10月の結論の皮肉な運命がやるせない。比江島修治はヴィヨン教授に一言の詫びを入れねばならなかった。思い出した10月の「雨」が修治をそうあおり立てた。
神に摂理されながら完成に至らぬ「存在しない雨」というものが、この世には無数に存在するのかも知れない。もしそうであれば、修治の今煽(あお)られるこの挫折にも等しい裏面史は、しばしば現実に存在する降り注ぐ雨より刺激的なのだ。だが、あらかじめ自らが挫折することで「雨を見ること」を感じさせる時間が現実に存在していることを、一体どう考えるべきか。そう想われると修治はひからびた地に立たされて熱い太陽を身に浴びるようであった。
「 教授はPluieと名付けましたよね・・・ 」
修治はシモーヌ・ヴェイユが『重力と恩寵』のなかで「メタクシュ」というきらきらとしたギリシア語を何度もつかっていたのを思い出した。メタクシュとは「中間だけにあるもの」という意味である。きっと雨にも重力と恩寵が関与しているのであろう。 雨は重力とともに地上に落ちてくるが、その前にはいっとき重力に逆らって天の恩寵とともに空中で中間結晶化というサーカスをやってのけているはずなのだ。ヴィヨン教授はその「いっとき」を追いつづけた人だったのだ。そう思って、あらためて教授と過ごした南フランスのエズ(EZE)での夏休みを振り返ってみると、教授は地上の雨にはいっさいふれないで、天から降ってくる途中の雨だけを凝視しつづけて修治が聴かせた童謡「雨」の雨音を聞いていたことに気がつかされるのだ。
そうしてあのときヴィヨン教授は、飼っていた駒鳥に「雨」とい名を付けた。修治がその鳥を眼に泛かべると、教授の手元からその鳥が帽子を啄(ついば)み飛来してくるように感じられた。 そう感じると、その駒鳥は狸谷に飛来してくるのだ。そうしてまたその駒鳥は、波田慎五郎が語っていた内容の、慎五郎一家の夢の出来事と重なり合ってくるのだ。
慎五郎の話では、狸谷では熱い太陽に煽られた慎五郎、秋子、夕実の三人が地蔵と化して佇んでいる。駒鳥はその、それぞれに三つの帽子をプレゼントしてくれた。どうしたことか駒鳥は、狸谷育った秋子には笠地蔵のあの菅笠を、慎五郎には黒いパナマ帽を、夕実にはピンクのリボンを掛けた麦わら帽子をかぶせてくれる。そして慎五郎は錯覚の赤い雨をふと抱かされていた。






「 赤い雨・・・・・! 」
昭和53年10月、高度成長期にふくれあがった中高年層の中で、ラインの管理職からはずれたオフィスの窓際にデスクを構えるミドルたちを「窓際族」と揶揄した年である。またこの年、原宿の竹の子族と、「あ~う~」という、大平首相のやたらに間延びした口調を修治は記憶しているのだが、微笑ましくもないそんな色彩の紡ぐ妙な慰めには、ほろ苦い世相をにじませていた。
東京という都会のくたびれる通勤や通学の、肩が触れ合う空間には、かんしゃく持ち、気配り下手、仕事でしくじったかの人が地下鉄に揺らされていた。その許容の物差しは微妙に各様で、ささいな言動があらぬ化学反応を引き起こす。思えば、そんな東京そのものが、巨大な満員電車のようなものであった。
しかし何かと縮こまりがちで、虫酸が走りそうなそんな時代に、対して丁寧に時間をかけて編まれた書籍には、万感、胸を襲って貫いていくものを感じさせられた。修治はそんな一冊と出逢ったのだ。その一冊が修治の世相に走る虫酸をゆっくり溶かしてくれた。修治は刻み込むように綴る著者の背中を感じ取りながら読み進めてみると、自身がその著者の何かを引き取って実現しなければと覚悟した。
「 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」
長い沈黙の中で、ふと修治はある種のひらめきを覚えた。
眼の中には、慎五郎が持参して見せた分厚い古文書がある。だが、その一冊は同じモノが東京の修治の自宅にもあった。ここがじつに奇遇なのだ。その同じ古文書を波田慎五郎から見せらたとき、修治はふと涙すら覚えた。
するとそんな修治の眼には、 おもむろにステッキを突きたて身体を起こすと、もう曲がらなくなった膝を固々しく曳き磨りながら静かに書斎へと向かったヴィヨン教授の面影が揺れて泛かんできた。そしてしだいに、教授の面影を湛えたその眼には、日本で最も古い「記紀」がそこに重なるように泛かんでいた。










二つの書に夷振(ひなぶり)という歌の記しがある。
日本書紀
あもなるや おとたなばたの うながせる たまのみすまるの あなだまはや みた
にふたわたらす あぢすきたかひこね
あまさかる ひなつめの いわたらすせと いしかはかたふち かたふちに あみはり
わたし めろよしに よしよりこね いしかはかたふち
古事記
あめなるや おとたなばたの うながせる たまのみすまる みすまるに あなだまはや
みた にふたわたらす あぢしきたかひこねの かみぞや
この夷振(ひなぶり)は大歌所(おおうたどころ)に伝えられた宮中を代表する楽舞である。鼓吹に合せて奏楽し、朝会公儀等の時に用いられる。 和歌の祖とされる下照姫の作とされ、由来は日本書紀の歌謡となる。
しかし古事記のこれは、日本語なのだろうかと解釈に苦しむ歌であるが、古事記には、その一部分が伝わる。
この歌を解釈した本居宣長は、
天なるや 弟棚機のうながせる
玉の御統 御統に あな玉はや
み谷 二(ふた)わたらす
阿遅志貴高日子根の神ぞや
と、して天織姫が首にかける宝石と、アジスキタカヒコネ神が発する光が谷を渡って輝く情景を描いた。
「 これは・・・・・、日本版の七夕、織姫と彦星なのだろうか・・・・・! 」
とも修治には思えるが、古今和歌集、その仮名序は、この歌について次のようにいう。
世に伝はることは、久方の天にしては下照姫に始まり
下照姫とは 天わかみこの妻なり
兄の神のかたち 丘谷にうつりて輝くをよめるえびす歌なるべし
ここでは、夷(ひな)を「えびす」と言い換えている。枕詞「あまさかる」は「ひな」で受けないと五七調にならないが、本来はエビスを修飾する言葉が「あまさかる」だったのかもしれない。そうであれば、夷振は「えびすぶり」になる。そう辻褄を合せると、西宮戎の「えびすかき」が宮中で披露されていたことにも通じるではないか。あるいは修治が今日訪ねた八坂神社とも重なり合う。
「 しかし・・・・・、 あまさかる鄙(ひな)という書き方は万葉集にはない。どうもここは、後代の解釈による当て字のようだ。(鄙)という字は悪い意味が強すぎて避けられていた。どうもそう思える・・・・・ 」
そう思い当たると、修治は眼を細く鋭くして、天井を見上げると夜空に北極星でも見出したかに一点を見た。そこにはかって東福寺門前の万寿寺でみたものと同じものが吊るし止めてある。
別荘にも同じものを取り寄せた。香織に頼んで御所谷の竹原五郎から拝借したものだ。
みつめると赤いトウガラシの小さな束が、鬼門を祓うとばかりに揺らいでみえる。あのとき、そう思えてやや嬉しさが微かに湧くと、しだいに修治はまた眼を別荘の庭先へと回したが、眼をやるその顔がチラリと窓ガラスに映ると、修治はにわかに笑みを浮かべたその自分の顔を、じっとみて口角に笑った。
さきほどまで、ある弔いの光景を浮かばせていた比江島修治は、慎五郎が持参して見せた分厚い一冊と同じものが東京の書斎の奥で眠っているのだと思うと、この世には、奇遇ではない宿命という実在を体感したようで身震いがした。今にも一羽の雉(きじ)が藪奥から飛び出してきて、ほろうちの甲高い声を空に向かって突きあげるようだ。修治の五体は指先の根まで振るえ、まったくそんな身震いをうつ病の男はさせたのだ。このとき男のうつ病も身震いして奮い立ったのだ。脳天まだツ~ンとした。
それによって、古い弔いの光景がにわかな色彩を加えられ、修治の眼に弔いがより鮮やかな蘇りの光景となって泛かんできた。また同時に京都阿部家の深い関わりと、山端集落との結びつきが泛かぶのだ。


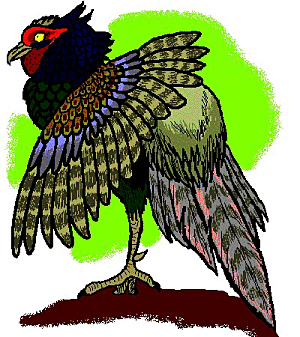



眼に浮かぶのは、もう15世紀も前の太古の、古い錆びれた日本の神々の弔いであった。
人間よる古事記が記される以前のその昔、そこに雉の鳴女(なきめ)という神がいた。 この鳴女こそが、今、比江島修治という男性の全身を振るえせている。 そして修治は、うつ病の眼を、発症する以前の強く若かりしころのように悠々とさせていた。
多くの神々とオモイカネは、「 鳴女という名の雉を派遣するのがよいでしょう 」と答えた。そこで、タカミムスヒとアマテラスは、雉の鳴女(なきめ)に「 あなたが言って、アメノワカヒコにも問いただして来なさい。(あなたを葦原中国に派遣した理由は、荒ぶる神々を説得して帰伏させろということのはずではなかったのですか。なのに、どうして8年もたっても復命しなかったのですか)とそう言って来なさい 」と命じた。 そうして、その鳴女は高天原から降りると、アメノワカヒコの家の門の楓の上に止まって、アマテラスとタカミムスヒの言葉をそのまま、つぶさに、言葉どおりに伝えた。
ところが、アメノサグメというものがこの鳥の言うことを聞いて、アメノワカヒコに「 この鳥はたいへん声が悪い。殺した方がよい 」と勧めたので、アメノワカヒコは高天原の神から持たされた、アメノハジ弓とアメノカク矢を使って、この雉の鳴女を射殺してしまった。
すると、その矢は鳴女の胸を貫いて、天上まで上っていき天の安の河原にいたアマテラスとタカギノカミのところまで届いた。タカギノカミというのはタカミムスヒの別名である。タカギノカミがその矢をとって見ると、血が矢の羽についていた。
タカギノカミは「この矢はアメノワカヒコに与えた矢である。」と言って、多くの神々に見せた。そして、「もし、アメノワカヒコが命令に背かないで悪い神を射た矢がここに届いたのならばアメノワカヒコにはあたるまい。逆に、アメノワカヒコに悪い心があるのならば、矢に当たって死ぬ。」と言って、その矢を取って矢が飛んできた穴から衝き返して下すと、朝の床に寝ていたアメノワカヒコの胸に当たってアメノワカヒコは死んだ。
ところで、高天原から派遣した雉は帰ってこなかった。「雉の片道使い」ということわざは、こういったことが起源になっている。
さて、アメノワカヒコの妻のシタテルヒメの泣く声が、風と共に高天原まで届いた。そして、高天原にいるアメノワカヒコの父のアマツクニタマとアメノワカヒコの妻子達が聞いて、地上に降ってきて泣き悲しんだ。
さっそくそこに喪家をつくり、河の雁を支社に食事をささげる役とし鷺を喪屋の掃除をする役とし、翡翠を食事をつくる役とし、雀を米をつく女とし、雉を泣き女として、八日八晩の間、連日にぎやかに遊んで死者の霊を迎えようとした。
このときに、アジシキタカヒコネノカミがやって来て、アメノワカヒコの喪を弔った。
そのとき高天原からやってきたアメノオヒの父と妻は、泣きながら「 私の子は死んでいない。ここにいる。私の夫は死んでいない。ここにいる 」と言って、手足に取りすがって喜び、泣いた。その父や妻が見誤ったのは、二柱の神が似ていたからで、見誤ったのも無理はない。 ところが、アジシキタカヒコネは、たいへん怒って、「 私は親友の弔いに来たのだ。それなのに、わたしを汚い死人と間違えるなど、とんでもない 」と言って、大きな剣を抜き、喪家を切り伏せ、蹴飛ばしてしまった。
この蹴飛ばされた喪屋は、ミノの国の相川にある喪山となった。持っていた剣は大量(おおばかり)といい、まだ神度(かむど)の剣といった。そうしてアジシキタカヒコネが怒って飛び去った時に、妹のシタテルヒメは、兄の名を知らしめようとして、次のように歌った。
天なるや 弟たなばたの うながせる 玉のみすまる みすまるに
穴玉はや み谷 二渡らす アジシキ タカヒコネの神そ
「 天上にいる若い織姫が首にかけている糸で結んだ玉飾り、その意図で結んだ玉飾りは、穴の開いた玉で出来ている。その穴のような谷を二つも渡られた。それがアジキシキタカヒコネノカミである 」
この歌は夷振(ひなぶり)である。修治は静かに眼を閉じた。






「 阿部富造・・・・・! 」
そんな瞼の裏に一人の男性を偲ぶと、かって妻の沙樹子とヒッチハイクで訪ねた沖縄の旅が泛かんでいた。
雉鳴きて平穏訪る、という。戦地から帰還した富造は、敗戦をそう感傷させる雉と出逢った。そこは生まれ故郷の山河、生駒山である。その生駒の山中で聞いた一羽のほろうちから、連想させる神の物語を、富造は感じたのだという。
「 戦争は終わったが、私は最も倭(ヤマト)を梃子摺らせた神という事になっている 」
と、神はさも悲しそう語りかけてきた。
どうやら、祀られている「杜人(モリト)(=王樹様)」と部下であった「守人(モリト)(=私)」が混同されていった結果そうなってしまった。こう言って神は腹を曲げている。
阿部富造がよくよく聞いてみると、戦争が終わって早々、監視の為に送られてきた雉鳴女(キジノナキメ)という女性の神霊が、そういう勘違いをしてしまったのが問題であるらしい。
さらに富造は、この神の悲痛な声に耳を傾けてみた。
私もまさかあの王樹様と間違われるなど欠片にも思わなかったので勘違いは進行し、中央の命令によって『モリト』の名を変えるよう言われた時も私の改名だと思っていた。神はそんなことをいう。
さらに、倭のイワレビコは切り札の八咫烏(やたがらす)と互角以上に戦う王樹様を随分と畏れているようで、名を変え、信仰が王樹様に向かないよう封じ続けていた、と。
これに従えば、史書において中央が使わした神の一柱としてやる、と。雉鳴女の話を聞くに、私が深く臣従している事が周辺地域の安定に必要なようで、従わねば再び矛を交え民を殺す事になるだろう、などと軽く脅迫してきた。元々が中央の仲間だ、等と書かれるのは不快だったので、後の世に間違いを正す事を約束に改名に従った。
私は王樹様を祀る者、社ヤシロの人として名を『杜人(モリヒト)』と改めた。
辛気臭い戦後処理も終わり、失われた時間を補うように急速に復興が続く。
鉄器文化は木材加工技術を飛躍的に上げた。より大型の舟の作成も可能となり、漁業は再び発展の時を迎えている。 少々コストが高いが、鉄製の農具も作製して農業の効率化も図れるだろう。
幸いにも山犬のおかげでモリトの血筋は残り、高度な技術を持つ者として国の再興を大いに担ってくれていた。私の民はきっとこれからも大丈夫だ。
今日も私はいつものように山犬の背に乗り、ぐるりと国を観察し、杜人神社へと帰った。
あまりに遅くなると監視役の雉鳴女が良い顔をしないのである。彼女はいつもピリピリした攻撃的な気配を隠そうとはしない。私は言ってみれば敵国の王に当たるのだからしょうがない話ではあるのだが、・・・・・。
山を登り、木々を掻き分け御社が見えてくると幾つもの気配がある事に気が付く。
漁民達が網を抱え境内で祈りを捧げていた。それを前に雉鳴女が困ったような表情でこちらを見ている。私が何事かと尋ねると、漁が上手く行くようにお願いに来たのだと言う。舟で沖に出るのは死の危険が付きまとう。大漁祈願よりは安全祈願のようだった。
……そのために、わざわざ山奥の緑深い神社まで来てくれた。
胸にありがたい気持ちが込み上げて来て一も二もなくすぐさま私は応えた。
漁港に御社を築いてもらえれば、波の荒れる日はすぐに鎮めてあげる。
私の言葉を聞くや否や、彼等はすぐさま飛び出し山を降りていった。
きっと2、3日の内に簡単な御社が拵えられるのだろう。分社を作るのは確かに考えていなかった。交番や派出所のように要所へ置いておくと便利だろうか・・・・・。
思索に耽る私に雉鳴女が疑問の声を上げる。いつになく鋭い視線はただの詰問でないと告げていた。私も、真剣に答える。
「 貴方は山の神ではなかったのか 」
私は、山の神であったとは思っていません。
「 貴方は海の神であるのか 」
時と場合によればそうする事も出てくるでしょう。
「 山犬に乗る神が海も治めると? 」
民を守るため、治めては駄目なのですか?
私は相手の言い分にちょっと悩んでしまった。神様は意外と『何とかの神』のように専業が多い。複数を兼ねる神も多いのだが、この聞かれ方はおそらく、『 中央が海を治める神霊を遣わすからお前は大人しく山だけ治めていろ 』の意味で言っているに違いない。
思わぬ所で叛意と取られかねない発言をしてしまったか!。そう内心で慌てる私だったが、雉鳴女は優しく微笑んだ。
「 私はどうにも貴方の事を見誤っていたようです 」
「 倭では荒ぶる野蛮な神であると伝えられておりました 」
「 真実は杜人の神は慈悲満つる賢神であったと 」
鳴女の字に賭けて、誤りを正す事を誓いましょう。・・・・・と、本来、私のお目付け役で上役でもある彼女が私に頭を下げた。私は間抜けにも驚きのあまり立ち尽くしていただけだった。
それから、月が一回り満ち欠けを繰り返した後、雉鳴女は中央へと帰っていった。あの質問の日から彼女は監視役にも関わらず私の仕事を良く補佐してくれた。鳴女とは伝令を主に行う神霊の一族で、多種多様な経験から凡そ何でもできるらしい。また手伝いに来てくれないかな、と私は凪いだ海に呟いた。
「 はやり、これは『鄙の国』の匂いだ・・・・・! 」
そう改めて感じ直した比江島修治は、沖縄の旅をまた思い起こした。





かなり以前の話(1978年・昭和53年)だが、 奈良で感触を抱き、そうして重箱の一段ほどに分厚い一冊を旅行カバンに押し込んで、阿部富造は本土復帰後の沖縄県に行くことにしたのだ。その一冊とは、青表紙の上製本、『鎮西琉球記』について書かれた重要な研究書籍であった。12世紀、源為朝(鎮西八郎)が現在の沖縄県の地に逃れ、その子が琉球王家の始祖舜天になったとされる。真偽は不明だが、琉球の正史として扱われており、この話がのちに曲亭馬琴の『椿説弓張月』を産んだ。日琉同祖論と関連づけて語られる事が多い。そして鎮西琉球記の異聞伝として京都阿部家が伝え遺す古書があるが、現在、この一冊が東京音羽の修治の書棚にある。
じつは富造が奈良より沖縄へ向かった一件に関して、その半年前の4月5日に、大阪府藤井寺市の三ツ塚古墳から古墳時代の修羅(しゅら)が出土した。比江島修治はその発掘に携わっていた。 修羅とは、仏教の八部衆の一人、阿修羅であり、また仏教の六道の1つ、修羅道ともみられるのだが、それが古墳から出土するものではない。古墳発掘の場で、修羅と書けば(ソリ)と読み、巨石運搬用のソリである。これは重機の存在しなかった時代に重いものを運ぶ重要な労働力を軽減させる手段であった。コロなどの上に乗せることで、摩擦抵抗を減らすことができる。
この発掘は全国的に大きな反響を呼び、同年9月3日には、朝日新聞社や考古学などの専門家によって、市内の大和川河川敷で、復元した修羅に巨石を乗せて牽引する実証実験が行われた。そしてこの実証実験の見学を終えた後、奈良に向かった修治はしばらく飛火野を歩きながら宿泊先のホテルへと向かおうとしたのだが、その途中、金龍神社の三叉路で、沖縄から来たという一人旅の男、名嘉真伸之と奇遇な出会い方をした。伸之は京都阿部家とは縁者である。修治は「おもろまち」で、この名嘉真伸之と落ち合う予定でいた。

「 まずは、安里(あさと)52高地を先に確かめておくか!。約束の時間までもう少し余裕がある・・・・・ 」
ゆいレールの車窓に国際通りの賑わいを覚えつゝ、七色の日傘ををさした修治は、おもろまち駅に降りた。そして改札を抜けた修治は1番出口より再び新しいシャッフル刺戟を周囲に感じながら、沖縄タイムズ社屋のメディアビルへと向かった。このビルから安里52高地がよく見渡せることを名嘉真伸之から聞かされていた。日傘の七色とは、雉子の鳴女の胸羽の輝きを暗示させる。かって奈良から沖縄へと向かった阿部富造は一羽の雉子を携えていた。その一羽の雉子こそが富造の意図した言霊(ことだま)なのであった。修治は歩きつつ時折、くるくると七色の日傘を回しては、この言霊を目覚めさせようとした。
駅西口に広がるこの「おもろまち」とは琉球最古の歌謡集「おもろそうし」にちなむ歌にちなむ区街だが、そこはかって米軍基地、返還後にその用地を新商業地区として再開発した那覇新都心である。
一方、駅東口の真嘉比地区は旧来の静かな住宅地でモノレール計画当時、駅名の仮称は真嘉比(まかび)駅であった。つまりこの地域は陰と陽に二分、みごとにクレオール化(混交現象社会)に染められた4種の顔色をみせるエリアなのである。
日本の顔、アメリカの顔、琉球の顔、そして沖縄の顔は、やはり複雑な顔をしていた。それにしても一見、すっかり垢抜けて都会派を気取る晴れ晴れとした界隈は、南国の華やぎと賑わいを見せているが、一帯はかって沖縄戦の激戦地のひとつとして知られる「シュガーローフの戦い」のあった、まことに惨劇な流血をみせた非情地帯なのだ。
旧日本軍はこゝを安里52高地と称し、地点は日本陸軍の首里防衛線の西端、守備隊の独立混成第44旅団配下の部隊が、猛進撃する米第6海兵師団と激戦を繰り広げた。日本軍側はシュガーローフを含めた3つの丘からなる巧みな防御陣地を構築し、海兵隊を撃退しつゞけ、丘は戦闘が行われた一週間で11回も国旗の色を塗り変えている。この戦いで米海兵隊側は2662名の戦死傷者と1298名の戦闘疲労患者を出したとされる。だが日本側については、この戦闘に限った統計がない。じつに甚大な人の終焉地が現在も不明なのだ。
「 あれが安里52高地だ・・・・・! 」
那覇市街地を眼下に見下ろすメディアビルからは、東シナ海までを臨む大パノラマの広がりがある。そして北側真下に扁平な円錐型の白い水道タンクを抱える小高い丘が見えるが、比江島修治はその一点をしばらく見据えていた。
















YOOSEE「沖縄からの声」









