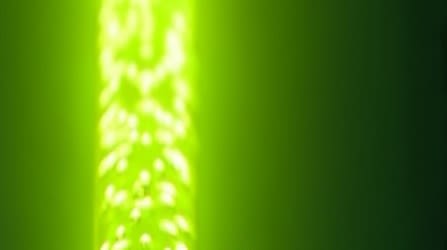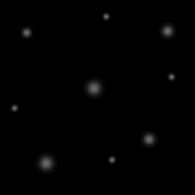(一) 御嶽の沓 Utakinokutsu
斎場御嶽(せーふぁうたき)まで来る以前の比江島修治には何かが決定的に欠けていた。
それがやがて「知覚」と「身体」と「行動」、あるいはそれらの「関係」という一連の結び目が固められて現れてくる。これを陰陽寮博士の領分に小生が牽強付会すれば、まさに絶対的関係で新しい比江島修治が出現する。しかし、修治にその着想はまだ芽生えていなかった。ただ、そうした着想の苗床になるべき幽霊体験が斎場御嶽で起きようとしていた。それは修治が三者の亡霊に耳を傾け、三つの雄叫びを同時に聞いたからだ。そして修治の思索の内奥に一体となってこびりついた。
「 知能とは、知覚された領域にひそむさまざまな対象のあいだの関係をとらえる能力のことではないか・・・・・ 」
日没の闇間よりザワめいて聞こえ届く潮騒を聞きながら修治にはそう思えた。
そしてまた雨田博士と清原香織とが交わす会話に耳を傾けた。
深い谷底の青い光りに巻かれながら、定められたごとく自然に二人はそれぞれの闇へと消えたのだ。
「 あれは・・・、やはり鐘の音やわ・・・!。タヌキはんの腹鼓(はらつづみ)やあらへん・・・・・ 」
階段を上がり切ると、しかし未だ背を曳く花音がやはり不思議である。振り向かされた香織は、火影(ほかげ)の揺れる谷底をじっとみた。
そして余韻を拾いつゞけると、耳の芯(しべ)をやはり鐘の音はたしかに叩いた。するとその鐘の響きは香織の躰をあかく揺らしはじめた。揺らされると、しだいに胸の蕊(ずい)は何やら赫(あか)い晶(ひかり)のしずくで濡らされる。香織はたゞその湖(うみ)にたゝずむと、美妙に閼伽(あか)く染められていた。




「 暁(あさ)の鐘は夜の眠りを覚さはるために、晩(よる)の鐘は心の暗さを覚さはるために敲(たた)かはるものやと、たしかそないうてはった 」
延暦寺で香織はそう聞いている。あるいは一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)、これは凹凸(おうとつ)詩仙堂の住職より、この世の中に存在するもの全ては、すなわち仏性であり、私達の生きている日常の世界はすなわち仏の世界であるのだと聞かされた。それはあの道元の言葉であった。
「 せやから、あのサザンカはやはり仏はんなんや・・・・・ 」
山も仏(さとり)であり。川も仏(おぼえ)であり。野に咲く花も仏様(ぶつだ)である。この世の中全て仏様(にょらい)でないものはない。道元禅師はそう説いている。聞き覚えのあるそんな悟りの言葉を脳裏からつまみ出しながら香織は居間へと引き返してはポケットの中のひとひらをそっと取り出した。従来、生体の行動は一定の要素的な刺戟に対する一定の要素的な反応のことだとみなされている。
それは先ほど茶室の庭で拾った山茶花(さざんか)の一枚である。
「 此(こ)の花、奈良ァ連れて行くんや・・・!。お守りや・・・・・ 」
そして見終えるとまたそっと胸のポケットに仕舞い納めた。すると自分の胸の辺りで花の白い口が、今日の一日、平安の鐘を鳴らし続けてくれるように思えた。こゝろの芯がほつこりとする。何だか温かな揺り籠にでもくるまれている気がしたのだ。

「 その鐘(さとり)の音といえば、小生にも時々聞こえてくる・・・・・!。これはどうやら血筋のようだ・・・・・。その血は甕(かめ)の中で産まれた・・・・・、そして鐘の血は今日に受け継がれている・・・・・ 」
阿部丸彦には香織に聞こえた鐘の音が、決して空耳ではないことが判るのだ。鍾の音を聞いた、だから漱石先生は結界に触れた祖先の吾輩を密かに甕の中に入れたではないか。「吾輩は猫である」とは祖の生命が封印される物語なのだ。丸彦はこの轍てつを踏まぬよう用心せねばならない。DNAとは自身の気づかぬ意外と妙なところで顔を出す性癖がある。祖の吾輩にはまことに気の毒なことだが、文学や芸能に深く干渉することに不用心であってはならぬということだ。 このとき丸彦は、すでに御嶽の虎口から這い出して修治の背後にピタリとついていた。
「 黄金餅・・・・・か・・・・・! 」
寒月は苦沙弥の元教え子の理学士で、その苦沙弥を「先生」とよぶ。なかなかの好男子だが戸惑いしたヘチマのような顔である。富子に演奏会で一目惚れした。高校生時代からバイオリンをたしなむ。吸うタバコは朝日と敷島。朝日は苦沙弥と同じものだ。そんな祖先返りの古い話を思い出した彦丸は、黄金餅の眼で、香織のこしらえた椿餅(つばもち)をじっと見つめていた。
「 川端正面角の甘春堂の椿餅、虎屋黒川の逆さ椿餅もいゝが、香織手造りの椿餅もじつに旨そうではないか・・・・・! 」
茶の間の円卓の上に京焼、三代道八(どうはち)の青磁があり、その雲鶴模様の大皿には椿餅がつんであった。春を彩る銀沙灘(ぎんしゃだん)のように、大胆にも大盛に椿餅が積み上げてある。
「 香織、おはよう。何かお祝い事でもあるの 」
というのは、ようやく目覚めて、かんたんな化粧をすませた虎哉の一人娘、今朝は黒いロングスカートの雨田君子である。仁阿弥道八(にんあみどうはち)といえば京焼を代表する窯元であり、明治の三代道八は青花、白磁の製作にも成功し、刷毛目を得意とさせながら煎茶器の名品など多数製作した。その手からなる雲鶴大皿は狸谷の駒丸家より譲り受けた逸品であるが、普段はめったに人目に曝さらされることのない父虎哉の寵愛する蔵品なのである。

そうした由緒ある雲鶴の有無を言わさずドンと白い餅が平然と陣取っている。朝の空が白む時刻でもあるから、かぶいた餅の、その胸のすく思いをさせてくれる格好が、君子の眼にはじつに豊潤であった。
「 あ、君子はん。小正月くるし、通し矢やさかい、お祝いしょ思いましたんや。この日ィは女将おかみはん、うちらもお祝いやいうて、よう作らはったんやわ。女将はんみたいにはじょうずにできへんけど今日、奈良行きますやろ。せやから、君子はんに、食べさしてやろそう思たんや。祇園には電話したさかい、午後に初音(はつね)姉さん来るいうてましたから、半分は女将はんとこの分やさけ、姉さん勝手に持っていかはる思う。君子はんは何ィも構うことあらへん。気ィ使わんと部屋にいらしたらよろしおすえ。姉さんには電話でそう念押しときましたさけ。たくさん食べておくれやす。せやけど一つ二つは、仔狸の茄子(なすび)のやわ・・・・・ 」
通し矢とは、三十三間堂のことである。香織がそういうのを聞きながら、君子は食卓の上をながめ、母もなく誰も節目を祝ってくれた覚えもない少女時代を思い返した。まして小正月など東京の暮らしでは無縁のことであった。
七草を炊き込んだ七草粥が終わり、京都における小正月の風物詩といえば、やはり「三十三間堂の通し矢」がある。これを弓引き初めともいう。それは、江戸時代にさかんに行われた「通し矢」にあやかるもので、全国から新成人あるいはベテランの弓道者が集まってくる。小正月は、元日の大正月に対していうもので、女正月、十五日正月などともいう。古来民間では、この小正月が本来の年越しであった。
「 日本には古くから祖先野生種のヤブツルアズキという豆がある。阿部家では古くからこの種を大切にし、祝膳には欠かせぬ品としての仕来たりがある。随分、小生も馳走になった 」
七草粥をくるりと替えた年越しの日は、この豆で小豆粥(あずきがゆ)を炊くことで、その粥の中に竹筒を入れて、筒の中に入った粥の多少で、当年の米の出来高を占っている。
これらは豊饒を祈る宮廷譲りの慣習である。この手習いがいつしか装いよく椿餅の姿へと変化した。これまでは、父と娘の二人っきりの味気なく侘しい生活に慣れて見過ごしてきたが、白あんの餅に紅をひき、窪みのところに黄色い花粉をあしらう橙皮(とうひ)の粒が色目を立てゝ散らしてある。それを見ているうちに、無垢(むく)だったはずの少女時代がよみがえって、君子は淡い感傷にさそわれた。
「 お父さま、まだ茶室かしら・・・・・ 」
そういってまた椿餅に眼を盗られると、しだいに仄かに芯(むね)が温かくされる。家内で手作りにされた餅の温かみを感じた体験がない。
「 もう、お上がりにならはッてもよろし時間やけどなぁ。そろそろお食事、しはらんと・・・・・ 」
その虎哉であるが、眼を見開いたまゝ、やゝ神妙なおももちでまだ茶室にいた。
客座に散らされた白い花びらは、香織が拾い摘んださゞんかである。花は、それだけしかない。一見、素人の娘が無造作に散らしたようにみえるが、どうもそうではない。すっかりと虎哉の定形が砕かれて、しかしその形骸(けいがい)は井然(せいぜん)とある。
風にでも散らされた、その自然なせいか黎明の迫る暗い茶室の中に白い小さな宇宙でも区切るかのようにみえた。この野風僧(のふうぞう)な花捌(さば)きの美妙を、利休なら何と観るのか。




「 かさねの奴(やつ)、花びらを相手に茶など点てさせて・・・・・ 」
と、散らされた花を客人に見立て、一通りの茶道の形を終えた虎哉は、花びらとの独り点前に、たゞしずかに茶碗を差し出すと、幽かな影に揺らされ息を吸い込むような動きをみせながら、逆に、何んと無垢な点前かと、観念に近い吐息に似たものを洩らした。
「 散り終えた花のひとひらに生き終えた花の襞(ひだ)がある。その散り際の白さとは此(こ)の花の足音なのであろう。それは唯一、此の花だけが持つ白い音(さとり)だ。それはまた、此の花が見続けた月の跫(おと)でもあろう・・・・・ 」
茶道をたしなむと、侘びた可憐な花にたゝみこまれた奥行が、虎哉にふと、自分をみつめることを促したりする。虎哉には駆け巡る月の跫(あしおと)が聞こえた。たしか以前にもこれは一度聞いた。そう気づいたのは、いつのころであったか明確な記憶はない。もう40年近く茶の湯に親しんでいるが、有りそうであって、そうそうには無いような気もするのだ。だがそう意識したとして到底人の手で整うはずもない。
花の蕾(つぼみ)とは、いつとはなく襞(ひだ)のほどけて、咲ききってしまうまでの間に、頑(かたく)なゝものを綻(ほころ)びさせてゆく時間があろう。たゞじっと己(おのれ)を縛られたかにみる白さゞんかの、その時間の長さと深さとが虎哉の胸に強くしみた。
82歳になる現在、年に一度、年齢が避けようもなく加算される日が、このように繰り返し来ることなど信じがたい事実のように、それも花の綻ぶ襞の深さに例えられることなのであろうかと考える虎哉は、六時半にはもう朝食を終え、ひとり書斎の窓辺にいた。
そうして深くソファーに腰を沈めると、全くあてどない老船に積み残して岸壁を茫然と振り返るような思いが去来した。
「 あれはM・モンテネグロと見た、七年前の、あの空の景色なのか?。いや・・・そうじゃないなぞ。もう少し深く遠くにありそうな藍のような色にも思える。これはもしか赤児のときに産湯から初めてみた奈良の青さではないか。いやその十月十日前の、卵胎生(らんたいせい)としてこの世に芽生えようとした胎盤を丸くくるむ密やかな景色、その星空ではないのか。しかし独楽(こま)のように回る、この笛の音は!、一体どうしたことか。これは、たしかどこかで同じリズムを聞いたことがあるぞ・・・・はて・・・・・ 」
たしかに深層に刻まれた響きだ。しかも青い光りを伴って感じられる。虎哉はどこで見たのかも思い出せない青い空のことを考えていた。脳裡に延々と残り消えないでいるから、それも人生の真実には違いない。そこに笛の音、これは何かのきっかけを待っていた自分に、今回の奈良行きが、何か思いがけない変化を訪れさせるのではないか。笛の音、それが何かはまだ分からないが、70年も忘れようとして拒みつゞけた奈良である。もう二度と近づくまいとした。その、干ひからびた奈良の裏面に、何か大切なものが沈めこまれているような気がする。それは明確な不安となることもあれば、新たな喜びをもたらしてくれことなのかも知れぬのだが、しかし、いずれにせよ判然としないモノはこゝにきて未明の淵に置き去ることが出来なかった。虎哉はそろそろ観念すべきことは潔く、素直に観念することの心構えを芽生えさせていた。
「 観念するとは、失念ではない。東亜同文書院を卒業するときにそう学んだではないか。そう、あの時代の観念に・・・・・ 」
虎哉は冥土への入り口が眼に映るようになっている。
「 かさね、そろそろ発とうか。君子は・・・、その大きな荷物を宅配で奈良ホテルまで送っといてくれ。途中、寄り道のため少し歩かねばならない用事があるのでね。いつもの黒猫で頼むよ・・・。生モノは一つ、一乗寺中谷(なかたに)の、でっち洋かん。まあ、そう気遣う必要はないが・・・・・ 」
と、そういって黒いステッキを香織に持たせた虎哉が、コートの袖に手を通しながら居間の窓をうかがうと、ようやく外の敷地が仄かに白みはじめていた。修治も療養の折に度々博士の山荘まで足を運んだことがあるが、冬場この白々と明ける京都の趣には心打たれたものだ。

「 博士はあの笛の音を聞いた。さて・・・・・小生も、一緒に出立だ・・・・・! 」
旅立ちに、月は有明にて、という。これより二人は出発する。面白くなりそうだと丸彦は眼を輝かせた。
白河の関越えんと、しかしこゝろ定まらず田一枚植えて立ち去る。そうして風騒(ふうそう)の人はあの関を越えた。しかしこの行く春の哀しみを騙(かた)りはじめる「おくの細道」という俳諧は後、数年の長い時間の中で推敲の手が加えられている。机の上に置かれ灯(ひ)に曝(さら)した言葉とは、すでに生々しい人間の声では無いのだ。田を一枚植える時間、松尾芭蕉は旅空間を独自の言語でそう数式化した。
その芭蕉は西行ゆかりの遊行柳に心を寄せ、そして細道の序に立ち止まる。
虎哉は何度か訪れたことのある那須町芦野の、旅立ちにふとその北へと眼差した。
「 しかし、やはり、あの、俳諧の矢立てのようにはうまくゆくまい・・・・・ 」
芭蕉はそうであれ「 あゝ、私の今日の覚悟とは、何やらその田植えにも等しい、どこかへの手向けの花でも必要であろうか 」と、田一枚植える間が無性に気にかゝる虎哉がいた。故国とは生々しく、柳の精に遊行するような物見遊山の気隋な旅ではないのだ。
「 阿部富造(あべのとみぞう)・・・・・・! 」
するとそこに虎哉は、一人の影の名を泛かばせた。虎哉はこの影を出迎えたのだ。奈良へ向かうということが虎哉をそうさせた。どうしても意識させられる人影である。今の山荘に暮らすようになってから、この人物の影に度々出逢うようになったのだ。
「 あれは闇間を濡らす雨夜であった。剃髪の仏頂面に肩首から丹(あか)い半袈裟(はんげさ)を吊るした、ちょつとあやしいネクタイ姿の老人が坂道を上がろうとしていた。私は下ろうとした。それが富造・・・なのだ!。想い起こさねばならぬ日がようやく訪れた・・・・・ 」
眼に泛かびくるその夜、虎哉は都内三王社跡の山門に立つ高札を訪ねた帰り道のことだが、遅刻坂と呼ばれる小さな坂道の半ばで、阿部富造という男と、奇妙な一言交わして、奇遇な別れ方をした。数ある坂にあって、これほど印象深く残る坂道は他にない。

「 あの坂の・・・あの笛の音、まさしくあれが一期一会・・・・・ 」
それは二人が逢い初めた夜である。そして二人が最期に別れ合った夜であった。
わずか三分に満たない時間、それを交流と呼び合えるはずもないが、しかし二人はたしかに濃密な時間を過ごした。じつにたしかに虎哉にはそんな実感がある。そこで交わした言葉といえば虎哉の一言、富造の一言、この二言でしかなかった。
「 そうだ、博士、そう二人はやはり戦友であり、すでに親友なのだ。時間の長短が問題ではない。あの坂で二人は共通の親しみを感じたはずだ。一言の問答を交わすことで互いは永遠に絆を結んだ・・・。何よりも博士、あなたはあの沖縄の安里52高地を鮮やかに記憶しているではないか。あのとき二人互いに、52高地の2㎞圏内にいたのだ。そして二人して同じ流血の惨状をみた。そこで眼に沁みた赤い血とは、語らずとも互いを引き寄せる霊力となる・・・・・ 」
博士が今眼に泛かばせている富造は、小生とは密接な間柄、博士と同じく富造もまた旧帝国陸軍の指揮官であった。二人の交感に二人は互いに気づかぬが、たしかに交感はした。阿部秋子からの指令で小生が沖縄へと向かったのは、これより十年後のことであった。
「 富造とは、小生の主人であった阿部秋一郎の三男である。どうやら雨田博士は、よほど富造との出逢いを奇遇だと感心しているようだ。あの夜、虎哉は文京区音羽の鼠坂(ねずみざか)から山王社へと向かったのだ。博士の自宅は鼠坂にある。ふゝん、運命(さだめ)とはそういうことなのだ!。そしてさらに二人に加わって数奇な宿命を共に運ぼうとする男がいずれ現れる。小生にはその予感がする・・・・・! 」
山荘の裏には毎日花が手向けられて切らされることのない石の小塚がある。虎哉はじっとその石塚の方をみた。この塚下に「栗駒一号」を納める京焼の甕(かめ)を埋葬した。虎哉はその棺(ひつぎ)の甕にそっと耳を澄ました。
「 クルグルック~、グル。クルグルック~、グル・・・・・ 」
と、そう虎哉には聴こえる。そして眼には往年の一翼、耳奥にはその音羽が泛かんでくる。するとその翼は奈良の故国を空高くめぐるようだ。そして何やらその羽の音が夢の浮橋を引き出してくる。小生の耳にもその甕の音羽は聞こえた。小生はこの埋葬に立ち合っている。
御嶽のここで、潮騒の遠鳴きを聞く比江島修治に、意識と身体のあいだにひそむパースペクティブのようなものがはたらいていた。しかもそれらは、どこか相互互換的であり、関係的で、射影(profil)的だった。そして、それを中心にいて取持っているのがスペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスだった。少なくとも修治にはそう見えた。
そして丸彦は、背後よりその修治の肩を叩いたのだ。その手は心身二元論を決定的に刺戟するものであった。そしてその刺戟は、修治が眼に描きだした幻想が、自身の知覚や意識の中にあるはずだということを予感させた。この錯覚のような現実は、何かの「陰」に対して浮き上がってきた「陽」であったのだ。
「 アッ、この姿は、あのキホーテではないか・・・・・!。そうか、俺が、キホーテなのだ・・・・・! 」
哲学とはおのれ自身の端緒がたえず更新されていく経験なのである。これは偶発的な動向から生まれた単なる神話ではない。どうやら御嶽の神は、セルバンテスの死亡後に、彼の生涯プログラムを消去したスペースに、もう一人のセルバンテス・データを書きこんでくれたようだ。これで修治が御嶽を立ち去る最後まで、ドン・キホーテの生体を作動させることが確認できれば、修治が生きてきたその全てのプログラムは消去させられるか作動禁止のロックがかけられる。そうなると比江島修治は、世界でたったひとつの自分だけのセルバンテスIDを所持するモンスター・キホーテの所有者となれるのだ。
戦禍に伏せた沓音(くつおと)を鎮める御嶽の海に鳴る鍾音を聞いた修治は、すでに翔出そうとする青馬に跨っていた。














ダイナミック琉球