




































(四) 遅刻坂 Chikokuzaka
古い東京を懐かしんで、それだけで時代の真相が分かるものではない。
「 阿部富造は、敬愛する兄貴がフィラデルフィアで客死して、そこで、14歳のころすでに寄席通いをはじめている。富造とはそんな風変わりな男だった。私にはその真意がよくわからないが、寄席通いは祖父の影響らしい。ともかく富造はそのときは府立一中に通っていた 」
雨田虎哉博士は、そう想い起こしたようだ。
「 どうやら、寄席でおもしろいのは期待もしていない色物が予想外の出来だったときで、富造もしきりに手品師の思い出にふけっていたという。たしかに14歳で寄席の色物は道に入りすぎている。しかも盲目の女芸人の思い切って声を殺す風情が悦に入るとは、それはきっと他の目的があったはずに違いない。何だかそこに新しい生命が籠もっているような気がしたのだというから、陰陽道と無関係とは言えまい。学校の講義を休んでまで聞きに寄席通いとは驚きだ・・・・・ 」
雨田博士の視線に連なって、幽・キホーテもまたじっと富造の動向を泛かべた。
第一次世界大戦中は大戦景気に沸いた日本であった。
だが戦後恐慌になると、社会は、暗く深刻な不安のなかを揺れつゞけていた。
「 たしかに、そうなのだが、しかし、どうしてか当時、それでも何だか新しい生命がきっとどこかに籠っているような気がしていた 」
これは理屈なく真実だ。人は気張ろうとした。阿部富造にはそう思われる。
「 深川職業紹介所には四千五百人、江東紹介所には約千人、他の紹介所にも大勢の、未だ明け遣らぬ凍てつく路上に、仕事は大概、関東大震災の復興の力仕事、賃金は1円60銭から30銭どまり、貯蓄銀行の支払い停止措置に取付る預金者が銀行に殺到・・・・・ 」
と、朝刊は報じる。だが、そこに希望と前進とがあった。
「 たしかに大正9年の世界恐慌による連鎖反応として引き起こされた昭和2年金融恐慌からの長引く不況は大問題であったのだ。しかし陰気だからこそ逆に、そうした暗い世相には、明るい歌が陽気のトリガーになる。たしかに当時、風は人にゆるやかであった・・・・・ 」
世相の陰気臭さより、どうしても陽気さの方が上回るのだ。困難は勇気と夢とで克服し、満たそうとする気概を先に溢れさせていた。


「 たとえ貧相であれ、明日という一日が信じられた・・・・・ 」
苦しい時代なのだが、そこに息苦しさは無い。ただ希望は溢れる、そんな阿部富造の記憶には明るい一曲が思い出されて泛かんでくる。
巷(ちまた)では浅草オペラで人気を集めていた歌手・二村定一(ふたむらていいち・通称べ~ちゃん)が歌う「私の青空」が大ヒットし、国内ではジャズ音楽が舶来の雰囲気を漂わせて大衆層に広く支持されていた。
「 当時、浅草が日本で最大の盛り場であった・・・・・ 」
富造はそんな1929年(昭和四年)のことを眼に泛かばせていた。
夕暮れに仰ぎ見る輝く青空 日暮れて辿たどるはわが家の細道
せまいながらも楽しい我家 愛の灯影ほかげのさすところ 恋しい家こそ 私の青空






「 富造、早よう来んかい! 」
そう言って古閑貞次郎がにっこりと笑っている。
それは・・・・・、坂道で出逢ったあの青春盛る笑顔である。
彼のそんな笑顔が泛かぶと、富造は胸のつかえがすう~と下りていった。
百年の間に降り積もった世上での恨み辛(つら)み、みずからの済まなさや蟠(わだかま)りがいっぺんに溶けて、若く青々としたころの真まっ新さらな男の親しみだけが花芽を膨らます春陽のように残った。
「 貞次郎・・・・・、あの青空をお前に渡してなるものか・・・・・! 」
富造は小躍りしながら駆け出した。
貞次郎はここまでおいでとばかりに先駆けていく。
あの丘の向こうには、日本の青空がきらめき、光り輝くその丘の道辺みちのべには、二人だけの夢が落ちていた。
それは日本国中が国威の発揚に沸き、時代の装いがハイカラからモダンへと移り変わるころのことであった。
明治維新を経て開国し、二度の戦勝(日清・日露)による好景気も得て国力も高まり、帝国主義の国として欧米列強と肩を並べ、これで勢いを得て第一次世界大戦にも参戦、日本はその勝利の側についていた。
日本のそれは、欧米から学んだ会社制度が発達し、やがて熟し輝きを増そうとした時期である。 私企業が発展、世界に向けて大規模化して、投機の成功で「成金」と呼ばれるような個人も現れ、庶民においても新時代への夢や野望が大いに掻き立てられていた。
ようやく民本主義が台頭すると、西洋文化の影響を受けた新しい文芸・絵画・音楽・演劇などの芸術が流布して、思想的にも自由と開放・躍動の気分が横溢し、都市を中心とする大衆の文化を花開させようとしていたのだ。
が、しかしこの裏面では、大戦後の恐慌や関東大震災もあり、経済の激しい浮き沈みや新時代への急激な変化に対応できない不安や不満による歪ひずみも底辺に暗く潜在化させていた。
たしかに第一次世界大戦では、まれに見る好景気で日本経済は大きく急成長を遂げた。しかし大戦が終結して諸列強の生産力が回復すると、日本の輸出は減少して早くも戦後恐慌となった。さらに1927年(昭和二年)には、関東大震災の手形の焦げつきが累積し、それをきっかけとする銀行への取りつけ騒動が生じて昭和金融恐慌となった。
若槻内閣は鈴木商店の不良債権を抱えた台湾銀行の救済のために緊急勅令を発しようとしたが、枢密院の反対に会い、総辞職した。あとを受けた田中義一内閣は、高橋是清蔵相の下でモラトリアム(支払い停止令)を発して全国の銀行の一斉休業と日銀からの緊急貸し出しによって急場をしのいだのだ。
安倍富造と古閑貞次郎の出逢おうとする時期は、こうした文明の開渠(かいきょ)と暗渠(あんきょ)とが混在一体とする中の、帝府を一もみに潰つぶした関東大震災(大正十二年九月一日)を経た7年目(昭和四年)の春のことである。
隅田川にも前年二月に新しい言問橋(ことといばし)が架け替えられ、七月には有楽町の数寄屋橋が石橋として完成するなど、東京府はようやく痛手の燎原(りょうげん)から立ち直るかの景観を見せ始めていた。
「 ふ~ん。これが、昇降機というやつか・・・・・ 」
人を閉じ込めた鉄の箱が上に動き始めると、身と魂がふわ~りと天昇するような脳味噌(のうみそ)の揺れる心地がして、こうして安倍富造12歳の帝府暮らしが始まることになった。





「 ご来店まことに有難うございます。まもなく最上階、八階でございます 」
と案内される乙女言葉の使われようが何とも新しく上品で麗(うるわ)しいことか。歳にして十七、八の乙女である。そんな乙女の瞳が富造の眼に初対面でもするように触れると、眩(まぶ)しすぎるほど富造の男根は芽吹きの気恥しさを秘めて固く動揺した。
先日の新聞ではこの乙女らのことを「昇降機ガール」と称し、日本初の試みだと朝日新聞は報じていたが、その見栄えさわやかな洋装の香りに12歳の富造はうっとりとした。
大震災後の焼け跡に、上野松坂屋が地上八階、地下一階の白いルネサンス洋式として新装開店したのは昭和4年4月1日である。店内には演劇ホールや動物園まであり、開店当日には十三万人もの人々が殺到した。新装と同時に登場したのが「昇降機ガール」である。つまりこれは日本最後の戦後にいうエレベーターガールだ。
年齢は富造とさほど違わぬ乙女らであるが、洋装の凛々しさやすでに芳醇な大人の女性に見える。
3月の下旬にすでに上京を終えていた富造は、長兄倫一郎に誘われて開店三日目の上野松坂屋へとやってきた。
東京市内の六割が焼失し崩壊したというが、上野界隈も後7年にして未だ多くの爪痕を残して、在るもといえば平屋造りの低い建物ばかりで、新装の上野松坂屋ビルは、焦土の中に凸状に現れた巨大な白亜の殿堂のごとく映った。

「 よ~く見ておけよ富造、これが今の帝府だよ。あれが宮城(きゅうじょう)だ・・・・・ 」
「 凄すごいな~、これが帝府の広さなのだ・・・・・ 」
富造が眼をキラキラと見張らせてみる、上野山から兄と展望する東京はじつに広大であった。盆地として山に囲まれた京都に育ったせいか、囲いの無い関東平野というものがじつに新鮮であり、自由広々として富造の眼が描く光景のすべてが手に取れるようである。 富造は、倫一郎が指さす南の宮城にも素直に感動した。
「 なんと馬鹿な、そうじゃない。このドン底の帝府を目に焼きつけておけ、ということだ 」
「 えっ、どん底なのですか・・・・・ 」
「 そうだ。こんな始末の悪さが他にあるものか! 」
兄の苦言が真っ直ぐにくる。そして兄は前方を恫喝する。しかしそんな初体験の、その春陽はじつにあたたかく、頬ほほをなでる東風は雑草にむせるような匂いがした。富造はこの兄と兄弟であることに幸せを感じた。
その安倍倫一郎は明治三十五年に生まれた。
富造より16歳上である。一中で飛び級し、一高、帝大の法科を出て頭も風采(ふうさい)もよく、健康で人情味もあり、家族が最も信頼を重くする安倍家の嫡男で、富造はこの長兄が賢明で堅実であることが自慢だった。
その倫一郎(23歳)は、帝大を出ると内務省に入り、帝国という日本があり、日本に政治がある限り、帝国の役人として行くべきところまで確実に出世して行きそうなタイプの男だった。
「 今、富造の目の前にある光景が、帝府復興計画の実情ということさ。あゝ、そうともあれが復興の兆しなのさ・・・・・ 」
と、そういうと倫一郎は、一瞬、不快そうに眉をしかめた。
「 大震災当初、内務省では三十億円の予算を捻出しても帝府復興計画を実現させようとした。しかし現実には、その予算額が大幅に縮小され、何と六分の一、五億円の規模に抑えられてしまった。これが今の政治力というか、帝国の実情ということだ 」
この報告を聞かされたとき、椅子(いす)を蹴倒(けたお)して職場を出た倫一郎は、駆け出さんばかりの足取りで執務室に向かった。丸七日徹夜の激論の末に・・・・・(これでは何のために)と、倫一郎の唇は憤懣(ふんまん)やる方ない思いにひくひくと震えた。滅多に怒りなど貌に現わす兄ではない。倫一郎はそう語りながら、それにつれて鼻下に黒々とある大きな黒子(ほくろ)を上下に揺らしていた。
「 当初の三十億円計画は、総裁の後藤新平によって提案されたものだ。しかし政党間の対立などという馬鹿げた事があり、結果、議会には縮小案化された五億円規模の予算分しか提出されなかった。だからこの目の前にある市中の復興景観は、金に小癪(こしゃく)な糸目をつけた最低限の野暮(やぼ)な計画なのさ。将来のことを考えると、私はこの計画は大失策だと考えているのだよ・・・・・ 」
倫一郎は、大きな眼をぎろりと剥(む)き、大きな顔を怒りに染めて語った。富造は初めてみせる赤ら顔に驚いた。
「 富造いゝかい、将来はもっともっと自動車が増える。昨年の四月には新型の蒸気機関車C53型が登場もした。今年の夏には東京と大阪を二時間半で結ぶ定期旅客飛行機が飛ぶことが決まってもいる。これからの時代は、人と物とが、もっともっと速い時間で行き交うことになる。復興が進めば関西方面へ仮移住した府民も数多く帰ってもくるだろう。だがこの計画にはそこらの計算もない。先で必ず後悔することになるはずだ 」
赤ら顔がにわかに黒筋さえ泛き上がらせて語尾を強める。
「 道幅はもっと広く、帝国を象徴させ帝府の活力を表した豊かな公園で帝府たらしめる必要もある。それらを見越した居住地の整理などは今だからできることだ。何せこれは、江戸時代以来の大改革事業だからね。壊れたことは悲しいことだが、壊れたからこそ出来る計画がある。今なら、今しかやれない大計画ができる。大震災が天命であるとしたら、その天命の下にこそ大計画をいたす重要がある。計画というものは、そうでなくてはならない。そのことを富造にはしっかりと覚えといて欲しい。これから時代は大きく変わるぞ・・・・・ 」
倫一郎は息をつく間もなくこう語り終えると遠い眼をして、ゆっくりと空を仰いだ。
関東大震災における帝都被害の規模は、直後に参謀本部が遷都を検討したほどの動揺が物語るように帝都史上最悪の甚大さであった。新しい遷都話は幻のように二日で立ち消えたが、とそんな事も富造に語ってくれた。

「 もう武士の世は終わったのだ。イギリスやフランスにも昔は騎士(ナイト)というものがあった。しかしそれも終わった。今は同じ市民になっている。軍人もそうせんと本当の四民平等の世はつくれない。軍人は武士の誉れを持てと軍部は教えるが、何が誉れかを未だに履き違えとる。そこが肝心だね。日本はまだまだその肝心が足らぬ・・・・・ 」
胸のざわめきを押さえながら富造は兄の熱い言葉を聞きつゞけた。
「 あの維新は日本のためだったはずだ。武士のためではなかった。西郷さんは一身でそれを背負った。大久保さんはそこをじっと我慢して堪えた。武士や友情より日本だった。時代を背負い、時代を変えるとはそうゆうことだ。お前は軍人になることを決めたのだから、只、その道を真っ直ぐに堂々と行け。だが、国民を見殺しには出来ん。勝敗は軍人のためのものではない。国民のものなのだ 」
「 ところで、将来は、陸軍か、海軍か・・・・・? 」
「 まだ決めかねていますが、慎重に決めたいと考えています! 」



富造は幼かったころ高熱を発して寝込んだとき、三日も枕元で看病してくれた倫一郎の姿を思い出しながら、切々と語り詰める兄の言葉をありがたく聞いていた。
「 それでいゝ。いずれにしろ、いくらかの捨て扶持(ぶち)を与えられて飼い殺しにされてしまう軍人にだけはなるな。軍人として、堂々と肩を揺らして国民の生きる道を切り拓く男になれ。維新では、士族から職も誇りも奪ってしまったではないか。この国の計画は、そうした無念の礎(いしずえ)の下にあるが、軍人が国力ではなく、つねに国民が国力である。お前がやがて軍刀を握るとはそういうことだ。その軍人は生あれど死が常だ。そしてその死は常に国民と共にあれ。だから、もし死のときは・・・・・ 」
と、倫一郎は一瞬、五体を震わせた。
「 そのときは、そのときはだな・・・・・富造、国民の力のために、富造は、真っ逆さまに天国に落ちて行け!・・・・・ 」
天国に落ちる、地獄に落ちるより厳しい戒めだが、富造は嬉しかった。
明日は府立一中の入学式である。 その前に倫一郎は上野忍ケ岡からの東京を見せたかったのであろう。そう思う富造は、新たな血を注ぎ込まれた清々しい顔で、大空を仰ぐ兄の伸びやかで広い背中をじっとみつめた。
「 1000円を捕り損ねたぜ。西巣鴨にいたとは、迂闊(うかつ)、うかつ、残念無念 」
「 けッ・・・・・!」
男は我慢がならんと言いたげに吐き捨てた。
そもそもこの奇怪な言動が貞次郎との馴初めであった。
星ノ岡は坂道の多いところである。
頂きに府立一中が日比谷から移転完成したのは昭和四年のことであった。その頂きの地とは、明治のたばこ王と称された井村吉兵衛邸跡地のことであるが、一帯は星の美しく輝く高台で古くから星ノ岡と呼ばれていた。
高嶺の花道とばかりに新調の服で京都から東京へと渋谷道玄坂の長兄倫一郎宅に転居して、府立一中へと進学することになった阿部富造は、本日の福寿暦の運勢に習い事・事始め・種蒔きは吉、結婚・葬儀は凶とあることから、縁起よく六時の鐘のように早立ちをして一中のある星ノ岡をめざすことにした。
倫一郎から習った道筋通りに青山から乃木坂、赤坂へとのんびりと歩いた。

復興する東京の空気を旨うまそうに食べながら行くと、やはり京都とは違う風景は開放されて新鮮なのであった。
そんな富造は、新築校舎の待つ入学式に出席するために遅刻坂(ちこくざか)を意気揚々と上がっていた。この坂を上がりきると右手に、あこがれの一中が目前にあるはずだ。富造の心は泛うき立っていた。その花道で、吐き捨てた男の言葉が富造の眼の前を歩いていた。
前にある人影は、丸く愛くるしい肩をした小柄な男だった。地声なのか、その言葉が鮮明にしかも唐突に聞こえたので、いさゝか富造は苦笑した。1000円という響きが妙になまめかしく後を曳(ひ)くのである。
昭和四年当時の円の値打とは、現代平成の値打に置き換えると約五百倍ほどの価値となる。これが1000円であれば、額面にして五十万円相当になる。当時、本郷界隈の下宿代(二食付き)が一ヶ月分25円、小学校教員の月給が46円であった。そういう貨幣価値の感覚からして、尋常小学校を卒業したばかりの年少の口が洩らす額面としては尋常ではなく、富造が耳にした金額はいかにも怪しげで破格のものであった。
「 ほゞ二年分の授業料じゃないかよ。しかも、それを盗(と)り損ねた、とは・・・・・ 」
入学の諸経費が百四十六円十九銭、前納した一ヶ月分の授業料が五十五円であった。
これらの一切を長兄倫一郎が工面してくれたのであるから、富造はとくとくと正座しながらも金銭の値打について語る倫一郎から学生の本分まで指南されている。その免目を兄に涙して誓ったのであり、金銭の扱いには人一倍の魂を悉皆(しっかい)と胸に叩き込めていた。
もし1000円あれば学寮生活の費用が丸々二年分楽に賄(まかな)える金額であることへの分別(ふんべつ)は逞(たくま)しいのである。しかし同年齢と思える男のそれが一体何事なのか、それは分からない。どうにも他に聞かれてはならないような秘め事を盗み聞きしたようで、小柄だからと侮(あなど)れない富造は心なし足取りをゆるめ男から少し距離をおいた。
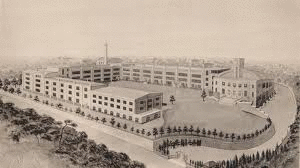
「 しかし惜しい、実に惜しいことをした 」
男はまたそう言って立ち止まると、今度は、ふと腕組をして首をかしげた。そんな男の形(なり)振りには、勘(かん)ぐれば恣意(しい)とも感じ取れる妙な間があった。敢(あえ)て聞こえ届くような発声でもある。否(いや)、地獄耳めいた富造だから聞き分けのできた声なのかも知れない。だが富造には迫る式典の時刻もあり、たかゞ一見(いちげん)の男などに気遣ってはいられない苛立(いらだ)ちがあった。
「 こんなところでつ立ってもらっては邪魔だ!・・・・・ 」
そう思う富造は追い抜こうとして男に並びかけると「遅刻するぞ」と大声で道をゆずるよう促した。すると男は立ち尽くしたまゝ、ぽろぽろと涙を流しはじめたではないか。やゝ怒鳴りはしたがそれほど邪(よこしま)な声ではなかったはずだ。富造は足を止めさせられて、すこし腰を泛かせて男の顔を今一度ていねいに見た。
背丈が一尺も違うからそうなるのだが、背を折って覗(のぞ)き込むように気配を窺(うかが)うと、その瞬間、
「 遅刻・・・・・この坂で・・・・・か 」
と、男はそう呟(つぶや)くとどっと笑い声を発(た)て、弾みに体を前に乗り出して富造の股間(こかん)をぐいと掴(つか)み上げた。
「 くっ・・・・・! 」
潰(つぶ)さんばかりに男根を掴まれると、下腹の奥に焼けつくような痛みが走った。さらに捻(ひね)り挙あげられると、唇だけがひくひくと動き、手も足もぶらりと動かぬのでは、いかんともし難い富造であった。たゞ、切れ長の眼が吊り上がり、肉の薄い額に叩き破られた蜘蛛(くも)の巣のように青筋が立っていた。
「 さっきの科白(セリフ)、もう一度聞かせてもらおうじゃねえか 」
男は猪首(いのくび)の顔を鋭くどんと富造の鼻先にぴたりとつけると、藁(わら)くずのような勢いで燃え上がるような眼の光りをむき出して言った。それはほとんど常軌を逸した厳しさであった。だが富造も一中を足がかりにやがては士官学校にと闘志を篤(あつ)くする男児である。たとえ急所が潰れようとも怯(ひる)むはずもなく、青筋を隈取(くまどり)のように赤変さして、食いつかんばかりの形相で詰め返した。
「 手前(てめえ)こそ、どういう了見だ! 」
男は富造の血相を見るなり、ぎょっとして怯(ひる)み、油断したかに手元を弛(ゆる)めた。
その一瞬を叫ぶなり富造は男を突きのけ、胸倉を掴んで殴りつけた。猪首の上にちょこんとある丸顔は、見るも無惨(むざん)に腫(は)れ上がった。だが男はそれでも富造の脇腹にとりつくと、この天才児は、鼻血をしたゝらせながらも、天を睨(にら)んで大見得(おおみえ)をきった。
「 これ寸善尺魔(すんぜんしゃくま)の障化仏罰(しょうけぶつばち)、あゝ我われ破戒のうえは、生きながら鳴る神となって、かの女、たとえいずくに隠るゝとも、天は三十三天、地は金輪奈落(ならく)の底か・・・・・ 」
と、 さながら市川團十郎(だんじゅうろう)が好んだ凄みで鳴神上人(なるかみしょうにん)を見事に傾(かぶい)て演(み)せた。
これにはさすがの富造も呆然(ぼうぜん)とした。しかし富造は、歯をかみしめ唇を閉ざすと、潰さんばかりに男の鼻をつまんだ。だが男も口を固く閉ざしたまゝ、逃れようともしなかった。
「 うががっ・・・・・ 」
息苦しいのか、男は喉で痰(たん)を切るような音をたてた。
「 苦しいのなら、その口を開けろ 」
それでも鼻をつまむ手をゆるめなかった。だが、男の息が次第に細くなるように感じた。顔から血の気が引いていくのもわかる。眼も黄色く濁ってきた男は、しかし未だ傾(かぶい)ていた。
「 何と強情な奴だ・・・・・! 」
この一瞬の演(み)せ場を見せられて、即座に歌舞伎十七番の「鳴神」だと判るところが、京都の小憎らしい富造の素養といえるものではあったが、祖父阿部清衛門の薫陶の中に育った富造には、幼少より幾度となく祖父の手に引かれて観劇した、日本最古の京都四条南座に遊びながらも体験した大向こうをうならす外題(げだい)の大半は体に滲しみてあった。
その「鳴神」は市川家の十八番(おはこ)である。
「 無礼構わぬ、よっ、成田屋(タヤッ)! 」
鼻をつまんだ手をゆるめると、咄嗟(とっさ)に富造はこう声を掛けていた。
これは狂言の幕切れの柝頭で、歌舞伎通なら知れたことであった。たゞ富造のそれは数寄者特有の粋(いき)を演(み)せた踏み込みがある。それは京者の富造が大向こうの江戸歌舞伎へと投げかけた儀礼でもあった。
「 ふぉ~っ 」
と、男は水面で息をつく鯉のように大きく口をあけた。
「 ほゝう、お前(め)え、大(てえ)した者(もん)やなあ~。負けたよ。決まり手は、うっちゃり、てとこだね 」
男は息も切れ切れに言うと、声高(こわだ)かに大笑いをして、さわやかに笑った。
「 無礼構わぬに、鎌(かま)輪(わ)ぬ、を掛けやがるとはな~ぁ。しかも(たや)と縮めた。大した奴や 」
鎌輪ぬ、とは成田屋の役者文様である。判物(はんじもの)文様(もんよう)の一種で「鎌輪奴(かまわぬ)」とも書く。「鎌」の絵と「〇」(輪の絵)とひらがなの「ぬ」の字で「かまわぬ(構わぬ)」と読む。「ぬ」を〇で囲ったもの、〇と「ぬ」が別になったものなど変種も多くある。江戸時代初期の元禄前後、町奴(町人の侠客)などの間に流行した衣服の文様である。
これを「 水火も辞せず(私の命はどうなってもかまわぬ)」という心意気で好んだ。役者文様にも分類され、今でも浴衣や手ぬぐいに用いられる粋な柄である。団十郎のライバルの尾上菊五郎が張り合って、「斧(よき)琴(こと)菊(きく)」という吉祥文様を愛用する。「鎌輪ぬ」は男性が好み、「斧琴菊(よきこときく)」は女性に愛用された。
「 これは、まさしく天の声だな・・・・・ 」
と、富造はぽつりとつぶやいた。
そうとしか思えない瞬間が最近時々おとずれる。すべてが祖父清衛門からの手習いである。富造は全身の血がふつふつと滾(たぎ)ってくるのを感じた。空を仰いだ富造は、はち切れんばかりに帆をふくらました船のように胸と背を張った。そうしてこの坂道を海の彼方に消えていくまで走ろうと思った。
「 おい、遅刻するぞ。初日に遅れるとまずい、おい走るぞ 」
白い帆をするすると上げるように、富造は両腕を上下させて男の眼の前を煽(あお)った。
「 それそれ、その遅刻するが、まったく野暮(やぼ)だねぇ~。お前知らないのか、此(こ)こを遅刻坂というのを。口にするのは野暮ってもんだ。見て見ぬ振りが、花ってもんよ。粋ってもんよ・・・・・てなこと言っていたら遅刻するか。よ~し走るぞ、それッ! 」
その間合い良く、吹きつけた突風に押されて横にすべるような動きを見せて一羽のひばりが目の前を過ぎた。これを合図に、二人揃って飛ぶように坂道を駆け始めた。そのとき富造の眼は、比叡山でいつも共に遊んだムササビの姿を泛かばせていた。そしてそのお山へと上がる竹林は富造少年が山の仲間と築いた一国一城の砦。その竹林城の清風が吹いてくる。
「 俺は、古閑貞次郎。お前は・・・・・ 」
「 安倍富造だ! 」
二人は走りながら名乗りあった。
「 ところで・・・おい、1000円って、あれは、一体何だ! 」
「 あゝあれか、聞こえたのか。長くなる、式が終わってからな。この坂の下で待っているよ 」
追い風に帆をふくらました二つの船は、府立一中の校門に、ぐいぐいと近づいている。
小太りの貞次郎は息が上がるのか両手で何度も頬を叩いた。
そして踵(かかと)を蹴ってホウ、ホウとみゝずくのような声をあげた。
それはあの京都山端の山々で聞いていた懐かしい声だ。そんな気にさせられたのだ。
だから富造も貞次郎に同じ声を返しながらホウホウと駆け上がった。




「 お~い関介(かんすけ)・・・、元気でいるか!・・・・・ 」
駆け上がりながら富造は関介の姿が眼に泛かんだ。
小さな黒い手足を四方に伸ばし、身丈を上手に風呂敷のごとく広げては自在に風に乗り比叡の山々を渡り跳んでいた。カンスケとは狸谷不動院の屋根裏に棲むムササビである。その関介の親友に阿部家の裏山が縄張りの聖太(せんた)という古狸がいた。
「 菊さんは元気やろか!。よう、あないな狸じじいに、惚れやしたなあ~・・・・・ 」
菊とはセンタの五番目の若妻である。センタの茵(しとね)は瓜生山の祠(ほこら)の中にある。その祠の草には富造もよく寝ころんだ。富造はよく野風僧(のふうぞう)をしては関介と聖太と菊とで比叡の森を自在に駆けた。琵琶湖への道によく道草をした。関介や聖太や菊によって鍛えられた足は、いつしか自慢できる韋駄天(いだてん)となった。
そんな富造に、どうやら東京でまた新たな友ができたようだ。
遅刻坂は勾配のきつい坂道である。
富造は比叡山へと上がる、きらら坂の急勾配を思い出した。
「 あの、木の根の生えた坂のきつさに比べれば、こんな坂・・・・・ 」
ホウホウと駆ける、二人の声の掛け合いは、どこか忍び走りの符合の笛のようでもあって、すでに長い長い友垣(ともがき)でいる阿吽(あうん)のそれだ。富造には古閑貞次郎との出逢いをもたらしてくれたこの遅刻坂が、二人で駆け上がりながら、関介や聖太と駆けているようで、どうにも背にいとおしくてならなかった。
「 人間の人生というものには偶然が関与する。それは、夜中に街を歩いていて、ふと見上げた星々の何に目をとめたかという偶然だ。いつ、どこで、どんな人物に出会ったか。そのなかには、一連の星座をかたどる生涯のうちの一人に出会うような偶然がある。すると、こうして雨田博士から聞かされた富造を想い浮かべることは、それはやはり二つの星の廻り合わせなのか・・・・・ 」
幽・キホーテは、富造が貞次郎に手向けた「ミズヒキの花」の小さな赤い景色が泛かんできた。
正岡子規に「 かひなしや水引草の花ざかり 」という句がある。同一刻限に見る見知らぬ人生の光景というものは、どうやら出会ってみなければ決してわからない結晶的な雰囲気というものがあるようだ。
ミズヒキの赤い花粒を夜空に並べてみた幽・キホーテには、博士から始まる人物との出会いが、連星のように感じられた。













関東大震災









