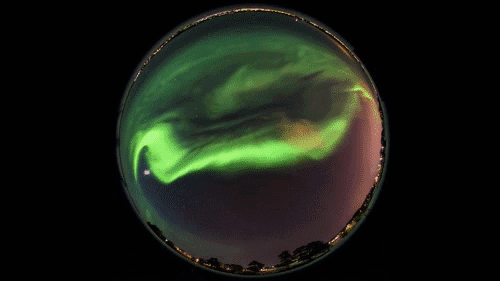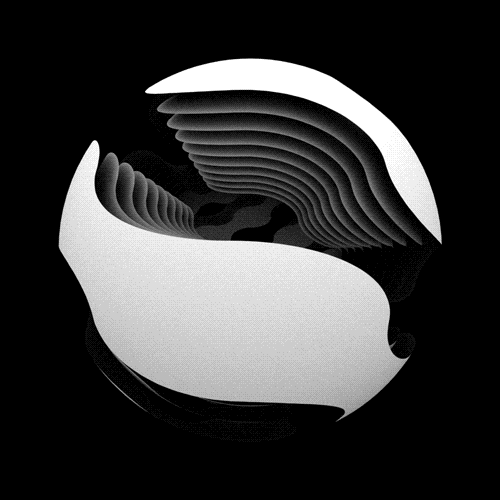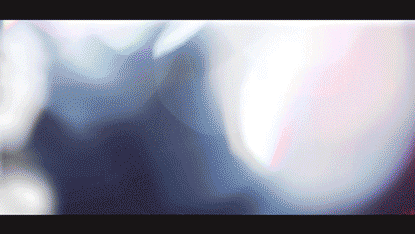(九) 高野川 Takanogawa
久高島(くだかじま)の闇にふとコメットが流れた。青白いテイルがみえた。
「 日本の支配者は彗星( comet)が接近しただけで変わることがあった。執権北条貞時もそうして引退したではないか・・・・・ 」
これなどは天人相関、地上に悪政があると、天上が詮議して彗星や流星や客星(新星)の出現をもたらすというものだ。
例えば、日本に元(モンゴル)が攻めてきた。蒙古襲来(元と高麗の連合軍)は文永弘安の2度だけではない。サハリン・琉球・江華島などの日本近域をふくめると、1264年から1360年までの約100年のあいだ、蒙古襲来は繰り返しおこっている。こうした襲来は、為政者や神社仏閣のあいだでは「 地上と天上の相関 」によって解釈されたのだ。
「 そうだとすれば、北米の同時多発テロという地上の出来事に対しては、天上の出来事が対応すべきであるということになる。世界各地の地上で天上を扱っているともいうべき屋代(日本は神社)に祀られている神々は、同時テロに対し何事を詮議したのであろうか。地上には神の加護を旗印に闘おうとする国民がいる、聖戦という人間がいる。あれを「神の戦争」と解釈する、そのことが異常だった・・・・ 」
そのために阿部明子は篠笛を吹いた。そう思われる幽・キホーテが斎場御嶽にいた。
「 すでに君達は、昨年、カタルシスが踊る現場を目撃したではないか・・・・・ 」
というモロー教授の言葉は、必然に沸き上がってきた闘争の解を平和のための能力システムに変換するというものだ。つまり事象を最も適切にアブダクションすることを生かすよう学生らに指南した。おそらくモロー教授は人間の生体を本質に解き、確実性を求めて不確実性を相手にしていないからであろう。そうすると戦争とは、傲慢の成果にすぎなくなる。
モロー教授にとって、意識とは「意識が向かうところ」で、弥勒とは「その先」だった。平和を真剣に願う未来派たちは「用心のその先、人智のその先」に、より周到に注意を向けるべきなのだ。
「 これを日本では、智外に非のあらんことを、定心に用心すべし、という・・・・・・ 」
そう思って幽・キホーテはまた雨田博士と清原香織の二人に眼差した。




梅の木の下に、幾輪かの水仙の花が仄々とある。
純白のそれが静かに上の紅梅の蕾つぼみを押し上げていた。
初めゆく朝の陽に射され花は透かされている。香織は、しだいに冴えいくその可憐な水仙の白さを眼でじっと追っていた。すると花に捕えられた眼は白く縛られている。
「 花は何のために咲くのか!。手折(たお)る花を人は看取れるのか! 」
虎哉もまた香織と同じように水仙の白さに眼を止めている。
白は顕色(しろ)くさせた。
若い香織と老人とではやはり感想が違う。白さとは、それを白だと認めると、老人の眼には自身の汚れが浮き彫りとなる。虎哉はしだいに透かされていく花鏡の白さに、それまで蓋(ふた)をしてきた問題が次々と噴出しては、ギシギシと軋(きし)み始めるような予感がした。
「 現代は(もっと快適な自由を!)という理想の追求がいつのまにか功利目的の追求にすり替わり、誰もが己の自由のテリトリーの保全に及々として独善的・排他的になり、しかもその個の自由を可能にするために犠牲になっている多くが不可視になっている・・・・・ 」
水仙の白さは、そんな人間社会の不自由さを映し出しているように思えた。
白を看取れない近視者の不自由が描かれていた。
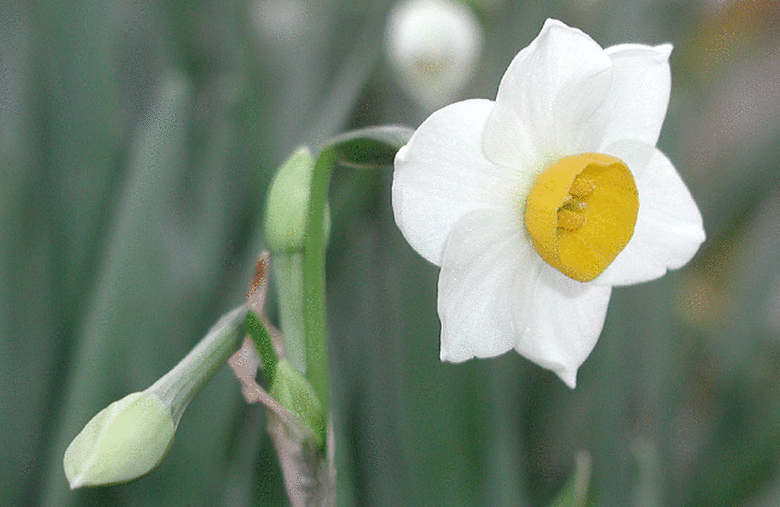
「 どうやら人は花の潔白の前に勝てない存在でしかない。九月十一日以降のアメリカ社会だけではなく、それは日本のどんな家族であれ鏡となって映し出している・・・・・ 」
これは当然、虎哉のモノでもある。たゞ水仙は白く自然体で、見事に社会のこれを鏡面の上に熨(のせ)てみせつけた。
「 それでも現代の人間は、自分が主役の自由な世界をせっせと拡張すべく、高度情報社会という画面の上を滑らせるのに忙しい眼先には潰すだけの暇すらないのであるから、日本の一集落にすぎない山端に咲く花の描く色模様など見てなどいられない。そうした自由にゆさぶられながら先進国は麻痺し縛れたごとく偏向のまゝ器(うつわ)だけを膨張させ続けている・・・・・ 」
白さにそう畏(おそ)れると、水仙はそれをもはや陋屋(ろうおく)の暗さに等しい不自由な世界として透かし彫りにし、小さくても漱(すす)ぐ力は薄情であることを虎哉に見せつけていた。
バス停の脇にさりげなく咲くその水仙は、別荘で働くようになった二年前に、車椅子生活の君子に見せてあげたい清原香織が北山の芹生(せりょう)から移植したものである。
そして一株ごと等間隔でバス停から道脇に植えられた白を目印に辿れば、別荘に着く。
晴天の日の午後に香織は度々このバス停まで君子の車椅子に付き添い、帰りの上り坂を押した。
そもそもこの花の白さは、比叡山西方院の鬼掛石の付近に野生する一株の水仙から竹原五郎が株別れさせて、北山の芹生で香織に育てさせていたものであった。水仙には黄色い花もあるが、それが白であることに竹原五郎の深い思い入れがあったようだ。
御所谷の五郎の暮らしぶりと密接である香織は、五郎がそうする心情を亡き父から知らされている。虎哉もまたそんな香織から、この水仙は何やら八瀬の地と深く関わる曰(いわ)くの花なのだという話を薄っすらとだが聞かされていた。
「 この花、神秘・・・・・、という言葉なんや 」
という、花言葉の話を君子から教えられたという五郎の笑顔を香織は思い出していた。
そうして指先で花びらに触れてみるとその花言葉は、植物の花や実などに与えられた、象徴的な意味をもつ言葉である。日本には、明治初期に、西洋文明とともに主にイギリスの花言葉が持ち込まれた。
「 花やかて言葉を持っている。それを知るとなッ、たしかにその花の言葉は、花の語る密言なんやわ。やはりそうやと、わいは思う。するとな、人は白状せなあかんのや・・・・・ 」
そんな話を君子が聞かしてくれたのだと言って、そう香織に語る五郎はいかにも嬉しそうであった。

「 せやけど、悲しい花やなぁ~・・・・・。神さまァ、泣きはったんやわ・・・・・ 」
ギリシャの青年ナルキッソスは、その美しい容姿から乙女達の心をとりこにした。しかし彼は決して自分から人を愛することはしなかった。ニンフ・エコーは働けなくなるほど彼を愛したが、彼は相変わらず冷たい態度で接し通した。これを見て怒った復讐の女神ネメシスは「 人を愛せない者は自分自身を愛するがいゝ 」と呪いをかけたのである。ナルキッソスは水面に映った自分自身に恋をし、食事も出来ずに痩せ細り、白いスイセンになったのだという。五郎はそんな青年の死に同情した。
けれども香織には、仕打ちしなければならない女神の心情が悲しいのだ。つまりナルキッソスは、その美しさと高慢がゆえ、復讐の女神ネメシスにより、水鏡に映った自分自身に恋させられた。水面の中の像は、ナルキッソスの想いに応えるわけもなく、彼は憔悴(しょうすい)して死ぬ。これは呪いとは何かを問いかけている。
「 五郎はんは女神を怒らせると祟(たた)る、だから怖いのだと言いはった 」
そして、その体は水辺であたかも自分の姿を覗き込むかの様に咲くスイセンに変わったという。このギリシャ神話の伝承からスイセンのことを欧米ではナルシスと呼び、スイセンの花言葉「うぬぼれ」「自己愛」が生まれたのだ。さらにこの神話がナルシスト(ナルシシズム)という語の語源ともなった。
比叡山の下、その山端に育つと死とは空気のように常に身近にある。そう育った香織は素直に戒めだと思えた。
「 学名はNarcissusというのよ。原産は地中海沿岸なのだけども古い時代に日本に渡来し野生化したの。スイセンという名は、中国での呼び名「水仙」を音読みしたものよ。水辺で咲くスイセンの姿を、仙人に喩えたと言われているわ。仙人は、中国の道教において、仙境にて暮らし、仙術をあやつり、不老不死を得た人を指すの。それは不滅の真理である道(タオ)を体現した人とされるわ。だから花言葉は(神秘)とも言われているのよ 」と。 五郎と同じように、車椅子を押す香織もそんな話を君子からしだいに詳しく聞かされた。耳奥のその声を引き出すと密かなのだ。すると耳も眼も白くなる。


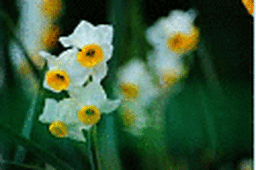


「 これは、密言の花や・・・・・ 」
五郎は以前からスイセンの花をそう呼んでいた。仙人は基本的に不老不死だが、自分の死後、死体を尸解(しかい)して肉体を消滅させ仙人になるという方法があり、これを尸解仙(しかいせん)というのだと語っていた。
「 小生の聞き覚えでは、これは道家(道教)の術である。一般にその仙人といえば、白髯を生やした老人というイメージがあるのだが、韓湘子かんしょうしなど若々しい容貌で語られる者や、中国では西土母、麻姑仙人(仙女)などの女性の仙人の存在も多く伝えられている。尸解の仙術を心得ると、人は肉体を残して魂魄(こんぱく)だけ抜け出た超人となる。最澄(さいちょう)は平安時代の僧で、日本の天台宗の開祖であるが、入唐求法(にっとうぐほう)の還学生(かんがくしょう・短期留学生)に選ばれて天台山に登り天台密教学を日本に持ち帰った。これが日本の天台宗の開宗となる。その天台宗の年分度者は比叡山において大乗戒を受けて菩薩僧となり、十二年間山中で修行することを義務づける。そうした天台千日回峰行僧の修行の姿が、仙人と同じなのだ・・・・・ 」
と、主人阿部秋一郎は語っていた。
おそらく比叡山に親しい五郎は、水仙をその阿闍梨(あじゃり)が尸解した白さだと考えている。


「 千賀子はん、どないしてはるかなぁ~ 」
そういゝながら香織は、先ほど会った五郎を泛かべ、すっかり朝の明けた鞍馬山の方をぼんやりとみた。
そして奈良から帰ったら一度芹生の丘の水仙に逢いに行きたいと思った。
「 千賀子さん、て、あの芹生のか・・・・・ 」
ふと何か、発見の素直な歓びに満ちている風景が泛かんできた。
「 そうや。今でもまだ、あの牛飼の少年のこと、じっと待ってはるんやろか・・・・・ 」
香織がそういう千賀子とは、今から二年前、虎哉が香織に連れられて初めて芹生の里を訪れたときに出逢った女性である。それは水仙の花がまだ蕾の固い初冬のころで、北山へと分け入って、香織が育てる水仙の丘を確かめた日のことであった。
しかしその丘を見るのとは別に、そこには灰屋川の上流になる清らかな流れを、そして北山杉の育つ原風景を、虎哉が今一度眼に焼きつけておきたいという願いもあった。その光景が泛かぶと、また、かって北山杉が聴かせてくれた朝の聲(こえ)を覚えた。


「 あゝ、あの千賀子さんだったら、きっと待っているだろうね。どうやら彼女はそんなお人のようだ・・・。魂魄眼(こんぱくがん)というが、気を集める眼とは、あゝいう人の瞳をいうのだろう・・・・・ 」
魂(こん)は陽に属して天に帰し(魂銷)、魄(はく)は陰に属して地に帰すと考えられている。
あの日、香織と虎哉は貴船(きぶね)の奥の芹生峠を越えて杉林の中をしばらく行き、一つの木橋を渡る途中で牛の鼻先に籠(かご)をかぶせて牛をひく少年と行き違った。
その牛の背には鳩籠を積んでいた。香織と同じように水仙の白さを見つめる虎哉は、その少年と牛のどうにも長閑(のどか)だった光景を重ねながら、少年を見送る千賀子の姿、その眼が湛える清らな精留(まどろみ)を思い出していた。そしてその千賀子は香織のことを雉(きじ)の子と呼んいた。
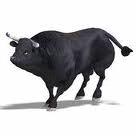
そもそも竹原五郎が芹生の里で比叡山の水仙を株分けし保存しようとした背景は、阿部家の山守屋敷を管理していた千賀子と深く関わっていた。そして二人は陰陽(おんみょう)で交わっている。千賀子は阿部富造の妹なのだ。
「 宇治ィ行かはったら、一度見ておくれやすか 」
と、千賀子はいった。そこに株分けした水仙がすでに植えられているという。そして日を改めた穏やかな冬の小春日に香織の案内で宇治の恵心院を訪ねてみた。虎哉はその恵心院での一日を思い出していた。
恵心院は、宇治川のほとりにある。
恵心院は年間を通じてさまざまな花が見られる、まさに植物園のようなお寺であった。京阪宇治駅から恵心院に向かうには、まず「さわらびの道」と名付けられた通園茶屋の脇を橋寺の山門前を通り宇治川に沿って続く道を進む。途中、左へ向かう「さわらびの道」との分岐があるが、そこをさらに宇治川に沿って進むと、宇治神社の鳥居を過ぎたところに、恵心院へ向かう緩い坂道の参道がある。
この参道の両脇に千賀子と五郎が移植した水仙の花が咲いていた。
さらに参道を上って行き、突き当たりを右に折れると正面に恵心院の山門が見えるが、このあたりでも水仙が咲いていた。その水仙に潮の香りを感じる陰陽の花が虎哉には不思議だった。
「 百万遍(ひゃくまんべん)、回向(えこう)しはる水仙の白い花、そんな気持ちで植えさせてもろてますんや・・・・・ 」
と、千賀子は頬笑みながら語ってくれた。それはじつに初々しい口元であった。
恵心院は弘仁十三年(822年)に弘法大師空海が開基した龍泉寺を源とする。真言宗智山派に属する古刹で、戦火による荒廃の後、寛弘二年(1005年)に比叡山の恵心僧都(えしんそうず・源信)が再興したと伝えられ、恵心院という名はこの再興の僧都にちなむものである。
「 後の世を渡す橋とぞ思ひしに 世渡る僧となるぞ悲しき まことの求道者となり給へ 」
と、虎哉は久しく思うこともなかったこの古い歌を思い返していた。
虎哉の眼には、今日、奈良へと向かう道がある。歌はその奈良の道へと通じていた。さらにこの歌は母が偲ばれ故郷を省みたくなるような歌なのであった。これは源信に宛てた母の歌である。源信は奈良の当麻に生まれ、虎哉もまた奈良に生まれた。その虎哉は、母よりこの歌がどのような意味合いを持つのかを、手習いとして幼心に覚えさせられた。それはまことに苦い記憶には違いないが、今となれば母恋に温かくある歌でもあった。
大和国北葛城郡当麻に生まれた源信は幼名を千菊丸という。父は卜部正親、母は清原氏、天暦二年(948年)7歳のときに父と死別した。信仰心の篤い母の影響により9歳で、比叡山中興の祖である慈慧大師良源(りょうげん・元三大師)に入門し、止観業、遮那業を学ぶことになった。14歳で得度し、その翌年には15歳で『称讃浄土経』を講じ村上天皇により法華八講の講師の一人に選ばれた。
そして、天皇より下賜された褒美の品(織物など)を故郷で暮らす母に送ったのである。
しかしその母は源信を諌める和歌を添えてその品物を送り返した。以後、源信はその諫言に従い、名利の道を捨てて、横川にある恵心院(現在の建物は、坂本里坊にあった別当大師堂を移築再建)に隠棲し、念仏三昧の求道の道を選んだ。紫式部の源氏物語に登場する横川の僧都とは、この源信をモデルにしたとも伝わる。

いずれにしろ千賀子のいう「 回向しはる水仙の花 」とは、畏れる人が、この世にめぐり遺したい清浄の花であった。
「 せやけどバス、えらい遅いなぁ~・・・・・。電車だと早うに行けたんやわ。きっともう伏見ィ過ぎたころや・・・・・ 」
苛々とした口調で香織は投げやるようにいった。
「 いゝかい、かさね。人生とは、待ちわびることだ。あこがれて希望を待ちわびるのが佳き人生の旅をする極意なのだ。自分で計る風なんか、たかが知れている。何かや、誰かに、計られた配剤の風にこそ、大きく享(うけ)るものがあるからね。人が人として長い人生を生きる間には、時として、動こうとしない時間も人間には必要だ。何もかもが人間の思い通りにゆくはずもない。だから、たゞひたすらと待ちわびる。ときには他界の摂理にでも身を委ねる時間というものを心がけることが大切になる。あの芹生の、牛を引いていた少年のようにな 」
と、苛立つ香織をなだめながら虎哉の眼には芹生で出逢った千賀子の姿が映されていた。
それは凛と背筋を立て、穏やかな眼差しを感じさせながらも何かを深く見つめた鳶色(とびいろ)の眼の女性であった。少年は牛を曳きながら奈良の長谷寺まで行くのだという。まさしく平安の観音信仰を彷彿とさせる。そう聞かされて虎哉は眼を丸くした。

「 あれは、たしかに隠国(こもりく)・・・・・。そして鳩の名は、栗駒・・・・・か 」
そう香織にいゝ聞かせながら虎彦は、めくり忘れて少し気がかりなことだが、昨年のさゝいな過失、日めくりの暦(こよみ)を思い出すと新春を迎えた今、どうにも幸福を求めようとする自分が苦手なのである。
馬齢のせいか、眼に見えて「残り日」が減ることがじつに面白くなかった。人生というものが80歳も過ぎると、消えていく時が見えにくいのがいゝのだ。年末に日めくりを千切ろうとしたとき、どうにも心まで吹き飛ばされるようであった。 だからあえて暦をめくり忘れることにした。しかしそうした確信的な自らもが、虎哉はまた苦手なのであった。めくる手数分だけ死の影を近く感じさせる日めくり暦は、そのときもう架けるのは止めようと思った。余命を思えば、実際すでに一、二枚の余白しかない。
「 ふ~ん・・・。・・、たゞ待ちわびること、えらい面倒な話やなぁ~ 」
面倒な話を聞く途中で耳を塞ぎたいのも若さである。
香織はやゝ目先につられ先走りする質たちの娘で、そんなときにいつも耳朶(みみたぶ)を指先でなぞり始める癖がある。その様子をながめながら虎哉は、香織がまた悩み始めていると思うと、そこに「 いずれの時か夢のうちにあらざる、いずれの人か骸骨にあらざるべし 」という一休宗純をふつと覚え、もう若くもないのに胸が躍る自分がいることが、夢でもあり骸骨でもありそうな揺れ間に立つようで、その隙間が自身でも何だか可笑(おか)しかった。
昔は、「仕事始めの日」というのは、新年の挨拶、顔合わせをするだけで、得意先を回り、屠蘇(とそ)を飲んで、午後には三々五々帰宅していたものだ。子連れの母さん社員が会社に来ていたりしていた。現代ではそんな風景は皆無、まず見られない。
松の内の正月六日までは、ドタバタしないものであったが、現在では、もう今日から定時出社定時退社ともなれば、サラリーマンは風情の余裕もなく大変である。全く世知辛く、日本独特の長閑でのんびりした正月が消えている。はっきり言って、過日を佳日として体験した老人にはつまらない時代なのだ。現代の人間は時間と経済とにコントロールされ浮遊するごとく生きている。こういうことが寒々と身に沁みてくると、やはり若者にはしつこい辛口となる。老いの舌は甘言を捏(こね)る余力などない。
「 儂(わし)のように老けてくると、時計が止まる時間が、どれほど嬉しいものであるかがよく解るようになる。死期が近づく手前で時計が針を止めて欲しいのだ。もしそうであれば本当に嬉しいと日々思うのだよ。しかしそうなればなったで、もう新しい明日などは永遠に訪れない。そうであってもピリオドだけは自らの意識で打ち終わりたい。最期だけはこの手で打ち遺したいものだ。これは、かさねには、まだ解らないと思う。だがね、若いかさねには、若いから耕して欲しいと思う時間がたくさんある。だから今の時間をしっかりと享け止めて見つめて欲しい。その時間とはね、真剣に待ちわびることでしか享け止めることはできないよ。だから、自分から進んで時間を止めては駄目なのだ。止めるのと享け止めるのでは大違いだからね。解るかい・・・・・かさね・・・・・ 」


「 へえ~・・・・・そうなんや。せやかて、うち馬鹿やし、盆暗(ぼんくら)やして、老先生のいゝはること、むずかしいて、うち、よう解らへん・・・・・ 」
そゝくさと虎哉から視線を逸らした香織は、くるりと元に向き直るとうつむいた。
さすがに主人の説法じみた難解な口どりには疲れるのか、霜柱を踏みつぶしながら妙に寂寞(せきばく)とした小さな背中をみせた。しかし、それをまたのんびりとみる虎哉の眼には、そうする香織の姿が、何やら冬ごもりのような、やわらかい絵になっていた。香織はむっつりとはしたものゝ「 君子はん、今ごろ、どないしてはるやろかなぁ~ 」と、ふとそのことを虎哉に訊こうとして、しかしそれをやめた。
「 えゝか、あの家やしたら、ほんに香織も幸せに暮らせるさかい、一にも二にもまず辛抱(しんぼう)やで。身を肥やす勉強や思たら辛うはあらへん。もし、辛い思ても、もう帰る家かてあらへん、そない思いや。何事も、味能(あんじょう)して、務め通さなあかへんえ 」
このとき香織は、雨田家に最初に連れられて伺う折々に、置屋(おきや)の女将佳都子と竹原五郎とが同じようにいって聴かせた二人の言葉を思い返した。
「 たゞ、待っていれば、それでえゝんやな! 」
佳都子と五郎の顔を泛かべ、香織は小さくしょんぼりといった。
「 いや、そうじゃない。違う。(えゝんやな)という、その言葉使いは少し不味(まずい)ね。(よろしィんやな)と言う方が、より上品だし適切だろうね 」
「 へえ~・・・。待てば、よろしィんやな 」
「 あゝ、そうだ。それでいゝ・・・。だが、バスが来てくれることに感謝する気持ちが込められていないと意味がない。バスがいつも来ることを、当たり前だと思っていたら、その気持ちがすでに駄目ということだ。かさねがいつも使う言葉で(来はる)(来てくれはる)の、あの(はる)の心遣いが大切なんだね。それは、京都で生まれ育った、かさねなら、簡単なことじゃないか。何もそう身構えて考えることもなかろう。生まれたまゝに、すでに身に染みているのだからね。ごく自然に振る舞えばいゝ。バスは来るのではなく、いつも(来てくれはる)のだからね・・・・・ 」
こういゝ終えた虎哉は、吐く息の白さも白いとは感じとれぬ杉木立の陰の薄暗さの中で、今も使われているとは信じがたい、そんな古めいた臭気がふと鼻を衝ついた。
「 香織が盆暗というのなら、私もまた何とぼんくらなことか・・・・・! 」
それは昔、六燭光の小さな電球が、六畳の部屋を薄気味悪く照らしていた光景である。
その中央に、凋(しぼ)んだように小さく、5歳の長男、光太郎の遺体が左向きに寝かされていた。
死後十日も放置され、壁に向かされたその横伏せの顔面は、被弾で潰された亡骸なきがらの青く涸れた顔をして、その首から下は消毒液が濡れて乾かぬほど、散布されていたのであった。
ふとよみがえるように感じた臭気とは、虎哉の両腕で固く抱きしめた後に、鼻先に遺された消毒臭に混ざった息子の死臭なのだ。
腐ったわが子の死体を嗅がねばならぬ親の痛恨の苦しみなど、あの戦禍の時代に、誰一人として省みて真意の涙など流してくれる者はなかった。誉れや奉公のために人は涙した。軍人の家の子として生まれたという小さな英霊の扱いとして狂気な同情を背負って我子は成敗された。西は宮城の方角であった。虎哉は、その亡骸を背負って5キロほどの夜道を宮城とは逆の隅田川の方へふらふらと歩いた。それは5歳児にして国を背負う亡霊の重みだ。その光太郎がまだ3歳であったころのことだ。虎哉は香織に今語ったのと同じ言葉で、幼い光太郎と会話したことを思い出した。
「 お父さん、バス遅いね。来るのかなぁ~・・・・・ 」
「 光太郎、来るのではないよ。バスは待っていると向こうの方から来てくれるものですよ 」
そんな光太郎がバスを大好きであったように、いや、亡くした息子が好きであったからこそ、そうなってしまったのかもしれないのだが、虎哉は電車とかいうより何よりもバスに乗ることが好きであった。バスを待つ息子の眼はたゞキラキラとしていた。
「 なして、そないバスがよろしやすのか?・・・・・ 」
と、以前、香織がそう問いかけたことがある。今朝もそう問われた。
そのバスが間もなくやって来てくれるであろう。虎哉が待つバスは、いつも亡くした光太郎を乗せてやって来てくれるのであった。そう思いたい虎哉は、そうした思いが果たして香織の場合、回答になるのかどうかさえ分からないが、ともかく応え返してみようと思った。亡国や亡霊を見過ぎた老人には御伽噺(おとぎばなし)が山のようにある。
「 私は、近年になって、生活に金をかけ始めたような、そんな生々しい富貴(ふうき)さが、まずもって嫌なのだろうね。戦中、戦後、荒れ果てゝいた家の中は、それでも、古い天井の下の採光の十分でない暗い家の中に幸せというものが漲(みなぎ)っていた。それにね、今は街や道は明るく、たしかに便利ではあるが、もう昼と夜の区別すらなくなっている。これも富貴な人工照明のせいで、未明などという言葉も現在では使い辛いほど、この世からは暗闇というものがなくなってしまった。やはり生きる人間には、陽と闇の按配(あんばい)がこの上なく大切なものでね・・・・・ 」
と、語ればまたどうしてもそんな面倒な返し方になる。きっと鼻の上に皺(しわ)をよせて、光太郎の亡き影を過ぎらせ一気に捲くし立てることだろう。そうする未練がましい自分がいることを虎哉は自覚できていた。すると聞かされた者の耳にまた同じ闇が訪れる。だから今更、香織にそんな応え方は止めようと思った。バスの、あの人臭さの中に身を沈めていると、バスを好んだ長男光太郎を偲べることは無論、多くの学生達が当時好んで使った言葉で言えば、何かに参加しているという好ましい実感が、乗合バスの中にはある。社会鍋や道普請(みちぶしん)にも進んで参加し、虎哉の若いころは、何より貧しいながらも生活道具を大切にし、使いこむ、磨きこむなどの工夫する痕跡に拘(こだ)わることで得ることの、尊さや美意識めいた価値観というものが存在したし、評価されたりもした。
そんな生活の模様が、当時よくバスの中には溢れていた。そんな風に懐かしくバスを想う虎哉は、靴の搖曳(ようえい)がおもしろいのだ。靴をながめていると些細なことにまで感動することがある。バスの中の靴は正直なのであった。しかも雄弁だ。

汚れても人目など憚(はばか)らぬ靴、新調だが埃をかぶり光らない靴、何年も磨きこんだ丹精の靴、いずれもが人それなりの味わいをもつものだ。しかも心が萎(なえ)て衰えそうになるとき、虎哉が一番欲するのは、群衆に紛れて、たゞ一人になることである。戎(えびす)の軍靴を見過ぎたからだ。そのためには真新しいバスでは駄目なのだ。古びてぼこぼこになった錆だらけの長い缶詰のような、鼻高のバスの中に、身をかがめていることが何よりも安らぎを与えた。しかし現代、そんな戦中戦後の最中を走るようなバスはない。それでは免罪の切符ではない。
だからせめて今日は、わずか5歳で戦火に炙(あぶ)られて夭折した光太郎の遺骨の多すぎる余生を抱くようにして、不便を承知して何度かバスや電車を乗り継ぎしながら、手枷足枷(てかせあしかせ)を切符にして、人肌臭い車輌で奈良までを揺られてみたいのだ。そう思うと、八瀬遊園の方からバス影が近づくのが見えた。
二人の待っていたバスが洛中の方へと遠ざかってしまうと、蓮華寺(れんげじ)の辺りにもう人影はない。高野川沿いに点在する人里は、低く冷たい北風の中にまだ眠っていた。
その蓮華寺は天台宗の寺院である。山号を帰命山(きみょうざん)とする。
竹原五郎が君子に会ってから後に立ち寄ると言っていたが、創建当時の山門が今日も残されている。
五郎は時折こゝに顔を出しては境内の植栽などを手入れしていた。虎哉も度々訪れて五郎の仕上げを四季折々に愛でてはいるが、蓮華寺というやわらかな響きより、むしろ虎哉には帰命山という山号こそに山端に存在する意義が感じられた。そうして虎哉はバスの車窓に何を見るのでもなく京都の寺々を尋ね回っては個々の佇まいを眼に写し残そうとした折々の日のあったことを想い起こしている。
「 そうした風情というものが、虎哉のレジリエンスには貴重な基軸となることが小生にもよく理解できる。いくら現代の先端技術を投入したインフラ整備を施したとしても、それはレジリエンスに相反する方法で、一たび破壊された伝統集落はその方法では戻らない。虎哉の考えるレジリエンスには地域の固体性と多様性が不可欠なのだ・・・・・ 」
十年前に雨田虎哉が八瀬に別荘を建てた当時から猫六は、他所者が何故この地にと思ったものであったが、彼の眼差しを拝察し続けてみるとそこらの理由が理解できるようになった。
「 例えば虎哉は、複数の樹木層からなる混成森林を山端地域に育て、その中心を動植物保護区としたモデル地を創出させ、コミュニティー、経済システム、生物多様性、生態系を取り戻すレジリエンスを構築したいのだ。そこには地域の固体性は重要で、つながりとしての寺院の存在に多様性を見出そうとしている・・・・・ 」
そうした虎哉のレジリエンス視点に丸彦が驚くことは、彼が環境保護とは多様な生き物全体を捉える必要があると考えていることだ。その多様な生き物の一つに人間という動物も他と同格扱いで位置づけていることである。そこが丸彦には面白いし、また感動もある。
「 何よりも虎哉には、祈りの場としての京都への畏敬いけいがある。こうした意識を下敷きにして虎哉が仰ぎみる延暦寺とは、寺名よりやはり比叡山なのである・・・・・ 」
そしてそのお山は、やはり生きていた。さらにその生霊(いきりょう)は虎哉の眼で明らかに蠢(うごめ)いている。遠くからみている限りの比叡山は、王城鎮護の山とされた聖なる山上の天台界という印象は薄い。だが冬山だけはあきらかに違う。
四明ヶ嶽の刻々と様相を変える雪景色は、神か仏の手がなしとげた天台宗ゆかりの霊山である中国の天台山を抽象させる白い鬼門の奇蹟なのだ。ともかくも山端に暮らす人々はそう感じ、そう信じて雪の四明ヶ嶽をしずかに畏れあおぐのである。いつもその「お山」が山端の暮らしを「見てはる」のだと感じるのだ。
虎哉はそんな比叡山を、蓮華寺の境内からながめてきた。
その移ろう四季の彩りの中で、山端集落の暮らしにも洛中とは違う営みがある。それは山を眺めみる人と、山中に居る人との違いである。そうした山端も暮らしてみると、一口では割り切れぬ多様な暮らしぶりであることに驚きもし感嘆もした。
蓮華寺は鴨川源流のひとつの高野川のほとり、かつての鯖街道の京都口のかたわら、上高野(かみたかの)の地にある。しかし、もとは七条塩小路(現在の京都駅付近)にあった西来院という時宗寺院であり、応仁の乱に際して焼失したものを江戸時代初期の寛文二年(1662年)に、加賀前田藩の家臣、今枝近義が再建した。このように京都の寺院は、永い風雪のなかで変化してみせる。そして寺院と密接にある人々の営みもまた変化した。
「 山に暮らしてはいるが、しかし潮の匂いをさせる竹原五郎もまたその一人であった。どうやら五郎という男は、阿部家と共に加賀前田藩と深く関わっている。そう感じられる・・・・・ 」
五郎という男を視ていると、虎哉には、永らく山林に関わった無数の日本の庶民の姿がごく自然に想起されてくるのだ。
「 老先生、ほら見ィや、高野川や。じきに真っ白うなるんやわ。もう寒うてカワセミもおらへん。死ぬ前ぇに、よう見とかなあかんえ~。五郎はんよく言ってはったわ。死んだら何もならんの人間だけやて。牛や豚は死んだかて丼(どんぶり)やら焼肉になりよるから人より偉いんやて。せやからお山の法師はんも、それ見習わはって精進しはるそうなんや。せやけど、カワセミは小魚漁(あせ)ってよう殺生しよる。ほやけど、カワセミは焼き鳥にはならへん。高野川のカワセミぃは人より偉いんや言うてはった。あないな殺生なら美しいて仏さん見てゝ喜びはるそうや。死んだらそれもう見れへんようになる・・・・・ 」

そんな香織のつぶやきは、反対の車窓をみている耳にも届いたのであろう。虎哉はコホンと一つ咳払いをした。
わずかに眼をなごめて「死ぬ前ぇに」の言葉の妙な揺らぎに、ポカンと口もとが崩れ、奔放な娘に微笑したようであった。
気随な虎哉の横に訝しくチョコンとかたく座る香織は、遠のく生まれ在所あたりの冬枯れる閑しずかさを、もう見飽きた風景とばかりに軽く感じ寄せ、その眼だけは朗らかに輝いていた。その香織は「 うちは何も頭から反対なんかしとらへん。心配なんは、老先生が死んだお父ちゃんに似てはるさかいや 」と、動かざる能面みたいに反応のない虎彦を按じながらそう思うのだ。
香織は水の流れが川石に砕けて光るのを見憶えると、下る流れがいつしか笛のような鼓動を打ちはじめ「 笛の上手なお人やった。その笛にあわせて高野川の風が踊らはる」、その父と高野川の光景がキラキラと懐かしくよみがえりくる。そんな香織は口をひきむすんでは「何や知らん、うち変な気持や 」と、つれない虎哉を横眼にながめては、しばらく眼を閉じたまゝにした。
「 こうした何の変哲もない茫洋(ぼうよう)とさせられる日常が、いつまで続いてくれるというのか 」
虎哉の青春期にはいつも戦争という非日常と接しあう日々の中にあった。そんな虎哉もまた香織と同じ山端の光景を眼に映しているのだが、虎哉は頭の中にポッカリと空洞ができていた。その空洞の中に、遠い遠い、故郷の奈良の、干からびた冬の古い土埃ほこりがひろがっていく。日本の仏(さとり)は、その故国よりはじまる。
今日、虎哉が越えるのは白河の関ではない。京都と奈良を結ぶ現在の県道と平行する般若寺の道、その奈良坂である。そこより遠くに望む大仏殿の屋根に、来る人は無事の到着を喜び、去る人は別れを惜しむ。
「 奈良坂は、そんな出会いと別れを幾度見てきたのであろうか・・・・・ 」
と、まず虎哉の眼には般若寺の甍が泛かんでいた。ともかくも虎哉にとって遷都を繰り返して至る奈良から京都の道はワジ(WADI)なのであった。ワジとは水流のない涸かれ川をいう。しかしその水は人の不可視なのであって涸れ川の上は常にfall or flow in a certain wayであり、気功の流れでもあるのではないかと思われる。虎哉はそこに、特定の方法で落ちる、または流れる、という二つの古都を結んではその流れを繰り返す気功の法則があることを感じるようになっていた。





川とは、絶えず水が流れる細長い地形である。雨として落ちたり地下から湧いたりして地表に存在する水は、重力によってより低い場所へとたどって下っていく。それがつながって細い線状になったもの、それが川である。人はその川のほとりにオアシスを見る。遷都とはこのオアシスへの移動なのだ。京都も奈良も涸れ川の泉の、そのオアシスであった。
「 百万遍(ひゃくまんべん)、回向(えこう)しはる水仙の白い花、そんな気持ちで植えさせてもろてますんや・・・・・ 」
虎哉はまた千賀子の残した言葉が思い起こされた。
「 百万遍念仏(ひゃくまんべんねんぶつ)とは、自身の往生、故人への追善、各種の祈祷を目的として念仏を百万回唱えることである。用いられる数珠を百万遍数珠と呼ぶ。聴きようでは都の川のせせらぎは、数珠を繰る涸れ川の聲(こえ)であろうか・・・・・ 」
京都洛北に10年ほど暮らしてみて判ることだが、比叡の原生林が杜もりになり、そこに祈りの空間を創りあげていく使命感があり、そうした人間と生態系の調和という発想に、古き良き日本人の先端精神を感じ取ることになる。
せゝらぐ高野川は念仏の数珠をくる。
そう思える虎哉にとって、狸谷の阿部家が代々いかなる発想で存亡を賭けて挑んだかを説くことは重要であった。
車窓からながめみる高野川の流れの中には、そこに重なるようにして虎哉には久しく懐かしい、しかし哀しくもある佐保川の流れが泛かんでいた。その里は万葉の、いにしえの国、大和なのである。
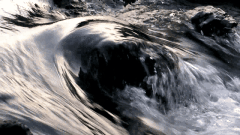


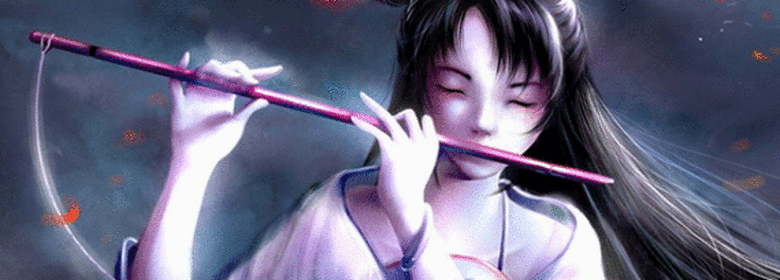











酒井雄哉 比叡山「断食、断水、不眠、不臥の難行」