




































(七) 安波茶橋 Ahachabasui
生まれ落ちた人間はすでに定律の道を踏み、人知れず他人の時間に我が身を分離して潜ませている。
その人間が地球上のどこかで、あの他人と巡り逢ったとき、人間はこの出逢いを「奇遇、偶然、必然」のいずれかの言葉で表現することになる。また他人も同じくこの表現のいずれかを選択する。そして見知らぬ二人は突然、これが運命であると自覚する。こうして天は人間の生命を運動させては美妙な配剤の処方で人を交差させるのである。さらに人間は地上を離れても定律した運命により無限に結ばれて廻向する。
この天があらかじめ投じた定律の摂理を「宿命」という。翌朝、比江島修治は一人の女性と出逢うことになるのだが、張本人である天はすでに今宵、時みつる声を二人の意識に架けたようだ。しだいに二つの意識は宿命の意図で引き寄せられ一本の道となる。
「 一人の人間と出会うには、確かにいろいろなことがおこる。沖縄で生まれ育った人間であっても、琉球史の上を歩くように出会うなどということは、まずありえない。そんな人間は、きっとよほどつまらない有識者なのだろう。たまたま近くの本屋で隣り合わせた人を友人とする場合もあれば、何かの評判に惹かれて興味を抱くこともある。以前から顔見知りでいたのに意識することなくずっと放ってある人を、何かの拍子で意識し始めることもある。それが結構おもしろくて、ついつい同じ穴のムジナや変人をたてつづけに好きになることも少なくない 」
問題は、その人をどのような意識状況にいたときに好んだのかということである。その意識状況によっては、別人に気をとられているときに見かけたために、その人間のおもしろさがまったくつかめず、十年以上もたってふたたび意気投合にしてみて、しまったとおもうこともけっこうおこる。修治が名嘉真伸之と出逢った場所は奈良の飛火野であった。
しかし当時、伸之は話していて、ずいぶんなトンチンカン男なのだ。だが彼は、当時はだれも試みたことがないノンフィクション俳句の先駆者であったのに。そして赤い蝶ネクタイ、琥珀色の角縁メガネ、低くて太った体躯、人間の背中にやたらに手をまわしてくる男であった。修治はそんな男には好まれなくてもいいやという偏見の中にいた。しかし年々意識を強くさせられる男なのである。やはり逢えないと気になってくる。夕食後の小さな固い湯船のなかで修治はそう考えたのだ。それでやっと出会ったのが入浴後の「 相部屋で語らう伸之 」であった。
晴天に暮れた沖縄の夜空には満点の星が輝いていた。
毎晩一合の酒と決めている修治は、泡盛のオンザロックを揺すりつつ15階の窓辺から那覇ベイエリアの夜景の彩りを一人ながめている。
「 阿部富造は、奈良にいて、あの炎上の不吉に恐れたのだ・・・・・。そしてあの時、八瀬童子らは平癒祈願を行った 」
そう思う眼には、センターポールから沖縄の地べたに引き落とし放火されて燃え尽きた日章旗の炎上が一つある。さらに二つ目の炎上として記憶に残る裁判の動向を映し出していた。この二つの炎上は強烈なインプレッションを与えたのだ。
日本国内を震撼とさせた麻原彰晃被告の第1回公判が延期になった10月26日、これとは別件でもう一つの判決が行われていた。それは「 日の丸焼き捨て事件 」の控訴審判決である。「日の丸焼き捨て事件」とは、1987年の沖縄国体のソフトボール開会式で、スコアボードの上のセンターポールにあった日の丸の旗が引きずり降ろされ焼き捨てられた事件だ。国内において日章旗が確信的に炎上させらるというセンセーショナルな出来事はじつに多くの国民が注目したのだが、修治には何もかもが乾いたように感じられ、根底には判読不能な表意文字によるマンダラのようなものがびっしりと描かれているような空漠たる衝撃を抱かされた。
当時、京都の陰陽寮博士の末裔阿部富造は奈良の旅中にあって、この日章旗の炎上を想い重ねながら昭和とうい時代の終焉を逸早く感じ取りつつ、富造は洛北集落の実情を記して阿部家伝を遺した。修治はその富造の動向に想いを重ねては、炎上する日の丸の光景を泛かべていた。そして沙樹子が嬉しそうに教えてくれた「 富造さんは、焦げたフランスパンのように濃い眉毛をしていたわ 」という男の風貌を想い起こしては、さらに富造の母沙耶子の故郷を眼差していた。そうして修治が感じとることは、沖縄と日本人は意外なほどに相互理解をしてこなかったのではないかということなのである。どうもこのへんの日沖事情には、かなり急がなければならない問題がはらんでいるようだ。すると修治は自分が何か厄介なナーコーマにでも捩(よじ)られながら地上を歩きまわっている夜行性の小動物のようにさえ思えてきた。
「 これは抗うつ薬パキシルのせいか・・・・・! 」
黒い甲殻をもったアルマジロのような小動物が奇妙なマンダラ模様を横切って行く。その小さな黒い影の行方を眼で追っていると、しだいに記憶から遠のいていた琉球の首里城と浦添城をつなぐ尚寧王(しょうねいおう)の道が泛かんできた。
「 はいたいサ~。はじみてぃやーさい、めんそーれ。どぅしサ~、しんかサ~。カリー!、カリー!、だからよ!なんでかね!。わん、キジムナー。あんまーが っやー あびとーんどー。あまんかい いびぬ あたんやー。安波茶(あはちゃ)サ~、うちなーゆーや まし やたん。 ぬーん うっさふくらさ そーてぃる する むん やさ。 かちゃーしー もーてぃ あしぶんサ~。さんしん ひち はねーかすんサ~。にらいかない んかてぃ うぅがむんサ~。んーぱ やてぃん さんとー ならん。安波茶サ~、シマショウネ。あんせ~や、あちゃ~や。ぐぶり~さびら、ぐぶり~さびら 」
いつしか修治はガラス窓越に、こんなウチナー口を聞かされていた。
「 アチャー、安波茶んかいはーれーば、阿部富造みーちが、うんじゅを待つてなますからね・・・・・! 」
弾み転がるさやかな黒い影は最後に丸まると、そう語りかけて夜空へと消えた。
そして窓ガラスには、丸い黒玉が転がる一筋の道が映し出されていた。









「 でーじなってる。でーじなってる。まっとばー通るとでーじなってる! 」
石は何事にも動じず、また霊力を宿すものである。
悪鬼(マジムン)は直進する性質があるため、道を直進してきた悪鬼がT字路にぶつかると、その家の中に進入することになる。そこでT字路などの突き当たりに「石敢當(いしがんとう)」を置き、魔よけとする。
徳利木綿(とっくりきわた)のピンクの花が咲いている。天に向けた枝先は曇天でさえ流麗である。
肌寒いその日は、鷹の小便(タカヌシーバイ)が降っていた。
「 ちゃ~するば~が~!? 」
小雨に濡れる桃色の花をみつめていた洋子のオバーは、結局、どうしたいのだ。あゝ!、と嘆いた。
そのオバーの眼には戦前のガーブーが泛かんでいた。
11月はサシバの群れが沖縄へ越冬する時期で、北風の吹く日は小雨が降りやすい。この雨をタカヌシーバイ、鷹の小便である。戦前の東町の商いがすっかり消えて、那覇のど真ん中のガーブー一帯が新繁華街になるとは誰も予想できない戦後の光景であったのだ。昭和初期の牧志周辺は湿地帯の広がる農村であった。戦前、洋子のオバーは与儀から東町の市場まで片道四キロの道を天秤棒で野菜を担ぎクバ笠を被って毎日四往復を歩いていた。市場内のガジュマルの木陰に、オバーの露店市(いしげ~まち)がひっそりとあった。
那覇の戦後復興期の米国占領下にあって、市民の旧市街地への移住禁止により県内外からの疎開民や避難民は、早期に解放された壺屋町や牧志町を中心とする地域に移住して戦後生活をスタートさせたのだ。すると1947年11月ごろに開南に闇市が自然発生し、那覇市は公共の立場から元市役所跡地に四百二十六坪の敷地を確保して1948年4月初旬に東町の市場を移転させた。したがって米軍の支配管理下にあった旧市街地が漸次開放され使用可能になっても中心市街地は旧市内に戻らず、周囲の発展とともに日陰のように発展することになる。
お盆に京都から帰郷した洋子は、何よりまず真っ先にオバーの眠る安波茶(あはちゃ)の墓にヒラウコーを焚いて合掌した。沖縄の娘としては猛省しなければならないのだが、じつに10年振りの墓参であった。
そんな洋子には、730(ななさんまる)というキャンペーン標語が眼の奥に鮮明にある。
当時、作業員数名は国際通りの歩道橋に白い横断幕を取りつけていた。
「 7月30日、朝6時から、車は左、人は右・・・・・ 」
と、横断幕にはそう記されている。7月30日、人は右、の文字が赤色に鮮やかだ。暫くその燃える緋(ひ)の赫(あか)は、洋子のオバー知花(ちばな)千代の眼を不動明王の迦楼羅焔(かるらえん)を見るごとく鮮烈に縛りつけていた。
それは1978年のことだ。その6年前の1972年5月15日に沖縄は日本へ復帰した。730とは、沖縄県において日本への復帰6年目に、自動車の対面交通が、右側通行から左側通行に変更することを示す事前キャンペーン名称である。1978年7月29日22時より沖縄県全域で緊急自動車を除く自動車の通行が禁止され、8時間後の翌日6時をもって自動車は左側通行となった。この8時間内に、全ての信号や道路標識の取り替え作業が行われた。
「 72年、核ヌキ、本土なみの復帰が決定・・・・・! 」
1971年に沖縄返還協定の調印、そして翌72年の5月、通貨交換のため琉球銀行や琉球相互銀行に行列する県民の姿を見続けた。洋子18歳の暑苦しい赤黒く焦がれた夏がこうして始まった。
「 与儀(よぎ)公園の、1971年、11月10日・・・・・ 」
洋子のその眼には、沖縄返還協定批准に反対し、完全復帰を要求する県民総決起大会に参加した女性らの姿がある。決起大会は那覇与儀公園で行われた。当日の大会はその後、浦添市までデモ行進を行い、途中、過激派学生の火炎ビン闘争で、琉球警察の機動隊員1人が死亡するなど大混乱となった。一方その眼には、協定批准の調印を祝う人々の姿がある。1971年6月18日夜、国際通りでの日ノ丸提灯(ちょうちん)、その祝賀ちょうちん行列を見た。そしてその前夜の那覇市、沖縄経営者協会事務所では、祝賀パレード用のちょうちんを準備する事務員らの姿があった。洋子には、この相反する二つの沖縄が眼の奥に残されている。この翌年の夏に、洋子のオバーは他界したのだ。炎天下に裏の畑で仰向きに太陽をみて仆(たお)れていたのだが、火山のようにぱっくり開いたオバーの口の中で金歯がびかりと光っていた。独り残された洋子はオバーの葬儀を終えた後、親戚を伝手に関西へと出た。
沖縄ではお盆を迎える時期に、より御嶽(うたき)の精子がエイサーのごとく小躍りして活発化する。
「 アチャーやなーちゅけー、安波茶ぬ墓んかい行きよーさい。かんなじ行きよーさいね。行きよーさいね。約束やいびーん 」
洋子はこんなウチナー口を聞かされた。その声は耳に馴染んだオバーのモノであった。
「 分かったよオバー。アチャーまた会いんかいいちゅんからね 」



琉球には、首里王府から発せられる布達や、地方からの年貢を運ぶために各地の間切(まぎり、現在の市町村にあたる区画)を結ぶ幹線道路である宿道(しゅくみち)が島の隅々にまで広がっていた。
そのうちの一つに、中頭方西海道(なかがみほうせいかいどう)がある。
首里城を起点に、安波茶、牧港を経て読谷に至るルートを指しているが、安波茶橋を越えたあたりまでほぼ中頭方西海道をなぞり、浦添間切番所跡を経由して「浦添城前の碑」にに至る道を、沖縄の人は「尚寧王の道」と呼ぶ。
尚寧王は1589年から1620年に在位した琉球王国の国王で、薩摩の侵攻を受けて江戸に連行され、二代将軍徳川秀忠に謁見したことで知られるが、その浦添按司家の出身であった尚寧王が、1597年に首里から浦添グスクまでの道を石畳にし、木造の橋を石橋にするなどの整備をするよう命じたものが「尚寧王の道」である。浦添城にある「浦添城の前の碑」はその時の記念碑で、碑文には平仮名の琉球文と漢文で、道作りの様子や竣工儀礼などの様子が書かれている。
「 外見では、あんなに俗っぽく見えてくる男が、まるで静寂から聞こえてくるエレミア記の響きのような俳句が詠めるのはなぜなのか 」
早朝に目覚めた修治は、一挙に名嘉真伸之の周辺が気になってきた。
出逢ったのは彼が25歳のときである。修治より2歳上で、高校を卒業した当時彼は、各地を転々と旅して7年をかけている。けれども、どの俳句の一行にも破綻がなく、透明度が維持されている。処女作ならこのような集中はどんな俳家にもありうることなのだが、その才能は群を抜いている。修治はその才能を当時の認識では見抜けなかったのだ。
たとえば『仏には遠い国』という処女句集の舞台は、北海道北部のチトカニウシとよばれている日本人でも気に止めることのない小さな村である。いわば「 小さな白昼のマタイ風土 」といった山合の散々としたアイヌ集落だ。沖縄戦で戦死した一人の日本兵がこの集落の生まれであった。句集は連句仕立てのそこに、戦死する前の父親を探している幼い息子が沖縄にやってきて、だんだん死の真相に近づきつつある大人への予感に怯えていく様子が克明に連ねて描かれていた。少年の母親も4歳のときにオホーツクの海で別れたままになっている。そのため、息子である少年は幼いころから道東、道央、道南を転々とした。つねに親戚の家にあずけられたのだ。つまりアイヌ民戦争孤児の流転記であった。こういう少年がしだいに年上の者を知り、少女に出会い、勝手な優しいおばさんに声をかけられていく。現代の日本社会で、どうなっていくかは決まったようなものだ。少年は大人への恐怖をもちつつ、自身に萌芽する自我と成熟におののくばかりなのである。何よりもまず少年がおののいたことは、この世には戦死という人間の死が存在するということであった。
「 首里の墓で撃たれて死んだ赤トンボ 」
この句で名嘉真は句集を〆ていた。
さらの句集を閉じる扉には「 アイヌの人の思いは、井戸のように深いところにあるとしても、琉球の人はそのアイヌ人からそれを汲み取り清らかな一杯の水を口に与える 」とある。これは、そもそも日本の古語というモノの成り立ちが、南の琉球の言葉と、北のアイヌの言葉とを源泉することを、名嘉真伸之は水質にたとえて暗示させ、同族の哀しみを織り上げている。こう言い終えて伸之は、芭蕉布の機織(はた)を止めた。北と南の神の国、それは大和の仏には遠い国なのである。


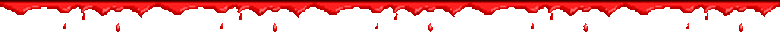





1200㎞のミドルフライトである。
琉球王国発祥の地・浦添ようどれの地点から、500mまで、北へぐんぐんと高度を上げた。
浦添グスクは13世紀ごろ築城され、15世紀までに英祖王や察度王などが居城とした。14世紀に中国や東南アジアとの交易で栄えた浦添は、王都として整備され、首里の原型となる。15世紀の初めに王宮が首里城に移転し、浦添グスクは荒廃したが、その100年後に、浦添出身の尚寧王が再び居住するようになる。
この浦添グスクの北側の断崖に「浦添ようどれ」がある。「ようどれ」とは琉球語で(夕凪、死者の世界、墓)という意味で、ここに英祖王と尚寧王が眠っている。この墓前の前で解き放たれ、北の秋空へと翔び発った。
「 秋浅く産まれたての大きないわし雲の稚児が、じつに爽やかだ。この北帰する黒潮の飛行ルートは、やはり秋がいゝ・・・・・ 」
こゝ数年、年に四回、この南海ルートでの飛行実験を繰り返している。
夏の季節風は黒潮の上を通過してくるため、湿度が非常に高くそれゆえ日本の夏は蒸し暑くなる。これに反して、冬は黒潮上を季節風が通過しないので、晴天が多くこれにより寒さを緩和させている。しかし冬場、高度1000mの上空は極寒である。やはり秋の空は爽快だ。
「 どうやら今回も黒潮の大蛇行は感じられない・・・・・ 」
とそう感じ、そしてふと振り返ると南後方の沖縄が豆粒ほどの小島になっていた。
「 後は、ほゞ半分、600㎞だ。それにしても、やはり焦土を経た琉球とは悲し過ぎる・・・・・! 」
古来、黒潮は京都を起点に、上り潮、下り潮と呼ばれていた。日本国の場合、どうしても物事の視点が宮廷の都を主軸に回ることになる。現在、沖縄は日本国、だが日本神話の時代には琉球は未だ生まれず異国なのである。後ろ髪にそう想われる琉球がじつに刹那(せつな)かった。
「 あゝ、だからカノン(Canon)だったのか。だから霞音(カノン)に編曲したのか・・・・・! 」
優しさと力強さが一つに溶けあって心に勇気を与えてくれる、そんな音階が耳奥から涌(わ)いてくる。そしてその和音(コード)の進行は、スローに演奏されるときには限りない郷愁を呼び起こし、高らかに歌われるときには、失意からの再生、希望を力強く訴え、人を力づける歌になっている。阿部秋子は、この1200㎞フライトの前に決まっていつもCANON(君子の霞音)を繰り返し聴かせてくれるのだ。
ようやく秋子の意図が理解できた。
「 秋子の編曲した霞音(Canon)、この和音を聞きながら琉球を俯瞰(ふかん)していると、打ち砕かれることを知った人だから言える、口先だけでない力づけの言葉が、原曲のパッヘルベルのカノン和音の進行に乗ったとき、限りないやさしさと説得力を持って全身に伝わってくる。秋子の編曲したこのカノンは、つまり沖縄の返還を完成させるための追複曲なのだ・・・・・! 」
本当に弱ってしまった時に、こんなに優しい慰めを与えてくれる楽曲もある。阿部秋子という女性は、悪戯や粗野で身なりを飾ることのない瀟洒(しょうしゃ)な人だ。
「 秋子の、その瀟洒な眼にして、やはり琉球とは瀟洒な故国なのである・・・・・ 」
本土の床の間には刀を佩(お)びて武門の格式を立てた。しかし琉球はそこに三線(さんしん)を立てた。相争わないそれが、一本の原木から二丁の三線を作る夫婦三線(ミートゥサンシン)である。この争いとは無縁な美学が本土に根付いた三味線の起源となった。沖縄とは根源にこの性質をもつ。黒潮の彼方をみすえるその眼には、ようやく大倭豊秋津島(おほやまととよあきつしま)が幽かに、本州の連なりが見えてきた。




「 左手は建日別(たけひわけ)の熊曽国(くまそこく)、そして前方が伊予之二名島(いよのふたなのしま)の四国・・・・・! 」
たしかに胴一つに四つの顔がある。あれが四国だ。
そしてその四国山脈を越えると、右手に、関西の広がりがみえてきた。
羽ばたくその眼下には淡道之穂之狭別島(あはぢのほのさわけのしま)、秋陽の下に淡路の島影が輝いている。
「 あッ、あれは淤能碁呂(おのごろ)、国生みの島だ。だが密か過ぎる。今日は、妙に静か過ぎるぞ! 」
天沼矛(あめのぬぼこ)で渾沌とした大地を二神はかき混ぜてはいるが、その精気が鳴門の渦にかき消されているではないか。そのため水蛭子(ひるこ)を乗せた葦舟は紀伊水道へと押し流されている。あやかな気功の停滞は危うさを感じさせた。
しかし、たゞ瀬戸内の海はおだやかに凪(なぎ)ていた。
「 淡路島上空は、おそらく乱気流、紀伊水道は気流が下降している・・・・・ 」
水蛭子の葦舟は紀伊水道を南へと下り、くるくると回りながら破れそうであった。
「 後200㎞だ。よし、進路を変更する・・・・・! 」
東の上空に不穏な気配を感じ、正面に寒霞渓(かんかけい)を眼に入れて飛ぶ一羽の鳩がいる。
土佐湾沖から讃岐(さぬき)五剣山(ごけんざん)の上空を超えてきた。
白亜の一翼を鋭角にし、鳩は一路たゞ北へ秋空を飛翔する。
払暁(ふつぎょう)、沖縄を飛び発った伝書鳩は京都へと帰還する「 聖護院(しょうごいん)六(りく) 」号である。
午後の小豆島上空はよく晴れていた。
その六号とは、京都隠密五流院の修験鳩、まもなく釈迦ケ鼻に差しかゝる。
「 あゝ、岬にいる、あれは丸彦(まるひこ)じゃないか。よし、霞音(カノン)を聴きながら、このまゝ進む・・・・・! 」
日本の国生みは、二神が島々を生む物語である。それは島生みの作法であり、六号はその日本神話・記紀を泛(う)かべていた。初めに大八島(おおやしま)が生まれ、次に六島が生まれた。六島の、その一つに小豆島がある。そう思うと六号は美妙な顔つきとなった。小豆島上空を通過しようと決めたころから、可憐な紅型(びんがた)を着た阿部秋子の姿が泛かんでいた。その秋子は鳩舎へと帰還する六号を待ち侘びていよう。想い逸ると自然に、六号の風切り羽は冴えた音を鳴らした。
「 卒(そつ)なく飛んでいる。あ奴(やつ)は、ひたむきに煩悩(ためらい)もなくやってくる・・・・・! 」
何か一言声をかけて、小生は、肩の一つも叩いてやりたい気がした。
聖護院六号は、背に超低膨張の硝子カーボン素材のカプセルを搭載する。小生とは猫の安倍丸彦である。その丸彦は小豆島の南にある白浜山の頂きにいて此(こ)の一羽を待っていた。

「 たゞし、小生は島内に一人でいるのではない・・・・・ 」
主人の安倍和歌子は島北部の星ケ城址にいる。星ケ城は、南北朝時代に、南朝方の佐々木三郎左衛門尉の飽浦信胤(あくらのぶたね)により築城された山城で、城址には星ヶ城神社がある。 東西の両峰には、空壕(からぼり)、鍛冶(かじ)場、水ノ手曲輪(くるわ)、烽火(のろし)台などの跡が発見されているが、和歌子は三日前から一帯の天文調査を行っていた。
「 こゝで北斗(ほくと)の七星、その一つ星が、あのときに零(こぼ)れ、六星になったんやわ・・・・・! 」
と、和歌子にそう奇想させる星ケ城の、落城時に関する伝承話が、安倍家伝にて伝えられている。この「北斗六星(ほくとろくせい)」の伝承は陰陽界にては名高く語られる話なのだ。北斗七星は、南朝方の名和長年(なわながとし)・結城親光(ゆうきちかみつ)・千種忠顕(ちぐさただあき)のほか、北畠顕家(きたばたけあきいえ)・新田義貞(にったよしさだ)らが次々と戦死し、軍事的に北朝方が圧倒的に優位に立つころに、地へと星を一つ欠いて落とした。したがって後醍醐(ごだいご)天皇にとっては凶事を兆したことになる。その小豆島は現代でこそ「しょうどしま」と称するが、中世には「しょうずしま」、そして太古には「あずきじま」と呼ばれてきた。
「 そのような古い小豆島は、歴史上の表舞台にはあまり登場しない。しかし・・・・・ 」
小豆島は古代から吉備国(きびこく)児島郡に属し、吉備国が分割された後も備前国(びぜんこく)に属すなど、中世までは本州側の行政区画に組み込まれていた。だが南北朝時代の騒乱に四国へと移る。飽浦信胤は、備前国児島郡飽浦を本拠とした豪族で、細川定禅(じょうぜん)の家臣として足利尊氏(あしかがたかうじ)に味方して活動、備中国征討や京都での戦いなどで功を挙げた武将であった。
「 この小豆島は、平安時代初期に皇室の御料地となる。しかし1347年、それまで南朝に呼応して島を支配していた飽浦信胤が、細川師氏(もろうじ)の攻めに倒されると、以後島は細川氏領となり皇室領は解体された。またこの細川氏は讃岐国(さぬきこく)守護であり、この時から政治的な支配者という側面では、島の支配は本州側の手を離れ、四国側に移ることになるのだ・・・・・! 」
と、そのことを頭に泛(う)かばせた安倍和歌子は、淡路島の方をながめていた。
星ケ城山817mは瀬戸内海の島々で一番高い山である。つまり、瀬戸大橋と大鳴門橋、明石海峡大橋の三橋が同時に見渡せるのだが、和歌子もまた星ケ城より、北へ目指す鳩の気配を見守っていた。
「 おい・・・黒鷹(くろたか)、聞こえるか。六号はそちらでは無い。小豆島のコースを選んだ・・・・・! 」
と、小生は淡路島の諭鶴羽山地(ゆづるはさんち)にいる黒鷹を呼んだ。島の最高峰であるが駒丸黒鷹もまたこゝに待機して北上する鳩の行方を追っていた。諭鶴羽山地(ゆづるはさんち)からは東寄りに紀伊水道の海域をよく観測できる。鳩の進路は、紀伊水道から北上することも予測されていた。
「 ちッ、そうかい。了解した。なら儂(わし)はこれから進行前方を警護するぜッ。いずれまた会おう 」
波の穏やかな瀬戸内は鷲(わし)・鷹(たか)・隼(はやぶさ)などの猛禽類にとって絶好の漁場である。そのため彼らの鋭い眼は常に島影に潜むようにあった。黒鷹はこの警護役であり遊撃隊なのだ。
「 やはり二郎の観察通りだ。進路をやゝ西寄りに修正している。今、八栗寺(やくりじ)上空を通過した。15分遅れたが問題はない。想定内の通過時刻、これで中央構造線は無事に越えた! 」
五剣山南中腹の八栗寺は遍路第八十五番札所、山内の一隅にて一時間前から双眼鏡で上空をうかゞっていた白羽(しらは)三郎は、那覇にいる出羽(でわ)五郎にそう連絡した。
「 了解!。六のダウジングが反応したのだ。淡路か鳴門の渦あたりにゼロ磁場を感じたのであろう。俺はこれから旧久米村付近の磁場密度を調査するよ。葛飾北斎の浮世絵・琉球八景にも描かれているが、そこから那覇空港に向かう。伊丹着は午後八時の予定・・・・・ 」
国際通りの県庁北口にいた出羽五郎はそういゝ終えると、じっと沖縄の青い空を見上げた。かって島だった那覇は、土砂の堆積により琉球王国末期に本島とつながる。この琉球八景にもある翡翠(あお)色を眼に浮かべたとき、その五郎は名を出羽五芳(ごほう)と入れ替えた。
「 現在のところ磁場密度に大きな変化はなさそうだ。六号は愛宕山(あたごやま)沿いに進入する・・・・・! 」
三郎は二郎にもそう伝え、同じく鳩舎のある京都へ報告し終えた。
そして三郎は八栗寺内の本堂と大師堂、また聖天堂に向かって静かに「 オン アロリキャ ソワカ 」と本尊真言を唱えた。
寺伝によれば、こゝで空海が虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)を収めた際、五本の剣が天から降り蔵王権現が現れてこの地が霊地であることを告げた。空海は降ってきた剣を埋め、天長6年に再訪し、寺山を開基したという。聖天堂には弘法大師作と伝える仏の守護神歓喜天(かんぎてん)が祀られている。このとき笠羽(かさば)二郎は高知足摺岬(あしずりみさき)にいた。
「 オン バザラ タラマ キリク ソワカ 」
三郎からの報告を了解した笠羽二郎は、金剛福寺(こんごうふくじ)にて本尊真言を唱えた。金剛福寺は遍路第三十八番札所、境内には亜熱帯植物が繁っている。沖縄那覇から京都間を直線で結ぶとき足摺岬はその線上にあった。
六号が南方より京都へと帰還する場合、東西に延びた中央構造線をどう飛び越えるかは一つの難関である。足摺岬は太平洋に突き出る足摺半島の先端の岬、二郎はすでに正午から岬の灯台付近に待機して六号の進路を観察していたのだ。




この聖護院六号が屋久島上空を通過しようかとする時刻に、ホテルをタクシーで出た比江島修治は安波茶橋へと向かっていた。
安波茶(あはちゃ)橋と石畳道は、1597年に尚寧王の命で浦添グスクから首里平良までの道を整備したときに造られたと考えられている。首里城と中頭・国頭方面を結ぶ宿道(幹線道路)として人々の往来でにぎわい、国王もこの道を通って普天間に参詣した。
橋は石造りのアーチ橋で、小湾川に架けられて南橋と、支流のアブチ川に架けられた北橋がある。深い谷の滝壷の側に巨石を積み上げる大変な難工事だった。南橋は沖縄戦で破壊され、北橋も崩壊していたが平成10年に北橋が修復された。橋の下流側には赤い血(椀)で水を汲んで国王に差し上げたと伝えられる赤血ガーがある。
「 あッ、あれは・・・・・!。えッ、清原香織!。そうだ、やはりあの香織ちゃんだ・・・・・! 」
安波茶交差点角でタクシーを降りた修治は、何気なく立体歩道橋の上を見上げた。歩道橋は交差点の四隅を立体高架して結んでいる。階段を下りながら修治の方へと近付こうとする三人の人影が見えた。その内の一人が京都にいるはずの清原香織なのだ。
階段の下で降りてくる香織を待ち構える修治は、ふふふと微笑みつつ、七色の日傘をくるりと開いた。












琉球の着物 2









