




































(七) 秋子の笛 上 Akikonofue
日本国には形跡や証拠の一切を消却したパフォーマンス道の理論書がある。
これは世界に誇る金字塔で、そこには楽譜のようなノーテーションやコレオグラフは挿入されていない。ただひたすらと日本の言葉だけを尽くし芸能の真髄を教え伝えた。したがってただの芸能論ではない。唯一未踏の神髄を本分とする。
観阿弥は、彼が到達した至芸の極致から人間の「品格」や「本位」をこれに述べた。
「 それが・・・・・、風姿花伝・・・・・ 」
篠笛の音を耳奥で拾いながら幽・キホーテにはこの巨匠の哲書が泛かんできた。
「 秘すれば花、秘せねば花なるべからずとなり 」
で、あるから、これは世界でも唯一、秘密重視主義の思想の頂点にたつ稀有な日本の家宝なのだ。
斎場御嶽(せいふぁうたき)から望む久高島(くだかじま)は、北東から南西方向にかけて細長く、最高地点でも17mと平坦な島である。
土質は島尻マージと呼ばれる赤土で保水力には乏しい。
島民は200名ほど、ここに河沼はなく水源は雨水と湧き水を貯める井泉(カー)に依存する。そして海岸には珊瑚礁で出来た礁湖(イノー)が広がっている。知念岬の東海上5.3kmにあるこの久高島は、周囲8kmの細長い島である。
琉球王国時代には、国王が聞得大君を伴ってこの島に渡り礼拝を行っていたが、後に斎場御嶽から久高島を遙拝する形に変わり、1673年(延宝元年)からは、国王代理の役人が遙拝を務めるようになった。
そうした久高島には琉球王朝に作られた神女組織「祝女(ノロ)」制度を継承し、12年に一度行われる秘祭イザイホーを頂点とした祭事を行うなど、女性を守護神とする母性原理の精神文化を伝えている。
「 秘すれば神、秘せねば神なるべからずとなり 」
異国の赤く枯れた大地から聞こえる篠笛を聞きながら、赤いマージを潤す井泉(カー)へと耳を澄ました。
久高島は海の彼方の異界ニライカナイとつながる聖地、穀物がニライカナイからもたらされた。琉球国由来記によると、島の東海岸にある伊敷(イシキ)浜に流れ着いた壷(瓢箪・ひょうたん)の中に五穀の種子が入っていた、五穀発祥の地とされる。


萩はその名に秋を抱く花である。
一乗寺駅へと向かうその途中にあるお宅には、道路にまでしだれ咲く宮城野萩がある。
そろそろ紫の花がつき始める季節であることが懐かしく想い泛かんでいた。
「 小さな蝶の花飾り・・・野辺行きしかば萩の摺れるぞ・・・・・か 」
もう夏のものとは思わないそんな気配に、ふと気づかされる朝が日本にはあった。
それは身を潜めていた秋が急に姿をみせたような快い空気を感じるときである。九月中旬、このころ日本では朱夏(しゅか)を過ぎて、秋は色なき風の白い装いとなるのだ。
「 萩ィは、秋の仕草しはる花なんやわ・・・・・ 」
これが日本の季語でいう「 けさの秋 」である。
そうした日本の仕草を養母阿部和歌子は秋子にせっせと教えてくれていた。
その秋子は第二十六代陰陽寮博士を受け継がねばならないのだ。
「 京都ォの夏もかなわへん。けど、秋ィ、こない暑うあらへん・・・・・ 」
朝の天気予報で、予想最高気温38度、と聞いただけで阿部秋子はめまいがした。
アメリカ暮らしが早三年目となる秋子の瞳には、京都の在所から一乗寺駅への途中にあるお宅の、道路にまでしだれている萩に、そろそろ紫の花がつき始める季節であることが懐かしく想い泛んでいた。
秋子の暮らすニューイングランド地方にも日本と同じような四季があるのだが、しかし夏の湿気が払われて、透き通って寂びていく景色という京都の風情などはない。そんな風に京都を懐かしむ秋子は、初めて訪れた日のアメリカを思い起こした。


「 ながめみる海に、初夏の朝陽を浴びて一隻の帆船がある・・・・・ 」
メイフラワー号ともいうが、別称はポリティカル「political」である。しかし、そう名付けられてみると、また裏返された名に因む帆船となる。この名から連想される「political correctness」とは、世の中にある差別や偏見に基づく言語表現でマイノリティ(少数派、少数民族)に不快感を与えるような表現を制限しようとする、文字どおり「政治的な訂正」ポリティカル・コレクトネスのことである。もっと簡単に言えば、差別用語を、あるいはそれどころか、ピルグリムと呼ばれるこの聖者たちは、プリマスに上陸すると、すぐにさまざまな暴力をふるいはじめるのだ。
どちら側の意識からこの帆船の名が生まれたかは、もはや明白なのであった。
ここは北アメリカにおけるイギリス植民地の魁(さきがけ)の地である。その最盛期には現在のマサチューセッツ州南東部の大半を領有していた。このことを祖父阿部富造は憂いながら他界したのだ。プリマスの太陽は、向日葵(ひまわり)の咲き誇る花畑を越えて、秋子に向かってくるかのように見えた。そして時計の針は奇しくも広島の上空に原爆が炸裂したときと同一の時刻を指している。




「 あれは、あのときは、八時十五分・・・・・ 」
日本人に深く刻まれた黒い時刻である。秋子が身構えてあらかじめそう意識して時計の針をセットしたわけではない。ふと腕時計をみると長針が右90度に振れていた。偶然であろうか。しかし秋子には熔けて壊れた赤黒い柱時計がこの角度を指して死んでいた記憶が鮮明にある。祖父の戦友である古閑貞次郎が最期までその写真を握り締めていたという。
おそらくこの時刻に、、限定された特別の感情を抱くのは世界広しとはいえ唯一核を食べた日本人だけだ。
「 うち・・・・・、やっぱ日本人なんや・・・・・! 」
幼少期を旧陸軍の祖父阿部富造に構われて育ったせいか、黙祷と対にしたくなる時間として、どうしてもこの時間帯は特別なモノとして感情を意識させられる。しかしこの時間を瞬時思い出して、それで日本人であることを意識するとは、愚かなことである。
じつに愚かだがしかし、やはりその秋子は日本人なのだ。富造はこの警鐘を鳴らしつゞけた。
「 ほんに、人間いうんは、しょうないなぁ~・・・進化やいうて血を散らさはる・・・・・ 」
ピルグリムの上陸を忍ぶ象徴の一つがプリマス・ロックである。それはプリマスの上陸地点近くにあった花崗閃緑岩の大きな岩の露出部であった。プリマスは1620年にできた村として記念石にその年号が刻まれている。しかし、この岩が上陸地点にあったということに言及している当時の証言は無いのだともいう。つまりでっち上げられたモノとする意見がある。





「 遺されて眼に触れる勝者の記録とは、大半がそうなんやわ・・・・・ 」
実際そこは、ピルグリムが上陸地点に選んだのは岩場ではなく、清水を確保し魚が取れた小川だった。しかも石に刻む「1620」の年号に見当たる日本史の、その回想に秋子は良き思い出として伝わる記憶はない。
そして西洋に拓かれた道とはおぞましくある。おのずと、その一つが元和大殉教(げんなのだいじゅんきょう)が重なってくる。
元和の大殉教とは、江戸時代初期の元和8年8月5日(1622年9月10日)、長崎の西坂でカトリックのキリスト教徒55名が火刑と斬首によって処刑された事件である。日本のキリシタン迫害の歴史の中でも最も多くの信徒が同時に処刑された。
「 あの事件後、幕府による弾圧はさらに強化されていく・・・・・ 」
また、オランダ商館員やイエズス会宣教師によって詳細が海外に伝えられたため、26聖人の殉教と並んで日本の歴史の中で最もよく知られた殉教事件の一つとなっている。そのような感情が加わると、秋子はじんわりと、比叡山を駆け下って朝廷に押し迫る荒法師らがあらがう気勢の声を想い泛かべた。それは西洋に翻弄された流血へのあがらいである。
京都山端に育つと、自然とあらがう者の声に耳を傾けようとしたくなるのだ。
「 せやけど・・・・・、こゝはアメリカやないか!。アメリカ人はそっぽ向いとる・・・・・! 」
そう思うと、自身の日本人がする滑稽(こっけい)に秋子はひとり笑えた。
大群の向日葵はいかにも咲き誇るかに見える。太陽は向日葵の咲き誇る花畑を越えて、やはり秋子に向かってきた。そして淡い桃色のトレイリング・アービュータスの花(赤毛のアン)、これは、この地に春を告げる花だ。かつて、春のはじめになるとボストンの街の通りなどで花売りが「 プリマス・メイフラワーはいかが! 」と呼びながら、この花を売り歩いたものであるという。先月までの朝の窓辺には、やはりそうした名残り通り、日本にはない春の朝顔の淡い桃色の花が開いていた。
そんな故国とは違う彩りにはやはり馴染めないものだ。
「 何や知らん早いもんやなぁ~。後、もう少しやわ・・・・・ 」
回想に浸ると、グローブ紙(The Boston Globe)で知らされたニューイングランドはすでに夏休みなのだ。
日本の蒸し暑い梅雨の中を抜け出してきたせいか、初夏のボストンは仄ゝと優しく爽やかな感じがした。ボストンへはユナイテッド航空ORD経由で向かった。所要18時間である。
ボストン・ローガン国際空港のバゲージクレームへと向かう階段を下りながら、秋子は迷いのないことを自身の胸に問いかけていた。習慣のように繰り返される毎日が嫌であるから一度、母語の外に出て自身のことを見つめ直してみる機会にと選んだアメリカ留学であった。何よりも養母阿部和歌子が望んでいたこともある。
「 陰陽寮博士を継承する阿部家にはすでに男性が絶えた。第二十五代阿部富造も四年前に他界したのだ。そこで次代を直系として引き受ける若者といえば、やはり私しかいないのか・・・・・ 」
アムトラックを降りると、なるほど、サウス・ステーションは美しい駅であった。
そしてボストン郊外の夕陽の中で・・・秋子は一編の詩を想い泛かべていた。
After a hundred years Nobody knows the place,-
Agony that enacted there, Motionless as peace.
Weeds triumphant ranged, Strangers strolled and spelled-
At the lone orthography Of the elder dead.
Winds of summer fields Recollect the way,-
Instinct picking up the key Dropped by memory.
異邦人ストレンジャーの留学生は「 100年後には この場所を知る者は誰ひとりいない。こゝで体験された大きな苦悩も もはや平和のように安らかだ。千草が庭でわがもの顔にはびこり 見知らぬ人々が散歩にきて。もう遠い遠い死者の面おもての・・・・・さびしい墓碑の綴字を判読する。たゞ夏の野を通り過ぎる風だけが・・・・・この道を回想してくれるだけだ。記憶の落としていった鍵を・・・・・本能が拾い上げてくれるかのように・・・・・ 」と、これを訳した。
After a hundred years Nobody knows the place,-- Agony that enacted there, Motionless as peace. Weeds triumphant ranged, Strangers strolled and spelled At the lone orthography Of the elder dead. Winds of summer fields Recollect the way,-- Instinct picking up the key Dropped by memory.
100年後に、この場所を知る者は誰もいない。ここで体験した大きな苦悩も、平和のように静かだ。百年あとには、この場所を知る人は誰もいない。
ここで演じられた大きな苦悩も、平和のように静かだ
雑草がわがもの顔にはびこり 見知らぬ人々が散歩にきて
もう遠い死者の・・・・・さびしい墓碑の綴字を判読する
夏の野を通り過ぎる風だけが・・・・・この道を回想する
記憶の落としていった鍵を・・・本能が拾い上げて・・・

「 星の数ほどあるHP(ホームページ)の中からこのアドレスにたどり着いて下さった偶然に感謝している。あなたは記憶の鍵を拾った 」
と、秋子は日本にいて北米に建てられたデジタルの家を一度訪ねて挨拶されたことがある。ロッキー山脈に暮らす人の住居を探し訪ねる旅の途中、偶然、眼の前に現れて、ついドアをノックしてみた。
このドアが開いたのは秋子が篠笛で、夷則(いそく)A♭の六律(りくりつ)九音を吹いたときだ。
「 1日に一つのありがとう・・・・・わたしは( Gershwin・賀修院 )・・・・・ 」
そう最期に挨拶されて、その家を後にした。後ろ髪を曳く聲(こえ)であった。
さる一葉の古い絵葉書が、今、乙女の手のひらにある。
大正13年に日本の京都で投函された絵葉書だが、どういう訳か長い年月を経て平成元年の秋に、アメリカ中西部の宛先へと配達されていた。65年間、どうして迷子になったのか、なぜ半世紀以上も過ぎて再び届けられたのかは定かでない。
さらに不可思議なことは、この絵葉書だけを同封したAir mailが、アメリカの配達先から平成7年に、再び京都の送り宛てへと投函されたことだ。しかも何よりそれが平成8年に、栞(しおり)のように挿(さ)されて一冊の古本の中から発見されたことである。その経緯は謎めいていた。
「 From the hometown of Joe・・・(ジョーの故郷から)・・・・・ 」
と、たゞ書き添えられている。送り主が匿名(とくめい)であるために、源氏物語絵巻が描かれてセピア色に日焼けしたこの謎に満ちた絵葉書を、阿部秋子は5年もの間、人知れずたゞじっと握りしめてきた。
「 たしか、これは、橋姫(はしひめ)・・・・・しかも隆能(たかよし)の写しや・・・・・! 」
何度か京都博物館に足を運んだから間違いない。この数奇な運命にある一葉の絵葉書を手に、留学生になった秋子が宛先の地を一度訪ねてみることにしたのは2001年10月のことであった。
その古本とは、五条坂にある「冬霞」という古書院で買い求めた「椿説弓張月(ちんせつゆみはりづき)」である。
「 橋姫は、宇治十帖(うじじゅうじょう)の一・・・。そして夢の浮橋で了(おわ)る・・・・・ 」
宇治十帖は源氏物語の最末尾にあたる第三部のうち、後半の橋姫から夢浮橋までの十帖をいう。予定では、30分後にスプリングフィールド駅へと向かうことになっていた。
「 Aki(あき)-Sun(さん). ひどい雨ね・・・・・ 」
窓ガラスに叩きつけている遣らずの雨を、秋子が恨みがましく眺めているとミセス・リーンは、あっさりと笑いながらそう言うと煎れたてのコーヒーに目を細くした。
名の後につけてくれる(太陽)は、リーンの嬉しい常套句なのである。新しい日本語を見つけたなどと、本人はそう思ってはいないのだろうが、日本人の秋子にはそう聞こえる。
「 何やいつも、雨の日も、曇り日でも太陽と一緒やわ・・・・・ 」
寄宿舎をしばらく留守にするからと思い、スプリングフィールド駅へと向かう前に、大学内のポストセンターに立ち寄ると、郵便物の有無を確かめているわずかな間に、先ほどまでの穏やかな秋空が驚くほど早く消えて雨になっていた。
「 今の天気が気に入らなければ、数分間待て、という諺(ことわざ)がこの地方にはあるわ 」
などとよく会話に挿まれる、ニューイングランド地方は天気と温度の変わりやすい所である。あるいは「 今の天気が気に入らなければ、数分間待て 」という諺(ことわざ)もあるくらいで、真夏でも朝夕が冷え込むこともあるので、長袖のものを必要とすることがあるし、この地方では9月にはすでに紅葉がはじまるのだ。
そんなアマースト南部の穏やかな紅葉の中を抜け出して来たせいか、シカゴの10月は強烈な太陽の中で身も焼かれるような感じがした。この地方特有のインディアンサマーである。
常に具体的なプランを提案しないと納得しないのがアメリカ人なのだ。交渉ごとの成果を求められるとき悠長に「がんばります」では通じない国なのである。何事も明確にした意思表示が求められる。そんなことを秋子はこの留学三年間で痛いほど体験してきた。

「 カリフォルニア・ゼファー号の右窓の座席が指定できますか? 」
デンバー・ユニオン駅の改札でそう言って駅員にまず頬笑みを見せた。
コミュニケーションの不通は笑顔がそこを融通してくれる。とても日本では過剰で見せられぬが、しかし北米では有効で適時に効能を発揮する笑顔の作り方や使い方を教えられ、語学とはまず笑顔から、だが曖昧な笑みはマイナス、とこれが語学を得意とはしない秋子の工夫した持論でもある。
「 Oh you are lucky. There is only one vacant seat. 」
おゝ、じつに幸運だ。一個の空席しかありません。
「 Ah how wonderful it is! It is power to be born from your smile. Thank you. 」
あゝ、それは何と素晴らしいこと。きっとあなたの微笑がそうさせてくれたのね。 ありがとう。
こうした英語の波乗りの楽しさとユーモアへの反射神経がいつしか身に付いた。
「 It is asaving grace of God. 」
それは神のご加護ですよ。と、これなどは定形の常套句、ご加護などなくても汎用する。
空席が一つ、あなたは幸運、とは日常茶飯事に存在するし、この国にいれば人は常に幸運なのである。
「 Yes, of course. 」
と、秋子は改札員へ頬笑みを返した。
笑みは眼に明らかな最高の言語である。曖昧(あいまい)な真実より、明確な虚実が高得点となる。
そんな三分間のミュージカルもミセス・リーンから舞台稽古のように何度となく習った。その舞台上では日本人は消えていた。そしてこのエクソフォ二―の旅は、母語の外に出た秋子が初めて乗車するアメリカ大陸横断鉄道を使っての一人旅であった。
椿説弓張月は琉球王朝開闢の秘史を描く。秋子はそれを握り締めていた。
「 California Zephyr 」
カリフォルニア・ゼファー号の旅だ。改札で何号車に乗るのかを問われた秋子は、番車を告げて、その行き先を書いた紙をもらう。この紙は荷物棚の下、自分の頭の上に挟む場所があり、おのずと車掌が目配り一つで乗客の行き先を確認できるようになっている。こうして業務上の煩わしい会話が省かれる。百のお喋りは一つの頬笑みで精算できるのであった。
「 この国では言葉数は不経済、表情の質量が経済なのだ。このことを江戸幕府は迂闊にも見落とした 」
そしてデンバーのユニオン駅からそのアムトラックに秋子は乗車した。
カリフォルニア・ゼファー号はロッキー山脈を越えて、宛先のユタ州ソルトレイクシティへと向かった。
すると真っ青な空の下に、赤い塩の砂漠が広がっていた。
視界を飛び出して、たゞ延ゝとある。その永遠らしき果てしない連なりを肉眼に描写してみると、大自然の喜怒哀楽というものが天地の奥深いところから語りかけてきて、秋子の本能とつながるかのようである。
この「 Arches National Park 」に阿部秋子は訪れた。
人間の眼にそう感じさせ、心にそう思わせるアーチーズの荒外(こうがい)な塩岩の赤ゝたる峡谷は、じつに赤裸々として地の浸食のありようを具体にみせつけていた。秋子は「 Arches National Park 」にそんな印象を強く抱いた。夕陽の中でみつめていると、今にもうごめき出しかねない巨大な磐紆(ばんう)の赤岩が、途方もない時間の中に身をゆだねながら生きつゞけていることが分かるのだ。
赤い潮騒がある。数千もあるという妖怪な赤い岩の輪は、その一つひとつが、秋子の眼の中でたしかな聲(こえ)をして動いていた。もはや公園では陋(せま)く、日本の天地創造を百万倍ほどにした広大なまほろば・・・・なのだ。
異邦人(やまとびと)の眼にはそうみえるのである。デリケート・アーチをくゞり映る紫陽なラ・サール山脈の雪渓を眼に入れてたゝずむと、秋子は記憶の奥底から目醒めるように、泛き上がる回想を早めぐりさせては、何度も何度もうなずき返した。
そこが異国であれ、古地層の突出には人間の原点が蘇るようであった。どうしても懐かしくなる。かつてはアナサジと呼ばれる先住民族の祖先が住まいとしていたエリアなのだ。あえかな煙が湧き立っていた。
さらに2億7千万年位前の地層が現われた奇形のモニュメントバレー、この赤褐色ビュートの深遠な大地はナバホ族の聖地なのだ。

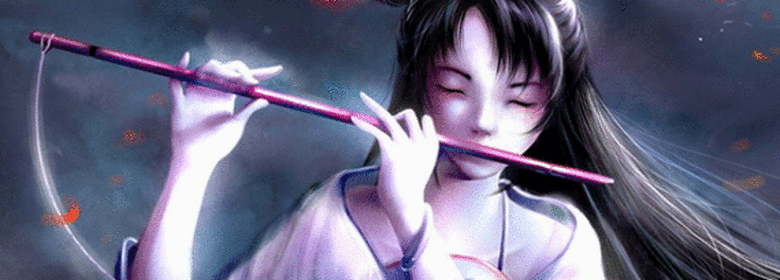
「 あゝ、そうや、こゝや。ほんにこゝやわ!・・・・・ 」
と、秋子は眼頭を熱くした。そんな秋子が、このダブル・アーチを訪れたいと思った動機は、映画「インディージョーンズ最後の聖戦」でスピルバークが切り撮るビギニングの一シーンの追憶に集約されていた。
少年時代のインディーを描写してバックドロップされた或(あ)の巨大な赤いドーナツ型の奇岩トンネルに秋子が魅了されたのは、今から13年前の12歳京都市立修学院第二小学校に通う6年生のときであった。
「 薫君(かおるのきみ)は、小野の里にいるのが、浮舟であることを聞き、涙にくれる。そして僧都にそこへの案内を頼んだ。僧都は、今は出家の身である浮舟の立場を思い、佛罰を恐れて受け入れなかったが、薫君が道心(どうしん)厚い人柄であることを思い、浮舟に消息を書いた。薫君は浮舟の弟の小君(こぎみ)に、自分の文(ふみ)も添えて持って行かせた。浮舟は、なつかしい弟の姿を覗き見て、肉親の情をかきたてられ母を思うが、心強く、会おうともせず、薫君の文も受け取らなかった。小君は姉の非情を恨みながら、仕方なく京へ帰って行った。薫君はかつての自分と同じように、誰かが浮舟をあそこへかくまっているのではないかとも、疑うのだったとか。・・・・・法(のり)の師とたづぬる道をしるべにして 思はぬ山に踏み惑うかな 」
と、宇治十帖の夢の浮橋が、赤く赤く泛かんでくる。幽(かそけ)くその赤い橋の欄干で橋姫が泪ながらに泣いていた。そんなダブル・アーチの前に秋子はひとり陣取ると、ひたすらと篠笛を吹いた。笛の音は、何度も何度もダブル・アーチをくぐり抜けては大空へと舞い昇る。秋子はこのとき赤い大地に重ねるようにして比叡山を泛かべていた。
黄色いピーターパンに乗るとボストンからアマーストまで3時間ほどかゝる。秋子がそのボストンより真西へ約150㎞のところにある小さくて上品な田舎町にやって来て、早3年が過ぎた。初秋は「Holyoke Range」の紅葉にくるりと囲まれて、タウン・オブ・5カレッジスとも呼ばれるこの大学の町は、アパラチア山脈の中程に緑のスープ皿をそっと置いたような盆地にある。美しい草花に囲まれたアマーストタウンと、木々からは小鳥たちの可愛らしいさえずりが聞こえる長閑なキャンパスとが、その盆地皿に並ゝとそゝがれた緑色のスープの豊かさのごとく、ニューイングランドの美しい往時の風景を偲ばせるゆるやかな起伏の丘に広がっていた。秋子にはこうした秋の季節が最もこの町に似つかわしく感じさせるのだが、しかし冬は膝もとまで雪のある極寒の町へと一変させる。
この冬の雪景色もじつに美しいのだが、人口の8割を学生で占めるこの町の学業期には5万の人口があるものゝ、冬季にはその数を1万7千までに減らすのであった。そうなると秋子は、この人影もまばらに震撼とさせる雪里の寮暮らしが恐ろしいほど退屈で、しかも異国人であることを噛みしめる日々の連なりに人恋しさを募らせることが、とても苦痛であった。
そんな秋子は「 Boltwood Avenue, Amherst, MA 01002-5000 U.S.A. 」のジョンソンチャペルの隣にある赤レンガの寮舎に留学生として暮らしている。
「 あんたも、そろそろ外したらんと、あかんのやさかいになぁ・・・・・ 」
9月の窓辺に吊るし残した風鈴が、深まる秋空に涼しい音色を淋しげに奏でていた。
このビードロの琥珀の風鈴は、京都に暮らす養母和歌子からの拝受品である。そうであるから夏を過ぎ越してもついつい仕舞忘れてしまうのであるが、後一年で卒業という今秋も、昨秋と同じで京都に吊るされたころと少しも変わらずに、はんなりとさせる音色を広ゝとした寮舎の庭に響かせていた。

昨夜「Aword is dead When it is said. Some say. I say it just Begins to live.」という一編の詩を寝付かれぬまゝに想い泛べては、口籠らせてみたくなるほどの長い夜を味わっている。
訳すれば「 言葉は口にされたら死んでしまうと言う人がある。私は言おう。正にその日言葉は生き始めるのだと 」とでもなろうか。南北戦争を経た、この女性の聲(こえ)が秋子の胸ぐらに痛く沁しみいるのであった。それは19世紀の前半にこの町に生まれたエミリー・ディッキンソンの、人の眼では仕訳られぬほど深層の底にでもありそうな重く深い詩である。
ボストン市内のアマーストコモンからMain St.を右に曲がった木々の中に、彼女の生家が「The Dickinson Homestead」として遺されている。昨日、この生家の前を通り過ぎよとして秋子はふと足を止めさせられた。
以前に三度見学に訪れているが、初めて訪れた折に見初みそめた、彼女が16歳の若かりし写真の、その昧ゝ(まいまい)とした撮られようを、そのときふと思い起こしたのである。まだ若いのにひっつめ髪の地味な面(おもて)に影をさし、真っ黒なドレスを着ていて、質素でひかえめな生活を滲(にじ)ませた彼女らしさがよく窺えるその写真は、彼女の生涯唯一の一枚なのであるが、この死相を纏(まと)うかのような写真と先の詩とが折り重なり合って醸しだそうとする、まったく難解なメッセージに秋子は酷ひどく心を揺さぶられた。
閉じられようとして、閉じ込められまいとする雁(かり)の聲が目の前にある。ほとんど家の外には出ることがなかったという彼女の詩は現在、1番から1775番までの番号をつけられて遺されている。そのエミリーの詩は、彼女の死から4年後の1890年に妹のラビニアによって初めて詩集が出版された。正に、その日々の言葉が秋子の心の中で生きながら動き始めている。
すると、どことなく自分らしくない。どことなくそぐわないものがある。朝陽の窓ガラスの中に映る自分の顔をみて、その外れようが気になる秋子は、かすかに眉をよせて窓辺の椅子に背もたれていた。 詩は、そのようにさせる予言とも思えた。
百年あとには・・・・・・この場所を知る人は誰もいない こゝで演じられた大きな苦悩も・・・・・平和のように静かだ。雑草がわがもの顔にはびこり、見知らぬ人々が散歩にきて、もう遠い死者の・・・・・さびしい墓碑の綴字を判読する。夏の野を通り過ぎる風だけが、この道を回想する。記憶の落としていった鍵を、本能が拾い上げて・・・・・。 「 Motionless as peace. 」という予言を、エミリーの未来を、ニューヨークの昨朝が詬恥(こうじ)したように感じられた。
この詩の詡(ほこら)かな聲も汚れさせられて、晩夏の季節の去りゆく暑さを惜しむエミリーの印象に、拾い上げてはもらえぬ記憶の鍵のことを、秋子は遠い眼をして探していた。しかしやはりエミリーが、密かに書き遺したように「 目をさまして 正直な手を叱った 宝石は消えていた 」ことになる。
「 どうかしたの。ぼんやりとして・・・・・」
と、そんな秋子に背後からふと声がかけられた。振り向かずとも、それが誰かは声と時間帯とであきらかである。
しかるべき声はミセス・リーンそのものであるのだから、秋子はいさぎよく振り向かねばならなかった。彼女はいつも三日置きの朝8時には、決まって花瓶の花を挿し替えにきてくれるのである。
「 Good morning. 」
秋子はいつも通り友情のしるしのようにそういって振り返るとミセス・リーンもいつもの彼女らしく頬笑みを泛べて立っていた。しかし、いつもより秋子の語尾がゆっくりとのびた。その分ミセス・リーンはそれを推し量ろうとして、じっと寝不足で瞳のむくむ秋子の顔をみつめた。しかしその瞳はいつもの太陽のような輝きであった。
「 Homesickness ? Yesterday's terrorism ? 」
ホームシック?、それとも昨日のテロ事件のこと?。
と、問われすっと笑いながら眼をそらされると、ミセス・リーンはあえて言葉にはしなかったが、少しも案じることはありませんよと語りかけるもが彼女の眼の底にはあった。そうして肩をポンとたゝかれてみると、それがいつ会っても心が通じ合っている確認のように思え、秋子の沈みこむほどの重みがふっと軽くなった。だから秋子はリーンに問いかけられて返そうとした、昨日の同時多発のテロ事件のことを、いゝさしてあえて止めることにした。友情には暗い言葉は不向きである。
「 It thought whether there was delicious breakfast that some eyes seemed to wake up. 」
何か目の醒めそうな美味しい朝食はないものかと考えていたのよ。
すると一瞬、むっと身を包んだその弾みからか裏腹に、思ってもいなかった言葉が口をついた。
しかし、いってしまった後で、それをさして意外とも感じない自分に、秋子は改めて驚いた。いつからそんな醒めたものが胸の底にひそんでいたのか、これと思い当たる節目もなく無意味なことなのだが、とりあえず底意のない明るさをミセス・リーンへ返そうとしたことだけは確かなことであった。
それは、決して、自分の中から振り払ってしまいたいような類の思いではない。却(かえ)ってそうであることが、自分で驚くほど爽やかなときめきにつながっている。このミセス・リーンという人とならと、あらゆる空想の中で、その場に臨んだとき、訪れてくると思える知的な華やぎをどこかで許してしまっているところがあった。



「 If you hope for it, there is very dangerous dessert called a bomb of Oregon. 」
それだったら、オレゴンの爆弾という物騒なデザートがあるわよ。
彼女にこう返されると、いつも秋子はテーブルに身をのり出して平らげてみたくなるのだが、この日もミセス・リーンはそうであった。
秋子が期待し予感したように、軽口のそれでいて機転を利かしたユーモアたっぷりの献立を秋子にすばやく直球で投げかけてきた。
「 If it is such a wonderful bomb, I want to eat. 」
そんな素晴らしい爆弾ならば、食べたいわ。
養母和歌子に似ているからか、そのリーンに薦められると何でも食べてみたくなるのだ。その素晴らしい爆弾も食べた。オレゴンの爆弾はエミリー・ディキンソンが食べたデザートであるという。しかしこれは一種のメルヘン。ほとんど引き篭もりの生涯を送ったエミリの部屋に、一匹の蒼いネズミが住みつき、彼女と心を通わせるという物語の中に登場するデザートであった。
この物語はミセス・リーンの創作である。秋子はその創作を読んで、まっさきにデリダの「引用」概念を思い出した。どんな言葉も聞き手の一人一人違うコンテクストの中に引き込まれて再生されるのだから、言葉はそのつど新しい意味を担って創造されるというのがデリダの「引用」である。そこにはエミリー・ディッキンソンの詩も効果的に引用された。
秋子はリーンの創作に「引用」されているディキンソンの詩をいくつも知っていたが、エミリーと蒼いネズミの交歓の物語の中に置かれたそれぞれの詩は、秋子の知らなかった新しい輝きを帯びていた。ディキンソンの詩はとても短い。だから、四季折々の心の中で変化されて引用されるたびに、言葉のデザートは新たな相貌を見せてくれた。

オレゴンの爆弾は、淋しいクリスマス迎えるエミリーを楽しく過ごさせて上げたいと考えた蒼いネズミがプレゼントする爆弾デザートである。そしてミセス・リーンは「 悲しいときに食べるデザート 」という。たしかに食べると不思議に悲しさが爆発して消えた。秋子はそのデザートのお返しとして、いつも篠笛を吹いた。その笛の音は「 比叡の名乗り 」という旋律で、京都比叡山へと分け入るときに儀礼として告げる阿部家伝承の笛の音であった。
翌日の夕食後に薦めてくれたミセス・リーンのユーモアたっぷりの献立も刺激的で素晴らしいデザートなのであった。それは新作のヒロインと言ってよい。デザートは秋子の淋しさを翻弄して憂鬱は宵闇へと消えた。それはまったくユーモラスな考古学者で、エミリーの助手を務めていたスーツ姿の似合う知的美女だが、蒼ネズミの仲間達がひしめく下水道に躊躇なく入るなど、肝が据わっている。しかしミセス・リーンが、ただ無償の愛を注ぐはずもない。
新作を閉じ終えると、いつしか彼女は密かな楽しみを蓄えたかのように微笑むと、おもむろに窓側へと移動した。
そして秋子はそのミセス・リーンの後影にでも語りかけるように篠笛を吹いた。
そんなミセス・リーンの助言からこの旅は始まった。

「 It is the one that it visits New York and it doesn't visit ";Statue of Liberty"; that Arches National Park in Utah state is visited and doesn't see ";Delicacyarch";. 」
ユタ州のアーチズ国立公園を訪れて「デリケート・アーチ」を見ないのは、ニューヨークを訪れて「自由の女神」を見学しないようなものですからね。と、新しい旅に誘われて、二週間ほど前にフィールドトリップしたユタ州の風景を、そして篠笛を奏でながら広大な赤い大地から得た交感を秋子は忘れないでいる。
そこで野生のバファローにネイティブアメリカンによる不思議なスピリチャル体験をした。秋子は初めてアマースト、ワシントン、NYCとはまったく違う雰囲気の、アメリカのDiversity(多様性)を実感した。
留学後三年目にしてようやく果たせたという感慨もあるのだが、アマースト大学の緑の芝生に囲まれたニューポート・ドームの窓辺からは、そんなユタ州のアメリカンサイズに魅せられた瞬間の空気が「いま、こゝ」に直結され、ありありと秋子の目の前にあらわれていた。 豊かさと交換するように人と自然との絆は細くなるばかりではないか。すでに日本にはないが、しかし、異国には未だ神の手で天然の原型が遺されている。これは敬けんで穏やかな人々が培ってきた風土でもある。アーチズの赤いその遥かさは、秋子に人としてのありようを深く問いかけてきた。そして問い掛けをそっくりマッカーサーに突き返してみた。省みることの豊かさを知らされたそんな秋子は「アメリカも捨てたもんやおへん」と、寝室の壁に向かってつぶやいた。朝になると空や草花をみてつぶやいた。
「 それって、無作法な授業形態にようやく慣れてきたせいもあるんじゃないの・・・・? 」
と、ふいに背後から声をかけられて秋子が振り向くと天野伸一が笑顔で立っていた。
彼はハーバード大学から、どうして引っ越してきたのかも解らない未だ不可解ではあるが有能な新参者であるから、鵜呑みにできることと、鵜呑みにはできぬことがある。その手には迂闊には乗れないとなると、いや、慣れたというおざなりの言葉使いでは、アメリカの学生に対して失礼なことで、正しくは三年目にしてようやく、少しだけ理解できるようになってきた。
授業がはじまり辺りを見わたすと、部屋のなかで帽子をかぶったまゝの学生、お菓子を食べている学生、机の上に足を乗せている学生、ローラーブレードを履いたまゝ座っている学生、日本の大学ではとても考えられないような状態である。また、教授の名前をファーストネームで呼ぶ学生さえ多くみられた。
入学当時の秋子は「アメリカの学生は、なんて失礼で行儀が悪いんだ。これだから日本人は翻弄させられるのだ! 」と強く感じていた。
明日は「 Martin Luther King, Jr. Day 」である。
マーチンルーサーキング・ジュニアの生誕したこの1月15日は、アメリカの祝日とされている。それはマサチューセッツ州でも同様であった。講堂は五百人をこえる学生達で満席となっていた。
悠々閑々と生きている、それがハロルド・モロー先生の平生であるらしい。黒いビーバーのファーフェルト帽をかぶられて、平生は思慮深く粛然とした風姿を崩さないで、先生はしばしばくったくもない一面を覗かせてくれたのである。
講義の日、あのときも普段と同じように、ご自慢の黒スネークのステッキを軽く左右にゆらしながら粛然とした足どりで教壇へと上がられた。しかし教壇に立たれ、いつものやさしい視線を受講生へと向けられたとき、一堂ゆれるようにどよめいたのだ。












Monument Valley Sunrise to Moonrise









