




































(六) 八瀬の五郎 下 Yasenogorou
安倍晋三、パククネ、習近平。日本、韓国、中国の、トップが入れ変わった。しかも北朝鮮が魁斗に牽引する。四国の、この変平であるようで妙に普遍を誘わない不安な躍動とは一体何か。こうした極東のざわめきに世界が聞き耳を立てた。特にオバマの耳は黒いオオカミのごとくピンと直立する。それが今日のボケきった日本人に、お得意のメイドイン・アメリカで深々とした鉄槌を打ち下ろしてくるようだ。あのときアメリカは日本人にさえ理解しがたい農事思想を丹念に解読し分解してみせたではないか。
アメリカ国家の私的哲学を伴うコンピュータが、戦後われわれ日本人の脳や心のはたらきに、どこまで食い下がれるかという問題は、1950年代にまだ日本の限られた工学インテリーを自負する人々が熱中し始めた当時から、比江島修治もそれなりに密かで先駆的な議論を内心で耕してきた。しかし今日まで修治はまだその技術が人の生体で「生きているシステム」というものを一度も覗いて確認したことがないのだ。そこに積年の疑問がある。
「 これは、それぞれが、犬狼になろうとする動きなのか。農耕的な偏平と沈着が遊牧的に溶融され、ゆるやかなこの変平感の背景に大陸の遠吠えが聞こえてくる。ここにきてまた、われわれ日本社会にも潜在する遊牧的な革新性や戦闘性を根底で疼かせてきた。そしてこの間隙にあってアメリカの遠吠えが聞こえてくる。戦後、日本オオカミは絶滅したはずだが・・・・・ 」
昨年末、比江島修治は除夜の鐘にそんな夢をみた。そのことを幽・キホーテは思い出した。雨田博士の動きが、当時の修治の気分にぴったりだったからだ。近年になって日本のトップが頻繁に入れ替わる世相に、修治の耳は何度かにわたるシャッター音を聞いた。結局、それが三国にまでなり昨年の掉尾を飾ることになった。そして国民はしだいに四方に感化されている。
「 アメリカを含む、五国には歴史にこびりついた故実病がある・・・・・! 」
まさか軍靴の音が鳴り響きはじめることはないだろうが、そう危うさを思って幽・キホーテはまた博士と香織のバス停へと眼差した。





四明ヶ嶽(しめいがだけ)の朝焼けは鈍(ドン)として暗い雲が流れる。
雨田博士は、老人の思い通りにならないのが若者の行動であり言動であるのであれば、それを自分の崩れ去る心の張りにしたかった。
「 茄子(なすび)の腹鼓(はらつづみ)はいつもの毒中(どくあた)り無しの柏手なのですから、特段、気にもなりませんよ! 」
ナスと一緒に煮込めば毒キノコで中毒は起きないという迷信がある。
五郎は意外そうな顔をして、そういう虎哉を呆(ほ~)っとみた。
しばらく黙っていたあとで虎哉は平静な声でいった。
「 竹原さんこそ、こんな朝早くに、どこかご商売にでも?・・・・・ 」
「 へぇ、それが・・・・・ 」
五郎が応え返そうとする、その脇で香織は、五郎が手に固くにぎる赤いリボンのついた大きな手提げ袋の中身に気がそゝられていた。指でおさえては、ピンと弾いて物音の何かを確かめている。
その紙袋のリボンは虎哉の眼にもたしかに、赤い羽をピンと立て上品に色気をふりまいていた。
「 何するんや。そないにしたらあかんやないか。やめなはれ・・・・・ 」
「 隠さんかてえゝやんか。リボンついとるし、これ一体何やねん? 」
五郎に慣れっこの香織は、まるで仔犬が尾をふり甘えるような甲高さで袋の中身を問いつめた。
赤いリボンは誰かへの贈り物に違いない。そのリボンと、指の感触から中身のおおよそを察した香織はもうそれ以上は自分の口からいゝだすまいとしていた。良質の作曲家の内面にさかしらな理性の入りこむ必要はない。ときおり慧眼(けいがん)な作家の音楽を聴いていると老いた虎哉でさえ、どんな自分の姿も可能なような気がしてくる。この躍動性と同じように香織が傍にいると、ふんわりとしていつも現実が希薄になる。虎哉はむしろその内面の飛躍をうらやましく感じるのだ。
「 しゃないなぁ~。これか、これわやなぁ・・・・・ 」
五郎は白い息を一度はずませて応え返そうとしたが、どうやら虎哉の存在を意識してか何やら気恥ずかしそうに躊躇(ちゅうちょ)した。そんな気にさせているようであると、明らかにじれったく虎哉にもその初心(うぶ)さが判る。頬をサクラ色に染める露わな男の純情がそこにある。先ほど、無意識に力んで斜めに踏み出した右足をス~ッと揃え直すと、五郎は弱ったように小さくなって神妙となった。
「 なぁ~教えてェ~な。そない、もったいぶらんと、何していえへんのやろか 」
香織はことさら謎めかした笑みを泛かべ問いつめる。そのためか気恥かしさが滝のように五郎の顔面に滲み出ているのが虎哉にもわかった。みかねる虎哉はそれとなく眼を笑みて促してみた。
「 しゃ~ない娘やなぁ~。これ、毛布のシャレたやつや。ブランケットいうて、舶来の膝掛けや。この毛はキャメルいうそうや。駱駝(らくだ)の毛を織ったモノや・・・・・。ほしてな、これは琉球の紅型(びんがた)や・・・・・ 」
ようやく弾みをえた五郎はもう満面の笑みで中身を披露すると、二人をみて得意そうであった。やはり虎哉の眼くばせが助け船になったのか、五郎は笑ってチラリと虎哉をみた。

「 寒い日ィ続きよるし、これやしたら元気取り戻さはるんやないか、と、そない思うてな 」
「 誰が、元気取り戻さはるんや? 」
それまで瞼の上を桃色にうつむきがちに聞いていた香織であるが、フィっと虎哉の前を横切ると、その身を二人の間に割り入れるようにして五郎から眼を逸らさずに訊(き)き質(ただ)した。
「 そんな怒った顔せんかて、これ、決まっとろうが、君子はんのや 」
こう聞かされて五郎と真向うと、訊き質してみて、しかしどこか自分らしくない。
香織は何かそぐわないものを感じた。見慣れてしかるべく泛かぶ、その君子の眼がまじまじとこちらを見返しているようにもある。そう感じたとき、父のものを貰った黒目が勝った香織の透き通る丸い眼は、五郎の目線から、こころもち下がっていた。
「 わい、こないだ道具屋寄った難波の帰りにな、船場にいったんや。ほなら、着物きた店の人がやな、これがえゝ、これがえゝ、いゝよるんや。ラクダやし、フランス製やいゝよるし、ほれで、わい、買こうてしもた。それから大正区船町の洋子はんとこ寄ったんや。琉球衣装は帯がの~て楽や思うてな。そんなんでコレ、君子はんに、今朝届けとこ思て・・・・・。その後、わて、蓮華寺に用事あるさかいに・・・・・ 」
虎哉の前だから、もじもじと、なかなかいえそうになく困っているのが虎哉にはわかっていたが、五郎はさもうまそうに北風を大きく呑み込んでから、二人に語りはじめると、眼をしばたいて瞳を炯(ひか)らして、じつに嬉しそうに話した。
堰(せき)を切るとこの男は真っ直ぐに表現する。その眼の炯(ひか)り、初めて会ったときにも感じたと虎哉は思った。
虎哉の認識では、男にはおおむね2種類のポーズの意識というものがある。
一つは自身の才能や容姿をより向上させて見せたいというしごくあたりまえだが、どこか偽善的な意識であり、二つは自分を「まともには見せたくない」という、偽悪的であるのだからそうとうにひねくれているのだが、それでいてつねに影響力を計算しつづけているような、どこか悲しい自意識である。しかし竹原五郎の爽快な笑顔は、あきらかに両者のいずれにも属していないのだ。

「 えらい早口やったなぁ~。うちのォは、次、船場行きはったときでえゝわ 」
そう口をつく怪訝(けげん)な言葉も、頬から顎(あご)にかけての弛(ゆる)やかな丸い線がそれを救ってくれる香織なのだ。君子の笑顔に、一足控えようとする乙女心がそこにあった。
「 あゝ、買うてくるさかいにな。そんなもん嘘いうもんかいな。赤い紅型かて買うてくるさかいに・・・・・ 」
もう香織は微笑んでいた。若いということは、何をみても聞いても老いとは違う意味を感じさせるものだ。香織は五郎が話をする途中から、赤地に白いストライプをあしらった温かそうなブランケットをながめ返しながら「 いつか、うちの子ォ生まれたら、こんなんで巻いて抱きたいな 」などと連想をふくらかし、あこがれの中の、すでに赤ん坊ができたという確信が、勝手にあつらえたまゝごとの慶事に寄り添って、仄々とした喜びに浸っていたのだ。
無論、五郎を慕う心根もそこにあった。そのような香織は、ブランケットを膝の上にのせて児を包み、ためつすがめつ見つめ直しても、まだどこにも仕舞いこむことができなかったのかも知れない。そしてようやくブランケットをたゝみ始めた、その手がまたふと止まると、両瞼からぽろりと涙をこぼした。
「 急にうち、何やしらん、おかしいんやわ・・・・・ 」
そういゝながら香織は、自身でそんな自分の感情に驚いていた。
母親の顔も知らずに育った、その事情の端々から、五郎が香織に明確には答えてくれなかった内容を、漠然と感じとることはあった。自分でそれらを訊き質そうとしなかったせいもあるが、聞けば何かが壊れる恐れを抱き続けてきたようにも思える。父親を亡くしてからは一人生きようとすることが精一杯で、そんなことには一切眼が向かなかったような気もする。しかし気づかぬうちに、母恋しさに染まっていたのかも知れなかった。そんな香織の眼は、視界全部に立ちふさがると思えるブランケットや黄色い紅型に向けられていた。
「 香織ッ、どないかしたんか?。次ィ、きっと買うてくるさかいに堪忍や。ほんに、ほんに堪忍やで・・・・・ 」
「 そんなん、何も気にしはらんでもよろしがな。うち今、夢ェみて遊んでたんやさかいに・・・・・ 」
「 せやけど、香織・・・・・そない言うても・・・・・ 」
「 えろう~、すんまへん。早よォ行きはって、大事ィな君子はん、味あん善じょうみたげとくれやす 」
と、さも悲しい声でこうつけ加えた。はっと我に返った香織は思いなしか君子を見守る五郎の眼も以前とは変わってきたように感じられる。するとまた香織の眼には君子の笑顔が泛かんできた。



以前の五郎なら、君子の優雅な言葉遣いや、隙のない身じまい、行儀のよさに近づけぬ思いをしたに違いない。香織もそうであったから判るのだ。しかし最近の二人は何となく隔たりが無いように思われる。
「 そんなん嬢(いとう)はんにィ、えらい冷たいものいゝやないか。失礼や。わい変な気持やわ 」
五郎は、気づかぬ素振りで通りすぎたい型の男とは、あらゆる点で違っていた。
そう虎哉には感じられる。子を産めぬと若いうちに決まっていた女の、どれほど淋しい人生なのかは、かって子を産んだ女でもわからぬもの。まして男には、もちろん父親の虎哉にもわからぬものだ。
そんな君子が十年を重ね経てようやく、おのずから賤(いや)しい身の上だと自覚している五郎になぜか警戒を緩めて親しんでくれている。五郎にはそんな思いに重なる親しみの他は何もない。晦日(みそか)に庭の手入れでもと別荘に顔をだした折「 体のそこらじゅうが怠(だる)いし、冷えると痛いいうて膝頭さすってはったんや。正月の挨拶もまだしとらへんし 」と、だから今朝そんな君子に届けたい一心でやってきたのだ。 洛北の八瀬に虎哉が別荘を建ててから十年になる。当時から君子はこの八瀬の集落で暮らしてきた。虎哉は東京都内の音羽鼠坂の自宅と、京都八瀬の別荘とを相互に暮らし分けたニ重生活で、折よく別荘にいてもその大半は外出がちになる。したがって、考(もの)いうまでもなく五郎との付き合いは君子の方が長い。
虎哉の不在中、五郎は不自由な君子のために面倒見もよく香織や他の手に頼みづらい用件や、厄介な世話を幾度となくかけているという話は君子から聞いていた。その君子のためにと、凍える寒さの中を御所谷からわざわざ歩いてきた五郎の言葉は、虎哉にとっても誠実で温かみのあることであった。
「 一生涯、病人ともいえる不憫者の君子というものは、親の眼からして、いつまでも子供のようなもの。私がそう努めねばならぬように、私がしでかした過失である。嫁ぐこともできずに遠に五十路いそじを過ぎた女でも、いやむしろ、五十歳を過ぎ、まもなく六十歳にさしかかる女だからこそ、歳の差のさほど違わない、五郎のような逞(たくま)しい男性が身近にいて欲しいのであろう 」
そう思う虎哉は、そんな五郎の一途な温もりで、急にいたらぬ我が身のひきしまるのを覚えた。


「 せやッたわ。五郎はんの渾名(あだな)ァ、蛸薬師(たこやくし)いうんや。せやろ。死んだお父ちゃん、五郎は、蛸薬師ィやいうてはッたわ 」
さる寺の僧侶が病に苦しむ母のために、好物のタコを買ったのだが、仏門の身でそれは何事かと問われ、咄嗟にその僧侶が薬師如来を拝んだところ、タコが薬師経と変化(へんげ)して、以来、母の病も癒(いえ)たのだという。その蛸薬師のことか、当の五郎はたゞ笑っていた。
「 旦那はん。今日、雪ィになりまっせ。お山がそないな匂いさしてはる。ほな、気ィつけて・・・・・ 」
そういゝながら五郎は指先で、香織の額をチョンと押した。
「 五郎といゝ香織といゝ、この二人は、何と同じような体臭を私に聞かせる者たちか! 」
虎哉はたゞ不思議さに戸惑い、この隠せようもない確かなモノを、どう抑えようか、しかたなく苦笑して終わらせることしか手はないと思ったが、その間に五郎は別荘の方へ歩き、向かい風にも平然とゆく逞(たくま)しい後ろ姿となっていた。小さくなるその五郎の影に、虎哉は、「 私と君子との関係が硬化しそうなときに、この五郎が現れたのだが、もしあの時期に別の男が現れても、おそらくこうはならなかったであろう 」と思うと、どことなく安らかな余光を弾いて五郎の影は消えた。
それは親という他人の加わる余地のない純真な影であった。それだけに虎哉は、蛸薬師という渾名に、もし縁あれば君子もきっと癒されるのでは、と思うと妙にその影の余韻に惹かれた。
比叡の西谷に隠(こも)るように暮らし、山岳の情緒豊かな雰囲気を漂わす五郎に、東京の都会育ちの君子が好意を寄せている。五歳で儚くも夭逝した兄を話にしか知らずして他に兄弟もなく育った君子だから、五郎を兄と感じて慕うのか。何よりも患うその君子に蛸薬師の五郎が親しみを抱いてくれている。
君子の実感では間違いなくまだ戦後なのだ。
暗くて惨めで、しかし二人なら先に希望がないわけではない。虎哉は比叡山という霊山がもつ神秘さをそこに感じていた。
「 えゝもん贈らはるわ。ほんま、よう考えはったなぁ~。きっと君子はんのことや、喜ぶ姿ァ、五郎はんに見せてくれはる。五郎はんは、ほんに一途な男はんやして、なあァ、老先生・・・・・ 」
ほっとして肩を落とした香織は大人びてそういうと、深い二重のまぶたを心もち伏せ加減にした。このとき、朝陽の奥に白々と融けこんでいった五郎の影が、虎哉と香織の心を占領し、バス停に残された二人は、比叡の山の向こうから昇る陽の静けさの中に、たゞシーンと包まれていた。
香織は梅の季節に五郎とこの辺りを幾度か通った春を思い返している。
虎哉は、正常な感覚が麻痺まひした君子の車椅子を押し続けた日々を思った。
坊さん頭は丸太町 つるっとすべって竹屋町 水の流れは夷川(えびすがわ)
二条で買うた生薬を たゞでやるのは押小路 御池で出会うた姉三に 六銭もろうて蛸買うて
錦で落として四かられて 綾まったけど仏々と 高がしれとる松どうしたろう・・・・・。
香織が何気なくふと呟く京のわらべ唄が、ひとり北風に吹かれて揺れていた。















いつしか京の市井に根付いたこの唄は、もはや京都において「 梵天(ぼんてん)」のようなものであろう。唄が梵(そよぎ)と、古都という風流を多様な趣を湛えて感じさせてくれる。今や日本の都会でわらべ唄が紡がれる風情は京都しかない。何気なく聴かされる京言葉の抑揚には、古都に根付いた素顔の風が吹いてくる。香織の歌は虎哉に京の地層の深さをしみじみと感じさせた。



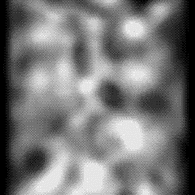
「 そうだ博士、それは地夭(ちよう)というものだ。六道の辻から噴いておる・・・・・ 」
このとき丸彦は博士の眼を見据えながら懐の大宝恵(おおぼえ)をギッと掴んだ。
「 博士の感じた、その地層とは地夭(ちよう)の趣きであり、京言葉一つにそよぎ顕れている。梵天とは仏語での色界の初禅天、大梵天・梵輔天・梵衆天からなる三天の淫欲を離れた清浄な天のこと、修験者が祈祷に用いる幣束(へいそく)も梵天。また大形の御幣の一つ、長い竹や棒の先に厚い和紙や白布をとりつけた神の依代(よりしろ)も梵天というのだ・・・・・ 」
阿部家の家業は専(もっぱ)らこれが本筋で、明治に陰陽寮が廃止されるまでは御所の御用達として天文学などを果(おお)せられていた。さらには浄瑠璃の終わりに祝言として梵天を語ったことから物事の終わり、ここから転じて追い出すことを暗示させる。
そして厄鬼払いが生まれたのだ。京のわらべ唄は地の利の裏に、梵天を皆くるんでそよぐのである。口ずさむと言霊(ことだま)でそよぎ、地を祓い、道を清める唄となる。
「 あッ、老先生ッこれ違うとるわ。今日、土曜日なんやして、あと十分待たんとあかんわ! 」
待ちくたびれた香織がバスの時刻表を確かめると、通常日の運行時間と、土、日曜の運行時間とは違うことに気づいたのだ。
「 えらいもんアテにしてた。うち、何てことや。老先生、ほんに堪忍やえ~・・・・・。何ぁ~んか、うちら二人して、たゞ、君子はん訪ねはる、そんな五郎はん、待っていたのか知れまへんなぁ~・・・・・ 」
風穴でもポカリと開いたような、そんな呟きが香織の唇から洩れたとき、花野に座る地蔵と出逢ったようなその仄かな言葉は、しかるべき余韻を虎哉の胸にしみじみと残して、踊りはじめた笛の音が空でも弾くように、しばらく北風の中に舞っていた。
「 かって日本の文明は、農耕のリズムと農耕の価値観にもとづいて発展してきたはずだ・・・・・! 」
幽・キホーテがそう感じた瞬間、その脳裏には不思議な光景がふと舞い降りてきた。
それはかって訪れたことのあるユタ州モアブのデリケート・アーチ、その延々と悠々とし不動のごとく見えた赤く枯れた大地であった。そしてその光景の中にかってヴィョン教授と眺めたフランスの子供たちの姿が夢でも語るように仮装化されて重なってくる。またさらにどうしたことか、誰かの奏でる篠笛の音が幻のように耳奥を刺して響かした。
「 かのアインシュタインの相対性理論が最期まで永遠に成立しているとすれば、物理法則が適用できない異次元空間の特異地点があらゆる多様なブラックホールにもなければならないはずだ。この笛の音はそこを引き出そうとでもするのか・・・・・ 」
という奇妙な推測を打ち出したことで、幽・キホーテは夜の御嶽(うたき)から見える暗い久高(くだか)の島影を揺らぐようにじっとみた。琉球の創世神アマミキヨが天から久高島に降りてきて国づくりを始めたという。
しばらくその篠笛の音の起伏に揺らされていた。














久高島・イザイホー









