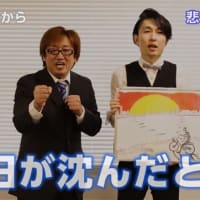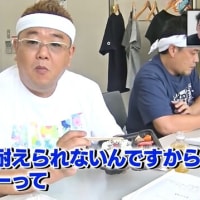1990年、1991年と二年連続で夏の甲子園準優勝を果たした沖縄県立沖縄水産高校。沖縄野球、そして沖縄県民の悲願を背負い、全国屈指の強豪校に育てあげた名将が栽弘義さんです。この栽さんをモデルにした映画が「沖縄を変えた男」です。
この映画は松永多佳倫さんの「沖縄を変えた男 栽弘義 -高校野球に捧げた生涯」を原案にしたフィクションで、琉球水産高校が舞台となり、モデルになったのは1991年の沖縄水産高です。この時の夏の大会は大野倫さん(元読売ジャイアンツほか)が右ヒジを骨折しながらも投げ続け、最後の最後に力尽きました。栽さんとチームの活躍が感動を呼ぶ一方で若い才能を酷使した采配を非難する声も少なくありませんでした。主人公の栽監督役はお笑いコンビ・ガレッジセールのゴリさんが務め、スタッフも出演者もほぼ全員が沖縄県民。栽監督の教え子たちも協力しています。2015年11月23日に糸満市西崎球場で行われたロケでは県民400人がエキストラ出演をするなど、地元での注目度は既に高い映画です。
■監督・部長としての甲子園通算成績
選抜大会出場7回 4勝7敗
選手権大会出場11回 25勝11敗 準優勝2回(1990年、1991年)
栽さんは1941年5月11日に沖縄県糸満市で生まれました。4歳のときに沖縄戦に遭遇し、3人の姉を失い、自らも背中に重傷を負います。ボールを握ったのは米国占領下の小学校四年生の時で、ソフトボールを米軍兵士からプレゼントされ、見よう見まねでキャッチボールを始めました。ボールもグラブもバットも、すべてが米軍のお下がりでした。
沖縄県の高校が初めて甲子園に出場したのは1958年夏の首里高校でした。その首里高と沖縄大会の準決勝で戦ったのが、栽さんの糸満高でした。この試合で二年生ながら、3安打を放ち、そのうち1本がホームランで、大会の打撃賞を受賞しています。
この試合で首里高の監督だった福原朝悦さんを見て、羨ましく思うとともに高校野球の監督を志すきっかけとなりました。当時の沖縄の高校で教員が監督をしているのは珍しく、糸満高は監督が顔を出すのは週1回だったそうです。選手と行動を共にしなければ、絶対に強いチームは出来ないと思ったそうです。
そして、教員を目指して中京大に進学しますが、沖縄出身ということでイジメられたそうです。沖縄の子が素足で走っている姿がテレビに映し出されたらしく(砂浜を走る姿だったそうです)、「お前、靴なんかいらないだろう」と脱がされたり、年配の英語教師には沖縄の日常語は英語だと思い込んでおり「授業に出るな」と言われ、抗議すると「発音に自信がないんだ」と言われたりしたそうです。
大学卒業後、沖縄に戻ると、1964年に那覇の小禄(おろく)高校に赴任し、ここから半世紀に及ぶ高校野球の指導者生活が始まります。当時は日米親善の意味合いで、米軍の輸送部隊がバックネットを作ってくれたそうです。那覇港で組み立て、それをクレーン車で学校に運び、グラウンドに備えつけてくれたそうです。
新任の指導者とあって、当時のキャプテンが「インコース打ちのお手本を見せてもらえませんか」と迫り、ひるんだらナメられると思い必死にバットを振ったそうです。幸い、腕をたたんで振るインコース打ちは得意中の得意であり、外野の向こうに青々とした水を湛えた漫湖が広がっていた、そこへ3本もホームランを叩き込みました。
また、ポリシーは「父母からお金をもらわない」というもので、栽さんも生徒たちも建築現場のアルバイトをし、部費に充てたり、米軍基地からバッティングケージに使えそうな網を譲ってもらい、防球ネットを作ったりします。また、トレーニング器具も手作りで、2つのバケツにセメントを入れてパイプで繋いだものをバーベルにしました。古新聞でボールを作り、室内バッティングをしたのも、栽さんが最初だったそうです。
そして、一番のアイディアは勝てずに悩んでいるとき、建築関係の本を読み、そこに地震に強い建物を造るには硬いものの間に軟らかいものを挟めばいいと書いてあったことから、女子マネジャーを考えついたことです。高校野球で女子をマネジャーにしたのは、栽さんが最初でした。全国に通用するチームを目指して過酷な練習を課したことから度々選手との対立を引き起こしていた頃のことです。
それでも着実にチームを強くし、1970年に初めて夏の沖縄大会優勝を果たし、南九州大会決勝まで駒を進めましたが、宮崎県代表・都城高校との代表決定戦に1-3で敗れ、あと一歩のところで甲子園大会出場はなりませんでした。
1971年に豊見城高(小禄高とは漫湖を挟んで近く)に転任し、1974年秋の九州大会でベスト4入りし、1975年の選抜で初めて甲子園に出場します。しかし、この秋の大会の時からは監督ではなく部長としてベンチ入りでした。情にもろい栽さんは年齢制限で試合に出場出来なくなった亀谷興勝さん(家庭の事情で小学校に二年遅れて入学)を「何とかベンチに入れてやりたい」と考え、「お前は試合に出られないから、監督をやりなさい」と言い、栽さんは部長の肩書となって采配を振るい、亀谷さんはサインを出す役目をして秋の大会を勝ち上がって甲子園をつかんだのでした。もちろん「19歳の高校生監督」は甲子園でも話題になりました。
その豊見城高は赤嶺賢勇さん(元読売ジャイアンツ)を擁し、一回戦は習志野高(千葉)に3-0で完封勝ち、二回戦は日大山形高(山形)に勝って、沖縄県勢として初めてベスト8を果たします。そして、準々決勝で優勝候補の東海大相模高(神奈川)と対戦し、「沖縄の栽弘義」を全国に知らしめる激闘を演じます。1-0とリードした九回裏、三番・原辰徳さん(前読売ジャイアンツ監督)を三振に仕留めて2アウト。しかし、後続に連続ヒットを浴び、同点。なおも一・二塁の場面でバッターが打ち上げたファースト後方のフライを落球してしまい、二塁ランナーが生還し、土壇場でサヨナラ負けとなりました。
この試合で高校野球ファンの感情を「同情」から「称賛」に変えましたが、甲子園における「悲運」の始まりでもありました。
この年の夏から監督に戻ると、1976年の春も出場(初戦敗退)し、同年夏からは三年連続で夏の甲子園ベスト8入りを果たすなど、豊見城高では監督として春、夏5度の甲子園出場をし、赤嶺さんだけではなく、今でも沖縄県史上最高のスラッガーと称される石嶺和彦さん(元阪神タイガースなど)らの名選手を育てました。
なお、豊見城高時代には2000坪の畑を借り、子どもたちとサトウキビを作り、ボールを買っていたそうです。
その後、学区制が採用されて選手を集めにくくなったことや、グラウンドその他の設備の不十分さなどから限界を感じ、1980年に全県から選手を集められ、学校が所有する広大な敷地を自由に使う許可を出してくれた沖縄水産高に転任して天下取りを目指していきます。
1984年夏に沖縄水産高で初出場を果たすと1988年まで五年連続で夏の甲子園に出場するなど、黄金時代を築きましたが、沖縄水産高でも甲子園ベスト8の壁をなかなか破れませんでしたが、1988年夏に初めてベスト4に進出しました。そして、1990年から二年連続で夏の甲子園で決勝にまで進出します。この時の中心選手が大野さんです。1990年夏は五番・ライトで出場し、26打数9安打(打率.346)。1991年夏は6試合すべて完投。決勝の大阪桐蔭高(大阪)戦は6-2と4点リードしながら、五回裏に6点を奪われ、逆転されます。これが深紅の大優勝旗に最も近づいたときでした。
「沖縄のチームが優勝しない限り、沖縄の戦後は終わらない」と栽さんが語ったという言葉が独り歩きしましたが、「事実誤認です。戦争と野球は違う。そんなことを言ったら、戦争で亡くなった方に失礼だ」と記者に語っています。栽さんの一番上の姉は集団自決でした。二番目と三番目の姉は戦争中に行方不明になったそうです。自身も4歳のときに手榴弾を浴び、背中に大ヤケドを負っています。米兵から「防空壕を出ろ」と言われ、怖くて出られず、手榴弾を使われたそうです。お母さん背中に負われていたからだそうです。そのためか、大人になってからも暗闇を怖がったそうです。甲子園期間中でも宿舎で寝るときは、部屋を真っ暗にしなかったそうです。
1991年夏の準優勝以後は甲子園出場は春夏合わせて4回。 1998年は新垣渚選手(東京ヤクルトスワローズ)をはじめ有力選手がそろったことで全国制覇が期待されましたが、春夏とも初戦敗退に終わり、この年が最後の甲子園出場となります。
2002年に保健体育教諭を務めていた沖縄水産高を定年退職、その後も監督を続けましたが、2007年2月に体調を崩し、5月8日に帰らぬ人となりました。
その三年後。我喜屋優監督率いる興南高が甲子園大会で春夏連覇を成し遂げます。
栽さんの指導方法は熱血であるが故に批判も集めたことも少なくありません。でも、栽さんは沖縄県民の夢を背負って戦ってきたことは事実です。甲子園で勝てば県民も自信が持てる。自分は憎まれても、勝てば選手が、そして県民が幸せになれると信じていたのでしょう。
「沖縄を変えた男」は2016年4月の沖縄国際映画祭でお披露目された後、6月に沖縄県内で公開され、全国公開も計画されています。