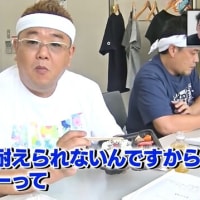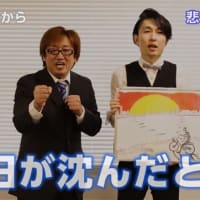第1回選抜中等学校野球大会は1924年4月1日から4月5日に行われました。
東西のバランスや販売戦略などが絡み、愛知県名古屋市の山本球場で行われ、翌年から阪神甲子園球場での開催となりました。ちなみにこの山本球場は大阪タイガース(阪神タイガース)対東京巨人軍(読売ジャイアンツ)の公式戦初開催地(1936年7月15日)でもあります。山本球場というのは、1922年に当時の名古屋市内で運動用具店を営んでいた山本権十郎さんが私費を投じて独力で建設した、本格的な野球場で山本さんの名前から山本球場と名付けられました。
選抜中等学校野球大会(現在の選抜高等学校野球大会)の第1回大会は当時の大阪毎日新聞社(現毎日新聞社)の意向によるもので、東海地方の野球ファンの要望に応えるという目的と、夏の全国中等学校優勝野球大会(現在の全国高等学校野球選手権大会)で関西地方の学校の優勝確率が高いことが、阪神甲子園球場で行われる地元の利(移動による負担が少ない)があるのか、関西の風土に関係あるのかを確認するという意味合いがあったそうです。それまで、夏の大会では関西地方の学校が8回中8回とも決勝に進出し優勝は8回中5回でしたから、そう言われても仕方がないものだったかも知れません。ま、なんだかんだ言っても、朝日新聞に対する毎日新聞のライバル意識があったと思います。
出場校は東京・早稲田実、神奈川・横浜商、愛知・愛知一中、大阪・市岡中、京都・立命館中、和歌山・和歌山中、愛媛・松山商、香川・高松商の8校でした。入場行進曲は「星条旗よ永遠なれ、ほか」です。
この開催地の風土に関しては代表校8校中3校だった関西地方の学校は和歌山中と立命館中が初戦敗退、市岡中は二回戦敗退であり、地域制優位はなかったとのことです。一方、東海地方の野球ファン拡大についての効果は大きく、1930年代に入り愛知県勢の中京商、東邦商、愛知商などと岐阜商を中心に東海勢が中等野球で一時代を築くとともに、1936年の職業野球(プロ野球)創設時に愛知県のチームが名古屋軍、名古屋金鯱軍の2チームが出来るほど野球が盛んとなりました。
主催者の毎日新聞社は毎年開催地を変えて全国各地で開催する構想だったそうですが、翌年の第2回(1925年)以後は高校野球(当時は中学野球)の聖地として知られる阪神甲子園球場での開催に定着するようになり、近畿地方以外での全国大会開催は国体、明治神宮大会を除くと春・夏を通してこれが最初で最後となりました。
なお、第1回大会の開催された山本球場はレフト側が狭く、ライト側が広いという変則的なフィールドで、レフトの定位置を越える飛球はそのままトタン塀を越えるホームランとなったため、この大会のホームラン12本は基準に満たない飛距離という理由で公式記録から外されていましたが、1988年に正式記録として認定されました。
さて、この第1回選抜中等学校野球大会で優勝したレジェンド校が四国・香川・高松商高です。創部107年目を迎える伝統あるチームが昨秋の明治神宮大会で全国初優勝。第1回選抜優勝校が2014年選抜優勝校に打ち勝ち、今年の選抜に出場します。
その伝統チームの指導を執るのが2014年に就任した長尾健司監督です。長尾監督は丸亀市立飯山中、香川大学附属坂出中などで指導し、全国で2度の優勝を果たし、指導力の高さは県内に知れ渡り、中学球界では名指導者と呼ばれました。また、高松商高の監督といえば、その学校のOBが監督になるというのが一般的ですが、長尾監督は丸亀高出身で、外部から招聘した形となるが、それだけ高松商は長尾監督に期待していたということになります。さらに、長尾監督を慕って監督就任と同時に入学した選手たちになります。
ただ、そんな長尾監督もここまで重ねてきた「熱」と「血」の努力と、立ちふさがって来たいくつもの「壁」がありました。
丸亀高校から「体育の教師になりたくて」進学した順天堂大でした。入部した野球部では、ベンチ入りしたのは1回程度で選手としてはレギュラーからほど遠かったそうです。順天堂大四年生で野球部の春のシーズン。順天堂大は伝統的に学生が監督を務めるそうで、長尾監督は立候補して監督になりましたが簡単ではありませんでした。それでも監督に名乗りを上げたのは「将来、教員になって野球の指導者になりたい」という強い思いからだったそうです。しかし、選手として実力が上の同級生に指示をすることは「下手だった私が監督になったので、采配に不満がある選手はあからさまに文句を言ってきた。当時は経験もなく、指導も未熟で反抗は当然だった」そうです。結局、いい成績が残せず終わった学生監督時代だったそうです。本当は能力が上の下級生を使いたいと思った時も、同級生からの反発を恐れて、そのまま四年生を使ったこともあり、「監督になったのは大失敗だった。あの時は『監督失格』でした」と振り返っていますが、そこから学んだことは大きく、「言うことを聞かない人間を納得させるには、もっと自分が勉強するしかない」と考えたそうです。
順天堂大学を卒業後、教員として大川中(東かがわ市)でした。ここでは生徒たちとがむしゃらに接したそうです。たった一年間で離れることになってしまったそうですが、野球部の最後の練習で、みんなが先生にノックして終わろうと部員に打たせたら、暗くなっても「先生、まだです」と打ち続けていたそうです。全力で教えてくれた長尾先生と離れることが嫌だった、部員たちの抵抗だったそうです。
数年後に勤務しが和光中(三豊市)。チームはバッターが一塁を駆け抜けてもいいことを知らないような野球部で、まったく勝てず、屈辱的なコールド負けもあったそうです。それでも、任期の一年間の最後に1勝することが出来ました。部員たちとの別れの日、部員たちはとんでもない行為に出て、次の学校に移動しようとする長尾監督の車の前に多くの部員が寝転び「別の学校に行くのなら、僕たちを引いて行ってください」と。かわいくて涙が出そうだったそうです。
綾歌中(丸亀市)時代に、長尾監督の指導を受けたのが、同じ選抜に出場する香川・小豆島高野球部の杉吉勇輝監督です。「生徒以上に一生懸命にやる先生だった。ノックを打つこと一つをとっても、とても楽しそうに野球をしていた。指導している人がこんなに面白そうにしているのだから、僕たちももっと野球を楽しまなければ」と思ったそうです。甲子園で、この師弟対戦を観てみたいものです。
進学校の香川大教育学部付属坂出中(坂出市)では、練習時間は午後4時から一時間しかなかったそうです。着替える時間などを考慮すると、実質45分程度。だから、練習時間が短いから強くなることが出来ないと始めから皆そう思っていたため、意識改革が必要だと感じて、「練習時間はわずか一時間しかないが、その中で私はどうすれば県で一番になれるかを考えている。君たちも一緒に考えないか」と就任時に言ったそうです。
前任の飯山中(丸亀市)で野球部を県大会優勝に導き、自分で考え積み重ねてきた指導方法と残してきた実績に手応えを感じていました。夏休みや冬休みなどを活用し鍛えた二年目の春。県大会ベスト4進出という成果を出し、三年目の春には初優勝。さらに四国大会でも決勝まで行くという快進撃でした。さらにこの三年目の2008年は県大会で夏も秋も優勝を飾り、三本の優勝旗が揃う前代未聞のことを成し遂げ、四国大会でも優勝し全国大会に初出場するなど、付属坂出中は中学野球界の注目校として成長しました。
そして、2014年の春、県の公立校の人事交流で高松商高に着任。
「自分のことは自分でやる。年上がまず動く」との考えで、ぎごちない上下関係を打破するため、監督自身が率先して、グラウンド整備に走り回る監督を見て部員もあとを追うようになりました。侍ジャパンの歴代指揮官の言葉も参考にし、「王さんも小久保さんも、練習から120%の力で振るんだ、と言われてました」と流す打撃練習は戒め、敦賀気比高、大阪桐蔭高に打ち勝つ打力を養いました。
第1回大会優勝校、20年ぶりの出場という注目ではなく、優勝候補の一角としての選抜大会です。
古豪復活と呼べるかどうかはこれからであり、伝統というのは続かないといけません。新生・高松商高の戦いぶりには注目です。