今回は,憲法発布の明治22(1889)年2月11日に沸き立つ東京から始まりました。
実際,当時国民の関心は政治に向いており,提灯行列やイルミネーションによってあちこちで新憲法発布を市民たちが祝ったそうです。
この一事を見ても,現代人たちは逆立ちしても当時の人々にかなわない,と思います・・・。
子規が喀血したのは確かにこの年だったようですが,2月の憲法発布の時ではなく,5月だったらしいです。
そして,「子規(ほととぎすの意)」と号したのもこの年だったようです。
療養のため帰郷した子規を真之が訪れるくだりは,原作にあったかどうか・・・。
お囲い池は各藩に有ったのでしょうか。
我が藩に有ったかどうかは定かではありませんが,会津藩の藩校である日新館には有ったようでした・・・。
・・・にしても鎮台がフリチン(フルチン?)で入るとは・・・(洒落にもならん・・・)。
もっくんが父ベンジャミン伊東と入っていたのは,道後温泉でしょうか・・・。
一度有名な本館の湯に入ったことがありますが,あんな感じでしたので・・・。
その父の訃報を,兄からの仏文の手紙にて洋上で知る真之。
良い味出しまくりだったベンジャミンが出なくなるのは残念です・・・。
「短気は損気,急がば回れ」
とは,私に向けた言葉のように思われてなりません・・。
しかし,今回はいつもに増してストーリーの進行が早く感じられました。
母が一人暮らす松山に再び帰郷する真之。
その後,大津事件を経てストーリーが動き出します。
大津事件がもたらした社会的影響は少なくなく,行政から司法権を切り離すことによって所謂三権分立が近づくことになったと思われます。
ロシア皇太子ニコライ(後の皇帝ニコライII世)に斬りつけた巡査大津三蔵は,西南の役に武勲をあげており,西郷生存説がまことしやかに言われたこの時期,西郷がロシアの軍隊とともに攻めてくる,といった恐露状態にあったとか,西郷が生きていれば自分の武勲が無効になることを恐れたとか,いろいろと言われているようです。
ここでは本論から外れますからこれ以上述べませんが,調べれば調べるほど謎めいた事件のようです・・・。
清国北洋艦隊の旗艦であった定遠が日本に回航したのは,実は明治19(1886)年だったようです。
同型艦の鎮遠とともに独で建造された当時東洋一の戦艦と言われましたが,実際に兵員の士気もモラルも低く,長崎ではとんでもない事件を引き起こしています。
実際に居合わせたかどうか定かではありませんが,東郷が「なまくら」と言った内容は確かだったでしょう・・・。
その後は,朝鮮半島を巡って清と開戦すべきか否かの政治家たちの緊迫した動きが描かれましたが,全く弛緩することなくストーリーが進行しました。
何故日本は朝鮮や遼東半島に出兵することになったのか,実によく分かるというものです。戦後の歴史教育によって,我が国は自国民から単純に,侵略戦争を仕掛けた悪の帝国,といった短絡的な考え方をされるようになりましたが,そんな単純なものではないことは,こうして当時の国際情勢を見れば一目瞭然です。
次回はいよいよ日清開戦(今回開戦してしまいましたが)のようです。
東郷が高陞号を撃沈した高陞号事件と豊島沖海戦は語られましたので,どうやら平壌攻略と黄海海戦,そして旅順要塞陥落まで行く模様ですね・・・。

実際,当時国民の関心は政治に向いており,提灯行列やイルミネーションによってあちこちで新憲法発布を市民たちが祝ったそうです。
この一事を見ても,現代人たちは逆立ちしても当時の人々にかなわない,と思います・・・。
子規が喀血したのは確かにこの年だったようですが,2月の憲法発布の時ではなく,5月だったらしいです。
そして,「子規(ほととぎすの意)」と号したのもこの年だったようです。
療養のため帰郷した子規を真之が訪れるくだりは,原作にあったかどうか・・・。
お囲い池は各藩に有ったのでしょうか。
我が藩に有ったかどうかは定かではありませんが,会津藩の藩校である日新館には有ったようでした・・・。
・・・にしても鎮台がフリチン(フルチン?)で入るとは・・・(洒落にもならん・・・)。
もっくんが父ベンジャミン伊東と入っていたのは,道後温泉でしょうか・・・。
一度有名な本館の湯に入ったことがありますが,あんな感じでしたので・・・。
その父の訃報を,兄からの仏文の手紙にて洋上で知る真之。
良い味出しまくりだったベンジャミンが出なくなるのは残念です・・・。
「短気は損気,急がば回れ」
とは,私に向けた言葉のように思われてなりません・・。
しかし,今回はいつもに増してストーリーの進行が早く感じられました。
母が一人暮らす松山に再び帰郷する真之。
その後,大津事件を経てストーリーが動き出します。
大津事件がもたらした社会的影響は少なくなく,行政から司法権を切り離すことによって所謂三権分立が近づくことになったと思われます。
ロシア皇太子ニコライ(後の皇帝ニコライII世)に斬りつけた巡査大津三蔵は,西南の役に武勲をあげており,西郷生存説がまことしやかに言われたこの時期,西郷がロシアの軍隊とともに攻めてくる,といった恐露状態にあったとか,西郷が生きていれば自分の武勲が無効になることを恐れたとか,いろいろと言われているようです。
ここでは本論から外れますからこれ以上述べませんが,調べれば調べるほど謎めいた事件のようです・・・。
清国北洋艦隊の旗艦であった定遠が日本に回航したのは,実は明治19(1886)年だったようです。
同型艦の鎮遠とともに独で建造された当時東洋一の戦艦と言われましたが,実際に兵員の士気もモラルも低く,長崎ではとんでもない事件を引き起こしています。
実際に居合わせたかどうか定かではありませんが,東郷が「なまくら」と言った内容は確かだったでしょう・・・。
その後は,朝鮮半島を巡って清と開戦すべきか否かの政治家たちの緊迫した動きが描かれましたが,全く弛緩することなくストーリーが進行しました。
何故日本は朝鮮や遼東半島に出兵することになったのか,実によく分かるというものです。戦後の歴史教育によって,我が国は自国民から単純に,侵略戦争を仕掛けた悪の帝国,といった短絡的な考え方をされるようになりましたが,そんな単純なものではないことは,こうして当時の国際情勢を見れば一目瞭然です。
次回はいよいよ日清開戦(今回開戦してしまいましたが)のようです。
東郷が高陞号を撃沈した高陞号事件と豊島沖海戦は語られましたので,どうやら平壌攻略と黄海海戦,そして旅順要塞陥落まで行く模様ですね・・・。











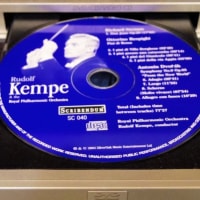
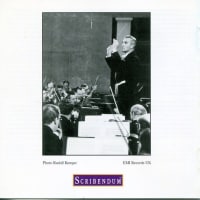
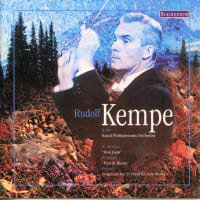







本日、次の演奏会のために、M大学へ行ったところ、「5月の演奏会で、ご一緒させてもらいました。」と、ごあいさつされました。K講習会でTIMPをお願いした方でした。狭い。M大の打楽器も見ることになりました。そういえば、今度、お邪魔します。
夕方から、雪になるかも・・との予想でしたが、雨の音がしています・・。
さて、今回のストーリーの中で、私も、一番心に残ったのは、「短気は損気、急がば回れ」の父上の言葉でした。
今の日々に、心に留め置きたい、一節です。
大河ドラマの倍の時間を費やしているせいか、毎週見るドラマとしては、じっくり見応えがあります。
本日も、解説付きにて、さらなる興味を深めています。
香川は,来年の大河でも岩崎弥太郎役という準主役のようで・・。
こちらにはいつでもどうぞ。
Telかメールで前もって連絡いただけるとありがたいです。
市内北部はみぞれでした・・・。
いろいろと注文が付く部分はありますが,本当に毎回見応えがありますね。
3年かかってコンプリートというのがネックですけど・・・。
制作者の志の高さがうかがえます。
本作のために「天地人」がおざなりにされた訳では無いのでしょうけど・・・。
次回も書けるといいです。
だんだん知識・考証不足を露呈しそうですが・・・。