
まことに、定義されたような「里山」での出来事です。
人の棲む都会からすこ~し離れた森林地帯へ
朝から皆さんが集まってきていて
焚き火です。
立春はとうに過ぎたとはいえまだまだ朝は寒い。

焚き火の材料は里山を手入れしたときに伐採した木々の枝なんか。

当日イベントについて説明したのは里山クラブの副会長
我らが松っちゃんです。

参加者は神妙に聞き入っておりました。
里山とは何ぞや?
そこでのクラブの活動内容
今後の目標などが判りやすく説明されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自分が子供の頃は日曜日なんか東京でも
落ち葉を集めてきて焚き火をするのが日常の風景でした。
焚き火の中には必ずサツマイモを放り込んで
焚き火が終わったら引っ張り出してホクホクの焼き芋を
みんなで食べた思い出があります。
いつの頃からか子供達や我々の周辺から
焚き火が姿を消してしまいました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて当日のメインテーマは椎茸の菌打ちです。
なんでも一袋1000個入りの椎茸菌を浸み込ませた小さなワインの栓みたいなの。
ちょっと湿っております。
椎茸菌が乾かないようにとの配慮だそうです。

これを2,000個クヌギや楢の丸太にドリルで穴を開けて
そこへハンマーで打ち込むんですね。


子供達も大活躍してトントンと菌を打ち込みました。
1~2年すると立派な椎茸が誕生します。

クヌギなんかの丸太はとても重たくてお爺さんが運ぶには
腰に来るから危険です。
ひとしきり菌を打ったら昼食になりました。
これがまた、気合の入った打ち込み饂飩で・・・
熟練の仕事師たちが饂飩を煮込んで振舞ってくれました。

これも焚き火同様の燃料を使って炊き込まれています。
饂飩はさる有名な方が前日から練って作られたとか。
味噌仕立ての大鍋には大根やニンジンなどの根菜類
それに猪肉が丁寧に前処理されたものが入ってます。
豆腐も入り、上からネギを掛けて頂きます。
めちゃんこ美味しかった。

役員の方々は立ち食いです。
我々のような素人はちゃんとテーブルと椅子に腰掛けて
おいしく頂きました。
そして美味しいおコメで作られたオニギリが出てきて
一同感嘆の声をあげます。
オイラは焼きオニギリ作りを担当しました。
これがまた、評判が良くて焼きあがったオニギリを
皆さんに召し上がってもらいました。

採れ立ての椎茸も焼いてポン酢を掛けて
食べると肉厚で神の味がしました。
里山っての
子供も大人も気楽に楽しめますが
ここまで整備するのは大変な労力が掛かってるようです。


「里山に菌打つ音や梅紅し」
準備された方々のご苦労に本当に感謝致します。
有難うございました!!
当日はさぁ~これからどうする?となって
夕刻から町で一献傾ける結果となりました。












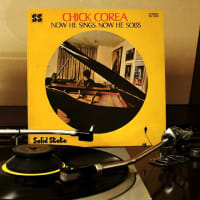







さすが、銀次郎さん。シイタケの植菌も焼きおにぎり作りも熱心に取り組んでくれました。
人知れぬ里山で黙々と山作業をやるだけでなく、たまには里山の現状や我々の活動を世間一般の方に知ってもらうことも大切ですね。
今後も遠慮なく、枌所の里山に遊びに来てください。
一度でもそういう話を聴けば、山を見たときに手が掛かってるかどうかすぐ判るようになるでしょう。
世間に説明することも大切な作業であるように思いますね。
折角の椎茸が沢山出る頃に伺いますぜ(ひひひ)。
ウソみたいな話ですが、今日そういった不思議現象がありましたU+1F631
ちょっと気味が悪いですU+1F614
スーパーに袋ずめされて並ぶまでの一部なんですが。一番、労力が要るのが切ってそこまで運び出して来る事なんですがね。
私も、去年の暮れにくぬぎの木を切って、乾燥、メーター前後に切って、尚乾燥、駒菌を打ち込みナイロンをかけて仮伏せし、時々剥ぐって散水して仮伏せしています。
もう少ししたら、野晒し状態で本伏せと成ります。けっこう労力を使いますよ。
自家消費分ですが、余る分は出荷に回るのではないのかと思われます。
松ちゃん様、お初です。宜しくお願いします。
里山を良くしようとする活動は良い事ですね。
私も、里山を先祖代々預かって居ます。
悪くしようとすると数年で悪く成ります。
そこから、良くしようとしますと労力は何倍も掛かるし、時間も長く懸かりますね。
つくづく思います。
先祖代々ある孟宗竹林(畑)が一時期、輸入物の
筍に価格を奪われて安くなり、労力を使っても似合わない状態でした。それと、消費者場慣れも有りますし。管理するには、凄く労力が要ります。年寄りには長々難しい問題です。
この辺では自慢出来る、畑には成って居ます。
まだまだ、遣るべき事は在るのですが、
竹については、色々なノウハウは持って要ます。鋸、切り方、処分の仕方、栽培、聞きたい事が有りましたらお気軽にお聞き下さい。
松ちゃん、ご立派です。
西谷様、お初です。お話しはお聞きしています。宜しくお願いします。
私も、リリアンが括れた事は何回有りますよ。
振り込み、合わせ等でなんかの拍子に潜って、釣をして行く内に、糸が切れたら括れてしています。
メーカーの穂先のリリアンは品やかで細い編み込みが時流ですよね。
穂先が折れて、修理用のリリアンは荒くてピンとしています。まず、そんな事には、成らないと思いますよ。余り不思議では無いです。
川三、理論です。
文章が長くなりました。
原木を切ってきたり、急な山道を運んだり、兎に角、お爺の出番ではないような気がしますね。
菌を打つための穴を空けたり、菌を打つことはたやすいことですが。
西谷さんの質問にも答えて頂き、有難うございました。
そんなに珍しい現象では無かったようでやれやれです。