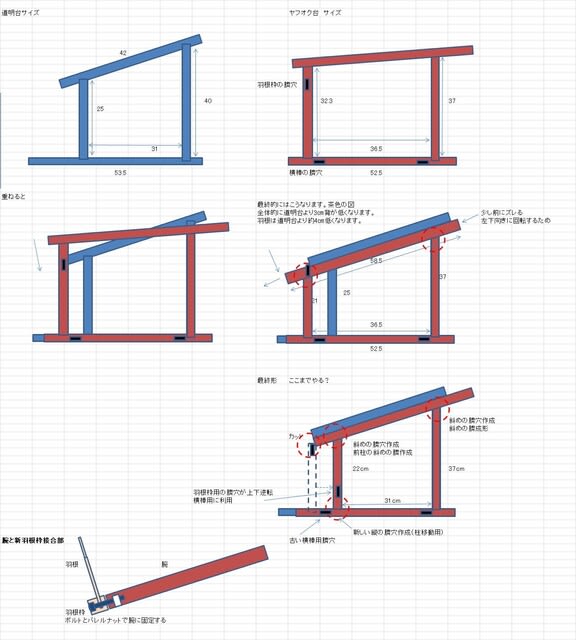先週綾竹台の3台目が完成した。
つづいて今度は高台の製作を依頼された。 妹に作ってあげたのを聞きつけて、お友達が、私にも是非、ということで・・・お引き受けした。
高台は、幅88㎝、高さ72㎝、奥行84㎝という大きさで、いわゆる小高台と中高台の中間くらいの大きさ、それなりに長い材木が必要になる。
先の綾竹台はハードメープルという無垢材を使って非常に良い出来だったので、今回も・・・と探したが、長さ、幅、厚み、本数、の合うものが手に入らなかった。
妹のと同じ高級木材、無節の雲杉にしようと決めかかったが、無垢材屋さんを物色していたら、レッドオークなら必要な長さのものが必要な本数手に入るには入るのだが・・・幅、厚みがごっつい・・・40㎜角しかない・・・
う~む、何とか自分でプレーナー処理するか・・・ということでレッドオークを注文した。 レッドオークは高級テーブルの天板や足などに使わる木材だ。
で・・・届いたのが・・・かなり・・・ひ・ど・い・・・こちらの要求に比してという意味で・・・
少しだが歪んでいる物、ねじれている物、50mmもあるもの・・・45㎜角のもの・・・40mm角どころではなかった。 そしてハードウッドだけに、お・も・い。 雲杉は軽くて扱いやすかったが、やはり、ハードウッド系は結構な重さがある。 原木で全部で27Kもあった。 まあ、どっしりしていいか・・・
届いた原木状態がこれ・・・表面は、接着剤がついていたりしてかなり汚い。 乾燥はしているようだ。
 届いた原木、レッドオーク
届いた原木、レッドオーク
二日かけて、マキタの電動プレーナーを使って、40mmx35mmの角材に仕上げた。 40mmx30mmにするには、削る部分が多すぎて、その勇気が湧かない。
曲がったり捻じれたりしていたものは調整してまっすぐにした。
完成した角材がこれ・・・表面はきれいに超カンナ仕上げとなっている。 かなり・・・い・い・・・
 木目もきれいに出ている
木目もきれいに出ている
中には、レッドオークの杢である虎斑が出ている物もある・・・全部ではないが・・・シルバーラインとも呼ばれる杢だ。 杢の好きな人には垂涎もの。
 右端2本の角材上面に虎斑の杢が出ている
右端2本の角材上面に虎斑の杢が出ている
これだけの本数を3mm~15mm、4面カンナ掛けしたのだから、出た削りくずも半端ない。 マキタの集塵機は容量限界を超え、詰まってしまって往生した。 もう集塵するより手で寄せ集めてゴミ袋に入れる方が早い。
ゴミ袋3杯分になったわ。 家の中には、あちこちにおが屑が散乱・・・
 ゴミ袋のおが屑
ゴミ袋のおが屑
ともあれ、角材の準備が完了した。 あぐらかいてプレーナーかけていたので、立ち上がれなくなってしまった・・・歳だね~・・・あいたたっ