令和3年9月24日(金)
「❷ごんぎつねの里」の続きです。

八幡神社へ来ました。
岩滑の氏神様です。
お詣りします。

拝殿です。
南吉は毎日この境内を通って、はなれの家と店(生家)を往復していました。

摂社の熱田神社と知立神社
これからはなれの家へ行ってみます。

道沿いに咲く彼岸花

はなれの家跡の案内がありました。

いまは一般の方が住まわれています。

さらに奥の方へ行ってみます。

今度はお寺さんがありました。
常福院です。
ここもお参りしていきます。

木々に囲まれて建つ本堂。

永禄年間(16世紀中ごろ)、岩滑城主の中山勝時が菩提寺として建立した浄土宗西山派の寺院。
戦前は境内で盆踊りが行われ、南吉もよく踊っていたそうです。

本堂の中へ入ってみます。

誰も居ませんw

お参りします。

ご本尊様。

右側に厨子のようなものが安置されていました。

どなたかしら?
御坊様のようですが。

本堂を出ました。
境内の様子です。

英霊碑がありました。

何か細長いものが生っていました。

これが中山氏の家老が植えたソテツですね。
いっぱい枝が出ていて、とっても大きいです。

裏の木に実が生っていました。
カリンかしら?

道を戻っていよいよ300万本の彼岸花の咲く矢勝川へ向かいます。
続きはまたにします。












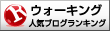

















何だか、ご一緒させて貰っている気分です。
こういった風景は、わたくしが子どもの頃には何処にでもありました。
貧しい中での執筆が、健康への配慮を失くしたのかもしれません。
今とは信じられない暮らしでしたから。
楽しみに訪問させて貰っています。
大正時代でしょうか。
あの時代は普通の暮らしだったのでしょう。
生活もですが、医療もまだ発達していなかったのでしょうか。
作家さんは若くして亡くなる方が多かったです。
でも貧しくとも自然に目を向けるこころは、本来の人間の生き方なんじゃないかと思ったりしています。
この後、彼岸花を見に行きます。
ありがとうございます。