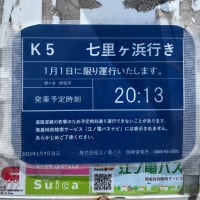こちらは人的被害がなくてよかったが、137人という全島民は船で隣の屋久島に避難する騒ぎとなった。
どういう暮らしをしてきたのか知らないが、島に戻って日常を取り戻すにはそれなりの時間が必要だろうし、避難した先で当面の生活を維持して行くというのも簡単なことではないだろう。
東北の蔵王のお釜周辺で火山性の活動が活発化しているそうだし、鹿児島の桜島も同様である。
何より足許の箱根の大涌谷の噴気の量が増えていて、しかも火山性地震が頻発しているため、観光シーズン真っ盛りの大型連休最中に火口付近の立ち入りが禁止されるという事態に陥ってしまっている。
絶景のロープウエイの運航は止まったままだし、1個食べると7年寿命が延びるという黒玉子は口にできない。
町役場や観光業者は深刻な顔をしているが、当然である。
気象庁や町役場では大涌谷周辺のごく一部が危険なだけで、それ以外の地域は何も心配することはない、と風評被害の拡大に気をもむ。
冷静に考えればそうなのかもしれないが、もう少しうがった見方をすれば、自然の活動のどこまでが人知の及ぶ範囲なのかという点である。
今の箱根を形作った噴火は太古の昔で、今さらそんな噴火はあり得ないんだろうが、何が起こるか分かったものではない。
知り合いのゴルフ好きの町長がよくテレビに登場して、普段はひょうきんなところを見せる人だが、そんな表情は押し隠してテレビのインタビューに答えているところなんぞは痛々しい。
多くの観光客にとって、箱根ばかりが観光地ではないのだから、君子危うきに近寄らずは身の知恵なのである。
「避難計画策定が義務付けられる50火山」というのがあるそうだが、それを見ると日本列島の近畿、中国、山陰、四国を除いた地域に海から列島を鎖状に縦断する形で火山が並んでいる。
よくもまあ、こんな狭いエリアにこんなにもたくさんの、しかも危険が予想される火山があるものかと、感心させられるくらいである。
わざわざ火山が集中している地域を選んで、しかも火口の脇で暮らしているようなものだ。
これではポンペイがいくつあっても足りないのではないか。
地図を見ていれば、火山の連なりがそれぞれ独立して単独で噴火を繰り返してきたとはとても思えない。
みんな地下深くでつながっているのだ。
そのうちのひとつの蓋が開けば、少しは圧力が弱まるのかもしれないが、何かの加減で急に地下深くの圧力が強まったら、いくつもの蓋が同時に開いてしまうんじゃあないだろうか。
東日本大震災直後に富士山で比較的規模の大きな直下型地震があった。
その時、多くの火山学者と地震学者は「ついに来たか」と富士山噴火の来るべき時が来たかと腹をくくったそうだが、その危惧が消えたわけではない。
大涌谷の眼と鼻の先が富士山である。富士山の眼と鼻の先が大涌谷、でもある。
社会人になって間もないころに小松左京の「日本沈没」というSF小説が出版されて話題になり、面白くて一気に読んだことを思い出す。
あれは確か富士山も箱根も大噴火を起こすのである。
ポンペイどころの話ではない。列島そのものが海中に沈んで消えてしまうのだ。
クワバラクワバラ。

「伽羅奢」と「名もなきバラ」がわが家の玄関を彩る

同様に「ブラッシングアイスバーグ」