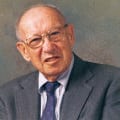京都大学の藤井教授が「他人に配慮できる人は運がよい」という論文を発表した。
「認知的焦点化理論」では、どのくらい遠くの他人、そして遠くの未来のことまで配慮できるか、ということを「配慮範囲」という尺度で表す。
人の心の「配慮範囲」には、「関係軸」と「時間軸」がある。
関係軸とは、家族→親戚→友人→知人→他人という順に、心理的な距離がだんだん遠くなっていく社会関係のこと。
時間軸とは、現在→数日先→自分の将来→社会の未来という順に、思いを馳せる時間的範囲が広がっていくこと。
自分から離れれば離れるほど、範囲が大きくなる。
これが「配慮範囲」である。
利己的で自分のことしか考えず、目先の損得しか関心が無い人は、配慮範囲が狭い。
逆に、他人や遠い将来のことまで思いを馳せることができる人は、配慮範囲が広い。
配慮範囲の狭い利己的な人は、ある程度までは効率よく成果をあげられるものの、目先のことにとらわれて協力的な人間関係を築けないため、総合的にみてみると、幸福感の感じられない損失が多い人生となる。
逆に、配慮範囲の広い利他的な志向を持つ人は、よい人間関係を持続的に築けるため、自分の周囲に盤石なネットワークをつくることができる。
言いかえれば、周囲のみんながこぞってその人を助けてくれることになる。
こうしてみると、よりたくさんの範囲の人、より遠い将来のことまで配慮できる人ほど運がよいというのも、ごくあたりまえのことに思えてくる。
:中野信子 脳科学者
配慮範囲を広くすることは、一緒にやる人を増やすことであり、マネジメントや人間力(ジンカンリョク)を機能させるために必要なことである。
より価値観の合うメンバー、より多くのメンバー、より大きな成果を出すには、配慮範囲を広くすることが大切である。