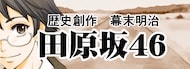推理ものをネタバレ無しで感想ての難しいですな。
英国推理作家協会は、犯行の動機の多くは「プライド」という事を、推理小説作法であげていたのですが
現代日本では多少違うのかもしれない、と感じます。
それは、個人の尊厳、プライドというものを傷つけられる場合
「どこで、誰に」が特定されても、直接相手に対して復讐という形で現れるのが少ないのでは、←閉塞感の原因
いやむしろパワハラその他も含めて、その相手に対してのストレートな憎悪は歪められ
「むしゃくしゃしてやった」等の理由での、「不特定多数」もしくは、自分より弱い者、
あるいは本当に最悪な場合これは「自分」に向けられるのでは、と思うのです。
東野圭吾作品が好きなのは、このご時世には、左だの右だの何か大きな物語を思想的バックボーンにした方が得とか
そういう事やりがちなんでは…というより、別にそうでなくていいものまで、それに照らし合わせて分別が行われてしまうのでは
と、思ったりする所、実にクールに、ひたすら「小さな物語」を庶民の視点、庶民の目線で描いていく、そんな所です。
長いものには巻かれない。
全てのキャラクターに「生活」かかってる感がいいです。
あらすじは冒頭で殺人、マスコミが報道するそれらしい犯人、しかし加賀には疑問が…という王道であります。
科学知識を駆使していないと解くことのできないトリックのようなのはありません。
しかし、テーマがすごく明確です。
これは小さくて大きい、「ダイイング・メッセージ」の話なのでしょう。
それと、作中ではむしろしつこく掘り起こされる事はないのですが「殺人の動機」
私はこれにかなり「!」と思いました。
近年、推理物はトリック重視になってきた感があるのですが、
松本清張のファンである私はやっぱり昭和ながらの「殺人の動機」というのに興味があります。
もちろん、推理小説の楽しみ方は、「動機はどうでもいいからトリック」というのもあるんでしょうが
トリックなんてパターンがあるし、謎という点で一番大きい謎は、人の心だと思うのですよ。
そして、その時代、その人の立場によって、「動機」は大きく揺れ動くのではないかと。
「恐れと保身」
これからこの作品を読んでみたい方は、どうかこの2つのキーワードを胸にと思います。
東野圭吾の作品に許し難い極悪非道の、絶対的悪人は出てこない。
けれど、鋭い社会眼で「絶対に許し難い悪」はごく身近に、それもかなりの透明度を持って存在している。
21世紀の現代の日本では不幸な事に、かつては殺人の動機になっただろう「大事にしていたものが傷つけられた、大事なものを失った」
なんていう方が日常茶飯で些末な事で
フツウと呼ばれる、日々生きる人達は「そんなの誰にでもある。でも乗り越えていかなければならない」として生きているのでは。
その代わりに動機になり得るのは、「自分の立場が脅かされるのでは」という不安。
「ヤバいことになる」のヤバいとは自分1人では使われない言葉なんだなあ、とも思いました。
ヤバいのは、「自分はもちろんの事」というその先の関係がある。
殺人事件なんてものは人がなすものであって、神の業ではないですから。
そういや司馬遼太郎もそんな所あるなあと思うのです。歴史なんて所詮人が動いて作ってきたものですから、と。
ただ、その「小さな物語」はなんて、場所や人や背負うものによって必死であり
概念で1つに括る事ができないものなんだと。
そのクールな人間観察眼たるや。
人が残すメッセージなんて結局は、理屈や理想で宙を斬るようなものではなくて
しっかりと誰かに渡したいもの、なんでしょうね。きっと。
英国推理作家協会は、犯行の動機の多くは「プライド」という事を、推理小説作法であげていたのですが
現代日本では多少違うのかもしれない、と感じます。
それは、個人の尊厳、プライドというものを傷つけられる場合
「どこで、誰に」が特定されても、直接相手に対して復讐という形で現れるのが少ないのでは、←閉塞感の原因
いやむしろパワハラその他も含めて、その相手に対してのストレートな憎悪は歪められ
「むしゃくしゃしてやった」等の理由での、「不特定多数」もしくは、自分より弱い者、
あるいは本当に最悪な場合これは「自分」に向けられるのでは、と思うのです。
東野圭吾作品が好きなのは、このご時世には、左だの右だの何か大きな物語を思想的バックボーンにした方が得とか
そういう事やりがちなんでは…というより、別にそうでなくていいものまで、それに照らし合わせて分別が行われてしまうのでは
と、思ったりする所、実にクールに、ひたすら「小さな物語」を庶民の視点、庶民の目線で描いていく、そんな所です。
長いものには巻かれない。
全てのキャラクターに「生活」かかってる感がいいです。
あらすじは冒頭で殺人、マスコミが報道するそれらしい犯人、しかし加賀には疑問が…という王道であります。
科学知識を駆使していないと解くことのできないトリックのようなのはありません。
しかし、テーマがすごく明確です。
これは小さくて大きい、「ダイイング・メッセージ」の話なのでしょう。
それと、作中ではむしろしつこく掘り起こされる事はないのですが「殺人の動機」
私はこれにかなり「!」と思いました。
近年、推理物はトリック重視になってきた感があるのですが、
松本清張のファンである私はやっぱり昭和ながらの「殺人の動機」というのに興味があります。
もちろん、推理小説の楽しみ方は、「動機はどうでもいいからトリック」というのもあるんでしょうが
トリックなんてパターンがあるし、謎という点で一番大きい謎は、人の心だと思うのですよ。
そして、その時代、その人の立場によって、「動機」は大きく揺れ動くのではないかと。
「恐れと保身」
これからこの作品を読んでみたい方は、どうかこの2つのキーワードを胸にと思います。
東野圭吾の作品に許し難い極悪非道の、絶対的悪人は出てこない。
けれど、鋭い社会眼で「絶対に許し難い悪」はごく身近に、それもかなりの透明度を持って存在している。
21世紀の現代の日本では不幸な事に、かつては殺人の動機になっただろう「大事にしていたものが傷つけられた、大事なものを失った」
なんていう方が日常茶飯で些末な事で
フツウと呼ばれる、日々生きる人達は「そんなの誰にでもある。でも乗り越えていかなければならない」として生きているのでは。
その代わりに動機になり得るのは、「自分の立場が脅かされるのでは」という不安。
「ヤバいことになる」のヤバいとは自分1人では使われない言葉なんだなあ、とも思いました。
ヤバいのは、「自分はもちろんの事」というその先の関係がある。
殺人事件なんてものは人がなすものであって、神の業ではないですから。
そういや司馬遼太郎もそんな所あるなあと思うのです。歴史なんて所詮人が動いて作ってきたものですから、と。
ただ、その「小さな物語」はなんて、場所や人や背負うものによって必死であり
概念で1つに括る事ができないものなんだと。
そのクールな人間観察眼たるや。
人が残すメッセージなんて結局は、理屈や理想で宙を斬るようなものではなくて
しっかりと誰かに渡したいもの、なんでしょうね。きっと。