
みなさんこんにちは、以前カンボジア事務所に勤務していました平野です。だいぶ以前になりますが、カンボジアの学校にはあまりトイレがないこと、そしてそれがカンボジアにおける女子教育の普及の妨げになっていることに触れたことがありました。今回もう少し詳しく説明させていただいて、さまざまな形の子どもたちの通学支援、そしてそれを通じた人身売買、児童労働の撲滅があることをお伝えできたらと思います。
【低いトイレの普及率と高い生徒の年齢】
世界銀行のある報告書によると、カンボジアの小学校でトイレのある学校は35%ということです。つまり多くは校舎のみなのです。水道のない農村部ではなおさらでしょう。農村部では、遅い入学と留年が珍しくないため、小学校にいる子どもたちの年齢はいろいろです。8歳で入学する子もいますし、ある小学校には17歳で結婚している6年生もいました。学校にトイレがないことは、やはり女子生徒たち、とりわけ月経のある女子生徒にとって学校に行くことに対する妨げになっているのです。このことは、安全な水と衛生設備へのアクセスをテーマにした最新版の国連開発計画の人間開発指数報告書でも指摘されています。また、世界銀行の報告書は農村部に女性の先生が少ないことも指摘しているのですが、このような農村部の学校の設備状況も影響しているのではないか、と思われます。
【児童労働、そして人身売買への影響】
児童労働は長らく貧困とダイレクトに結びつけられてきましたが、最近ではそれ以外にもさまざまな原因があることが指摘されています。その中で、学校の質、教育そのものと設備の両面での質、も児童労働の発生に少なからず影響のあるものと言われています。例えば学校にトイレがないことで嫌な思いをした子どもが学校に行かなくなってしまったときに、ひどく貧しい家庭ではなかったとしても、「だったら働きなさい」ということになる場合などです。そしてそれが女の子の出稼ぎだったりすると、人身売買をはじめとしたさまざまな危険に遭う可能性が増してしまうのです。もちろん学校におけるトイレの有無を直接人身売買に結びつけることはできません。しかし、みなさんの生活同様カンボジアの農村部の生活、そしてその中で人々が下していく判断にも多様な背景があり、トイレの問題もまたその一つの要素なのです。
【保健衛生の観点から】
排泄行為を衛生的に行わないことは下痢などの病気の原因になり、適切な医療が受けられないことが多い農村部では、これは大きな危険につながります。あるユニセフの保健衛生啓発パンフレットには、幼い子どもたちの死亡や病気の原因の半分以上は、不衛生な食べ物、水、あるいは手を通じて口に入るばい菌によるものだ、とあります。こうした状況を受けて、政府や国際機関、NGOはTVでのキャンペーンや村でのワークショップなどを通じて衛生管理の意識啓発をしています。そんな中で、学校の設備や環境は「隠れたカリキュラム」と言われます。授業で説明しないことからも子どもたちはさまざまなことを学ぶからです。マイナスの面を言うと、トイレがなく先生も校庭の隅で用を足している学校では、子どもたちに衛生管理の大切さを教えるにも限界があるということにもなります。逆を言えば、適切に管理された衛生施設があれば、子どもたちが手洗いなどの適切な衛生的行為を学び、実践していく場にもなるということです。また、トイレ建設を支援の一環とする場合は、トイレが欲しいかどうか、欲しいならばどのように維持管理できるかなどを子どもたちと考えていくことで、責任や協調を教えながら子どもたちをエンパワーしていくよい機会にもなるのです。
国際子ども権利センターが支援しているプロジェクトでは、以上のような観点から、子どもの人身売買・性的搾取・児童労働を防止する目的で、トイレ建設を支援しています。
久しぶりの投稿となりましたが、学校へのトイレ建設支援の意義について、あるいはカンボジアの貧しい農村が抱える問題の多様性について考える上での参考になれば幸いです。
写真は国際子ども権利センターの支援で学校に建設されたトイレです。
子どもたちが学校に通い続けることができるために
http://jicrc.org
【低いトイレの普及率と高い生徒の年齢】
世界銀行のある報告書によると、カンボジアの小学校でトイレのある学校は35%ということです。つまり多くは校舎のみなのです。水道のない農村部ではなおさらでしょう。農村部では、遅い入学と留年が珍しくないため、小学校にいる子どもたちの年齢はいろいろです。8歳で入学する子もいますし、ある小学校には17歳で結婚している6年生もいました。学校にトイレがないことは、やはり女子生徒たち、とりわけ月経のある女子生徒にとって学校に行くことに対する妨げになっているのです。このことは、安全な水と衛生設備へのアクセスをテーマにした最新版の国連開発計画の人間開発指数報告書でも指摘されています。また、世界銀行の報告書は農村部に女性の先生が少ないことも指摘しているのですが、このような農村部の学校の設備状況も影響しているのではないか、と思われます。
【児童労働、そして人身売買への影響】
児童労働は長らく貧困とダイレクトに結びつけられてきましたが、最近ではそれ以外にもさまざまな原因があることが指摘されています。その中で、学校の質、教育そのものと設備の両面での質、も児童労働の発生に少なからず影響のあるものと言われています。例えば学校にトイレがないことで嫌な思いをした子どもが学校に行かなくなってしまったときに、ひどく貧しい家庭ではなかったとしても、「だったら働きなさい」ということになる場合などです。そしてそれが女の子の出稼ぎだったりすると、人身売買をはじめとしたさまざまな危険に遭う可能性が増してしまうのです。もちろん学校におけるトイレの有無を直接人身売買に結びつけることはできません。しかし、みなさんの生活同様カンボジアの農村部の生活、そしてその中で人々が下していく判断にも多様な背景があり、トイレの問題もまたその一つの要素なのです。
【保健衛生の観点から】
排泄行為を衛生的に行わないことは下痢などの病気の原因になり、適切な医療が受けられないことが多い農村部では、これは大きな危険につながります。あるユニセフの保健衛生啓発パンフレットには、幼い子どもたちの死亡や病気の原因の半分以上は、不衛生な食べ物、水、あるいは手を通じて口に入るばい菌によるものだ、とあります。こうした状況を受けて、政府や国際機関、NGOはTVでのキャンペーンや村でのワークショップなどを通じて衛生管理の意識啓発をしています。そんな中で、学校の設備や環境は「隠れたカリキュラム」と言われます。授業で説明しないことからも子どもたちはさまざまなことを学ぶからです。マイナスの面を言うと、トイレがなく先生も校庭の隅で用を足している学校では、子どもたちに衛生管理の大切さを教えるにも限界があるということにもなります。逆を言えば、適切に管理された衛生施設があれば、子どもたちが手洗いなどの適切な衛生的行為を学び、実践していく場にもなるということです。また、トイレ建設を支援の一環とする場合は、トイレが欲しいかどうか、欲しいならばどのように維持管理できるかなどを子どもたちと考えていくことで、責任や協調を教えながら子どもたちをエンパワーしていくよい機会にもなるのです。
国際子ども権利センターが支援しているプロジェクトでは、以上のような観点から、子どもの人身売買・性的搾取・児童労働を防止する目的で、トイレ建設を支援しています。
久しぶりの投稿となりましたが、学校へのトイレ建設支援の意義について、あるいはカンボジアの貧しい農村が抱える問題の多様性について考える上での参考になれば幸いです。
写真は国際子ども権利センターの支援で学校に建設されたトイレです。
子どもたちが学校に通い続けることができるために
http://jicrc.org



















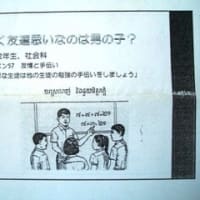
児童労働に至る背景には様々な原因へ繋がる糸がある。
それを1本づつ手繰っていけば、或いは、
2回3回と手繰らないと到達しないかも知れない、
そうすると"原因"が各々見えてくる。
大変地道かつデリケートな作業になるんだろうと
想像されますね、でも誰かがやらなくてはいけない。
例えば僕たちが。
その"原因"の一例で挙げていただいている
トイレの件。
学校の衛生設備を整えて、そこで生徒たち自らが
考え実践してもらうことで、衛生面の向上を図り、
同時に集団生活における規律なども学ぶことになって
子ども達がエンパワーメントされる。
それは、分かります。
ただ、レポートを読ませていただいて
真っ先に素朴に疑問に思うことは
「トイレがない学校がある」
という事実の存在です。
どうして学校建設の際に、
その点が考慮されていなかったのか???
本当に素朴に疑問に思います。
予算的に後回しにされていたんでしょうか。
このケースの根本原因がよくわからないんです。
私も初めはびっくりしました。
たぶん、内戦後、とにかくたくさんの学校を至急建設する必要があり、予算が限られたなか、トイレは後回しになったのではないでしょうか。実際、現在でも、カンボジアの何と83%もの人がトイレなどがない、非衛生な環境に住んでいます。(ユニセフ子ども白書2007年)その割合は、東南アジアでカンボジアが最も高いかもしれません。
家にもトイレがない状態のなか、学校につくる必要を感じなかったということもあるのではないでしょうか。
8割以上・・・
自分の家にもない環境というのは ちょっと想像を絶する状況ですね・・・
今の日本に長い間住んで染み付いた常識の上で物事を見てしまうとショックを受けることがあまりに多いです(先の中川さんのレポート、法廷内で拳銃を振り回す者がいたとか、路上強盗における警察の対応等々)。
そういう意味からも、この「カンボジアだより」というのは、色付けのないほんとうのカンボジアの状況を伝えてくれ、読者に大きなインパクトを与えて色々と考えさせてくれるものとして貴重な存在だと、そう思いました。
日々私たちが何の気なしに使っているトイレというものの重要性をあらためて考えさせられました。トイレを設置することを通じて、さまざまな教育の機会も生まれるのですね。
国際子ども権利センター、カンボジア事務所の近藤 千晶と申します。
カンボジアの学校にトイレがないことに関連する補足をさせていただけたらと思います。
日本では当たり前にどこでもトイレがあります。そして当たり前に水もあります。カンボジアの学校にトイレがあったとしても、水がなければ、手を洗うこともできません。トイレで水を流すこともできません。カンボジアの一般的なトイレには紙はありません。男性も女性も紙は使わず、水で洗います。
この水の確保が大変難しい地域もあります。特に乾季のとき。水がなければ、トイレを使うことはほとんどないでしょう。トイレがあっても水がないために使われていないトイレをみたことがあります。学校によっては子ども達が使うと汚すから、汚したあと、掃除に使う水がないから使えないというのも聞いたことがあります。トイレが壊れてしまって修理費がないから修理できないという学校もあります。せっかく海外からの支援、好意でできたトイレも一度壊れてしまったら使えません。(学校の予算、その後の支援者からの関心にもよりますが)
水がないなら井戸を掘ればいいと思われますが、井戸を掘る水がないこともしばしばあります。お金があったとしても水がそこにでるかもわかりませんので、水脈検査をする必要があります。トイレがあっても水がなければ保健衛生もできません。プノンペンの街中は日本のように水道があります。でもちょっと離れたらもう水道はありません。みんな大きな水がめに貯めています。せっかくあるトイレもいろいろな事情で使われていないところもあるのです。日本にいると当たり前のことがこちらでは当たり前ではないことがたくさんあります。こちらに住んでいると日本ではたくさんの資源(または水)を無駄に使っているのではないかと気になることがあります。
近藤さんがおっしゃられている通り、
確かにカンボジアを見てから日本を振り返りみてみると、「MOTTAINAI」ことが多そうです。
1回でバケツ何十杯分の水が消費される日本のトイレ・乗る人もいないのに動いているエスカレーター・人もいないのに点いている室内灯、等々。
日本に住んでいる私たちは、カンボジアを見ることで改めて気付かされる無駄なことって結構あるのかも知れませんね。反省・反省。。
そういえば随分以前TVで見聞きしたことがあります。
それはボランティアで農機具や医療器具を寄付したけれども、維持管理できる者がいないので、一旦壊れてしまうと、そのまんま放置され利用されなくなっている現状をリポートした内容でした。
今考えれば、そういうボランティアの在り方は、無責任極まりないものだ、と考えさせられます。