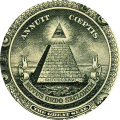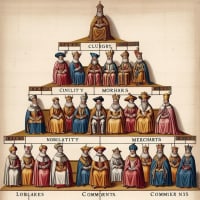ここまで法華経に関する事の考察を続けてきた。そこで見てきたのは、一念三千と久遠実成という教理について、これは単に大乗仏教の延長線上にあるというものでもなく、実は近年になり西欧文化の中でも類似した事が語られ始めているという事から、やはり人の心の本質として普遍的な事を含んだ教理ではないかと言う事だ。であればこそ、自行の為に勤行要典として法華経が読誦される事にも、それなりに意義があると言う事だろう。
しかしこと勤行について、本尊はどうなのだろうか。大石寺や創価学会、顕正会に於いても本尊として日蓮の文字曼荼羅を用いている。この日蓮の文字曼荼羅を本尊とする事に、どの様な意味があるのか、いや、そもそもこの日蓮の文字曼荼羅とは如何なるモノなのか。そこについて少し思考を向けてみたい。
本尊とは根本尊敬という言葉略語で、宗教で尊ぶ対象を指す言葉だ。
日蓮宗系では本尊としてこの文字曼荼羅を採用している。まあ信仰者としての立場で「採用している」という言葉で言うのも如何なものかと思うが、取り敢えずその様に言っておく。但し日蓮宗ではこの文字曼荼羅以外に釈迦仏像を本尊としたり、同じ境内内には大黒天や鬼子母神を祀り、日興師が晩年まで居所とした重須本門寺には天照大御神の社もあったりする。
そもそも日蓮がどの様な本尊観を持っていたのか、少し日蓮の御書を振り返ってみる。
「問うて云く法華経を信ぜん人は本尊並に行儀並に常の所行は何にてか候べき、答えて云く第一に本尊は法華経八巻一巻一品或は題目を書いて本尊と定む可しと法師品並に神力品に見えたり、又たへたらん人は釈迦如来多宝仏を書いても造つても法華経の左右に之を立て奉るべし、又たへたらんは十方の諸仏普賢菩薩等をもつくりかきたてまつるべし」
(唱法華題目抄)
この御書は日蓮が立宗宣言以降、初期の頃の御書だが、ここでは法華経八巻もしくはお題目を本尊とする事が書かれていて、もし余裕があるのであれば、そこに釈迦多宝二仏像を左右に置き、普賢文殊菩薩像を置くことを述べている。
「日本乃至一閻浮提一同に本門の教主釈尊を本尊とすべし、所謂宝塔の内の釈迦多宝外の諸仏並に上行等の四菩薩脇士となるべし」
(報恩抄)
ここでは「本門の教主釈尊を本尊とすべし」とあり、これは宝塔内の二仏を本尊とする事だと言う。そしてその他の諸仏や地涌の菩薩を脇士とする事が述べられている。
「問うて云く末代悪世の凡夫は何物を以て本尊と定むべきや、答えて云く法華経の題目を以て本尊とすべし」
(本尊問答抄)
この本尊問答抄は弘安期に書かれたものだが、日蓮が晩年になった時には明確にお題目を本尊とすると書かれている。しかし文永元年に四条金吾が釈迦仏安置の際、日蓮に開眼供養を相談し、それに対して木絵二像開眼供養事という御書を認めて、仏像の意義について述べていた。ただ佐渡流罪以降という事もあるのだろうか、本尊問答抄をみるとそこには明確に法華経の題目を以って本尊とすべしと書かれているのである。
日蓮が文字曼荼羅を完成させたのは何時頃なのだろうか。現存する文字曼荼羅を確認していくと、初めて文字曼荼羅として顕されたのは「楊枝本尊」というもので、こちらは文永八年十一月に顕され、現在は京都の立本寺に所蔵されている。この文字曼荼羅は楊枝の先を砕いて筆の様にして認められたという事から、この様な名称がついているが、相貌はというと中央にお題目が認められており、その両脇に愛染明王、不動明王を著す梵字があるという大変簡素なものだ。日蓮の文字曼荼羅で現在の相貌に近いものは文永十一年六月に顕された沙門天目授与の本尊で、こちらは現在のところ京都府の妙満寺に所蔵されている。
文献的に調べてみると、文永十年に佐渡始顕本尊があると言われているが、こちらは明治八年(1875年)に発生した身延大火で焼失されたと言われており、現在では身延二十一代日乾が模写した本尊が現存するだけであり、真筆は既に存在していない。しかし文永十一年にも楊枝本尊が顕されており、こちらも先の楊枝本尊同様、中央の主題のお題目と左には「四大天王」、右には「日月衆星」と認められた簡素なものなので、恐らく日蓮自身も文字曼荼羅については試行錯誤を佐渡流罪前後にしていたのかもしれない。
以前、大石寺では一閻浮提総与の大本尊こそ「万機万縁(すべての人に与えられた本尊)」と言い、それ以前の日蓮の文字曼荼羅については全て「一機一縁(一人のために与えた本尊)」と呼んで立て分けしていた。しかし日蓮はそのような立て分けを考えていたのだろうか。そもそも近年になり大石寺の大本尊は後世の作とされ日蓮が認めたものではないとされている。
また創価学会では2014年の会則改正に伴う教義変更で、日蓮直筆のものは全て「事の本尊である」とし、どの本尊を祈る対象にするかは創価学会が決定すると言っているが、その解釈は果たして正しいものなのだろうか。
私が思うに文字曼荼羅を本尊とするのは良いが、日蓮自身はその文字曼荼羅を全ての信徒に授与する事を果たして考えていたのかという疑問がある。何故ならば現存する日蓮直筆の文字曼荼羅は123体あるが、その多くは現在寺院に保管をされており、在家信徒宅に所蔵されているのは数が少ない。これはつまり日蓮は信徒に対して頻繁に配布していたのではない事を伺わせるからである。
そこから考えると日蓮の本尊観というのは、やはりお題目を主題にするという考え方はあるものの、当時の信徒の中には四条金吾の様に法華経の経巻と共に釈迦仏像を置いて本尊としていたりするなど、文字曼荼羅だけを本尊として安置するという考え方は無かったのではないかと、私は考えているのである。
あと一つ。この文字曼荼羅の本尊の事について、日蓮の御書で初めて書かれたのは「如来滅後五五百歳始観心本尊抄」となっているが、ここでは「観心本尊」と述べている事から、この文字曼荼羅はもしかしたら観心の修行をするための本尊であったのではないだろうか。そうであれば出家した門下や一部在家の信徒に与えたとして、広く信徒に与えるものではないだろう。
観心の修行とは天台宗で言えば内観の修行であり、日蓮が表に出した「一念三千」という教理についても、天台宗では内観行を行う際の指南として教えていた事であり、魔訶止観などには一切明かされていなかった。その事も併せて考えてみると、この文字曼荼羅の本尊としての位置づけは、現在、大石寺や創価学会、顕正会などが考えて行っている事とは、全く違う事だと私は考えているのである。