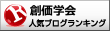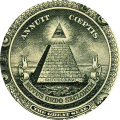さて、三惑について続けていきます。先のページでは「見思惑」という事で、これは物事の捉え方などが間違えているが故に、様々な迷いが出てしまうという事でした。今回は「塵沙惑」になります。
◆塵沙惑について
塵沙惑とは何か。これをネットで探すと創価学会関係のものが多く検索されますが、それらを私は引用しません。青木隆氏の「天台智顗における三惑について」という論文がありますが、そこではこの塵沙惑については以下の様に述べています。
「塵沙の惑は菩薩の化他行の障碍になるものであることが知られる。」
つまり菩薩が化他行を実践する際に、塵沙(塵や沙の様に細かな様々な迷い)の様な迷う心を塵沙惑と言うそうです。そしてこの先の「無明惑」についても同様に菩薩が持つ迷いと言われています。
菩薩というのは「菩提薩埵」の省略とも言われていますが、仏教に於いては仏の教えを人々に弘め、衆生救済を実践する姿を呼びます。法華経によれば久遠実成の釈尊と言えども、この娑婆世界では菩薩道を行じる姿として現れていた事が明かされていました。「我本行菩薩道」という言葉がそれに該当します。
仏教とは釈迦の説いた教えを基にした宗教です。だからその教義の基礎はやはり釈迦の来し方が影響している事でしょう。考えてみれば先の「見思惑」とは、極めて個人の内面的な迷いと言っても良いのではないでしょうか。釈迦も伝説によればこの世界は苦悩に満ちている事を感じ、そこで出家を決意する訳です。そして出家の後、その苦悩の根源について思索を続けます。そして苦行林に行き、苛烈なまでの苦行を行った後、その苦行では答えは得られないと確信し、苦行林を去る訳です。そして菩提樹の下に結跏趺坐して瞑想し、夜明けの明星を見た時に悟ったと言われています。ただ悟った直後の釈迦は、人々にその悟った内容を語る事はせず、自分自身で楽しんだと言われています。
この段階で断じた惑とは「見思惑」なのかもしれません。
しかしその後、伝説では「梵天勧請」と言われていますが、大梵天王が釈迦の前に出現し、多くの人々に悟った法を説く事を求めます。そしてその求めにより釈迦は人々の中に法を説き始めました。
まあ伝説では「梵天勧請」と言われていますが、恐らく釈迦の中でも逡巡したのかもしれません。自身の知り得た内容を、人々の中に説きだす事の難しさ、それに付随する様々な労苦。聡明であった釈迦であれば、これらの事を当然考え、悩んだはずです。そしてこの悩み苦しんだ事が、まさに「塵沙惑」の一分であった様に私は思うのです。
◆無明惑
次に三惑の最後、無明惑について紹介します。無明惑とは「成仏を妨げる一切の煩悩の根本となる惑のこと。菩薩だけが断尽することができるとされるところから、別惑ともいう。」というものです。無明とは人の心の根源にある迷いで、全ての迷いとは無明から派生しると仏教では説いています。
そして迷いの根源にある無明は、菩薩だけが断じる事が出来るというのは、つまり心の中にある根源の迷いというのは、他者との心の関わりによってのみ、断じる事が出来ると言うことなのでしょう。
釈迦も実は「三惑已断」といい、これら三惑を断じたと言うのも、いわゆる「開悟(悟りを開く)」ときに断じたと言うことではなく、もしかしたら生涯を通じて、これら心の中にある「迷い」と向き合い、乗り越える努力を続けた人であったのではないでしょうか。この三惑という事を振り返ってみると、私はその様におもえてなりません。
つまり人が人生の悩みや苦しみを乗り越えるためには、他者に対して関わることが大事であり、その中にこそ苦しみの超克があるという事なのかもしれません。振り返ってみれば、人が悩み苦しむ時、往々にして自分自身だけに目を向けて、そこから脱却する事に苦心惨憺しますが、この三惑という考え方からすれば、悩みを持つからこそ、より人に寄り添うという姿勢が重要だと言うことなのでしょう。
(続く)