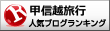日本天文学会投稿原稿 案 日本語版 図は省略しました
概要
日本国山梨県北杜市にある
縄文時代の遺跡・金生遺跡には、40メートルの大配石遺構があります、その中に石棒が立てられてあり、太陽暦観測施設となっていることが分ってきた。観測点は八節の暦の立春、立秋、冬至であることが判明した。
また各観測点にはランドスケープとして対応する山が設定されている。遺跡の立地については、太陽運行を表示するアナレンマ解析によってもシミュレーションされて、同様な結果となっている。
遺跡の立地からも遺構からも太陽暦が示されているので、縄文時代後期には太陽暦が確立していたものと推測できる。このことからは、縄文時代のかなり早い時期から太陽暦の開発が進められていたものと推定出来る。
立春、立秋の暦日 2点が観測されていた理由は、太陽暦と太陰暦をシンクロさせるために観測が行われ、二つの暦は地域により平行利用していたものと推察する。
また遺跡が示す暦日は基本的に現代の太陽暦と一致していることから、太陽の運動は4500年前から変わっていないことが初めて立証されるものと考える。
序論
縄文時代に太陽暦が存在した事に関して、遺跡の遺構として八節の暦を示すようなものは見つけられていない。
縄文時代は、狩猟採集による定住をする古代文化で、農耕は無いとされている。太陽暦が存在するとすれば、その必要性は主として農耕にあると考えるので、これまでの既成観念は根底から崩されることになる。
またこれまで世界の何処の文明に於いても、太陽観測により正確な太陽暦が作成されたという遺跡も暦も、今までの所 見出されていないことから、世界の文明史に於いて、縄文時代の太陽暦の存在とその遺構の存在は、これまでの世界史の想定に見直しを迫るもので、文明史理解の上で画期的なものと成ると考える。
1 )観測方法
1.遺跡の立地と太陽運行との関係の観測
2.遺跡に存在する配石と、配石内に存在する石棒が、立地するランドスケープとどのような位置関係にあるのかを観察する。
3.石棒観測点と推測するノーモンの位置と、太陽の運行とには、どのような関係があるのかを観察する。
4.観測は、特定暦日観測には 1日あれば済むものなので、観測に使用するノーモンは、その時のみ設置しての使用となる。ノーモンの高さは、石棒に影が到達する 約 2.4メートルの高さのものを使用する。
2)観測結果
1.立地と太陽の運動の関係
立春の日の出は、通称茅が岳の金が岳から出ることが分った。立秋の日には笠無山からの日の出となる。
冬至の日の入りは甲斐駒ヶ岳となっていた。
こうした観察結果はアナレンマ解析によってもほぼ再現できた。
2.配石の石棒と日の出の関係
配石内で石棒と日の出位置を見通してみたところ、立春、立秋、冬至を示す石棒とそれぞれのノーモン台の位置とが想定できることが分った。また冬至の日の出の初光が配石の北限界となり配石デザインの基準となっていることも分った。
3.八節の暦の暦日の観測結果
配石の内にあるノーモン台と考える位置にノーモンを立て、八節の暦のそれぞれの暦日に日の出を観測して次のような結果を得た。
・現在の太陽暦の立春の日の出には、ノーモンの影は立春石棒に正確に落ちることが分った。
・冬至の日には冬至の石棒の位置にノーモンを立てれば、立秋のノーモン台の位置に影が落ちる。
・立秋は現在の太陽暦の立秋より2日早い暦日に立秋石棒に影が落ちる。
4.ノーモンについて
立春の日の出は高い山の峰から出る、このため立春の日の出観測には高さ 2.4メートルのノーモンが、立春石棒に影を射すためには適切な高さであることが分った。
したがって石棒で 1日程度の精度で暦日を判別するためには、ノーモン台と石棒間の距離22メートルとノーモンの高さはほぼ 2.4メートルが必要である。

3)議論
1.縄文時代の太陽暦は、現在の天文学による暦日とは異なる結果を見せていて、八節暦に暦日が合うことから、縄文時代には八節の暦を計算していたものと考える。
観測点は現代の太陽暦にほぼ一致しているので、これだけ正確な暦を造っていたと云うことから、縄文時代に暦が必要とされていたのは農耕が存在していて、地形や地域の特性に合わせて耕作するための栽培暦作成の必要性からであると考える。
ノーモンについて
ノーモンが何処で何時開発されたのか、現在まで明確にされていない。
金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設の存在から、この時期にノーモンの存在は疑えないものと考える。
これからノーモンの開発は縄文時代の中期以前と考える。
2.縄文時代後期にこれほど正確な太陽暦を造っていたと云うことは、縄文時代後期よりかなり前から暦作りは始まっていたものと考える。
土器を調べてみると縄文時代中期には 3波状突起口縁の土器が造られていたことが分った。また縄文時代後期以後には、5,7波状突起口縁の土器が造られていたことが分った。
特に 3波状突起口縁の土器が造られていた時期には、3を示す土器や土偶が様々に造られていたことも分ってきた。この 3という数は二十四節気の暦を造るときに最終的に利用することになる数である。それは立春日を求めた後に月の暦とシンクロさせるためには45日を 3分割することが必要となるからである。15日は月の暦の朔望日数30日の半分になるからである。
更に調べたところ、縄文時代早期には 2、4、6波状突起口縁の土器が造られていた。また縄文時代前期には 8、12波状突起口縁の土器が造られていた。こうした土器は太陽暦と太陰暦の特徴的な数字を示すものである。
この事から縄文時代早期から太陽暦と太陰暦が造られ始めていたと推測する。
2は一年365日を冬至と夏至で二分割した半年一年暦を示すものと考える。
これは鮭の遡上回帰漁のために、遡上回帰時期を予測するために造られたものと考える。
6は朔望が半年に6回であることを示すもので、海辺の潮干狩りを集団で行うために開発したものである。月の満ち欠けから潮の干満を予測出来る太陰暦が造られたことで、縄文早期から巨大貝塚が造られることになったと考える。
4は月の暦の半年ベースと同様に、半年4分割の暦を作り、季節を知り、春の始、立春を求めて、栽培するマメ類などの種蒔き時期など栽培暦を作るためだったものと考える。
縄文時代前期の 12は、数や計算に関する知識が進化して、365日という数字が扱えるようになり、半年ベースから一年ベースの暦、12月の暦を作ったものと考える。 また 8は同じく一年ベースの八節の暦を造るようになったものと考える。
その後縄文中期には八節の暦から二十四節気の暦に進化、月の暦とのシンクロさせることが成立したと考える。
さらに 5,7の数からは、太陽暦は七十二候のカレンダーが造られ、太陰暦は 7日一週間の暦が造られたものと考える。こうしたことは生業を進めるための作業暦として使い易いものに工夫されて使用されていたものと考える。
3.金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設建造の意味
暦日観測点は二十四節気でも七十二候のカレンダーでも立春観測を行えば暦は正確に作成できる。
それなのに金生遺跡で発見した観測点は、立秋観測点が存在した。何故なのか、それは月の暦と正確にシンクロさせるためには、半年ベースで月相を観測する必要があったものと考える。
海辺の地域と内陸で暦が使い分けられていたとすれば、立春で暦日を合わせても、半年後の立秋には太陽暦と月相の変化にはズレが生じてしまうので、例えば祭の期日を決めていても太陽暦地域と太陰暦地域では日にちがずれてしまい社会生活に不都合が生じてしまう。それを防ぐためには春と秋の作業日程を正確に保つ必要があることから、立春と立秋とで時計合わせをしたものと考える。
4.縄文時代早期に暦が造られていたとすると
縄文時代には、世界の古代文明の何処よりも早く太陽暦と太陰暦が開発されていたことになる。
古代文明の開始は何れも7000年前頃からであることから、縄文時代の暦の知識が世界各地に伝わっていたとの推測が生まれる。
金生遺跡・大配石は40年前に発見発掘されていた。この時に縄文時代に暦は無かったという先入観無しに立地と太陽の関係を調査していれば、今回の発見はその時に出来ていたはずである。残念なことはこの期間に中華人民共和国により、二十四節気の暦がユネスコ世界遺産に登録されてしまったことである。
しかし、今回の発見は日本全国各地に於いて考古学者の地道な発掘作業と記録、展示が行われてきた成果によるものであること、その正確な復元と記録の努力に対して賞賛とお礼を申し上げる。
5.縄文時代・新石器時代の生業開発の歴史
暦開発の歴史記録があることから、縄文時代草創期から土器に残された縄文という造形記録から新石器時代の生業開発の経緯が解明できる可能性があると考える。
縄文土器に残されている模様は、単に模様を付ける目的で作られた道具を使用したのでは無く、
生業のために開発した道具を使用した記録であると考える。
したがって土器、弓矢、釣り糸、漁網の開発は縄文時代草創期から前期までの縄文土器時代に行われていて、縄文土器に造形して記録されていた可能性があり、縄文土器から新石器時代初めの生業開発経緯の歴史が解明できる可能性があると考える。
4)結論
1.金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設では太陽暦 二十四節気 の暦日 すなわち冬至、立春、立秋が観測されていたことは確実である。
この観測点はランドスケープの山によっても示されていること、またアナレンマ シミュレーションによっても再現されているので、太陽運行を縄文人が認識していたことは明白である。。
2.縄文時代に太陽暦が必要となり開発されていたことは、農耕が行われていて、その要請から地域毎の特性に合わせた栽培暦を作るためという可能性が極めて高いと考える。
3.縄文時代の太陽暦の開発
太陽暦開発の歴史的経緯は土器に数が記録されていて、歴史経過が辿れるものであり、それは世界史上でも、文明史の中でも最も早い時期の記録であると考える。
「文明とは」の定義は現在明確にされていないが、過去・現在から未来を予測する暦開発は思考活動の画期であることから、これこそが文明の開始の判定基準であると考える。
4.現在世界標準時と子午線がグリニッジに置かれているが、縄文時代の太陽暦観測の遺跡の存在から、それは金生遺跡に移すことが良いのでは無いか。
5.金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設は太陽の運動が4500年前から変わっていないことを証明する初めてのエビデンスでは無いか。
5)付録
1.大配石と異形の土偶 金生遺跡 新津健 新泉社
2.金生遺跡を世界遺産にしよう会 https://blog.8goo.ne.jp/johmonkinseistar
表示するには 8 を除いてご覧ください。!!!