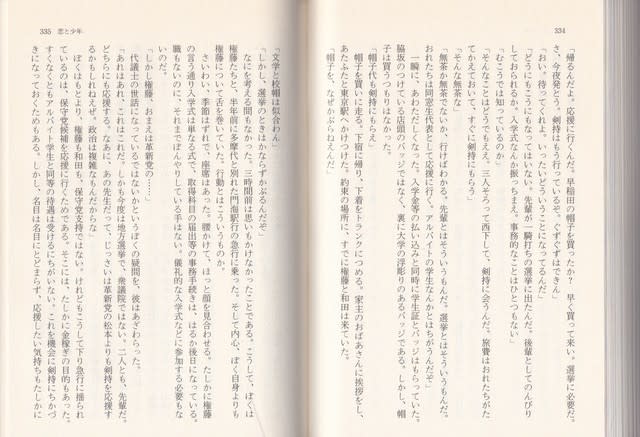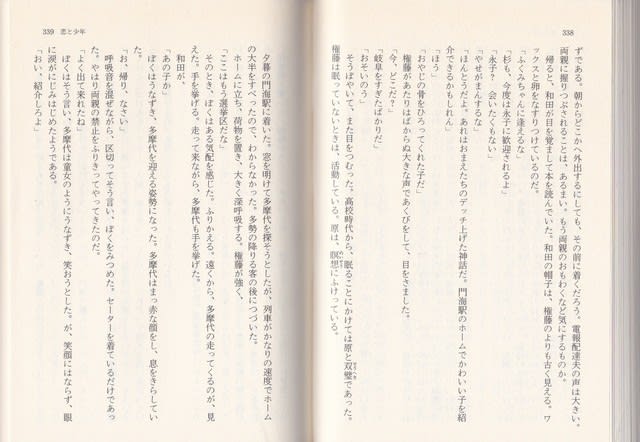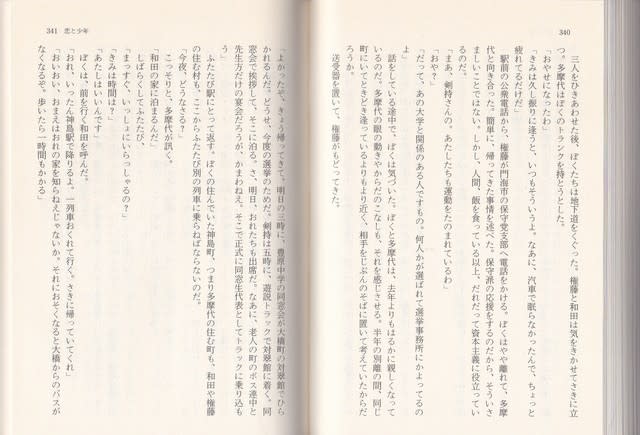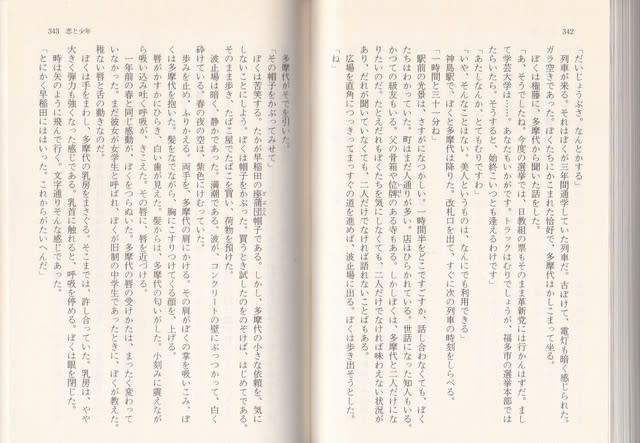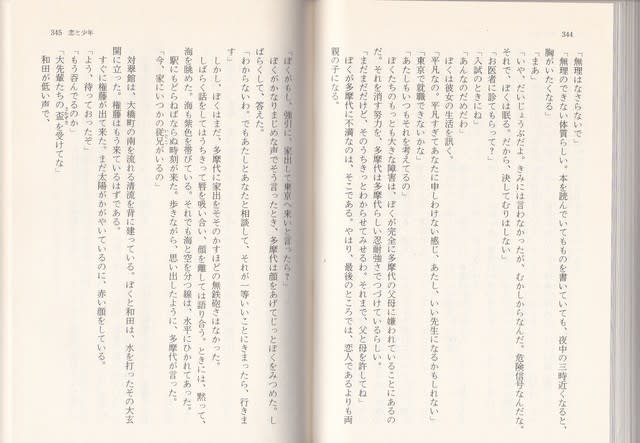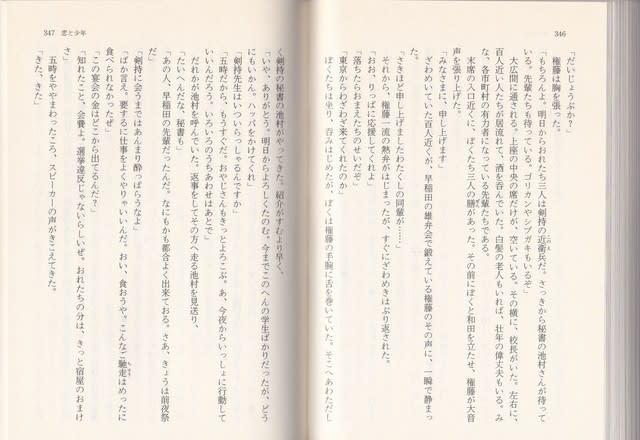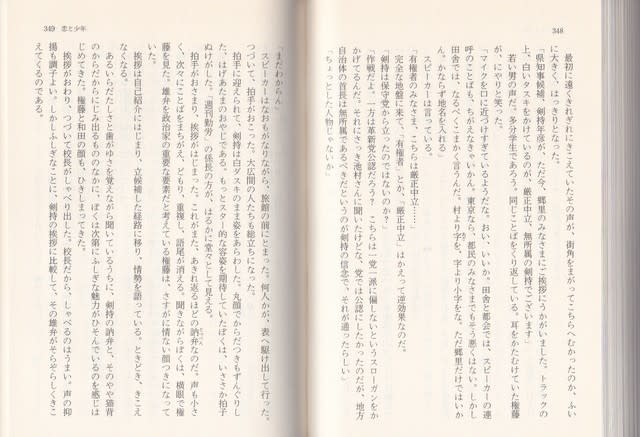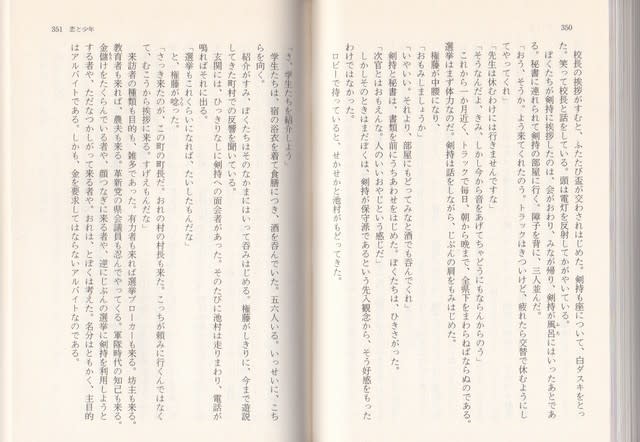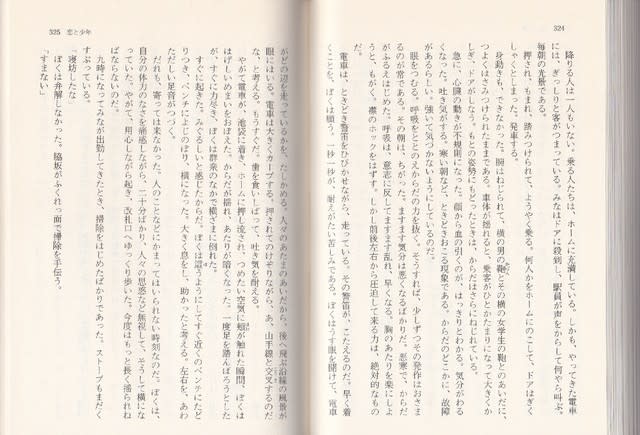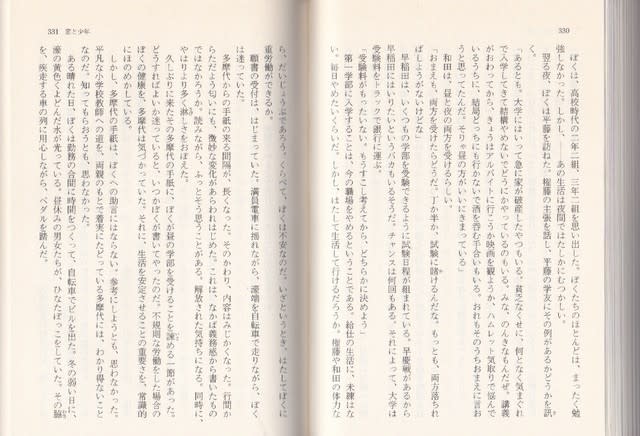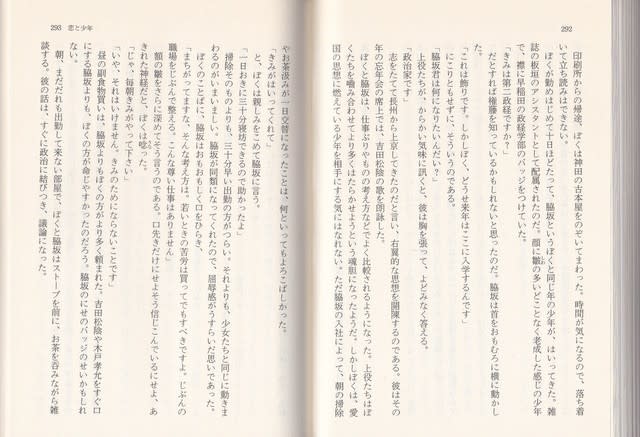・・・・・この作品は、1963年5月河出書房新社より刊行さた長編作品ですが、自らの青春体験を基幹と
した初期作品の代表作です。富島健夫の初期作品は、《青春》をテーマとしての基本姿勢を踏まえて
《青春の心》を描き出してきた作家である。他の作品で【雪の記憶】・【故郷の蝶】・【故郷は遠きにありて】
・【夜の青葉】・【明日への握手】等々の基幹となる自伝的要素の強い作品ではないだろうかと思う。
富島健夫が、主人公(杉良吉)の名を借りて終戦直後から昭和二十年代後半の時代背景の中での
少年期からの青春群像を描き出している。終戦前まで日本の植民地であった地からの引き揚げ者、そして
貧しく空腹と孤独感のなかでの思春期を学制改革の施行を機に新制高校二年となって男女共学の学生
時代を過ごしてゆくのである。主人公の成長とともに変化してゆく女性像や空想の中で女性(少女)と遊び
現実の女性とのギャップの中で生まれて初めて恋を告白する。また、他の女性関係が綴られる時の失恋
もある。・・・富島健夫は「青春の心は、生きてある限り消えぬものである。ゆえに、ぼくは生きてある限り
青春の心を文章に表現していこうと決意している。」とあとがきしている。この作品の解説者 清原康正氏の
文を引用させていただくと、富島健夫は、この永遠の普遍性ともいうべき《青春》を《不易流行》と表現して
《不易=永遠に変わらぬ本質的な感動》と《流行=時々新しい事を求めて移り変わるもの》そして、「人間
には、不易と流行があり、不易なる真実は、千年を経ても不易であって、もともと小説はそこに視点を据える
べきであって、流行はどうでもよいのである。」(【夜の青葉】のあとがき)・・・したがって、不易なるもの
それは《青春の心》でありそこに視点を据えて自らの青春体験を投影させることで彼の内部に《青春の心》
が常に存在し続けていることを示すものだ。
1951年生れの私は、自身の青春時代と重ね合わせてみても世代を越えて《不易と流行》である《青春
の心》に感銘を受ける次第です。
やはり、時代が違っていても同郷という生活空間で少年期から青春期を過ごす中での《青春の心》は、
何ら変わりはありません。私にとって、この作品の中に描写されている主人公の具体的な行動が良く解り
、身近に感じられるのです。特に(8)P137~P157が印象に残っています。・・・・・
※【作品文中引用転載】
・・・・・・・・・・・その年の正月三日は、晴れていた。ぼくは平藤と駅で落ち合った。文芸部の新年宴会
が、部員の黒石の家でもよおされるのである。黒石の家は、山奥の村にあった。黒石の父は、そこの村長
である。黒石は一人息子で、どんなわがままでもきく。そこがぼくたちのつけ目だった。部員たちのささや
かな会費と、ぼくと石崎(先生)が苦心して部費から捻出する金額では、酒豪のそろった宴会がすむわけ
はない。後は村長さんに任せようというのである。黒石は三年だが一組で、お坊ちゃんで、どうして文芸部
にまぎれこんできたか、わからない。大橋駅(行橋駅)で落ち合ったぼくと平藤は、うなずき合った。
「よし、買うか」 山奥のその集落行きのバスに乗る前に、ぼくと平藤は煙草屋の前に立ち、堂々とピース
を一個ずつ買った。マッチも買い、ポケットにしまう。高校生でも、飲酒は大目にみられている。厳禁されて
いる喫煙を同時に断行しようと、かねがね約束していたのだ。
買ったピースを、ぼくたちは宴会なかば、石崎(先生)の前で取り出した。周囲に、男女の部員たちが
居流れている。平藤は気取った手つきで煙草を口にくわえ、マッチをすった。ぼくもそれをまねた。
「先生」 石崎を呼んだ。石崎は、ぼくたちを見て、目をまるくした。ぼくたちは紫煙をくゆらせはじめる。
そのうち、ぼくは大きく煙を吸った。ややからい感じがしたが、予想したほどでもない、あたまがぼんやり
となり、いい気持ちになった。眼がかすみ、上体がゆれた。息を吐く、眼が見えはじめ、気分は普通に
もどった。
「ほう、ピースだのう。わしに一本くれ」石崎はそう言い、ぼくと平藤は一本ずつを献上した。石崎は
うまそうにそれを吸いはじめる。煙草を吸いながら、ぼくは少女たちの反応をうかがった。永子は知らぬ
顔をしていた。ほとんどの少女たちがそうである。非難している眼もあった。玲子がそのまっ黒な大きな
眼におどろきをあらわして、ぼくをみつめていた。他に原や和田そして西中もこころみる。・・・・・中略・・・・・
ともあれ、担任教師や善良な女生徒たちの前ではじめて煙草を吸うという革命的な所業は、芝居好き
の心》に感銘を受ける次第です。平藤の思いつきそうなことであった。ぼくはそれにひきずられたのだ。
石崎がぼくたちをとがめないことは、最初からあきらかであった。
石崎よりも、ぼくは永子をより多く意識していた。そこには、永子に拒否されつづけているぼくの、自虐
的な快感があった。ざまあみろと叫びたい気持ちである。何がざまあみろか、ざまあみているのはじぶん
ではないか。・・・・・中略・・・・・その黒石が、まっさきに酔っぱらった。彼は常になく積極的に歌ったり
しゃべったりしていたが、やがて一人の少女の肩を抱いて、ぼくや石崎と話をしている村長さんの前に
進み出た。黒石の眼は充血してすわっており、、少女は首筋まで赤くなっている。
「おとうさん、ぼく、この人が好きなんです。おとうさんから、結婚を申し込んでください」大きな声であっ
た。一座は一瞬、静かになった。歓声の渦となる。少女はもがいて逃げようとした。・・・・・中略・・・・・・
・・・・・ぼくが酔っぱらってしまった。ぼくは永子の前にあぐらをかき、どぶろくの入ったコップをつきつけた
つけた。「呑め」 「いやよ、そんなの」 「そう言わずに呑め」 平藤がよろめきながらやってきた。彼は
ぼくの横に坐り、得意のジェスチャーをまじえながら、ぼくが永子を愛していることの深さについて演説し
はじめた。
「ぼくにはね、まったく君の気持がわからん。杉(主人公)はね、ぼくの親友なんだ。その親友がだ、
これほど君を思っているのにだ、けしからん。君はいったい・・・・・」「おい、よせ」 「いや、よさん。ぼくは
玉井さんをなぐる。どうだ、なぐられてもいやか」 永子は笑いながら聞いていた。・・・中略・・・
石崎はぼくの腕をつかまえて坐らせ、「いや、黒石さん。この子はね、一匹の女もものにできないほどの
大間抜けでしてね。おい、しっかりしろ」・・・・・・中略・・・・・・・広間に戻ると、少女たちは相談していた。
永子が、ぼくへ寄ってきた。「あたしたち、もう帰ります」・・・・・・少女たちは帰り支度を始めた。さすがに
石崎は教師の身分を忘れないと見え、ぼくたちをたしなめた。ぼくたちは、見送った。少女たちの姿が
見えなくなって、急に寒さを感じる。・・・・・「永子のやつめ」 「おれたちは女にふられるようにできている
だ、平藤は別だがな」・・・・・・中略・・・・・・あの日、ぼくたちは少女たちを送ってから荒れた。もっといて
欲しかったし、できればいっしょに泊まりたかったのだ。しかしおとなたちがおこがましくも想像するように、
ぼくたちは少女のからだに触れたかったのではない。もっと感傷的であまっちょろい。ただ彼女が、そこに
いればいいのだ。もしぼくたちのなかに、年上の女から性の手ほどきを受けた者がいたら、彼の願望は異質
なものだったろう。そういう少年もぼくたちも、性欲を持っていることにはかわりはない。しかし現実の異性に
接した場合に展開される心理の動きは、はっきりとちがうのだ。眼のつけどころもちがう。ぼくたちはそこに
異性のムードを感じたし、経験者は女のからだを感じるのである。・・・・・中略・・・・・朝、・・・雨戸をくると、
外はみごとな雪景色であった。なおも降り続いている。・・・・・平藤がつぶやいた。「恋に悩みの雪の朝」
・・・・・ふいに、ぼくは起った。「帰る」みなは、おどろいてぼくを見上げる。黒石はうろたえた。・・・・・
「どうしたんだ?」 「玉井永子の家に行く。逢いたいんだ」 みんな顔を見合わせた。「冗談じゃない。この
雪の中を、山を越えて行けるものか」・・・・・・「いや、行く。どうしても逢いたくなったんだ」・・・・・「よかろう、
行って来い。杉良吉はおおばかやろうだ」 吹雪になりかかっていた。雪はななめに吹付けている。ぼくは
歩き出した。・・・集落の中ほどから左に折れる。・・・・・「きのう、永子たちはこの道を通って帰ったんだ」
ぼくや平藤が乗ってきたバスは、村を縦に割って流れる川に沿って走っている。ぼくたちの学校も、その
川の下流にある。ぼくは今、山を境にした背中合わせの町へ歩いているのである。その町からぼくの住む
神島町(苅田町)へ通じる汽車が出ている(田川線)。・・・・・吹雪の山道をそうしてたどりながら、ぼくは、
自分の行動の無意味さを理解していた。・・・徒労なのだ。・・・・・しかし、ぼくはこうせずにはいられなかった。
笑うやつは笑ってもよい。笑うのが、当然である。しかし、ぼくにとって、これが真実なのだ。
ふしぎなことがある。そのとき、ぼくは永子への恋のために、身をやつしていた。永子へ、一歩一歩、近づ
いていた。坂の下りにさしかかって、からだがらくになって、ぼくのあたまは空想の世界に遊びはじめる。ぼ
くは例の理想の少女の声を聞いたのである。彼女は乳色の空から、雪を浴びながら降りてきて、ぼくと並ん
だ。同時に、ぼくの眼から道は消え雪も消えた。かわって、あたたかい太陽の降りそそぐ春の芝生があらわ
れる。ぼくたちは語りはじめる。・・・・・道はなだらかになった。・・・・・永子の住む町が遠く見えた。・・・・・
やがて町に入る。家々の軒も低い、小さな町である。角帽と肩の雪を丹念にはらいおとした。宿酔いはすっ
かりとれ、気分は爽快であった。【杉良吉は、黒石の城井村の家から犀津町(犀川町)まで歩いたのだ。】
永子の家はすぐにわかった。駅近くの、人家の密集した中に、かたむくようにして、建っていた。・・・・・・・・
・・・・・「豊原高校(豊津高校)の玉井さんいらっしゃいますか?」 永子が出てきた。顔にはにかみ笑いを
うかべている。畳の上に坐った。「こんにちは」永子はそう言った。・・・・・「きみに会いに来たんだ」「ひとり?」
「うむ。ちょっと出ないか」 「ちょっとでいいんだ」 「出れないわ」 「ちょっとでもか」 「あの、父が呼んでます
から」・・・僕は唇を噛む。ふいに、背中が寒くなった。脱いでいた帽子をかぶった。「じゃ、お邪魔したね」・・・
「さようなら」 最後の永子の声だけが、きわだって大きかった。ぼくはその家を後にした。ぼくは駅に行き
列車の来る時間を見た。・・・・・二時間近くもあった。・・・・・永子は列車の時間を知っている。気を変えて
ぼくを追ってこないだろうか。まだそんな期待を捨てなかったのだ。・・・やがて列車が来てぼくは乗ったの
だが、ついに永子もだれもあらわれなかった。・・・・・途中、大橋駅(行橋駅)に降りた。ここで、日豊本線に
乗り換えるのである。・・・・・・・・・・・当時、蒸気機関車で筑豊から田川線で行橋駅を経由して苅田港への
石炭輸送や通勤・通学の交通手段であった。
・・・その名残が、私の高校時代まであった。蒸気機関車SL96が通勤通学の唯一の交通手段だった。
※現在の福岡県京都郡みやこ町犀川・豊津並び京都郡苅田町そして、行橋市等々の京築エリアでの
戦後、昭和二十年代半ばの高校生事情という時代背景がそこにあったのである。
JPEG0426-0175~0426-0183 P-352~P-368
《20》・・・・・この作品は、1963年5月河出書房新社より刊行されました。
ご紹介するのは、1995年5月15日 徳間文庫初刷刊行分です。
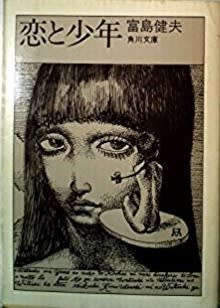



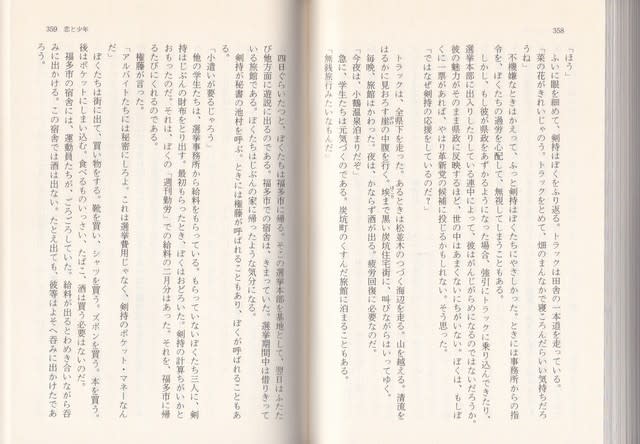

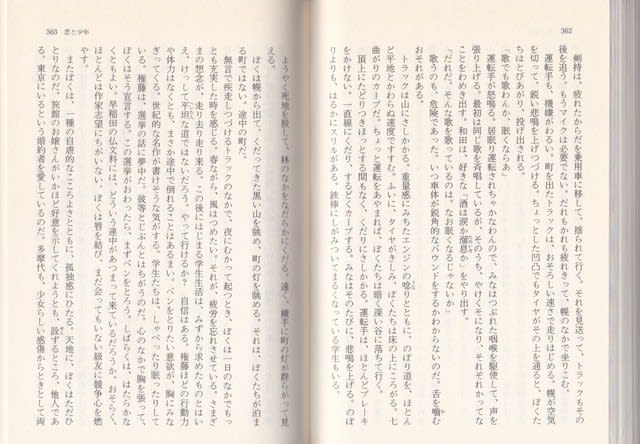


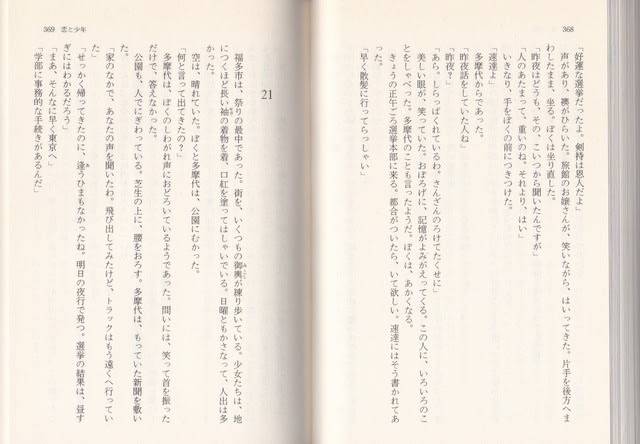
次回は、 《21》・・・・・この作品は、1963年5月河出書房新社より刊行されました。
ご紹介するのは、1995年5月15日 徳間文庫初刷刊行分です。
した初期作品の代表作です。富島健夫の初期作品は、《青春》をテーマとしての基本姿勢を踏まえて
《青春の心》を描き出してきた作家である。他の作品で【雪の記憶】・【故郷の蝶】・【故郷は遠きにありて】
・【夜の青葉】・【明日への握手】等々の基幹となる自伝的要素の強い作品ではないだろうかと思う。
富島健夫が、主人公(杉良吉)の名を借りて終戦直後から昭和二十年代後半の時代背景の中での
少年期からの青春群像を描き出している。終戦前まで日本の植民地であった地からの引き揚げ者、そして
貧しく空腹と孤独感のなかでの思春期を学制改革の施行を機に新制高校二年となって男女共学の学生
時代を過ごしてゆくのである。主人公の成長とともに変化してゆく女性像や空想の中で女性(少女)と遊び
現実の女性とのギャップの中で生まれて初めて恋を告白する。また、他の女性関係が綴られる時の失恋
もある。・・・富島健夫は「青春の心は、生きてある限り消えぬものである。ゆえに、ぼくは生きてある限り
青春の心を文章に表現していこうと決意している。」とあとがきしている。この作品の解説者 清原康正氏の
文を引用させていただくと、富島健夫は、この永遠の普遍性ともいうべき《青春》を《不易流行》と表現して
《不易=永遠に変わらぬ本質的な感動》と《流行=時々新しい事を求めて移り変わるもの》そして、「人間
には、不易と流行があり、不易なる真実は、千年を経ても不易であって、もともと小説はそこに視点を据える
べきであって、流行はどうでもよいのである。」(【夜の青葉】のあとがき)・・・したがって、不易なるもの
それは《青春の心》でありそこに視点を据えて自らの青春体験を投影させることで彼の内部に《青春の心》
が常に存在し続けていることを示すものだ。
1951年生れの私は、自身の青春時代と重ね合わせてみても世代を越えて《不易と流行》である《青春
の心》に感銘を受ける次第です。
やはり、時代が違っていても同郷という生活空間で少年期から青春期を過ごす中での《青春の心》は、
何ら変わりはありません。私にとって、この作品の中に描写されている主人公の具体的な行動が良く解り
、身近に感じられるのです。特に(8)P137~P157が印象に残っています。・・・・・
※【作品文中引用転載】
・・・・・・・・・・・その年の正月三日は、晴れていた。ぼくは平藤と駅で落ち合った。文芸部の新年宴会
が、部員の黒石の家でもよおされるのである。黒石の家は、山奥の村にあった。黒石の父は、そこの村長
である。黒石は一人息子で、どんなわがままでもきく。そこがぼくたちのつけ目だった。部員たちのささや
かな会費と、ぼくと石崎(先生)が苦心して部費から捻出する金額では、酒豪のそろった宴会がすむわけ
はない。後は村長さんに任せようというのである。黒石は三年だが一組で、お坊ちゃんで、どうして文芸部
にまぎれこんできたか、わからない。大橋駅(行橋駅)で落ち合ったぼくと平藤は、うなずき合った。
「よし、買うか」 山奥のその集落行きのバスに乗る前に、ぼくと平藤は煙草屋の前に立ち、堂々とピース
を一個ずつ買った。マッチも買い、ポケットにしまう。高校生でも、飲酒は大目にみられている。厳禁されて
いる喫煙を同時に断行しようと、かねがね約束していたのだ。
買ったピースを、ぼくたちは宴会なかば、石崎(先生)の前で取り出した。周囲に、男女の部員たちが
居流れている。平藤は気取った手つきで煙草を口にくわえ、マッチをすった。ぼくもそれをまねた。
「先生」 石崎を呼んだ。石崎は、ぼくたちを見て、目をまるくした。ぼくたちは紫煙をくゆらせはじめる。
そのうち、ぼくは大きく煙を吸った。ややからい感じがしたが、予想したほどでもない、あたまがぼんやり
となり、いい気持ちになった。眼がかすみ、上体がゆれた。息を吐く、眼が見えはじめ、気分は普通に
もどった。
「ほう、ピースだのう。わしに一本くれ」石崎はそう言い、ぼくと平藤は一本ずつを献上した。石崎は
うまそうにそれを吸いはじめる。煙草を吸いながら、ぼくは少女たちの反応をうかがった。永子は知らぬ
顔をしていた。ほとんどの少女たちがそうである。非難している眼もあった。玲子がそのまっ黒な大きな
眼におどろきをあらわして、ぼくをみつめていた。他に原や和田そして西中もこころみる。・・・・・中略・・・・・
ともあれ、担任教師や善良な女生徒たちの前ではじめて煙草を吸うという革命的な所業は、芝居好き
の心》に感銘を受ける次第です。平藤の思いつきそうなことであった。ぼくはそれにひきずられたのだ。
石崎がぼくたちをとがめないことは、最初からあきらかであった。
石崎よりも、ぼくは永子をより多く意識していた。そこには、永子に拒否されつづけているぼくの、自虐
的な快感があった。ざまあみろと叫びたい気持ちである。何がざまあみろか、ざまあみているのはじぶん
ではないか。・・・・・中略・・・・・その黒石が、まっさきに酔っぱらった。彼は常になく積極的に歌ったり
しゃべったりしていたが、やがて一人の少女の肩を抱いて、ぼくや石崎と話をしている村長さんの前に
進み出た。黒石の眼は充血してすわっており、、少女は首筋まで赤くなっている。
「おとうさん、ぼく、この人が好きなんです。おとうさんから、結婚を申し込んでください」大きな声であっ
た。一座は一瞬、静かになった。歓声の渦となる。少女はもがいて逃げようとした。・・・・・中略・・・・・・
・・・・・ぼくが酔っぱらってしまった。ぼくは永子の前にあぐらをかき、どぶろくの入ったコップをつきつけた
つけた。「呑め」 「いやよ、そんなの」 「そう言わずに呑め」 平藤がよろめきながらやってきた。彼は
ぼくの横に坐り、得意のジェスチャーをまじえながら、ぼくが永子を愛していることの深さについて演説し
はじめた。
「ぼくにはね、まったく君の気持がわからん。杉(主人公)はね、ぼくの親友なんだ。その親友がだ、
これほど君を思っているのにだ、けしからん。君はいったい・・・・・」「おい、よせ」 「いや、よさん。ぼくは
玉井さんをなぐる。どうだ、なぐられてもいやか」 永子は笑いながら聞いていた。・・・中略・・・
石崎はぼくの腕をつかまえて坐らせ、「いや、黒石さん。この子はね、一匹の女もものにできないほどの
大間抜けでしてね。おい、しっかりしろ」・・・・・・中略・・・・・・・広間に戻ると、少女たちは相談していた。
永子が、ぼくへ寄ってきた。「あたしたち、もう帰ります」・・・・・・少女たちは帰り支度を始めた。さすがに
石崎は教師の身分を忘れないと見え、ぼくたちをたしなめた。ぼくたちは、見送った。少女たちの姿が
見えなくなって、急に寒さを感じる。・・・・・「永子のやつめ」 「おれたちは女にふられるようにできている
だ、平藤は別だがな」・・・・・・中略・・・・・・あの日、ぼくたちは少女たちを送ってから荒れた。もっといて
欲しかったし、できればいっしょに泊まりたかったのだ。しかしおとなたちがおこがましくも想像するように、
ぼくたちは少女のからだに触れたかったのではない。もっと感傷的であまっちょろい。ただ彼女が、そこに
いればいいのだ。もしぼくたちのなかに、年上の女から性の手ほどきを受けた者がいたら、彼の願望は異質
なものだったろう。そういう少年もぼくたちも、性欲を持っていることにはかわりはない。しかし現実の異性に
接した場合に展開される心理の動きは、はっきりとちがうのだ。眼のつけどころもちがう。ぼくたちはそこに
異性のムードを感じたし、経験者は女のからだを感じるのである。・・・・・中略・・・・・朝、・・・雨戸をくると、
外はみごとな雪景色であった。なおも降り続いている。・・・・・平藤がつぶやいた。「恋に悩みの雪の朝」
・・・・・ふいに、ぼくは起った。「帰る」みなは、おどろいてぼくを見上げる。黒石はうろたえた。・・・・・
「どうしたんだ?」 「玉井永子の家に行く。逢いたいんだ」 みんな顔を見合わせた。「冗談じゃない。この
雪の中を、山を越えて行けるものか」・・・・・・「いや、行く。どうしても逢いたくなったんだ」・・・・・「よかろう、
行って来い。杉良吉はおおばかやろうだ」 吹雪になりかかっていた。雪はななめに吹付けている。ぼくは
歩き出した。・・・集落の中ほどから左に折れる。・・・・・「きのう、永子たちはこの道を通って帰ったんだ」
ぼくや平藤が乗ってきたバスは、村を縦に割って流れる川に沿って走っている。ぼくたちの学校も、その
川の下流にある。ぼくは今、山を境にした背中合わせの町へ歩いているのである。その町からぼくの住む
神島町(苅田町)へ通じる汽車が出ている(田川線)。・・・・・吹雪の山道をそうしてたどりながら、ぼくは、
自分の行動の無意味さを理解していた。・・・徒労なのだ。・・・・・しかし、ぼくはこうせずにはいられなかった。
笑うやつは笑ってもよい。笑うのが、当然である。しかし、ぼくにとって、これが真実なのだ。
ふしぎなことがある。そのとき、ぼくは永子への恋のために、身をやつしていた。永子へ、一歩一歩、近づ
いていた。坂の下りにさしかかって、からだがらくになって、ぼくのあたまは空想の世界に遊びはじめる。ぼ
くは例の理想の少女の声を聞いたのである。彼女は乳色の空から、雪を浴びながら降りてきて、ぼくと並ん
だ。同時に、ぼくの眼から道は消え雪も消えた。かわって、あたたかい太陽の降りそそぐ春の芝生があらわ
れる。ぼくたちは語りはじめる。・・・・・道はなだらかになった。・・・・・永子の住む町が遠く見えた。・・・・・
やがて町に入る。家々の軒も低い、小さな町である。角帽と肩の雪を丹念にはらいおとした。宿酔いはすっ
かりとれ、気分は爽快であった。【杉良吉は、黒石の城井村の家から犀津町(犀川町)まで歩いたのだ。】
永子の家はすぐにわかった。駅近くの、人家の密集した中に、かたむくようにして、建っていた。・・・・・・・・
・・・・・「豊原高校(豊津高校)の玉井さんいらっしゃいますか?」 永子が出てきた。顔にはにかみ笑いを
うかべている。畳の上に坐った。「こんにちは」永子はそう言った。・・・・・「きみに会いに来たんだ」「ひとり?」
「うむ。ちょっと出ないか」 「ちょっとでいいんだ」 「出れないわ」 「ちょっとでもか」 「あの、父が呼んでます
から」・・・僕は唇を噛む。ふいに、背中が寒くなった。脱いでいた帽子をかぶった。「じゃ、お邪魔したね」・・・
「さようなら」 最後の永子の声だけが、きわだって大きかった。ぼくはその家を後にした。ぼくは駅に行き
列車の来る時間を見た。・・・・・二時間近くもあった。・・・・・永子は列車の時間を知っている。気を変えて
ぼくを追ってこないだろうか。まだそんな期待を捨てなかったのだ。・・・やがて列車が来てぼくは乗ったの
だが、ついに永子もだれもあらわれなかった。・・・・・途中、大橋駅(行橋駅)に降りた。ここで、日豊本線に
乗り換えるのである。・・・・・・・・・・・当時、蒸気機関車で筑豊から田川線で行橋駅を経由して苅田港への
石炭輸送や通勤・通学の交通手段であった。
・・・その名残が、私の高校時代まであった。蒸気機関車SL96が通勤通学の唯一の交通手段だった。
※現在の福岡県京都郡みやこ町犀川・豊津並び京都郡苅田町そして、行橋市等々の京築エリアでの
戦後、昭和二十年代半ばの高校生事情という時代背景がそこにあったのである。
JPEG0426-0175~0426-0183 P-352~P-368
《20》・・・・・この作品は、1963年5月河出書房新社より刊行されました。
ご紹介するのは、1995年5月15日 徳間文庫初刷刊行分です。
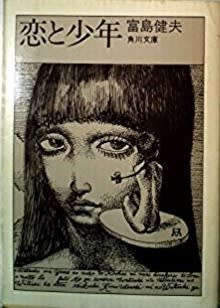



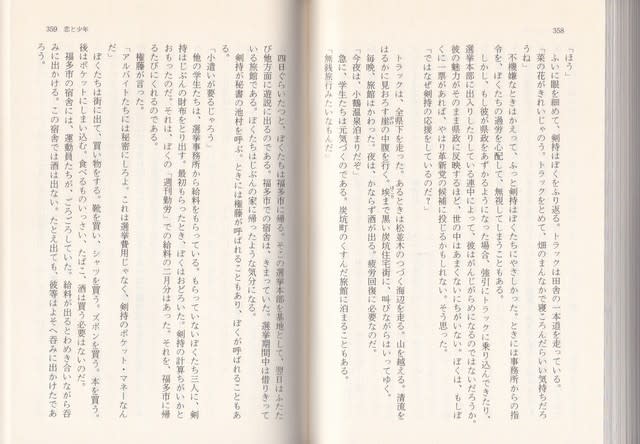

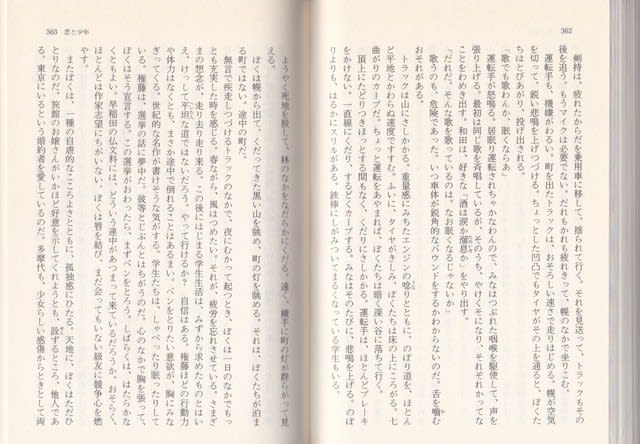


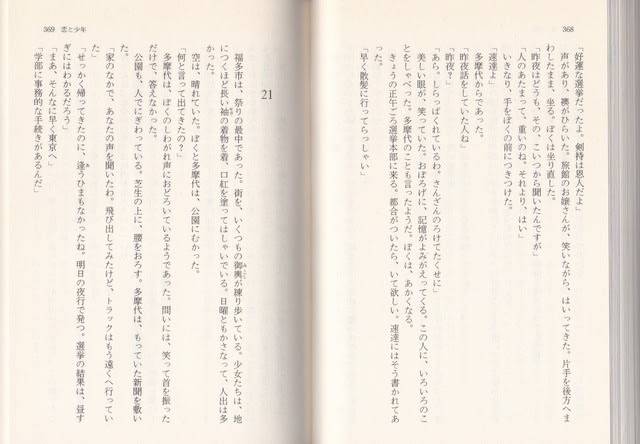
次回は、 《21》・・・・・この作品は、1963年5月河出書房新社より刊行されました。
ご紹介するのは、1995年5月15日 徳間文庫初刷刊行分です。