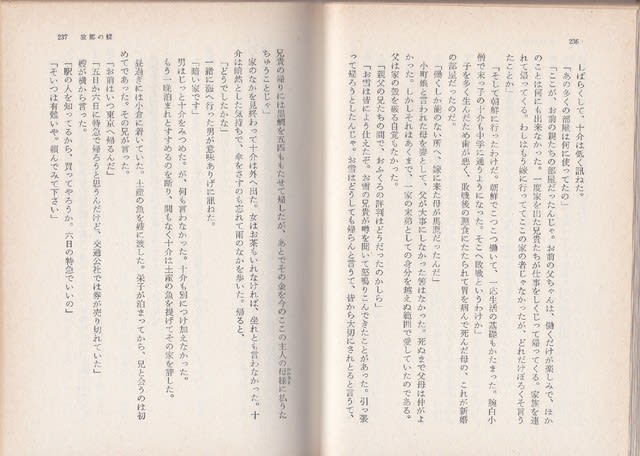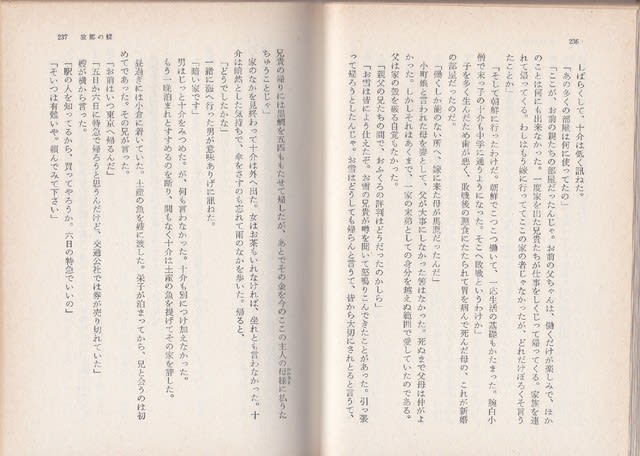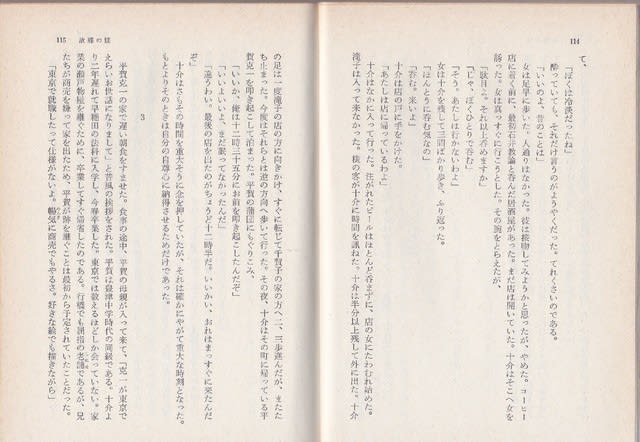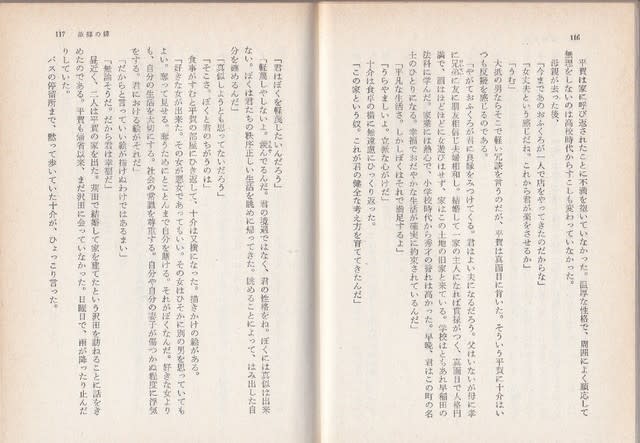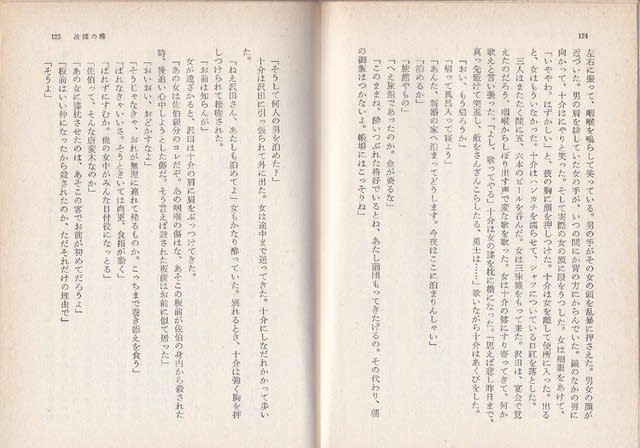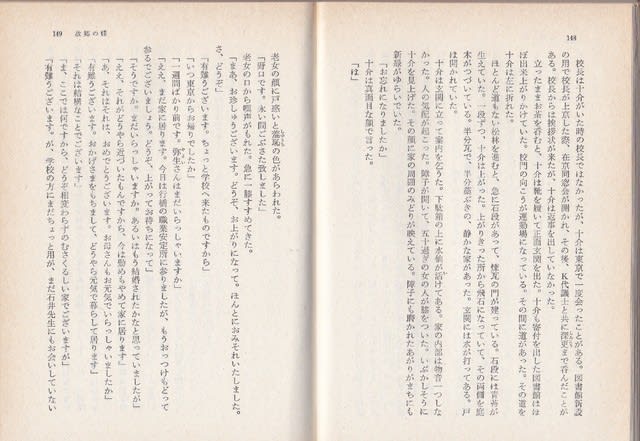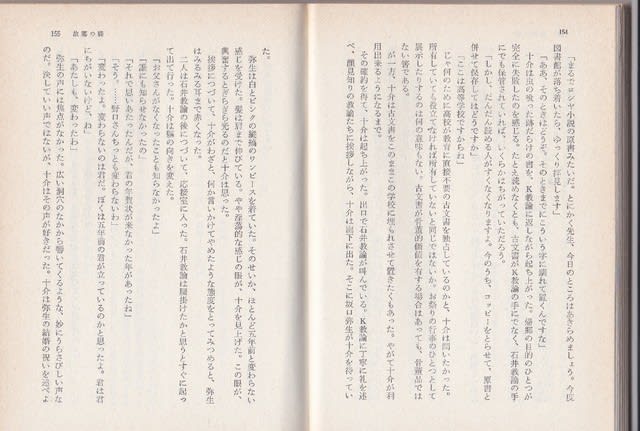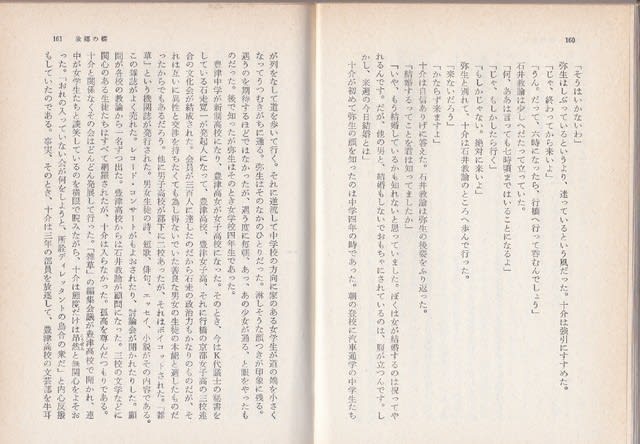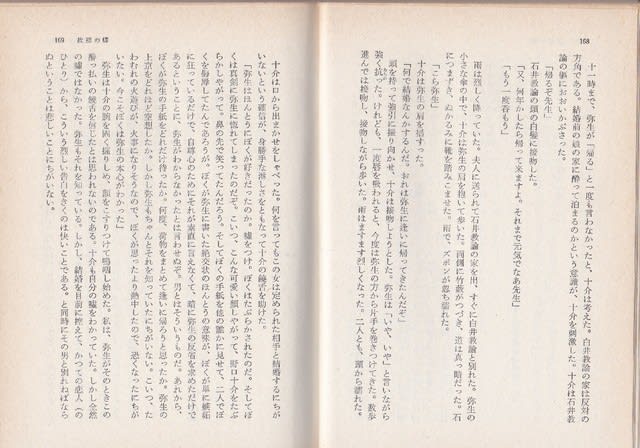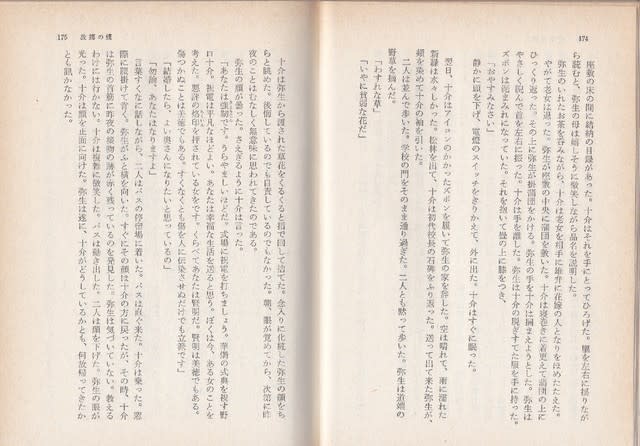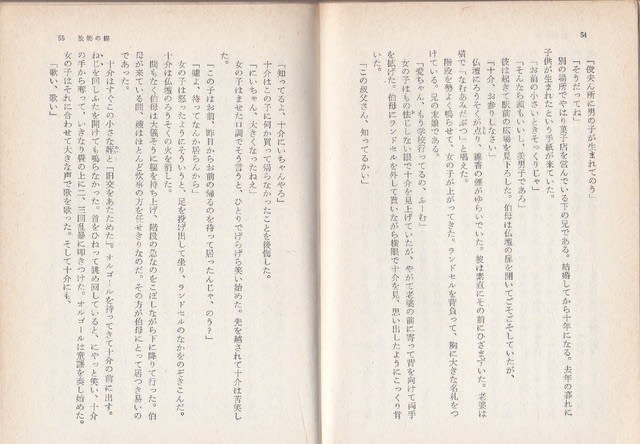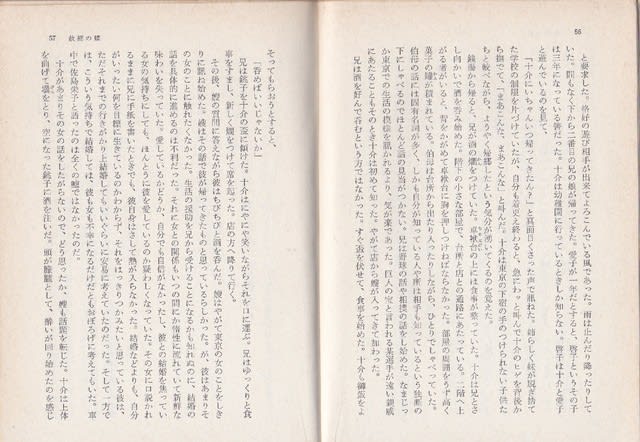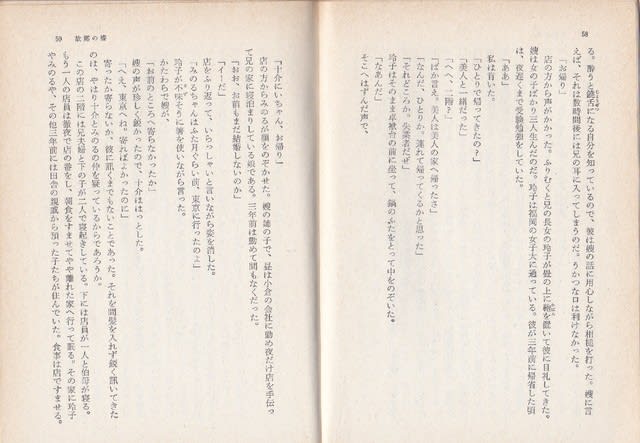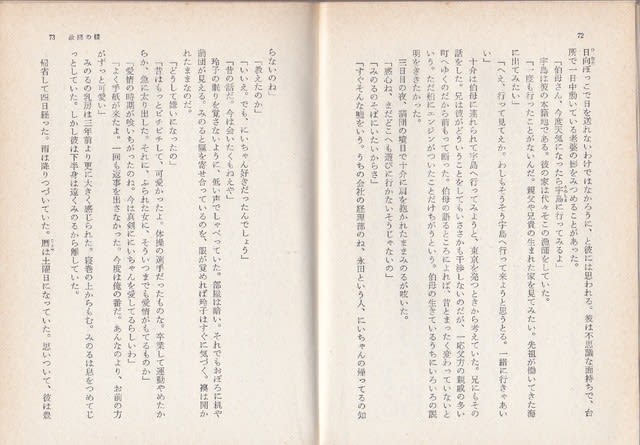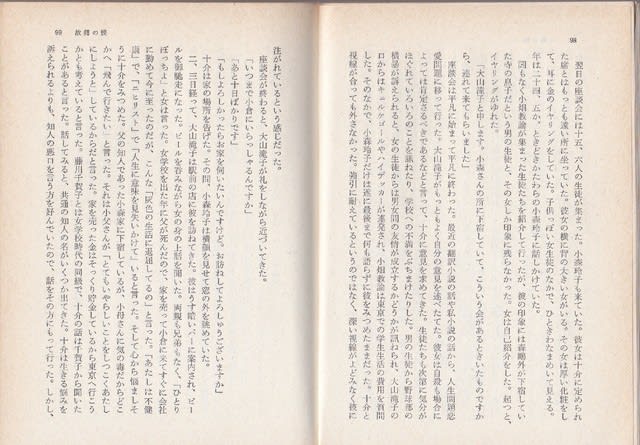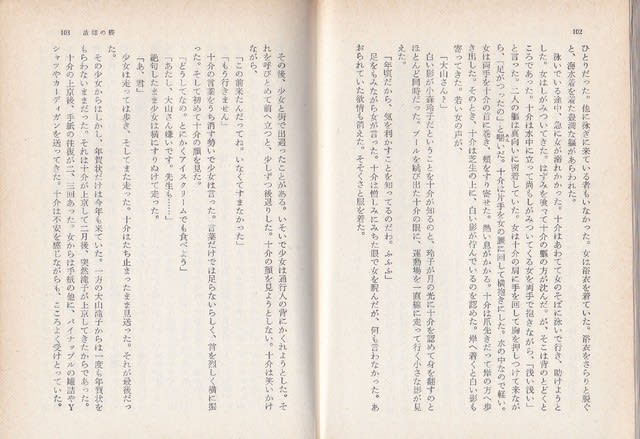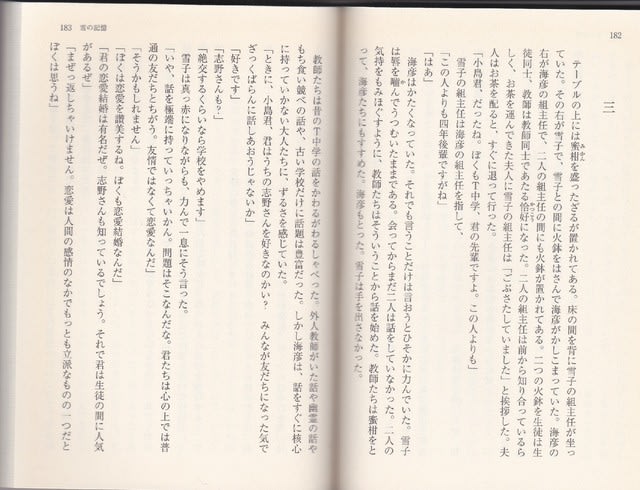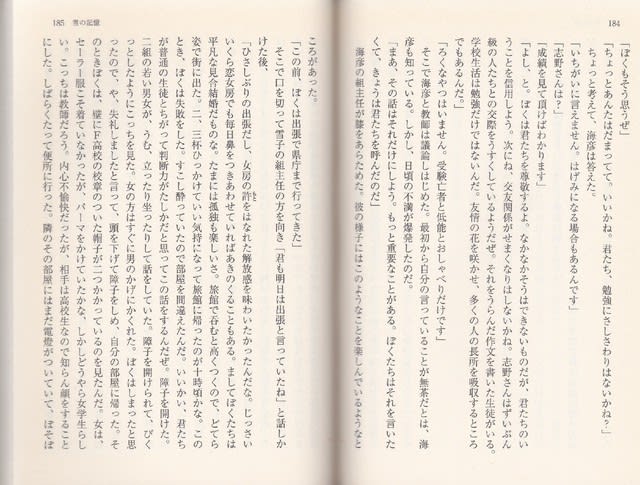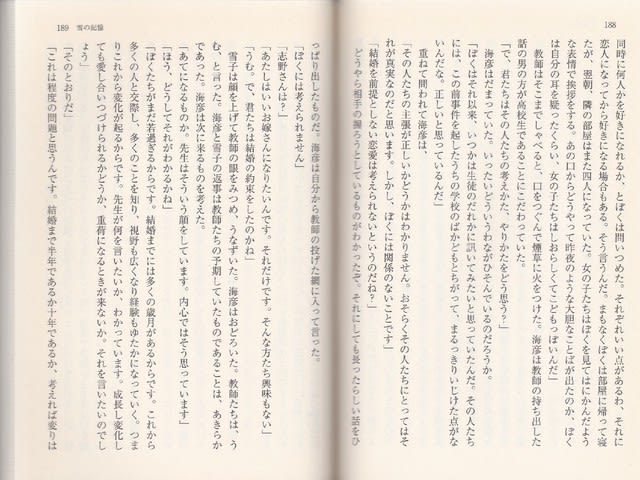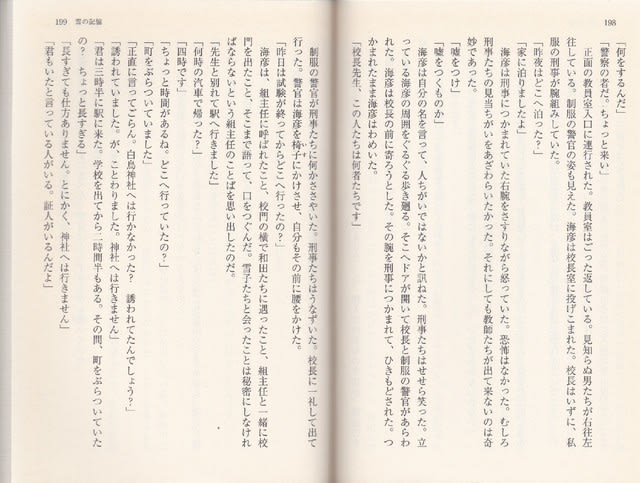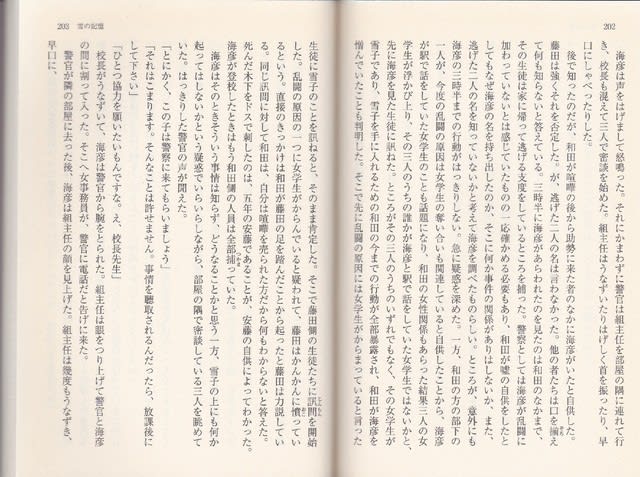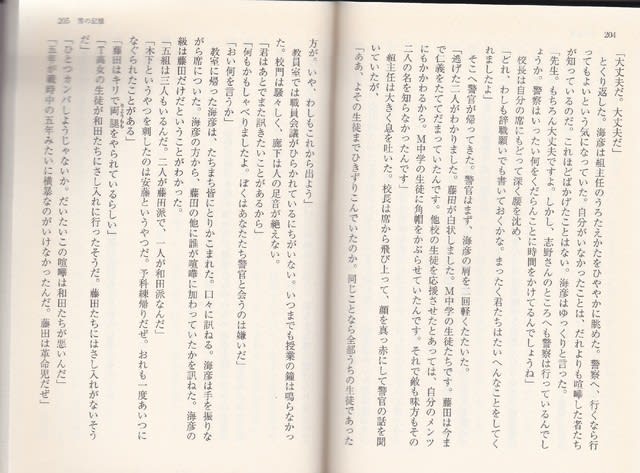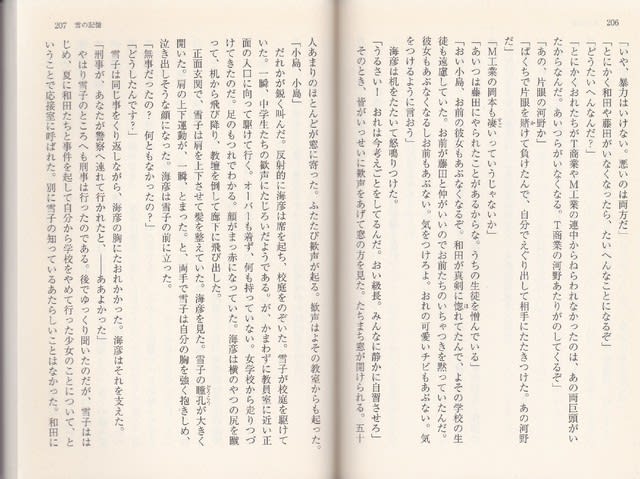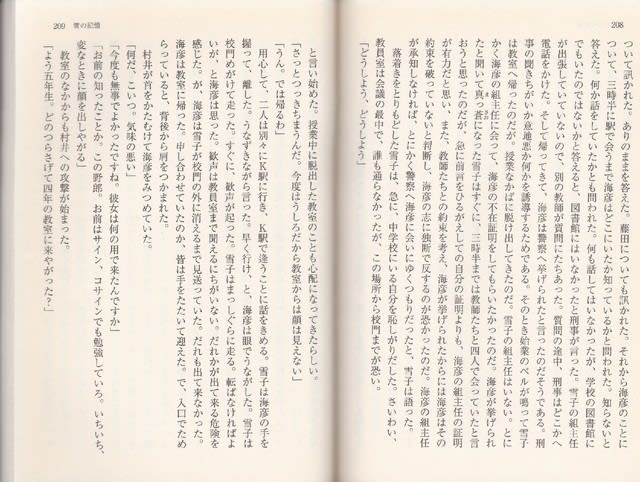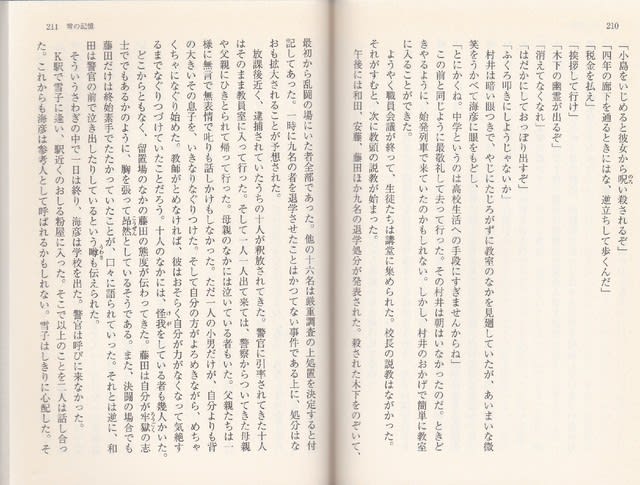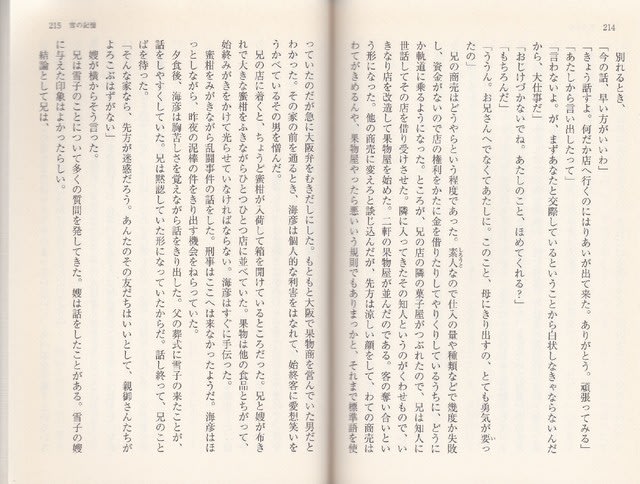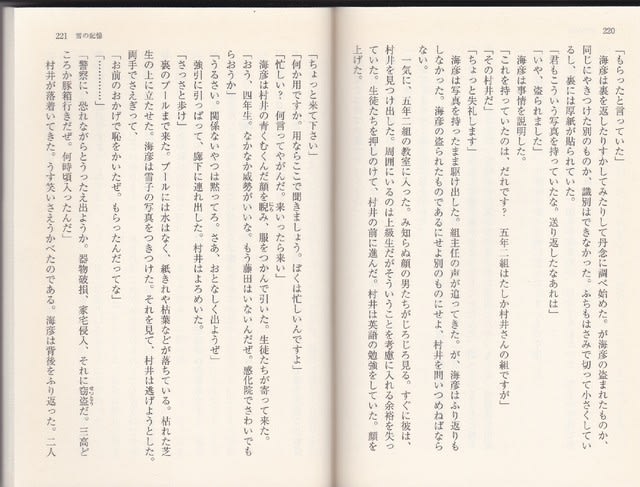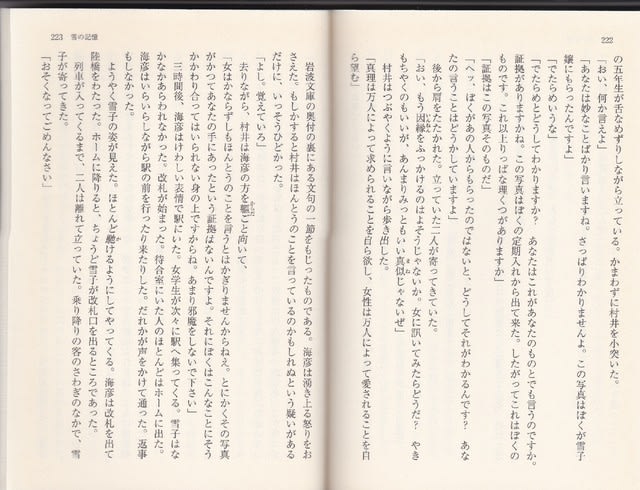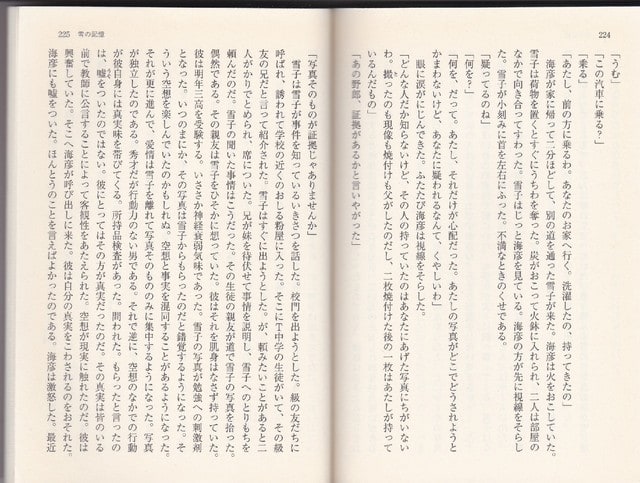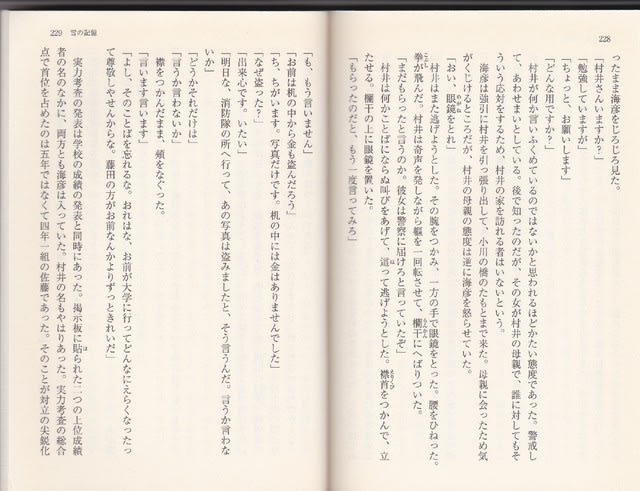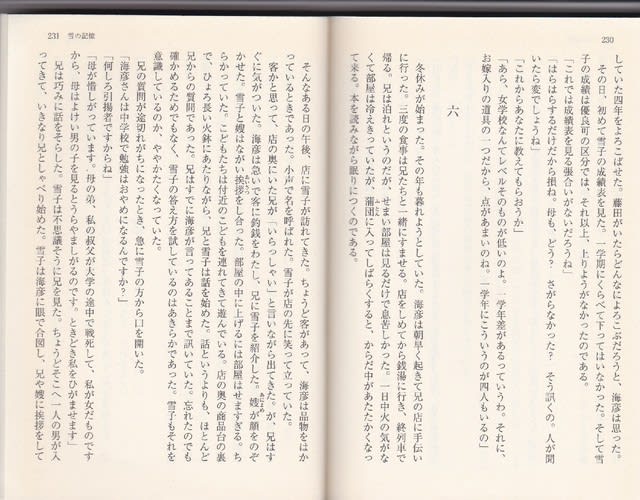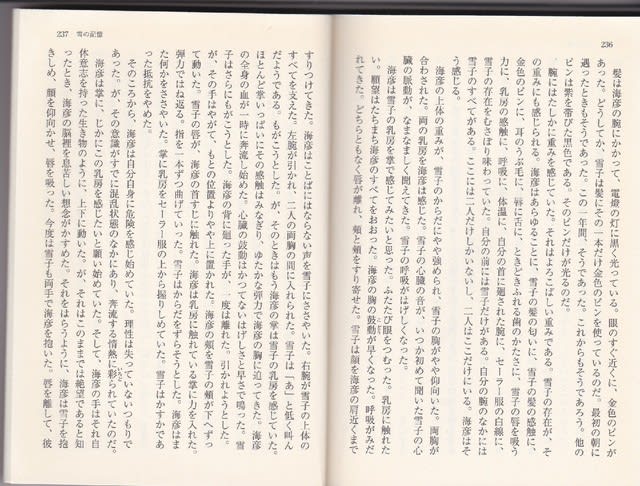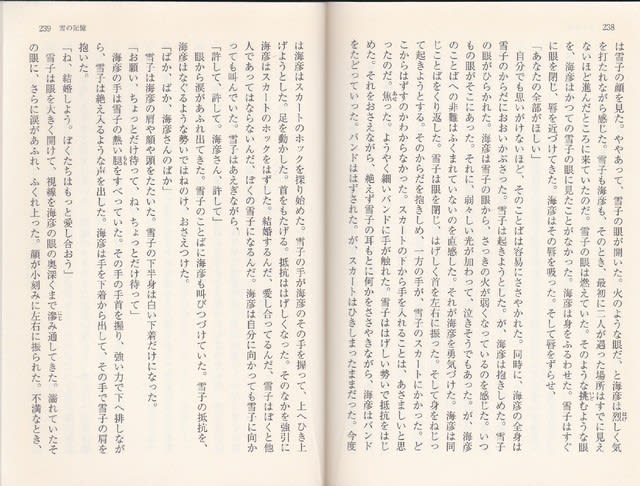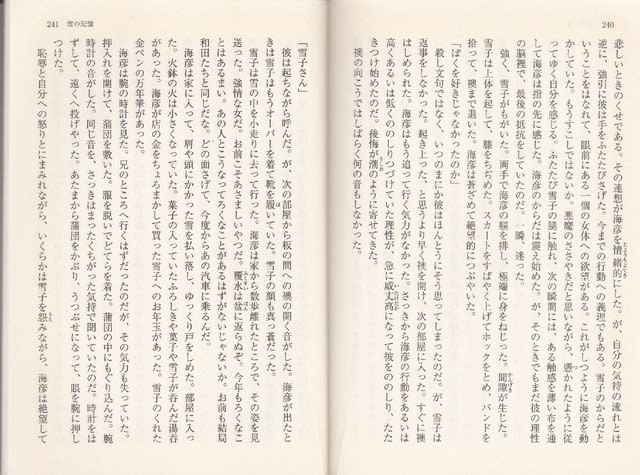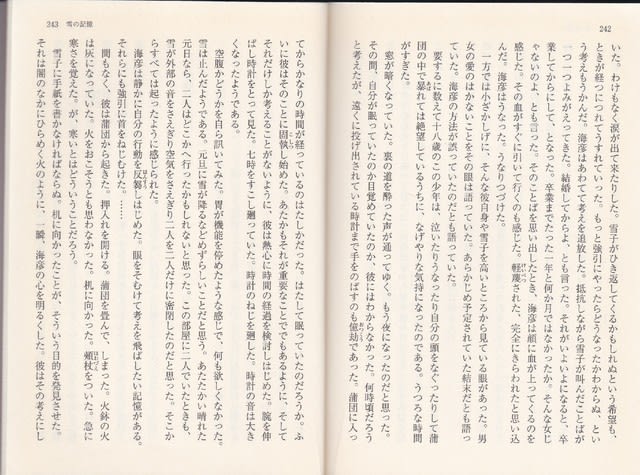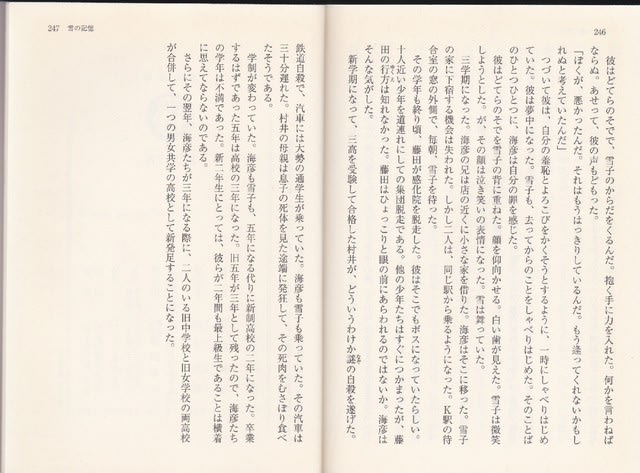第三章 [三]~[六]を紹介します。
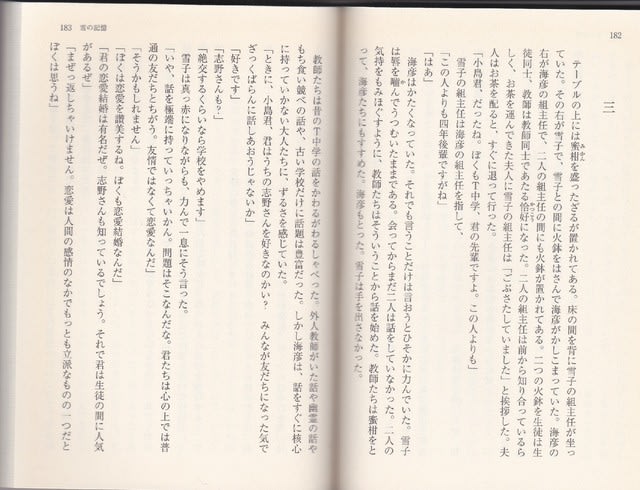
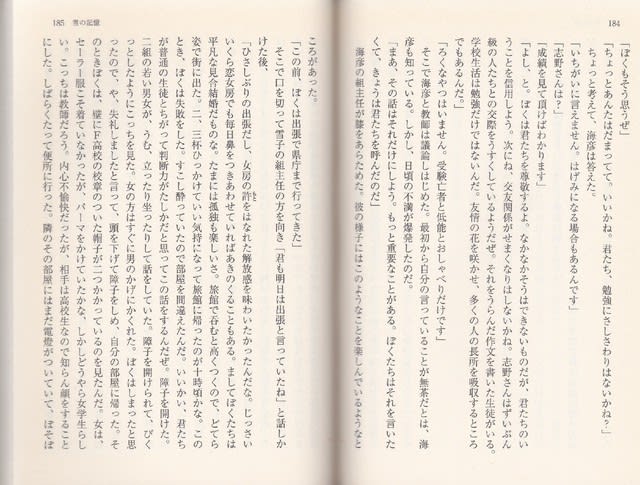

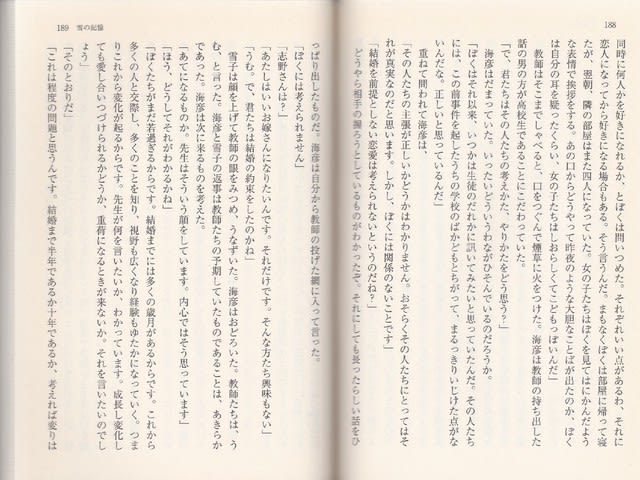



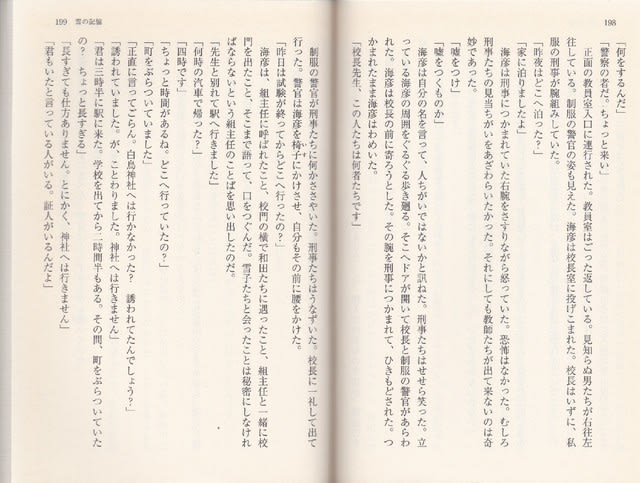

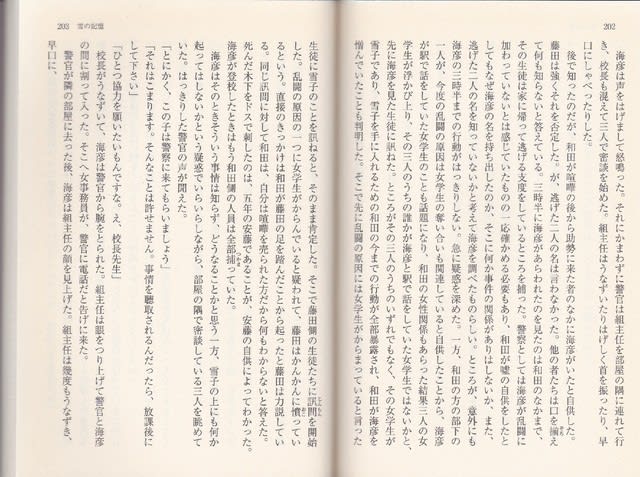
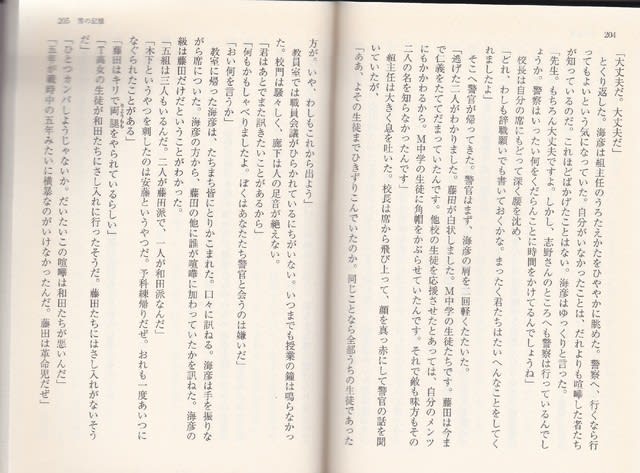
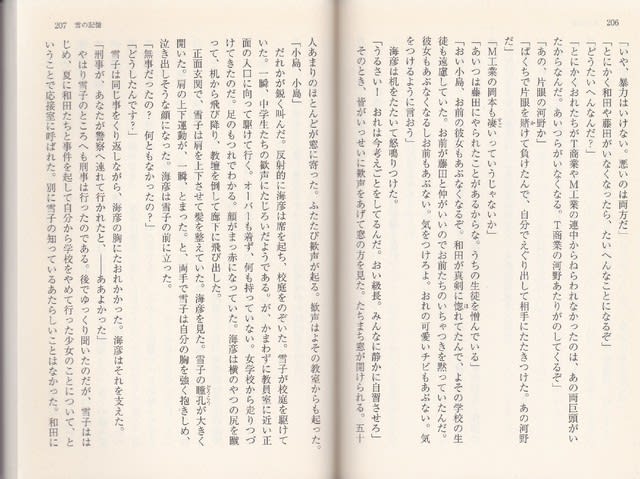
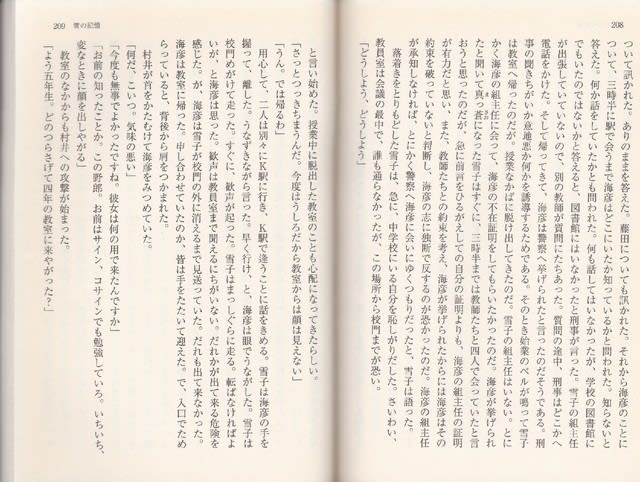
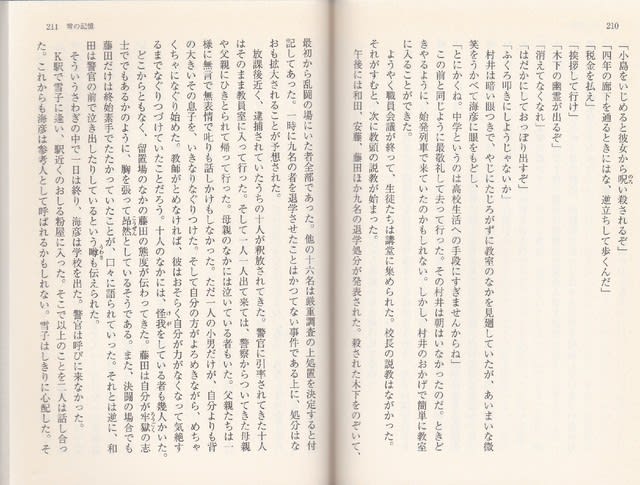

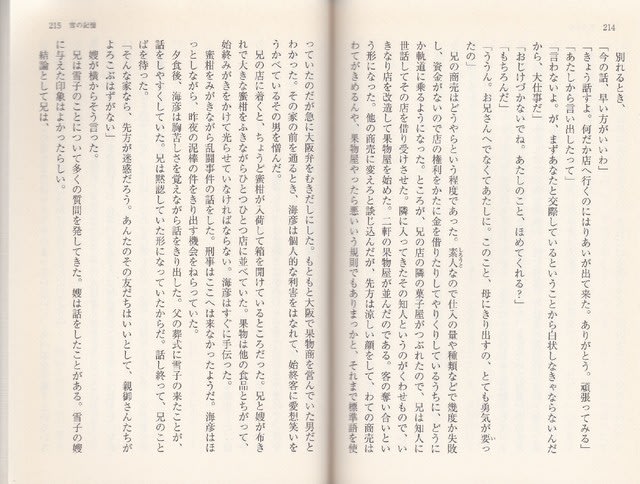


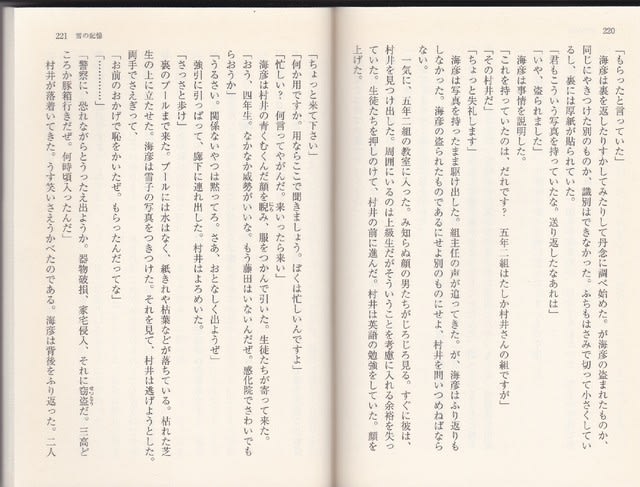
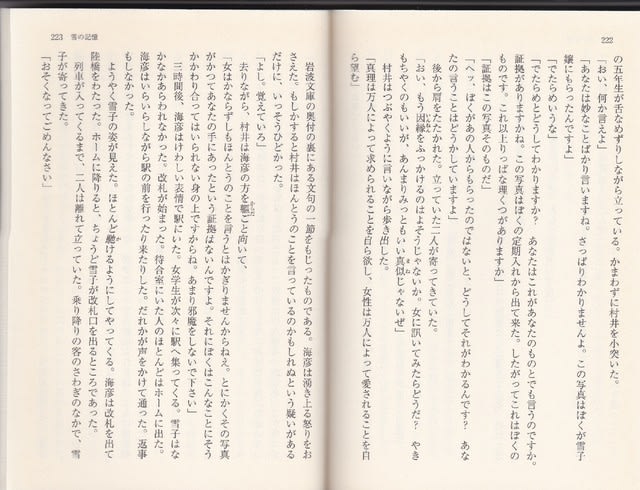
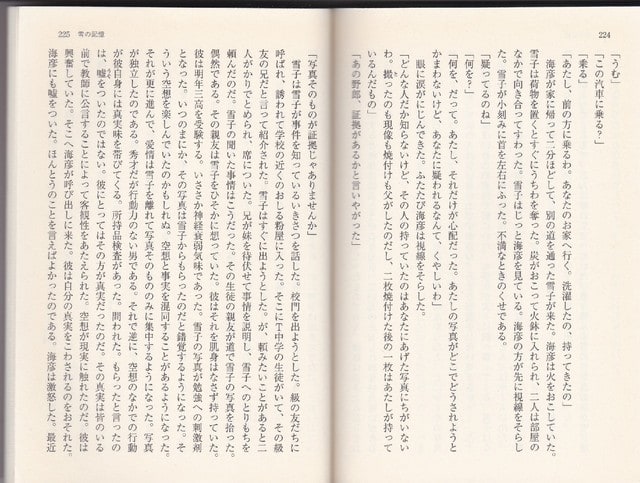

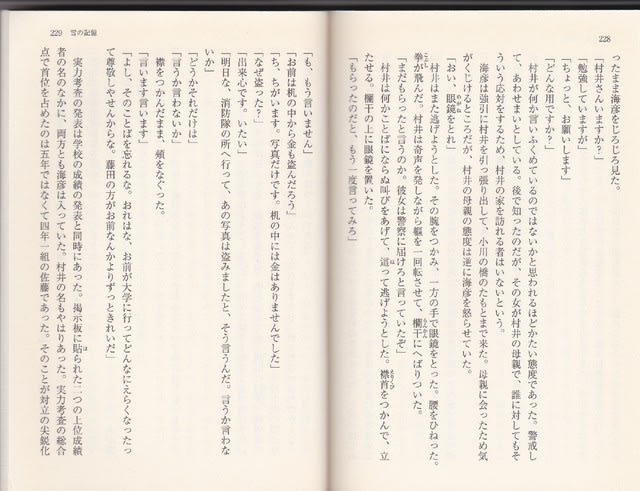
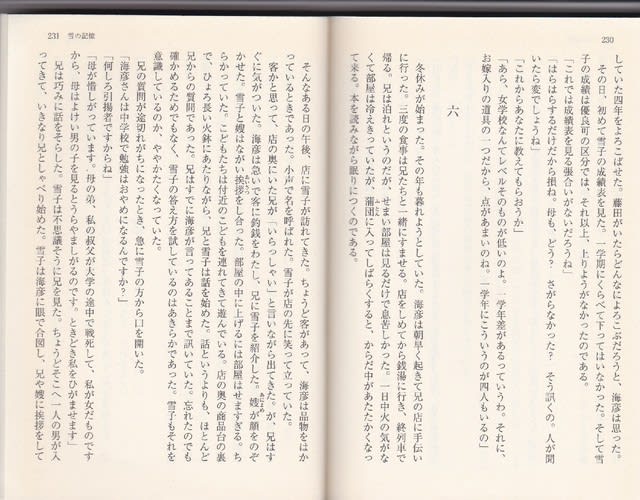


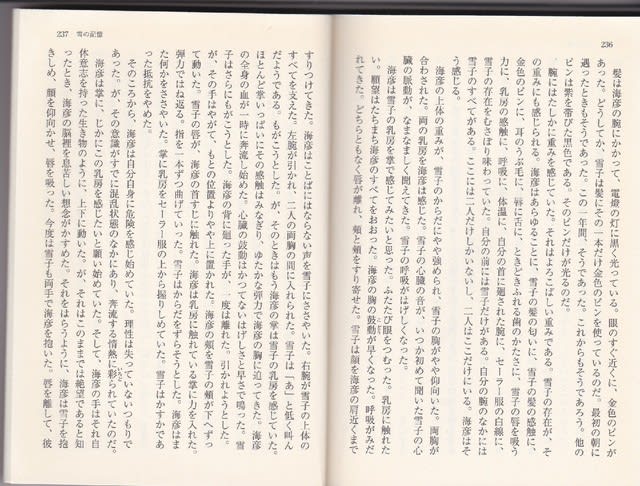
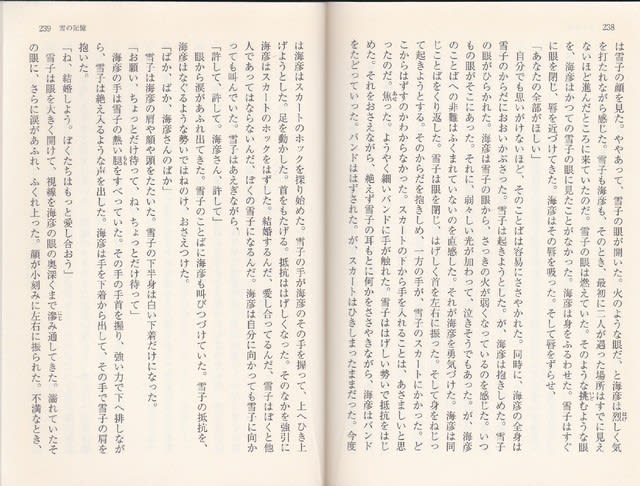
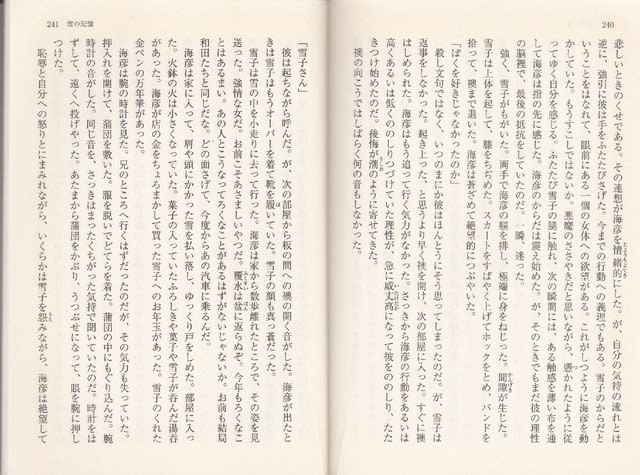
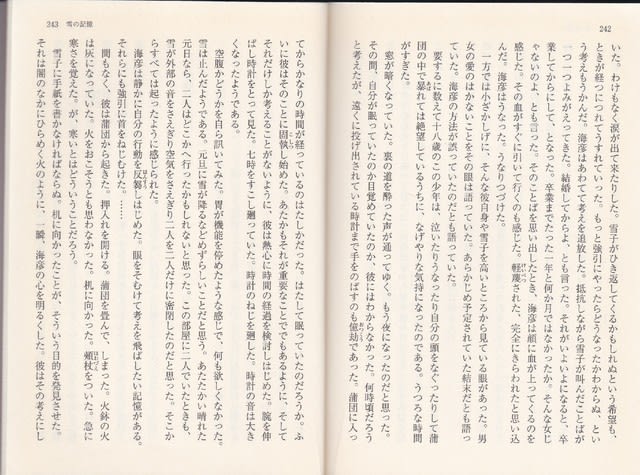

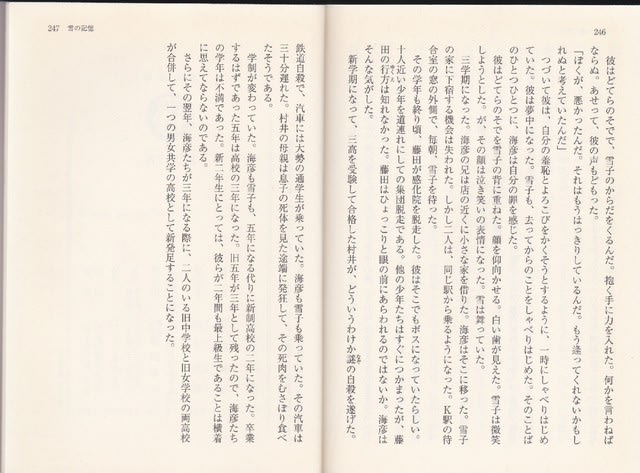
※【雪の記憶】最終回※
・・・富島健夫【雪の記憶】を読みながら映画《北国の街》を鑑賞する。映画【北国の街】では、全く描写
がなく、富島健夫の【官能小説の原点】ではという節がある。・・・・・
・・・欲望と愛情のうごめく恋愛観の交錯のなかで・・・・・
冬休みが始まってその年が暮れた。正月元旦、目を覚まして雨戸をあけると、
めずらしく一面の雪であった。雪はなおも降り続いている。十時から元旦の式があり
式が終わって、二人は駅で逢った。雪は降り続いている。映画などには行きたくなかった
。人にわずらわされることなく、二人だけで元旦をすごしたかった。二人は海彦が一人で
住んでいる家に行くことにした。
・・・・・長い間、二人は動かなかった。海彦と雪子は逢瀬を重ねるごとに互いに愛おしさ
が増して熱い抱擁となってゆく。雪子と初めて遇った朝から今までの間の様々な素顔が、
どこかつかまえどころのないまま、海彦のいらだちを誘うように、次々に消えては浮かんだ。
この一年間の自分の意識には、必ずこの人が存在していたのだ。雪子のいない人生は考え
られない。・・・海彦の願望はたちまちすべてをおおった。そのころから、海彦は自分自身
に危険を感じ始めていた。・・・「あなたの全部が欲しい」・・・その言葉は容易にささや
かれた。海彦の全身は雪子のからだにおおいかぶさった。雪子はあえぎながら、「許して、
許して、。海彦さん、許して」眼から涙があふれ出てきた。「ね、結婚しよう。ぼくたちは
もっと愛し合おう」雪子の顔が小刻みに左右に振られた。眼前にある一個の女体への欲望が
ある。これが執拗に海彦を動かしていた。海彦の体は震え始めた。そこに感激が生じた。
雪子は上体を起こして退いた。海彦は蒼ざめて絶望的につぶやいた。「ぼくを好きじゃ
なかったのか」雪子は返事をせず次の部屋を通り、オーバーを着て靴を履いて小走りに雪の
中を去っていった。海彦は羞恥心と自分への怒りにまみれながら、少し雪子を恨みながら
海彦は絶望していた。数えて十八歳のこの少年の眼は、男女の愛のはかないことを語っていた。
・・・海彦は静かに自分の行動を反芻し始めた。雪子に手紙を書かなければと机に向かった。
その時、出入り口の戸が鳴ったように思われた。・・・「海彦さん」雪子の声をはっきりと
聞いた。「あたしを嫌いにならないで!」雪子のふたたび来た意味がよく分かった。自分が
雪子に与えた苦痛が、なまなましく実感され、純粋な後悔がおしよせてきた。
「ぼくが、悪かったんだ。それはもうはっきりしているんだ。もう逢ってくれないかも
しれぬと考えていたんだ」その言葉の一つ一つに、海彦は自分の罪を感じた。
雪子は微笑もうとした。が、その顔は泣き笑いの表情になった。・・・雪は舞っていた。
三学期になった。海彦の兄は店の近くに小さな家を借りた。海彦はそこに移った。二人は
同じ駅から乗るようになった。待合室の窓の外側で、毎朝、雪子を待った・・・
・・・その学年も終わり新学期になって、学制がかわった。海彦も雪子も、五年になる代わ
りに新制高校の二年になった。さらに翌年、海彦たちが三年になる際に、二人のいる旧中学校
と旧女学校の両高校が合併して、一つの男女共学の高校として新発足することになった。
※富島健夫 原作【雪の記憶】を読み、日活映画【北国の街】を鑑賞すると、学生時代を回顧してしまう
のですが・・・思春期から青年期への道標ともみてとれる場面や現実味を帯びた描写に遭遇したり
で、感受性が高く結論のない心身の成長期であるが故に、成就出来なかった事柄への挫折感だろうか?
・・・いづれにせよ、《かけがえのない時代》を検証することにかわりはない。!!!
次回からは、【故郷の蝶】を紹介します。