[[[[質問&回答ページ]]]]
もし北京がペキンなら東京はトンキンになるはずで、トンペーと読むのがあれば東北でしょう。
北がペ(厳密にはペイ)で、京がキンからチンになり、東がトンだとわからないのですか?
北 Bei(ウェイド式Pei) … 第3声
京 jing(ウェイド式ching)←ging(ウェイド式king) … 第1声
東 Dong(ウェイド式Tung) … 第1声
したがって「東京」はDong1jing1,「東北」はDong1bei3です。
英語での言い方を列挙します。
上海 Shanghai☆
北京 PekingまたはBeijing☆
東京 Tokyo(中国ではDong1jing1)
武漢 Wuhan☆
ちなみに「五飯」であればwu3fan4ですがこういう熟語が存在するか疑問です。
似たような熟語で「五反運動」wu3fan3 yun4dong4があります。
「五」がウー(wu3)だとわかったら、ハン(han4)は「漢」だとわかりそうなものですが。
「五」がウー(wu3)だという知識はどこからですか?
「孫悟空」はSun1 Wu4kong1です。
「ドラゴンボール」の「孫悟飯」を中国人が北京語で読んだら
Sun1 Wu4fan4でしょうね。
それから「北京」を日本語の音読みで読むなら「ホッキョウ」か「ホッケイ」になるはず。
「キタキョウ」だと「キタ」が訓読みだから湯桶読みで、「東京」を「ヒガシキョウ」と読むようなものです。
どうして「上海」が「ジョウカイ」でないか、「北京」が「ホッキョウ」でないかは単なる慣用、歴史的偶然の産物と言うしかないですね。
「武」が日本語音で「ム」「ブ」で、「五」が「ゴ」なのに中国でウー(Wu3)になるのは北京語で語頭子音が脱落したせいです。
ほかに「呉」はWu2です。
だからWu3 Da4wei3は「武大偉」、Wu2 Yi2は「呉儀」になります。
日本人が中国の地名、人名を日本読みにしているのは中国人が日本の地名、人名に対してそうしているから。
「悠仁」は日本で「ヒサヒト」だろうが「ユウジン」だろうが中国でYou1ren2です。
「青島」は中国山東省の町でも青島幸男の姓でも関係なくQing1dao3です。
「青海」は日本の地名でオウミと読むのがありますが、中国ではQing1hai3で青海省と同じです。
また日本語の漢字の音読みには呉音、漢音、唐音、訓読があります。
「明朝」は明日の朝なら「ミョウチョウ」、中国の明王朝なら「ミンチョウ」で、「ミン」は唐音。
ややこしいことに唐代に入ったのが漢音で、唐音は明や清(シン、Qing1)の時代に入ったもの。
だから唐音では語末のngを「ン」で採用します。
「アンドン(行燈)」「アンギャ(行脚)」「インコ(鸚哥)」がそうです。
「ペキン」「シャンハイ」「カントン」「ホンコン」も唐音に近いのですが、どうも英語経由で入った可能性がありますね。
「北京」は「ペキン」なのに「京劇」が「キョウゲキ」というのは面倒。
北京語では「北京」Bei3jing1と「京劇」jing1ju4で「京」jing1の音は一定です。
☆mao zedong 英語 漢字
☆deng xiaoping
Deng XiaopingやJiang Zeminが誰のことかわからない日本人は今でも結構いるかも知れません。
☆北京の読み方[1]
☆北京の読み方[2]
☆英語における中国の固有名詞[1]
☆英語における中国の固有名詞[2]
☆中国人の名前の日本語読み☆
☆杭州と広州の中国読み☆
☆中国の地名で英語表記がBosun☆
☆黒龍江(ヘイロンチアン省)、遼寧(リャオニン省)の綴り☆
2010/4/2517:00:28
もし北京がペキンなら東京はトンキンになるはずで、トンペーと読むのがあれば東北でしょう。
北がペ(厳密にはペイ)で、京がキンからチンになり、東がトンだとわからないのですか?
北 Bei(ウェイド式Pei) … 第3声
京 jing(ウェイド式ching)←ging(ウェイド式king) … 第1声
東 Dong(ウェイド式Tung) … 第1声
したがって「東京」はDong1jing1,「東北」はDong1bei3です。
英語での言い方を列挙します。
上海 Shanghai☆
北京 PekingまたはBeijing☆
東京 Tokyo(中国ではDong1jing1)
武漢 Wuhan☆
ちなみに「五飯」であればwu3fan4ですがこういう熟語が存在するか疑問です。
似たような熟語で「五反運動」wu3fan3 yun4dong4があります。
「五」がウー(wu3)だとわかったら、ハン(han4)は「漢」だとわかりそうなものですが。
「五」がウー(wu3)だという知識はどこからですか?
「孫悟空」はSun1 Wu4kong1です。
「ドラゴンボール」の「孫悟飯」を中国人が北京語で読んだら
Sun1 Wu4fan4でしょうね。
それから「北京」を日本語の音読みで読むなら「ホッキョウ」か「ホッケイ」になるはず。
「キタキョウ」だと「キタ」が訓読みだから湯桶読みで、「東京」を「ヒガシキョウ」と読むようなものです。
どうして「上海」が「ジョウカイ」でないか、「北京」が「ホッキョウ」でないかは単なる慣用、歴史的偶然の産物と言うしかないですね。
「武」が日本語音で「ム」「ブ」で、「五」が「ゴ」なのに中国でウー(Wu3)になるのは北京語で語頭子音が脱落したせいです。
ほかに「呉」はWu2です。
だからWu3 Da4wei3は「武大偉」、Wu2 Yi2は「呉儀」になります。
日本人が中国の地名、人名を日本読みにしているのは中国人が日本の地名、人名に対してそうしているから。
「悠仁」は日本で「ヒサヒト」だろうが「ユウジン」だろうが中国でYou1ren2です。
「青島」は中国山東省の町でも青島幸男の姓でも関係なくQing1dao3です。
「青海」は日本の地名でオウミと読むのがありますが、中国ではQing1hai3で青海省と同じです。
また日本語の漢字の音読みには呉音、漢音、唐音、訓読があります。
「明朝」は明日の朝なら「ミョウチョウ」、中国の明王朝なら「ミンチョウ」で、「ミン」は唐音。
ややこしいことに唐代に入ったのが漢音で、唐音は明や清(シン、Qing1)の時代に入ったもの。
だから唐音では語末のngを「ン」で採用します。
「アンドン(行燈)」「アンギャ(行脚)」「インコ(鸚哥)」がそうです。
「ペキン」「シャンハイ」「カントン」「ホンコン」も唐音に近いのですが、どうも英語経由で入った可能性がありますね。
「北京」は「ペキン」なのに「京劇」が「キョウゲキ」というのは面倒。
北京語では「北京」Bei3jing1と「京劇」jing1ju4で「京」jing1の音は一定です。
☆mao zedong 英語 漢字
☆deng xiaoping
Deng XiaopingやJiang Zeminが誰のことかわからない日本人は今でも結構いるかも知れません。
☆北京の読み方[1]
☆北京の読み方[2]
☆英語における中国の固有名詞[1]
☆英語における中国の固有名詞[2]
☆中国人の名前の日本語読み☆
☆杭州と広州の中国読み☆
☆中国の地名で英語表記がBosun☆
☆黒龍江(ヘイロンチアン省)、遼寧(リャオニン省)の綴り☆













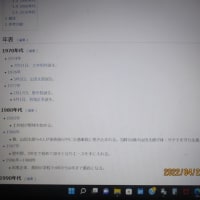



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます