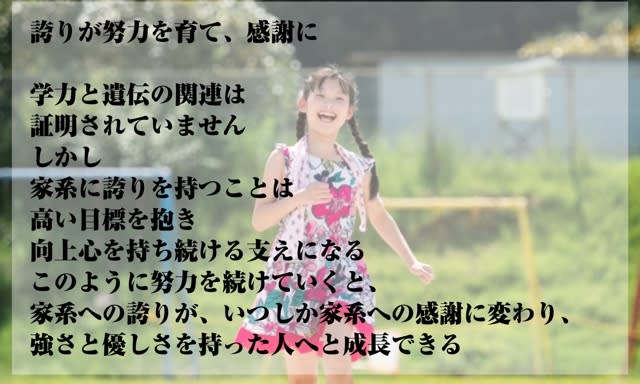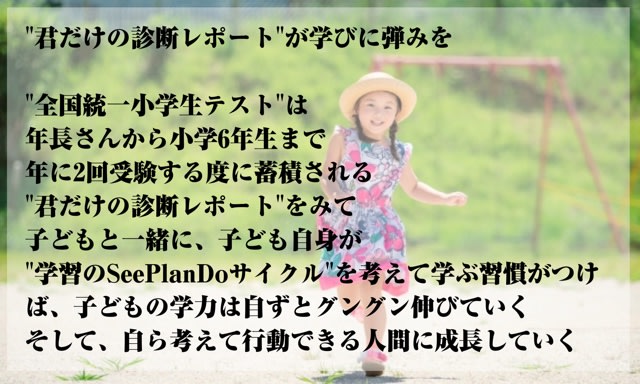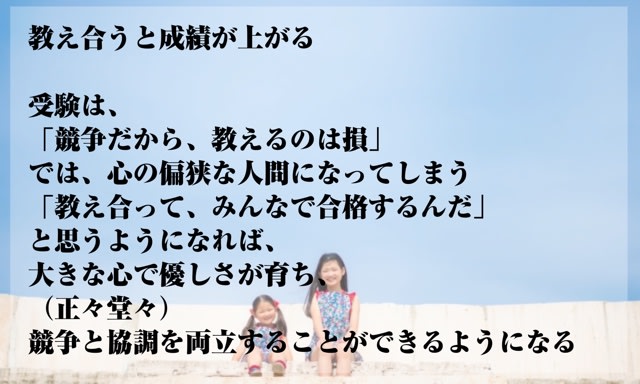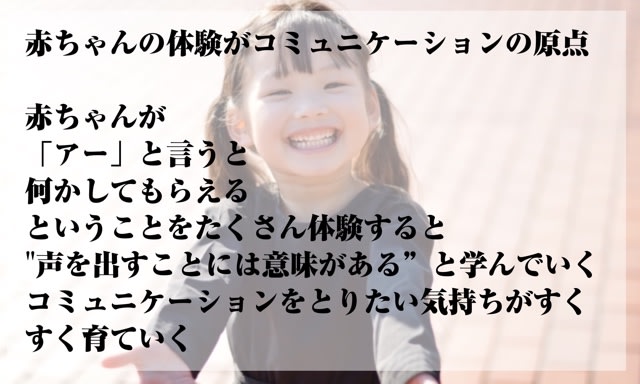
こんにちは、四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回も、コミュニケーションについて書きます。
❤︎外交的な子どもと内向的な子ども
自分の意見をズバッと言える子どもと
恥ずかしくて言えない子ども
これは、その子の性格によるのでしょうか。
私は、赤ちゃんの時の体験が大きく作用すると思います。
❤︎赤ちゃんがコミュニケーションの出発点
赤ちゃんは、
泣けばおむつを替えてもらえる、
あやしてもらえる……
自分が発信すると何かしてもらえる、
という経験を繰り返すことで、
"声を出すことには意味がある”
と学んでいきます。
応答を繰り返すなかで、
コミュニケーションが楽しくなり、
ことばを覚える意欲にもつながっていきます。
❤︎赤ちゃんが声を出したとき、まねをして返す
赤ちゃんに「声を出すことには意味があるんだよ」と教えてあげます。
そのために、
赤ちゃんが声を出したときに、
その声をまねて返してあげましょう
こうしたやりとりから、
赤ちゃんは、
声を出すことがコミュニケーションになるのだ、
とだんだん理解していきます。
❤︎期待通りに反応してあげる
赤ちゃんは、
自分が「いないいないばあ」をすれば、
相手から反応を期待します。
だから、
赤ちゃんの期待通りに反応してあげることがとても大事です。
期待通りにいかないと、ムッとしてしまうこともあります。
❤︎子どもは繰り返しが好き
また、
子どもは、
同じことの繰り返しがものすごく好きです。
何度も「いないいないばあ」をしてくることもあるでしょう。
その繰り返しの中で、
頭の中の働きが確実なものになっていきます。
❤︎目を見て、ゆったりしたリズムで、できるだけ静かなところで話す
赤ちゃんの目を見て、
少し高い声で言ってみてください。
そうすると.
赤ちゃんはこちらをずっと見てくれます。
同じことばを、
同じ調子で繰り返してあげるのも、
赤ちゃんの安心感につながります。
❤︎「この人に伝えたら、聞きてくれる」体験
「おはよう。おはよう。いいお天気だねえ」……
そんなゆったりしたリズムが、
赤ちゃんにとって聞き心地もよく、
「ああ、わかり合えた」という時間になります。
赤ちゃんが「この人に何かを伝えたら、
待ってくれる、聞いてくれる」と感じるリズムになるように、意識してみてください。
❤︎「伝えたい」という気持ちを育てるために
そして、もう少し大きくなり、
子どもが夢中になって何かをしているとき、
そばにいるだけでも十分です。
子どもは、
親が寄り添ってくれることで、
「自分がしていることを認めてくれている、
興味を持ってくれている」と感じて、
うれしい気持ちになります。
子どもが振り返ったり、
手をつかんできたりすることがあれば、
そのタイミングでしっかり応えてあげます。
❤︎「伝えたい」という気持ちを大切に
子どもはいろいろなものに興味を示します。
そのそれぞれにおいて、
それを「伝えたい」という気持ちを大切にしてあげれば、
コミュニケーションがドンドン育ってきます。
❤︎まとめ。赤ちゃんの体験がコミュニケーションの原点
赤ちゃんが「アー」と言うと
何かしてもらえる
ということをたくさん体験すると
"声を出すことには意味がある”
と学んでいきます。
コミュニケーションをとりたい気持ちがすくすく育ていきます。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回も、コミュニケーションについて書きます。
❤︎外交的な子どもと内向的な子ども
自分の意見をズバッと言える子どもと
恥ずかしくて言えない子ども
これは、その子の性格によるのでしょうか。
私は、赤ちゃんの時の体験が大きく作用すると思います。
❤︎赤ちゃんがコミュニケーションの出発点
赤ちゃんは、
泣けばおむつを替えてもらえる、
あやしてもらえる……
自分が発信すると何かしてもらえる、
という経験を繰り返すことで、
"声を出すことには意味がある”
と学んでいきます。
応答を繰り返すなかで、
コミュニケーションが楽しくなり、
ことばを覚える意欲にもつながっていきます。
❤︎赤ちゃんが声を出したとき、まねをして返す
赤ちゃんに「声を出すことには意味があるんだよ」と教えてあげます。
そのために、
赤ちゃんが声を出したときに、
その声をまねて返してあげましょう
こうしたやりとりから、
赤ちゃんは、
声を出すことがコミュニケーションになるのだ、
とだんだん理解していきます。
❤︎期待通りに反応してあげる
赤ちゃんは、
自分が「いないいないばあ」をすれば、
相手から反応を期待します。
だから、
赤ちゃんの期待通りに反応してあげることがとても大事です。
期待通りにいかないと、ムッとしてしまうこともあります。
❤︎子どもは繰り返しが好き
また、
子どもは、
同じことの繰り返しがものすごく好きです。
何度も「いないいないばあ」をしてくることもあるでしょう。
その繰り返しの中で、
頭の中の働きが確実なものになっていきます。
❤︎目を見て、ゆったりしたリズムで、できるだけ静かなところで話す
赤ちゃんの目を見て、
少し高い声で言ってみてください。
そうすると.
赤ちゃんはこちらをずっと見てくれます。
同じことばを、
同じ調子で繰り返してあげるのも、
赤ちゃんの安心感につながります。
❤︎「この人に伝えたら、聞きてくれる」体験
「おはよう。おはよう。いいお天気だねえ」……
そんなゆったりしたリズムが、
赤ちゃんにとって聞き心地もよく、
「ああ、わかり合えた」という時間になります。
赤ちゃんが「この人に何かを伝えたら、
待ってくれる、聞いてくれる」と感じるリズムになるように、意識してみてください。
❤︎「伝えたい」という気持ちを育てるために
そして、もう少し大きくなり、
子どもが夢中になって何かをしているとき、
そばにいるだけでも十分です。
子どもは、
親が寄り添ってくれることで、
「自分がしていることを認めてくれている、
興味を持ってくれている」と感じて、
うれしい気持ちになります。
子どもが振り返ったり、
手をつかんできたりすることがあれば、
そのタイミングでしっかり応えてあげます。
❤︎「伝えたい」という気持ちを大切に
子どもはいろいろなものに興味を示します。
そのそれぞれにおいて、
それを「伝えたい」という気持ちを大切にしてあげれば、
コミュニケーションがドンドン育ってきます。
❤︎まとめ。赤ちゃんの体験がコミュニケーションの原点
赤ちゃんが「アー」と言うと
何かしてもらえる
ということをたくさん体験すると
"声を出すことには意味がある”
と学んでいきます。
コミュニケーションをとりたい気持ちがすくすく育ていきます。