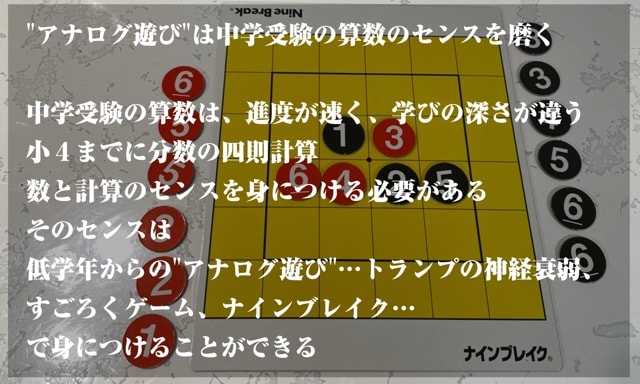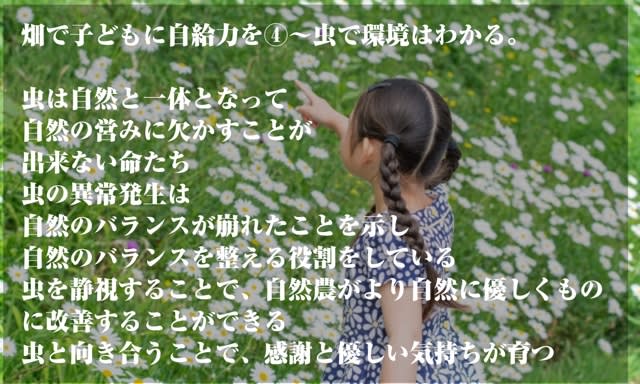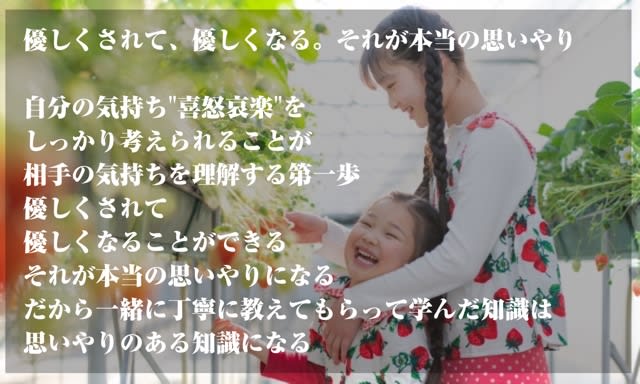
こんにちは、四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、思いやりについて書きます。
❤︎自己中心的は当た前
小さい子どもは、
自分中心でしか物事を考えられません。
これはごく自然な成長の過程です。
3歳ごろから
徐々に他人と自分とは異なる感情をもつことを
理解すると言われています。
その過程で子ども同士のけんかが起こるのは当然のことです。
❤︎思いやりの心を育てるために
❶相手の気持ちを一緒に考えよう
人を思いやるためには、
「他人がどのような気持ちか」
を考える力、共感できる力が必要です。
しかし、
お子さまにとって
他人の気持ちは簡単に理解できるものではないため、
少しずつ教えてあげる必要があります。
まずは、
自分の気持ちを客観的に見れるような
声かけをしましょう。
「どんな気持ちだった?」
「どうして本を貸してあげなかったの?」……
そして、
他人の気持ちを想像させましょう。
「あの子はどんな気持ちだったと思う?」
「こんなことを言われてあの子はどう思ったかな?」……。
こうした会話が、
相手の気持ちを感じとる練習になります。
❷いろいろなことが思いやりを育てる
①"ごっこ"遊び
働くパパになったり、
育児をするママになったり、
先生のなりきることは、
他人のことを考えることに繋がります。
②"読み聞かせ"
絵本を読み聞かせてあげたり、
自分で読んでもらうことにより、
登場人物の気持ちを考えます。
やっていいことダメなことを学びます。
❸ものを大切にすることを教える
人だけでなく、
動物、植物、食物……
ものに"感謝"の気持ちを持つことも大切です。
周りにものがあり溢れる現代だからこそ、
ものに対するありがたみを感じにくくなっています。
だから、
「いただきます」
「ごちそうさま」
を言い、
食物に感謝したり、
自分より小さな動物を大切にしたり、
ものを大切に扱うことを教えよう。
そうすれば、
他人のものや、
他人の気持ちも大切に扱うようになります。
❤︎大人の背中を見て子は育つ
思いやりは、
言葉だけで教えられるものではありません。
行動を見せることが何よりも有効です。
子どもは、
大人の行動をよく見て、
それをまねをしようとするからです。
親がお互いを敬い合い、思いやり、
「ありがとう」「ごめんね」
などの言葉をかけ合う。
ものを粗末に扱わない。
そして、
子どもの言葉に耳を傾け、
優しく接しましょう。
優しくされたことのない子は、
優しさの表し方がわかりません。
自分が受け入れられた、
優しくされたという喜びが、
思いやりの心を育てます。
❤︎勉強で思いやりを
語彙を一緒に覚え、
読解力を一緒に学び、
国語力を伸ばすことは、
他人の言葉を理解することにつながります。
いろいろな文章を一緒に読み
そこで展開される登場人物の心の動きを考えることは、
いろいろな感情があることを体験し、知らことにつながります。
勉強も先生が優しく教え、
子どもが穏やかな気持ちで勉強できる雰囲気で。
相手の思いを理解すること、
相手の感情を知り、考えることは、
思いやりにつながると思います。
❤︎まとめ。優しくされて、優しくなる。それが真の思いやり
自分の気持ち"喜怒哀楽"を
しっかり考えられることが、
相手の気持ちを理解する第一歩です。
優しくされて、優しくなることができます。
それが真の思いやりになります。
だから、
一緒に丁寧に教えてもらって学んだ知識は、
思いやりのある知識になります。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、思いやりについて書きます。
❤︎自己中心的は当た前
小さい子どもは、
自分中心でしか物事を考えられません。
これはごく自然な成長の過程です。
3歳ごろから
徐々に他人と自分とは異なる感情をもつことを
理解すると言われています。
その過程で子ども同士のけんかが起こるのは当然のことです。
❤︎思いやりの心を育てるために
❶相手の気持ちを一緒に考えよう
人を思いやるためには、
「他人がどのような気持ちか」
を考える力、共感できる力が必要です。
しかし、
お子さまにとって
他人の気持ちは簡単に理解できるものではないため、
少しずつ教えてあげる必要があります。
まずは、
自分の気持ちを客観的に見れるような
声かけをしましょう。
「どんな気持ちだった?」
「どうして本を貸してあげなかったの?」……
そして、
他人の気持ちを想像させましょう。
「あの子はどんな気持ちだったと思う?」
「こんなことを言われてあの子はどう思ったかな?」……。
こうした会話が、
相手の気持ちを感じとる練習になります。
❷いろいろなことが思いやりを育てる
①"ごっこ"遊び
働くパパになったり、
育児をするママになったり、
先生のなりきることは、
他人のことを考えることに繋がります。
②"読み聞かせ"
絵本を読み聞かせてあげたり、
自分で読んでもらうことにより、
登場人物の気持ちを考えます。
やっていいことダメなことを学びます。
❸ものを大切にすることを教える
人だけでなく、
動物、植物、食物……
ものに"感謝"の気持ちを持つことも大切です。
周りにものがあり溢れる現代だからこそ、
ものに対するありがたみを感じにくくなっています。
だから、
「いただきます」
「ごちそうさま」
を言い、
食物に感謝したり、
自分より小さな動物を大切にしたり、
ものを大切に扱うことを教えよう。
そうすれば、
他人のものや、
他人の気持ちも大切に扱うようになります。
❤︎大人の背中を見て子は育つ
思いやりは、
言葉だけで教えられるものではありません。
行動を見せることが何よりも有効です。
子どもは、
大人の行動をよく見て、
それをまねをしようとするからです。
親がお互いを敬い合い、思いやり、
「ありがとう」「ごめんね」
などの言葉をかけ合う。
ものを粗末に扱わない。
そして、
子どもの言葉に耳を傾け、
優しく接しましょう。
優しくされたことのない子は、
優しさの表し方がわかりません。
自分が受け入れられた、
優しくされたという喜びが、
思いやりの心を育てます。
❤︎勉強で思いやりを
語彙を一緒に覚え、
読解力を一緒に学び、
国語力を伸ばすことは、
他人の言葉を理解することにつながります。
いろいろな文章を一緒に読み
そこで展開される登場人物の心の動きを考えることは、
いろいろな感情があることを体験し、知らことにつながります。
勉強も先生が優しく教え、
子どもが穏やかな気持ちで勉強できる雰囲気で。
相手の思いを理解すること、
相手の感情を知り、考えることは、
思いやりにつながると思います。
❤︎まとめ。優しくされて、優しくなる。それが真の思いやり
自分の気持ち"喜怒哀楽"を
しっかり考えられることが、
相手の気持ちを理解する第一歩です。
優しくされて、優しくなることができます。
それが真の思いやりになります。
だから、
一緒に丁寧に教えてもらって学んだ知識は、
思いやりのある知識になります。