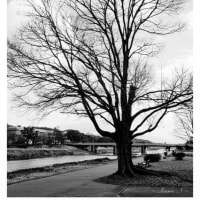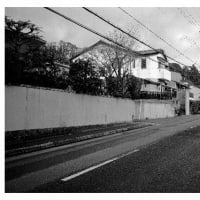南座(正式には 京都四條南座)
東山区四条通大和大路西入
南座の歴史は古く、
元和年間(1615~1623年)
京都司所代板倉勝重が四条河原に7つの櫓を官許する。
この頃を南座発祥とする。(歌舞伎事始)…とあります。
古くから歌舞伎の劇場として有名で、毎年11月末日より12月末まで行われる顔見世公演が行われています。そのときには「まねき」と呼ばれる役者の名前を書いた「白木の看板…勘亭流で」が劇場の入り口上に飾られます。
明治39年(1906年)より松竹が経営しており、年間を通じて演劇などが行われています。現在の建物は昭和4年(1929年)に竣工し、平成2年(1990年)に外観をそのまま残しつつ内部を改装され、平成3年(1991年)新装オープンしました。
現在、登録有形文化財になっているそうです。

東山区四条通大和大路西入
南座の歴史は古く、
元和年間(1615~1623年)
京都司所代板倉勝重が四条河原に7つの櫓を官許する。
この頃を南座発祥とする。(歌舞伎事始)…とあります。
古くから歌舞伎の劇場として有名で、毎年11月末日より12月末まで行われる顔見世公演が行われています。そのときには「まねき」と呼ばれる役者の名前を書いた「白木の看板…勘亭流で」が劇場の入り口上に飾られます。
明治39年(1906年)より松竹が経営しており、年間を通じて演劇などが行われています。現在の建物は昭和4年(1929年)に竣工し、平成2年(1990年)に外観をそのまま残しつつ内部を改装され、平成3年(1991年)新装オープンしました。
現在、登録有形文化財になっているそうです。