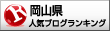令和7年2月22日(土)、やかげ文化センターホールで開催された人権啓発講演会に参加しました。講師は作家であり僧侶の家田荘子さん。「一緒に生きていこう 〜あなたの愛を求めています〜」というテーマのもと、家田氏自身の経験を交えた講演が行われました。
家田荘子って作家だっけ?
25年ほど前に属していた国際結婚のコミュニティで、「家田荘子が出家するらしいよ。」という話を耳にしたのが記憶に残っている。
ググってみたら、「極道の妻たち」が出てきた。さぞかし、壮絶な話が聴けるのだろうなと思いつつ参加してみたら、案の定だった。
民生委員や本陣文学賞に入賞している人などの意識高そうな知り合いが聴きに来られていた。
講演の内容
壇上で、原稿も無しに淡々と少年院に入った少女やエイズが流行り始めたばかりの頃の患者へのインタビュー、自身の体験などを語られた。
作家やジャーナリストは、そうやっていろいろな人に取材して、多くの人に知ってもらうのが仕事だが、そこに突き動かされるパワーの根っこには自分自身の源体験があるんだろうと思う。
ふと、思い出したこと
最近NHKで観たドキュメンタリーを思い出した。「きょうも都会の公園で~福岡・天神 警固公園~」。家庭に居場所が無くて、集まってくる子どもたちの話。
家田荘子氏の弔いの活動
家田さんは、関東大震災で亡くなった500人の遊女の霊を25年以上も弔っているそうです。NHKの大河ドラマで話題になっていますが、女性や不幸な人たちに寄り添っている作家の姿勢が伝わってきます。
講演を聴いて感じたこと
今日、一番実感したのは、歩み寄ってお互いに理解する事の大切さ。
ありがとうございました。