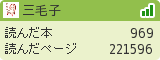VIDEO 1. 棒踊り, Jocul cu bâtă, Bot tánc, Stick Dance2. 帯踊り, Brâul, Sash Dance3. 踏み踊り Pe loc, Topogó, In One Spot4. 角笛の踊り, Buciumeana, Bucsumí tánc, Dance from Bucsum5. ルーマニア風ポルカ, Poarga Românească, Román polka, Romanian Polka6. 速い踊り,Mărunțel, Aprózó, Fast Dance[てるみんるーむを開く]
VIDEO 山本 準 ✨[てるみんるーむを開く]
山本 準 のオリジナル作品の「Jours qui Passent 過ぎ去りし日々」 をテルミンで演奏しました。VIDEO [てるみんるーむを開く]
VIDEO 「素晴らしき紅マグロの世界」 をテルミンで演奏しました。Bing Image Creator に作ってもらったものを動かしました。 記事をnote [てるみんるーむを開く]
VIDEO イクルデザイン の須藤 生さんの手により優美な曲線とゴールドのノブを持つ筐体に生まれ変わりました![てるみんるーむを開く]
VIDEO 「ロンドンデリーの歌」 を、Trio di Montagna が演奏しました。Trio di Montagna を編成し、じっくり取り組みました。 それぞれの自宅でのリモート合奏です 。by 三毛子Trio di Montagna [てるみんるーむを開く]
生成AI って急速にすごいことになってますね。 今までにも静止画を作ったりはしていたのですが、最近は曲も作ってくれます。VIDEO Suno で作ったピアノだけのトラックの上で Claravox Centennial を気ままに弾き散らかしてみました。 6回弾いて重ねてあります。PAN と Reverb はちょっと弄りましたが、他の音源は使っていません。いちどに2分だけしか作れない(続きを作る方法はあるけど)ので、そこまでだけど。「生成AIはまだテルミンを知らないらしい 」 という記事をnote に書きましたので、そちらも合わせてお楽しみください。[てるみんるーむを開く]
VIDEO 「Robinson Crusoe」 だ!と思ったので・・・そちらのほうをテルミンで弾いてみました。[てるみんるーむを開く]
VIDEO [てるみんるーむを開く]











 てるみんるーむ
てるみんるーむ YouTube
YouTube