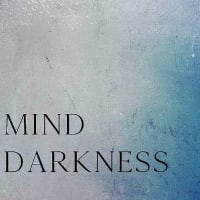やっぱりまだまだFilmにはかなわないのかな~なんて考えてます..........................
今日は日中ぼ~っとNHkを見ていると高校講座で美術で「写真を撮る」ことがテーマで放送されていました。
おいらはContrastとかLatitudeを考慮して撮る事が多いのですが、特に気にしているのはやっぱり
「黒の締まり」
に尽きるかと思います。
Glareな黒というのはPrint Outした写真でしか表現できない部分なんですよね。
おいらはもっぱらPrint OutではなくComputer上で調整を行い渡します。
理由はPrint Outというのはお金が掛かるからに他なりません。
しかし今日は見た高校講座ではVideo Cameraを通してでも
・素晴らしい「黒の締まり」
・豊かなボケ味
・豊かな階調
が直ぐに解りました。
加えて露出も適正なモノが多くて感心しましたな。
露出を測光する部分が写されていませんでしたが、あれは露出計(測光計とも言うでしょうね)で測ってでないと撮り慣れていない人には撮れないQualityでした。
高校で美術を学ぶ専門的な所があるのは聴いてはいましたがやはり学んでいるだけあって構図が良かったのも感心しました。
Filmの緊張感はDigital Cameraには無いと言われがちですが、確かに意識しないとやたらとShutter数が増えているのも感じます。
しかし「緊張感がないのか」と言われるとそうではないでしょう。
Filmの場合は一枚一枚のCostが大きく「失敗が許されない」という意識が強すぎるだけなんですよね。
またFilmで写真を撮ると時間が掛かり写真を撮るというProcessを大事にするべきだという意見が語られていましたが、Filmだけが時間が掛かり苦労があると言う言い方をされていたんですが、おいらはそうは思いません。
今回の放送ではMonochrome写真を撮っておられました。
よって現像処理もPrintも自分で行うということで進行されていました。
確かに現像液を調合したり、管理する(温度の維持など)のも手間が掛かるのは理解できますが、これは自分で行える施設を有していたり近くにそういう借りる事が出来て実行できるからでしょう。
また最も大きなこととして
「Cost」が掛かる
のも忘れてはならないFactorです。
一般人はおいそれと借りる事が出来ませんし、近くにない人はそれこそとんでもない金額をかけてPrintする施設を構築させねばなりません。
それ以外の方法としてはStandardな方法である「店に任せきり」になってしまうでしょう。
Film時点では「減感(感度を下げ気味に現像する)、増感(感度を上げ気味に現像する)」の指定やPrint時に「明るめに、暗めに」、「色温度を調整して」など漠然とした指定しか行えないんですよ。
おいらはFilm時代から撮っていますからね。
それに写真屋さんで働いていた事もありPrintも現像機も触っていました。
まあ触っていたと言っても現像機の場合は店にあるのでは増感、減感は行えずフォトラボ(Photo Laboratory)に送る事しかできませんでした。
Printerはかなり調整が出来ましたけどね。
彼処で学んだ事というのは今でも役に立っているんですな。
RGBとCMYKの色の調整方法も学びましたし、光源によって調整する方法を店長から教えて貰ったモノです。
懐かしいな~..................
ところでDigitalが時間が掛からず直ぐにPrintできるというのは全くの誤解です。
確かに確認は直ぐに出来ますし、Filmと比較すると緊張感がないかも知れません。
しかし知れば知るほど調整する項目が増えて最適な写真を作り出すのは一苦労するんです。
余り知らない人であれば撮ったら撮れた状態でPrintすると言う事が多いでしょうけどね。
写真を知っているのであれば現像SoftwareやPhotoshopの調整項目に愕然とするんではないでしょうかね~............
おいらは自分で撮った写真でPrint Outするとなると一枚に数時間は最低でも費やします。
最終的に10Patternは作ってPrint Outも納得するまでしたいのですが、出費を少なくする為にL版やKG版などで試しPrintして見ます。
この時点でNGなら大きくする事はありません。
おいらが撮った写真で大きくPrint Outするのは1万枚に数枚程度しかないですな。
Digital Photoを始めて大きくPrint Outした写真は10枚程度しかないですもん。
写真の枚数的には20万枚ぐらい撮っていますけどね。
撮ろうと思えば相当数撮れますけど、RAW現像する時点で選別して良い写真を選び出します。
そしてその写真の中からPrintしようとSympathyを感じるモノをPrint Outする訳です。
おいらは暗室でPrintを行った事はありませんが、あのような環境を作り出すのであれば相当な金額が飛んでいくのは明らかです。
それにFilm代と現像代というのはおいらの生活を圧迫し、苦しい目に遭っていたんですよね。
そう考えるとDigitalのMeritというのは凄く大きいんですよ。
一年で30万~50万程度は使っていました。
そう考えると今のCostというのは5分の1もしくはそれ以上に少ないCostで写真を撮っている訳ですよ。
Digital Cameraで撮る写真というのは幾つもの最終形態が存在します。
Filmの場合はほとんどの場合にPrintが最終形態ですがね。
WEBやBlog(WEB Design)、雑誌や本と広告(DTP)、Print、ScreenSaverや壁紙などにも使用可能です。
ここで書いておかねばならない点としては、
どれに焦点を当てるかによって加工方法や調整方法は変わってくる
と言う事実です。
撮り方も変わりますし、現像方法やRetouch方法も変わるんですよね。
WEBでは自己主張の強い写真というのは入り口にこそ必要かも知れませんがね。
文字の邪魔にならないように加工を施す必要があるんですな。
BlogはおいらもUpしていますが、一番上に持ってくる写真と間に挟む写真というのは変わってくるんですよね。
概ねですが、途中に挟む写真というのは説明を加える為に間に挟む事が多いんですよ。
まあ全部が全部ではないのであしからず。
DTPなどではもっと複雑なことを考慮する必要があるでしょうね~。
まあ、関心がありますがお足がないので今のところは難しいんですな。
そしてPrintはおいらもしますので少しは解ります。
Printする時の注意点としてColor Managementがしっかり出来ていないと駄目なんですよね。
今のところColor Printerが無いので家でPrintすることはないのでなんなんですが、Printerが無い事の方が問題であるという点には触れないでください。(笑)
おいらがPrintするというのは今のところは店でPrintするということになるのですが、家でもPrintしていた事がありますので色調の調整に本当に困りました。
Color Management Toolが余裕が出来ると欲しいな~と思っているのですが、Computerを手に入れる事が先決でしたのでまだまだ先になりそうです。
Printの基本としてまず発色の傾向をつかむ必要があります。
色域というのはPrinterでPrintする方が濃くなります。
Color Managementしていない状態でPrintするとですけどね
これは原因としては印画紙の白さに起因します。
印画紙というのは「液晶のように発光していない」というところがPointなんですな。
加えて「ISO白色度」という言葉があります。
これは光の反射率の高さによって変わってくるんですな。
100%の反射率は「鏡」になります。
反射率というのは光の吸収度によって変わるんですよ。
よって反射率がほとんど無いものというのは真っ黒になります。
これは人が認識している「色」の概念を形成する上で重要なんですよね。
客観的に決められたモノというのは個人の主観から来るImageとかけ離れたモノになるのは当然なんですよ。
訳の解らない方向に行きましたので話を戻します。
印画紙というのはComputerのようにBack Lightが光らないのでPrint Outした写真とMonitorで見る写真では違って当然といえば当然なんですな。
真っ白といっても反射率が低くなるという事は幾分「暗くなる」ということなんです。
つまり暗く見えて当然なんですな。
見る媒体が違うだけでかなり違うと感じるはずです。
ところがPrint Outした写真には「見る条件」というのが揃っている必要がある訳ですよ。
これは知らない人が多いのですが、写真の正しい見方を知っておくのも本気で写真を楽しむ為には必須の知識です。
基本的に写真というのは
5000K(ケルビン=Kelvin)という色温度で光が全面に照射されること
で始めてその写真を見る準備が整ったという事になります。
この条件だったならばColor Managementが行われているならば同じ発色になるようにPrintされManagementされていないならば調整する必要のある発色傾向を分析できるという事になります。
でも発色傾向というのはInkを交換しただけで変わりますし、MonitorのBack Lightの劣化によっても起こります。
つまり本気でColor Managementするのであれば相当な手間が必要になるという事なんですよ。
Inkの交換は一本でも変えると起こるんですよ。
かなり精度の高い純正のInkでもどうしても誤差というのが生じてしまいます。
追求していくのであれば撮り貯めておいてInkも揃えておき、一日で満足の行く写真を作り出すのが理想的でしょう。
一ヶ月に一度か二ヶ月に一度そういう日を作ってその日はColor ManagementをWork Flow全体に施し一気に行ってしまうという事ですな。
MonitorのColor Managementは一ヶ月に一回ぐらいするのが望ましいとされています。
おいらはToolを手に入れる事が出来るならばDisc Utilityと同じぐらいの頻度で行うでしょうな。
一週間に一回程度Disc Utilityを行っていますからね。
Printerの場合はPrint Outする以外の時はInkを抜いておくでしょうし、Maintenanceを行う事は多いでしょう。
おいらが家でPrintするのであれば本格的なPrinterを導入してからになるでしょうし、多分ですがMonitorとの誤差が気になるのでColor Management Toolを手にしてからになるでしょう。
気が遠くなるぐらい先になるな~................
まあそれなりに頑張っていますので頑張りが満ちたと感じた時点で購入するでしょう。
取り敢えずPrintは店で行うという事には変わりはないですな。
Screen Saverとか壁紙に関しても書いておきましょうかね。
これはPrintするのにも共通するのですがね。
規格に合わせる必要があるんですな。
縦横比が違うMonitorというのを誰しも経験した事があるでしょう。
これはTVでも言えます。
これをアスペクト比といいます。
長辺と短辺の比率のことでCameraから排出されたDataをそのまま用いられるという事は90パーセントの割合で”ありません”。
Printの場合は長辺が切られますし、Screen Saverや壁紙の場合は短辺の上下どちらかか上下辺両辺が切られます。
Printを申し込む際には自分が望むPrintを行いたいのであれば自分でこの辺りを揃えて申し込まなければならないんですな。
壁紙やScreenSaverでも一緒です。
自分の意図と違う切られ方をするというのは調整までした作品では非常に強い違和感が生まれます。
だから自分の意図した構図に自分自身で行わなければならないんですよ。
こう考えると同じDataでも相当な調整量が必要になる事が解るでしょう。
Filmの場合では任せきりだったのに全部自分で行う必要があるというのは「嬉しい」ととるか「大変」ととるかがDigital DataやDigital写真の知識度によって変わってくるという事なんですよね。
長い事書きましたが、アスペクト比(Aspect Ratio)って「ぺはべべではなかったんだな~知らなかった。
ずっと「アス”ベ”クト比」って書いてきたので今から過去の記事を訂正していきます。
今日は日中ぼ~っとNHkを見ていると高校講座で美術で「写真を撮る」ことがテーマで放送されていました。
おいらはContrastとかLatitudeを考慮して撮る事が多いのですが、特に気にしているのはやっぱり
「黒の締まり」
に尽きるかと思います。
Glareな黒というのはPrint Outした写真でしか表現できない部分なんですよね。
おいらはもっぱらPrint OutではなくComputer上で調整を行い渡します。
理由はPrint Outというのはお金が掛かるからに他なりません。
しかし今日は見た高校講座ではVideo Cameraを通してでも
・素晴らしい「黒の締まり」
・豊かなボケ味
・豊かな階調
が直ぐに解りました。
加えて露出も適正なモノが多くて感心しましたな。
露出を測光する部分が写されていませんでしたが、あれは露出計(測光計とも言うでしょうね)で測ってでないと撮り慣れていない人には撮れないQualityでした。
高校で美術を学ぶ専門的な所があるのは聴いてはいましたがやはり学んでいるだけあって構図が良かったのも感心しました。
Filmの緊張感はDigital Cameraには無いと言われがちですが、確かに意識しないとやたらとShutter数が増えているのも感じます。
しかし「緊張感がないのか」と言われるとそうではないでしょう。
Filmの場合は一枚一枚のCostが大きく「失敗が許されない」という意識が強すぎるだけなんですよね。
またFilmで写真を撮ると時間が掛かり写真を撮るというProcessを大事にするべきだという意見が語られていましたが、Filmだけが時間が掛かり苦労があると言う言い方をされていたんですが、おいらはそうは思いません。
今回の放送ではMonochrome写真を撮っておられました。
よって現像処理もPrintも自分で行うということで進行されていました。
確かに現像液を調合したり、管理する(温度の維持など)のも手間が掛かるのは理解できますが、これは自分で行える施設を有していたり近くにそういう借りる事が出来て実行できるからでしょう。
また最も大きなこととして
「Cost」が掛かる
のも忘れてはならないFactorです。
一般人はおいそれと借りる事が出来ませんし、近くにない人はそれこそとんでもない金額をかけてPrintする施設を構築させねばなりません。
それ以外の方法としてはStandardな方法である「店に任せきり」になってしまうでしょう。
Film時点では「減感(感度を下げ気味に現像する)、増感(感度を上げ気味に現像する)」の指定やPrint時に「明るめに、暗めに」、「色温度を調整して」など漠然とした指定しか行えないんですよ。
おいらはFilm時代から撮っていますからね。
それに写真屋さんで働いていた事もありPrintも現像機も触っていました。
まあ触っていたと言っても現像機の場合は店にあるのでは増感、減感は行えずフォトラボ(Photo Laboratory)に送る事しかできませんでした。
Printerはかなり調整が出来ましたけどね。
彼処で学んだ事というのは今でも役に立っているんですな。
RGBとCMYKの色の調整方法も学びましたし、光源によって調整する方法を店長から教えて貰ったモノです。
懐かしいな~..................
ところでDigitalが時間が掛からず直ぐにPrintできるというのは全くの誤解です。
確かに確認は直ぐに出来ますし、Filmと比較すると緊張感がないかも知れません。
しかし知れば知るほど調整する項目が増えて最適な写真を作り出すのは一苦労するんです。
余り知らない人であれば撮ったら撮れた状態でPrintすると言う事が多いでしょうけどね。
写真を知っているのであれば現像SoftwareやPhotoshopの調整項目に愕然とするんではないでしょうかね~............
おいらは自分で撮った写真でPrint Outするとなると一枚に数時間は最低でも費やします。
最終的に10Patternは作ってPrint Outも納得するまでしたいのですが、出費を少なくする為にL版やKG版などで試しPrintして見ます。
この時点でNGなら大きくする事はありません。
おいらが撮った写真で大きくPrint Outするのは1万枚に数枚程度しかないですな。
Digital Photoを始めて大きくPrint Outした写真は10枚程度しかないですもん。
写真の枚数的には20万枚ぐらい撮っていますけどね。
撮ろうと思えば相当数撮れますけど、RAW現像する時点で選別して良い写真を選び出します。
そしてその写真の中からPrintしようとSympathyを感じるモノをPrint Outする訳です。
おいらは暗室でPrintを行った事はありませんが、あのような環境を作り出すのであれば相当な金額が飛んでいくのは明らかです。
それにFilm代と現像代というのはおいらの生活を圧迫し、苦しい目に遭っていたんですよね。
そう考えるとDigitalのMeritというのは凄く大きいんですよ。
一年で30万~50万程度は使っていました。
そう考えると今のCostというのは5分の1もしくはそれ以上に少ないCostで写真を撮っている訳ですよ。
Digital Cameraで撮る写真というのは幾つもの最終形態が存在します。
Filmの場合はほとんどの場合にPrintが最終形態ですがね。
WEBやBlog(WEB Design)、雑誌や本と広告(DTP)、Print、ScreenSaverや壁紙などにも使用可能です。
ここで書いておかねばならない点としては、
どれに焦点を当てるかによって加工方法や調整方法は変わってくる
と言う事実です。
撮り方も変わりますし、現像方法やRetouch方法も変わるんですよね。
WEBでは自己主張の強い写真というのは入り口にこそ必要かも知れませんがね。
文字の邪魔にならないように加工を施す必要があるんですな。
BlogはおいらもUpしていますが、一番上に持ってくる写真と間に挟む写真というのは変わってくるんですよね。
概ねですが、途中に挟む写真というのは説明を加える為に間に挟む事が多いんですよ。
まあ全部が全部ではないのであしからず。
DTPなどではもっと複雑なことを考慮する必要があるでしょうね~。
まあ、関心がありますがお足がないので今のところは難しいんですな。
そしてPrintはおいらもしますので少しは解ります。
Printする時の注意点としてColor Managementがしっかり出来ていないと駄目なんですよね。
今のところColor Printerが無いので家でPrintすることはないのでなんなんですが、Printerが無い事の方が問題であるという点には触れないでください。(笑)
おいらがPrintするというのは今のところは店でPrintするということになるのですが、家でもPrintしていた事がありますので色調の調整に本当に困りました。
Color Management Toolが余裕が出来ると欲しいな~と思っているのですが、Computerを手に入れる事が先決でしたのでまだまだ先になりそうです。
Printの基本としてまず発色の傾向をつかむ必要があります。
色域というのはPrinterでPrintする方が濃くなります。
Color Managementしていない状態でPrintするとですけどね
これは原因としては印画紙の白さに起因します。
印画紙というのは「液晶のように発光していない」というところがPointなんですな。
加えて「ISO白色度」という言葉があります。
これは光の反射率の高さによって変わってくるんですな。
100%の反射率は「鏡」になります。
反射率というのは光の吸収度によって変わるんですよ。
よって反射率がほとんど無いものというのは真っ黒になります。
これは人が認識している「色」の概念を形成する上で重要なんですよね。
客観的に決められたモノというのは個人の主観から来るImageとかけ離れたモノになるのは当然なんですよ。
訳の解らない方向に行きましたので話を戻します。
印画紙というのはComputerのようにBack Lightが光らないのでPrint Outした写真とMonitorで見る写真では違って当然といえば当然なんですな。
真っ白といっても反射率が低くなるという事は幾分「暗くなる」ということなんです。
つまり暗く見えて当然なんですな。
見る媒体が違うだけでかなり違うと感じるはずです。
ところがPrint Outした写真には「見る条件」というのが揃っている必要がある訳ですよ。
これは知らない人が多いのですが、写真の正しい見方を知っておくのも本気で写真を楽しむ為には必須の知識です。
基本的に写真というのは
5000K(ケルビン=Kelvin)という色温度で光が全面に照射されること
で始めてその写真を見る準備が整ったという事になります。
この条件だったならばColor Managementが行われているならば同じ発色になるようにPrintされManagementされていないならば調整する必要のある発色傾向を分析できるという事になります。
でも発色傾向というのはInkを交換しただけで変わりますし、MonitorのBack Lightの劣化によっても起こります。
つまり本気でColor Managementするのであれば相当な手間が必要になるという事なんですよ。
Inkの交換は一本でも変えると起こるんですよ。
かなり精度の高い純正のInkでもどうしても誤差というのが生じてしまいます。
追求していくのであれば撮り貯めておいてInkも揃えておき、一日で満足の行く写真を作り出すのが理想的でしょう。
一ヶ月に一度か二ヶ月に一度そういう日を作ってその日はColor ManagementをWork Flow全体に施し一気に行ってしまうという事ですな。
MonitorのColor Managementは一ヶ月に一回ぐらいするのが望ましいとされています。
おいらはToolを手に入れる事が出来るならばDisc Utilityと同じぐらいの頻度で行うでしょうな。
一週間に一回程度Disc Utilityを行っていますからね。
Printerの場合はPrint Outする以外の時はInkを抜いておくでしょうし、Maintenanceを行う事は多いでしょう。
おいらが家でPrintするのであれば本格的なPrinterを導入してからになるでしょうし、多分ですがMonitorとの誤差が気になるのでColor Management Toolを手にしてからになるでしょう。
気が遠くなるぐらい先になるな~................
まあそれなりに頑張っていますので頑張りが満ちたと感じた時点で購入するでしょう。
取り敢えずPrintは店で行うという事には変わりはないですな。
Screen Saverとか壁紙に関しても書いておきましょうかね。
これはPrintするのにも共通するのですがね。
規格に合わせる必要があるんですな。
縦横比が違うMonitorというのを誰しも経験した事があるでしょう。
これはTVでも言えます。
これをアスペクト比といいます。
長辺と短辺の比率のことでCameraから排出されたDataをそのまま用いられるという事は90パーセントの割合で”ありません”。
Printの場合は長辺が切られますし、Screen Saverや壁紙の場合は短辺の上下どちらかか上下辺両辺が切られます。
Printを申し込む際には自分が望むPrintを行いたいのであれば自分でこの辺りを揃えて申し込まなければならないんですな。
壁紙やScreenSaverでも一緒です。
自分の意図と違う切られ方をするというのは調整までした作品では非常に強い違和感が生まれます。
だから自分の意図した構図に自分自身で行わなければならないんですよ。
こう考えると同じDataでも相当な調整量が必要になる事が解るでしょう。
Filmの場合では任せきりだったのに全部自分で行う必要があるというのは「嬉しい」ととるか「大変」ととるかがDigital DataやDigital写真の知識度によって変わってくるという事なんですよね。
長い事書きましたが、アスペクト比(Aspect Ratio)って「ぺはべべではなかったんだな~知らなかった。
ずっと「アス”ベ”クト比」って書いてきたので今から過去の記事を訂正していきます。